1.ローマ人の物語13「最後の努力」

/塩野七生著
〈第一部〉ディオクレティアヌスの時代(294~305)
・帝国
エンパイアーの語源~インペリウム=支配する、統治する、命令する、を意味する動詞から生まれる。政体(共和制・帝政)のは関係なく、自分たち以外の国や民族まで支配下に置く覇権国家であれば「帝国」である。
ディオクレティアヌスの統治期間(20年)蛮族の侵入は無かった。
蛮族の方にはローマ化する気もなくなったし、ローマもローマ的でなくなった。
[以前は敗者は敗北の後は喜んでローマ化を喜んだ]
ローマ帝国は「元首政」から「絶対君主制」への第一歩を踏み出した。
皇帝は「市民中の第一人者」から「支配する者」となり、一般人からは皇帝は仰ぎ見る存在となった。~それまで私邸の召使いが使う言葉であった「御主人様」は、市民が皇帝に対して使う言葉になった。市民中の第一人者は支配者に、市民は臣下に変わった。皇帝の服装は宝石をちりばめたものに変わった。
・権力とは、それを持つ者を堕落させるが、持たない者も堕落させる。
四頭政は官僚的ヒエラルキーを生んだ
東方―正帝ディオクレティアヌス(首都ニコメディア)―副帝ガレリウス(首都シルミウム)
西方―――正帝マクシミアヌス(首都ミラノ)――――――――副帝コンスタンティヌス(首都トリアー)
地方組織は、管轄区・県となりその官僚の任命権も皇帝が握った。
・税制も変わった
アウグストゥス時代は、国家は税収の範囲内でしか手がけなかった。
ディオクレティアヌス時代になると、国家に必要な経費が課税された。
・ほとんど全ての職業に世襲制が布かれた。
【増田総括。ディオクレティアヌスは、それまでの軍人割拠を統一し蛮族侵入を防いだが、古代ローマのローマらしさのほとんどがなくなり、中世の絶対君主制を準備した。】
〈第二部〉コンスタンティヌス時代(306~337)
兵站=ローマでは兵站はars=英語ではartつまり技(わざ)、すなわち人間がなすべき全てのことを意味したが、以降兵站はロジスティクス=輸送が使われる。
・コンスタンティヌスは元老院議員を富裕度に応じて四段階に分けた。
・コンスタンティヌスは新しき首都[ビザンティウム]、新しき政体、新しき宗教による、新生ローマ帝国を実現しようとした。
・元老院の始まり~数多くの部族の連合体であった王政時代のローマで300人にもなった部族長達を集め王への助言機関として設置された[紀元753年]。
紀元509年に共和制に移行。
・「金本位制」を導入~金貨で給料をもらう国家公務員はますます富裕化した=銀・銀貨の価値は低下
〈第三部〉コンスタンティヌスとキリスト教
・ミラノ勅令312年=キリスト教を宗教の一つとして公認した。
「各人は自信が良しとする宗教を信じそれに伴う祭儀に参加する完全な自由を認められる。キリスト教徒に認められたこの宗教の完全な自由は他の神を信仰する人々にも同等に認められる。
~それまで弾圧時に没収された教会の資産は返済された、同時に没収財産を競売で手に入れて所有していた者に国家による補償をした。
・宗教を大義名分に使えなければ争いは人間同士のことになり単なる利害の衝突に過ぎなくなる。ゆえに争うことが損と分かるや自然に収まる。宗教を旗印にすると問題は常に複雑化する。
・一神教では教祖の言行が最重要の教理になる、その教理は解釈し意味を説き明かす人を通すことによって一般の信者とつながってくる。
教理の存在しない多神教では専業の祭司や聖職者階級は必要としない、一神教ではこの種の人々の存在が不可欠になる。
=教会資産の必要性の一つは聖職者達を養い維持することにある。第二は恵まれない人々への慈善事業のためである。つまり、資産は教会活動で重要克不可欠な要素である。
・コンスタンティヌスは皇帝の私有財産=つまり帝国最大の地主になっていて本来は国家財産をキリスト教会に寄付した。
・さらに聖職者階級の独立・公務免除=[あらゆる公務に就かない権利]を強力に支援した。~没落していた中産階級は教会に引き寄せられていった{キリスト教会の聖職者の独身が義務づけられたのは中世には行ってから}
ニケーア公会議[325年]アリウス派とアタナシウス派N教理論争を調停。~神とその子イエスは同位か・同位でないか、つまり〈三位一体〉説=神とその子と生霊は一体であり同位であるという説と十字架上で死んだイエスは神ではありえない、とする論争。イエスは死んだが三日後に復活したのだから神になった。
~多神教であったローマでは祭司はいたが聖職者[神の意志を人間に伝えるのを仕事にする人]はなかった。
なぜコンスタンティヌスはキリスト教信仰に熱心だったのか?
キリスト教徒の数は5%で決して多数派ではなく少数派であった。
塩野の答えは、【支配の道具】である。
ローマの皇帝の任期は終身であった、皇帝のリコールは肉体の抹殺しかなかった、三世紀リコールが次々と起こり政局は不安定となった。
権力者に権力行使を託すのが人間であればリコールも人間である、この権利が人間でなく他の別の存在であったらどうであろうか、多神教ではそれは無理だが一神教ではそれは可能だ。
「各人は上に立つ者に従わなければならない、神意外には権威を認めないが現実の世界に存在する諸々の権威も神の啓示があったからこそ権威になっているのだ、だからそれに従うことは結局はこれら現世の権威の上に君臨する、至高の神に従うことになるのだ」[パウロ]
=現実世界の統治・支配の権利を君主に与えるのは人間ではなく神である、とするアイデアの有効性。
~神意を伝えるのはキリスト教では聖職者であり、上級の聖職者・司教である。
司教を見方にする方策とは?
・教会資産の保証とその増やすこと~教会の建設・資産の寄贈・聖職者の公務と納税の免除・独身者への法律上の不離の改称・司法権を司教に認めた.
「コンスタンティヌスは、現世ではキリスト教の教えでは大罪でもやらざるを得ない以上、キリスト教徒になるための洗礼をあのような行為はやろうにもやれない時にまで先延ばししたのである」
1.ローマ人の物語 14 キリストの勝利最終巻/塩野七生著
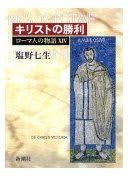
・人間の顔を表現する場合、その人の顔の現実を映すだけでなく、表現する側がどう見るかをも映すものである。どのような面構えであって欲しい、とでもいう想いの現れでもある。
・神に向ける関心の高まりに反比例して人間への関心は低下したのが帝国末期の特色の一つか、とさえ思ってしまう。
・キリスト教がローマ伝来の宗教と違ったことの一つは、専業の聖職者階級をもつ点にあった。
「偶像」はギリシャ語・ラテン語でもともと「イメージ」を意味する言葉から派生した。~「偶像崇拝」は宗教的な象徴として具象化された像を尊崇すること、特定人物を絶対的な権威として尊敬するこ意味する。
日本語で、偶像と訳されている言葉の語源はidolo、アイドルもイディオーター(馬鹿)も、この派生語である。
・偶像崇拝禁止令に続いたのが、神殿の閉鎖命令であった。 閉鎖まで来れば破壊に進むのは時間の問題である。
・退役兵=ヴェテラーヌス=ヴェテラン、三世紀からは20年の兵役期間は死文化した。
・職業の世襲制は脱税の一手段を産み出した。聖職者は免税=脱税となり、地方自治体の有力者層は雪崩を打ってキリスト教化した。
ミラノ勅令=諸宗教の信仰の自由を保証した文面になっているが、それは建前で本音はキリスト教に公式な立場を与えることであり、その後コンスタンティヌスはキリスト教優遇への道をひた走る。
ギリシャ語・ラテン語の異端はそもそも選択の意味で使われ、「塾考した末に選択した説」であって排斥まで行く「正統な解釈からはずれた説」ではなかった。それが一神教になると選択ではなく、正しいか誤りかとなる。選択ならば共生は可能だし道理さえ認めれば相手に歩み寄ることも可能だが、異端になっては共生も歩み寄りも不可能になり残るは自分が排斥されない前に相手を排斥する布かなくなってしまった。
・オリエントには、現代のイラク・イラン・アフガニスタン・パキスタンが一緒になった大国が古代のは存在していた。
・異教徒=パガヌスと言う言葉は、もともとキリスト教徒がギリシャ・ローマ教徒を
指して言った、未だに迷信を信じている田舎者、の意味をこめた蔑称であった。
・統治ないし支配の権利を君主に与えるのが「人間」ではなく「神」であるとする考え方の有効性。
・これまで国費を使ってなされてきた、教会を建造して寄贈すること・教会活動の経費の財源となる教会資産(農奴付き農耕地・工員付き手工業・店員付き商店など)の寄進や寄付は全て廃止された。[皇帝ユリアヌス]
人間を導くのが神ではなく人間を助けるのが神々の役割である多神教では、神の教えなるもの・教理が初めから存在しない。それゆえ教理を解釈する必要もないからその解釈を調整ないし統一しそれを信者に伝える人=祭司階級は必要ないし存在しない。
・投機は古代にも存在した、語源はラテン語のスペクラティオ=考えをめぐらせることの意味。
・石造りの建物は家事に強いというのは誤解で、柱・壁・梁など多くは木材が使われている。
・キリスト教の司教は自分の教区の教会資産を思い通り使える立場にあり、また司法権まで握っており、権力者である。抗争は過激さはこの権力が介在していたからだ。
宗教が現世をも支配することに反対の声を挙げたユリアヌスは、古代では唯一人一神教のもたらす弊害に気付いた人ではなかったか。古代で唯一の一神教はユダヤ教だが、選民思想を持つユダヤ教徒は自分たちの信仰に他者を引きずり込む考えからして持っていなかった。キリスト教だけが異なる考えを持つ人々への布教を重要視してきた宗教なのである。
・蛮族の精神とは日々の労苦に耐えることで生活を立てるりも他人の者を奪って生活の糧にする生き方を良しとする考え方である。
・蛮族による収奪と国家による重税の双方に攻められて農民の生活は苦しくなる一方であった。彼らは独立よりも保護を選ぶようになる。農民は農奴に変わったのであった。
この頃になって私(塩見)は、ローマの滅亡・崩壊・分解・解体とかは適切の表現ではないと思い始めている。もう存在していない、溶解が妥当と思う。ローマ人がキリスト教徒に敗れたのではなくローマ人がキリスト教徒になってしまった、のだ。
ローマ人はしねば二人の天使が両側から支えて天に昇る、と信じていた。そういう古代人にとって地獄(落ちたら責め苦しか待っていない)は新しい概念であり、恐怖であ
った。
三位一体派はこの時期以降カトリックと呼ばれるが神とその子イエスは同格であり・それに聖霊を加えての三位は一体であるとする。アリウス派はイエスは限りなく神に近いが神とは同格ではないとする。
異端の排斥
・教えを説くこと/聞くこと/集団で聞くこと/そのための場所を提供すること/それを知った司法関係者が告発しなかった者~全財産が没収され追放された。
・さらに異端者に他の人々は交渉をもってはならない。
・異端者を探し出し裁決するための特別の機関が設立された。
皇帝・グラティアヌスはこれまで兼務してきた最高神祇官の就任を拒否した。
・女祭司制度を消滅させた。
・神殿に維持費を出さず、神殿の経費を没収した。
・神殿は閉鎖された。
・神像は破壊された。
・神々に捧げられてきたオリンピックも幕を閉じた(393年)
388年テオドシウスはキリスト教をローマ帝国の国教にするよう元老院に提案し承認された。
・時代が過ぎるにつれて聖人の数も増え近現代になると寝取られ男までが守護聖人をもつと言う有様で、一年に余る聖人数となり祝日をはずれた聖人の祝祭日=万聖節=11.1という。
395年、テオドシウスは息子二人に帝国を二分し世を去った。
東ローマ帝国・西ローマ帝国とそれぞれ独立した無関係な二つの国になった。
ローマ人の物語完結である。
メモ紛失・ブログ作成ミスなどで再読、入力のやり直しと多くの時間を費やした最終巻だった。
NHKでフランス世界遺産縦断の旅があった。
「中世の面影が残る」とのコメントがたくさん流れたが、古代ローマの影響についてはほとんど触れられず、であった。
プロバンスについては、そのことに触れずには語ることはできないのにとつくずく思った。そもそもプロバンスはローマの属州(=プロバンス)の意味なのだから。
古代ローマは、秦と同じ時代であり、その同時代に秦では万里の長城が造られ、ローマでは街道・水道が造られた。
長城も街道も侵略を防ぐ目的で造られた。
それだけを見ると長城は非生産的、街道は生産的のように見えるが、
それは、中国では秦と匹敵する国が他にもたくさんあってそれらをうち破ることなしには秦の生きる道はなかった、
ローマでは、城壁に囲まれた都市国家=ポリスという形・比較的狭く国が作られたことなどが関係しているのではないだろうか。
シルクロードはまだできていないが、ローマとオリエント(ペルシャ)そして秦とは既に交流があったという。
始皇帝の兵馬俑にはその名残が残っているという。
鐙はローマでも秦でもまだ発明されていなかったらしいが、
鞍は秦では使われていたという。
ローマと秦は、今日のヨーロッパとアジアの源流であり、
その精神は今も息づいているように感じられる。
また、ローマは東方には、現代のイラク・イラン・アフガニスタン・パキスタンが一緒になった大国が存在していたこともローマの生成と発展にとっては大きな影響があった。中国にとっても北方の騎馬民族の存在は大きいが、ローマにとっては大国であるパルティア=オリエントの存在は、それとは計り知れない位置を占めていた、つまり戦争はありながらも交易はするが、お互いの地を占領することは現実的ではなかった。
ローマの全盛時は、キリストが生まれた時代でもあった。
唯一神を絶対視する一神教=キリスト教が、多神教の古代ローマ溶解させ、時代は中世へと入る。
中国もおそらく古代は多神教であったのだろう。その後、仏教・道教・儒教などの宗教が中国社会の中でも生まれるが、それらは多神教であって、一神教は起こらなかった。
中国・アジアでは一神教が生まれず、支配的宗教にならなかったのはどうしてであろうか。
これらのことは現代にも影響しているのでは無いだろうか?
キリスト教・ユダヤ教・イスラム教という一神教はたしかに、広い意味でのオリエントで生まれたのだが。
イスラム教は、今日ではアジアで広く信仰されているがインド・中国では支配的ではない。
一神教の世界では、靖国問題は理解が難しいだろう。
靖国問題は、A級戦犯が合祀されていることだけが問題・重要なのではない。
戦争で死んだ人間が神として、祀られ・信仰されているのだ。
多神教のローマでは、皇帝の何人かは、その死後、神として祀られているが、
キリスト教の世界ではそうしたことはない。
ただ、その後、信仰の対象となった聖人は無尽蔵に造られた。
古代は多神教であった。
ローマ[ヨーロッパ]は一神教のキリスト教に溶解(塩野)したが、秦・アジアはその一部はイスラム教になったが多くは多神教のままである。
一神教と多神教の共存はあり得るのだろうか。
ヘーゲルはアジアでは生まれようがない。
今日のアジアは、共通性より多様的な感じがする。
だが紛れもなくアジアには一体性・同一性があるように感じられる。
ローマは今なお多くのことを私に語りかける。
塩野さんの後書きはない。
「それは(五世紀)、皇帝の息女が蛮族の長に嫁ぐ世紀でもあった。」
で、この長い物語は閉じられた。
1.図解雑学・ローマ帝国/坂本浩
ざっと流れを整理しようとしたのだが、期待したのが無理だった。
2.中国文化故事物語/王矛(ワン・モウ)・王敏(ワン・ミン)
著者の博学はすごいのだが諸説の紹介は専門的で煩雑な感じだ。それはさらっとながして良いのでは。「黄色の信仰」「苗字」「観音様」「徐福は神武天皇か」など興味深話題がたくさん。
3.人々のかたち/塩野七生・雑誌フォーサイトに連載された映画エッセイ集
4.『映画の名画座』/橋本勝/社会思想社・現代教養文庫~259本だてイラスト・ロードショウ
=イラストが面白く、たくさんの映画を極短く紹介・絶版で古本史上でかなり高いらしいがカバーが無く廃棄した。
2.ルネサンスとは何であったのか/塩野七生ルネサンス著作集1

写真は表紙に使われたミケランジェロの「アダムの創造」
・見たい、知りたい、わかりたいという欲望の爆発が後世の人々によってルネサンスと名付けられることになる、精神運動の本質でした。
・宗教には教典をもつ宗教か、それをもたない宗教かの違いがある。教典をもつ宗教はユダヤ教、キリスト教、イスラム教でいずれもが一神教。教典をもたない方の代表はギリシャ人やローマ人が信じていた宗教でこちらは多神教。 独立した聖職者階級をもつかもたないかの違い、聖職者とは教典を解釈し一般の信者に説き聞かせる、ギリシャ・ローマには聖職者階級は存在する必要も無かったし、存在しなかった。
・中世は土地を資産とする経済構造下にありその土地を所有する封建領主が主導権をふるっていた時代、これに対し、土地は持っていないが頭脳は持っている人々が集まって作ったのが都市国家。頭脳宗団であった都市に住む住民達の一人一人の生産性は高くルネサンス盛期では封建領主や修道院の所有地で働く人の40倍にもなっていた。フレンツェ・ヴェネツィアの経済力の方がフランスやイギリスやトルコを完全に凌駕していた。
思考と表現は同一線上にあってしかも相互に働きかける関係にある。明晰で論理的に話しかけるようになれば頭脳の方も明晰で論理的になる。~自分の目で見、自分の頭で考え、自分の言葉で話し書くルネサンス、神を通して見、神の意に添って考え、聖書の言葉で話し書いた中世。
現代イタリア語の基本は14~16世紀フレンツェのダンテからマキャヴェッリ等によって完成した。イタリア語では古文が存在しない、そのまま現代に通じる。
ヴェネツィアではペストの潜伏期間とされている40日を過ぎた後でないと入港させなかった。検疫という言葉はヴェネツィアの方言40日間の意味から来ている。
デカメロンとは10日の物語の意味だが、10をあらわすギリシャ語のデカと日をあらわすhemeraの合成語。
政治とは、行き過ぎを是正することで経済の繁栄を長続きさせる人智、と言い換えても良い。
レオナルド・ダ・ヴィンチは見ることのできないものを論ずるのは意味がないと言ってプラトン・アカデミーには参加しなかった。
宗教とは信ずることであり、哲学は疑うことである。哲学では原理の樹立と破壊をくり返し行うことによって成される。
マキャヴェッリは考えた。
千年以上もの長きにわたって指導理念であったキリスト教によっても人間性は改善されなかったのだから、普遍であるのが人間性と考えるべきだと。
・十字軍とはそもそも人口が増加したヨーロッパに増えた人口を養っていけなくなってパレスチナに繰り出したのが発端。
・異なる考えも認めたのがルネサンスならば認めることを拒否したのが反動宗教改革=カトリック教会内部に生まれた危機意識の所産で異端裁判嵐が吹き荒れる時代になった。主役はスペイン人となった。
・ヴェネツィアでは、利益率の高い胡椒を初めとする香味料を運ぶ大型ガレー商船は個人の所有は許されず国家所有であった。
・ヴェネツィアでは、プラトンアカデミーのような古典の研究機関はなかったが、古典を対訳までつけて、文庫本で出版した。
ルネサンスの遺産とは、
①芸術品
②精神の独立に対する強烈な執着=自分で見、自分で考え、自分の言葉で話し表現し他者に伝える。
③二元論ではなく一元論的考え方。
~キリスト教では神は善であり、悪の方は悪魔としか言いようがない。善と悪・精神と肉体・神と悪魔というように元は二つに分かれている。
~古代のギリシャ・ローマでは神さえも善と悪の双方を持つ存在であり、まして人間では自分の内に善と悪の双方を持つ。古代を復興したルネサンスでは当然ながら人間が中心にならざるをえない。悪もまた我にあり、なのだから自己コントロールを求められる、精神も強靱でなければならない。
《とにかく一神教の害毒は計り知れない。今日のアメリカは一つの一神教と言える、世界の唯一超大国の善なのだから。金日成もしかり、スターリン主義の共産主義も、毛沢東・ヒトラーもそうであった。唯一絶対を掲げるものを一神教とすると少し世の中見えてくる。全てをこれで割るのは乱暴だが。仏教は一神教ではないが、他力本願=絶対的な仏に導かれる、は一神教につながるかもしれない。
絶対神にあこがれ・信仰する人の精神はどこから生じるのだろうか?
古代ローマの次はルネサンスか中国かと思っていたが、間をおこう。》
1.紅衛兵の時代/張承志著/岩波新書
わが友マキアヴェッリ―フィレンツェ存亡/塩野七生著
・マキアヴェッリは1469.5.3生まれ。

・15世紀後半のイタリアはミラノ公国、ヴェネツィア共和国、フィレンツェ共和国、法王庁国家、ナポリ王国が列強として連なる大国であった。
・『君主論』のモデルは、チューザレ・ボルジアであった。
・16世紀初頭の都市国家フィレンツェの人口は約50万人であった。
・プラトンやアリストテレスの時代の政治[ポリティカ]は、倫理[エティカ]と同じことであった。
・マキアヴェッリが指導者に求めた三大要素は
①ヴィルトゥ=力量・才能・器量、~元々の意味は生命力が最上の状態で発揮され た時の人間
②フォルトゥーナ=運・好運、
③ネチェシタ=時代の要求に合致すること
・真のルネサンス魂はレオナルド・ダ・ヴィンチに体現されている。
・もともとその面の素質があったからその結晶である作品が生まれるのであって、環境はその素質を自覚させる役割しかもたない。
・マキアヴェッリ作喜劇『マンドラーゴラ』
・ある制度を維持したいと思えば、時にはその制度の基本精神に反することもあえてする勇気をもたねばならぬ~マキアヴェッリ
・ローマ法王が招集して成立する同盟は、普通、神聖同盟と呼ばれる。
・『君主論』:時代が変われば統治の方式もそれに応じて変わる必要がある。1513年。
・『政略理論』:共和制を維持したければ時には共和制の精神の反することもあえてする勇気をもたねば、共和制そのものをつぶしてしまう結果になる。1516年。
・『戦略論』:市民兵制度確立の必要性を徹底して論じる。1521年。
・1527年ドイツ・スペイン連合軍はローマ(バチカン)を陥落させる。現代ローマにバロック建築が多いのは、この時の略奪でルネサンス建築の8割が破壊された。ローマの人口は9万から3万に減った。
~フィレンツェはメディチ家が追放され、共和制に復帰した。マキアヴェッリは書記官に立候補したが落選した。その10日後、マキアヴェッリは病気で死んだ。58歳。
~1530年、フィレンツェ共和国は神聖ローマ帝国の手によって滅亡した。
以降、専制君主政が始まり実質的にはスペインの支配下に入り、反動宗教改革野荒らしが吹きまくり、ルネサンス時代は終焉した。
~1559年、マキアヴェッリの全著作は良きキリスト教徒には不適当なものとされ、禁書に指定された。
最後に「これを読み終えられた今、あなたにとってもこの男は、「わが友」になったでしょうか」と書いて塩野はこの本を終えたが、私のは今ひとつマキアヴェッリが魅力ある人物には感じられなかった。
・マキアヴェッリがルネサンスのまさに時代の渦中にいて、ミケランジェロに製作代金を届けたり、政治論だけでなく演劇の脚本まで書いていたことは知らなかった。
また、フィレンツェの大統領府の書記官(ノンキャリア)=課長クラスとして外国と交渉したりしたことも知らなかった。
覚えていない/佐野洋子

楽天のポイントの締め切りが近づいたので、久しぶりに新本を買った。
1990年頃の雑多のエッセイ集だが、ちっとも古くさくない。
佐野さんの本はいつも楽しい、それでいてつらくもある。
気に入った文。
【立てば芍薬座れば牡丹、歩く姿は百合の花に人格は必要か。バラはバラだからバラなのである。
年老いて自分の役割が終わると、男達の言語も終わるのである。
今や、私の生きる目的はいかなるババアになるかということに尽きる。
私は読むはじから忘れていくので、いくら本を読んでも何の役にも立たない。読んでいる間だけ面白いのであって、読み終えるとすっかり忘れている。】
以下余談
12月に入って剣道の道場に再び通い出した。
自分では健康と暇つぶしで行っているのに、脚が曲がっているだの、腕がどうのと人の欠点を指摘し、教えたがる人がいるのは本当にヘキヘキだ。
好きにさせろっての、いかんせんこの世界は、マイナーで、保守的で古い。
でも30秒も持たないで「参りました」と休んでまた稽古。
大汗をかくほどの一生懸命にはならない。
同じく、12月に入って英会話の勉強を始めた。
もっぱらリスニングだ。
ネットは大変便利で、外国語のラジオが聞ける。
重いカセットレコーダーに録音して通勤時に聞いている。
携帯CD、MDもデジタルレコーダーも持っていないので。
VOAのスペシャルイングレッシュは初心者向けにゆっくりしゃべる。
聞き取りはできないが耳ざわりはいい。
ゆっくり過ぎる時はスピードをちょっと速めて。
だが、女性アナは、あの過剰な英語らしい発音でなんともイヤらしい。
ラジオジャパン、ABC、CNN、などいずれも早過ぎる、を通り越して聞き難い、いやそれも通り過ぎてこれはもう騒音である。
NHKのラジオジャパンは口がマイクに近すぎて息継ぎの音がとにかくうるさい。
これは日本人アナウンサーがネイティブらしく早くしゃべるために、小声でしゃべるためだと思う。
日本人を使うのはどうしてなのだろう。
VOAは文字化もされているので、翻訳ソフトで翻訳するが、日本語に全くなっていない。わからない単語の意味を調べるには一括翻訳が便利だが。
新しいソフトはもっと良くなっているのかもしれない。
さて、いつまで続くであろうか。
そのため、しばらく読書は休止。

/塩野七生著
〈第一部〉ディオクレティアヌスの時代(294~305)
・帝国
エンパイアーの語源~インペリウム=支配する、統治する、命令する、を意味する動詞から生まれる。政体(共和制・帝政)のは関係なく、自分たち以外の国や民族まで支配下に置く覇権国家であれば「帝国」である。
ディオクレティアヌスの統治期間(20年)蛮族の侵入は無かった。
蛮族の方にはローマ化する気もなくなったし、ローマもローマ的でなくなった。
[以前は敗者は敗北の後は喜んでローマ化を喜んだ]
ローマ帝国は「元首政」から「絶対君主制」への第一歩を踏み出した。
皇帝は「市民中の第一人者」から「支配する者」となり、一般人からは皇帝は仰ぎ見る存在となった。~それまで私邸の召使いが使う言葉であった「御主人様」は、市民が皇帝に対して使う言葉になった。市民中の第一人者は支配者に、市民は臣下に変わった。皇帝の服装は宝石をちりばめたものに変わった。
・権力とは、それを持つ者を堕落させるが、持たない者も堕落させる。
四頭政は官僚的ヒエラルキーを生んだ
東方―正帝ディオクレティアヌス(首都ニコメディア)―副帝ガレリウス(首都シルミウム)
西方―――正帝マクシミアヌス(首都ミラノ)――――――――副帝コンスタンティヌス(首都トリアー)
地方組織は、管轄区・県となりその官僚の任命権も皇帝が握った。
・税制も変わった
アウグストゥス時代は、国家は税収の範囲内でしか手がけなかった。
ディオクレティアヌス時代になると、国家に必要な経費が課税された。
・ほとんど全ての職業に世襲制が布かれた。
【増田総括。ディオクレティアヌスは、それまでの軍人割拠を統一し蛮族侵入を防いだが、古代ローマのローマらしさのほとんどがなくなり、中世の絶対君主制を準備した。】
〈第二部〉コンスタンティヌス時代(306~337)
兵站=ローマでは兵站はars=英語ではartつまり技(わざ)、すなわち人間がなすべき全てのことを意味したが、以降兵站はロジスティクス=輸送が使われる。
・コンスタンティヌスは元老院議員を富裕度に応じて四段階に分けた。
・コンスタンティヌスは新しき首都[ビザンティウム]、新しき政体、新しき宗教による、新生ローマ帝国を実現しようとした。
・元老院の始まり~数多くの部族の連合体であった王政時代のローマで300人にもなった部族長達を集め王への助言機関として設置された[紀元753年]。
紀元509年に共和制に移行。
・「金本位制」を導入~金貨で給料をもらう国家公務員はますます富裕化した=銀・銀貨の価値は低下
〈第三部〉コンスタンティヌスとキリスト教
・ミラノ勅令312年=キリスト教を宗教の一つとして公認した。
「各人は自信が良しとする宗教を信じそれに伴う祭儀に参加する完全な自由を認められる。キリスト教徒に認められたこの宗教の完全な自由は他の神を信仰する人々にも同等に認められる。
~それまで弾圧時に没収された教会の資産は返済された、同時に没収財産を競売で手に入れて所有していた者に国家による補償をした。
・宗教を大義名分に使えなければ争いは人間同士のことになり単なる利害の衝突に過ぎなくなる。ゆえに争うことが損と分かるや自然に収まる。宗教を旗印にすると問題は常に複雑化する。
・一神教では教祖の言行が最重要の教理になる、その教理は解釈し意味を説き明かす人を通すことによって一般の信者とつながってくる。
教理の存在しない多神教では専業の祭司や聖職者階級は必要としない、一神教ではこの種の人々の存在が不可欠になる。
=教会資産の必要性の一つは聖職者達を養い維持することにある。第二は恵まれない人々への慈善事業のためである。つまり、資産は教会活動で重要克不可欠な要素である。
・コンスタンティヌスは皇帝の私有財産=つまり帝国最大の地主になっていて本来は国家財産をキリスト教会に寄付した。
・さらに聖職者階級の独立・公務免除=[あらゆる公務に就かない権利]を強力に支援した。~没落していた中産階級は教会に引き寄せられていった{キリスト教会の聖職者の独身が義務づけられたのは中世には行ってから}
ニケーア公会議[325年]アリウス派とアタナシウス派N教理論争を調停。~神とその子イエスは同位か・同位でないか、つまり〈三位一体〉説=神とその子と生霊は一体であり同位であるという説と十字架上で死んだイエスは神ではありえない、とする論争。イエスは死んだが三日後に復活したのだから神になった。
~多神教であったローマでは祭司はいたが聖職者[神の意志を人間に伝えるのを仕事にする人]はなかった。
なぜコンスタンティヌスはキリスト教信仰に熱心だったのか?
キリスト教徒の数は5%で決して多数派ではなく少数派であった。
塩野の答えは、【支配の道具】である。
ローマの皇帝の任期は終身であった、皇帝のリコールは肉体の抹殺しかなかった、三世紀リコールが次々と起こり政局は不安定となった。
権力者に権力行使を託すのが人間であればリコールも人間である、この権利が人間でなく他の別の存在であったらどうであろうか、多神教ではそれは無理だが一神教ではそれは可能だ。
「各人は上に立つ者に従わなければならない、神意外には権威を認めないが現実の世界に存在する諸々の権威も神の啓示があったからこそ権威になっているのだ、だからそれに従うことは結局はこれら現世の権威の上に君臨する、至高の神に従うことになるのだ」[パウロ]
=現実世界の統治・支配の権利を君主に与えるのは人間ではなく神である、とするアイデアの有効性。
~神意を伝えるのはキリスト教では聖職者であり、上級の聖職者・司教である。
司教を見方にする方策とは?
・教会資産の保証とその増やすこと~教会の建設・資産の寄贈・聖職者の公務と納税の免除・独身者への法律上の不離の改称・司法権を司教に認めた.
「コンスタンティヌスは、現世ではキリスト教の教えでは大罪でもやらざるを得ない以上、キリスト教徒になるための洗礼をあのような行為はやろうにもやれない時にまで先延ばししたのである」
1.ローマ人の物語 14 キリストの勝利最終巻/塩野七生著
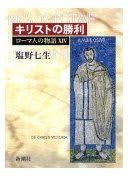
・人間の顔を表現する場合、その人の顔の現実を映すだけでなく、表現する側がどう見るかをも映すものである。どのような面構えであって欲しい、とでもいう想いの現れでもある。
・神に向ける関心の高まりに反比例して人間への関心は低下したのが帝国末期の特色の一つか、とさえ思ってしまう。
・キリスト教がローマ伝来の宗教と違ったことの一つは、専業の聖職者階級をもつ点にあった。
「偶像」はギリシャ語・ラテン語でもともと「イメージ」を意味する言葉から派生した。~「偶像崇拝」は宗教的な象徴として具象化された像を尊崇すること、特定人物を絶対的な権威として尊敬するこ意味する。
日本語で、偶像と訳されている言葉の語源はidolo、アイドルもイディオーター(馬鹿)も、この派生語である。
・偶像崇拝禁止令に続いたのが、神殿の閉鎖命令であった。 閉鎖まで来れば破壊に進むのは時間の問題である。
・退役兵=ヴェテラーヌス=ヴェテラン、三世紀からは20年の兵役期間は死文化した。
・職業の世襲制は脱税の一手段を産み出した。聖職者は免税=脱税となり、地方自治体の有力者層は雪崩を打ってキリスト教化した。
ミラノ勅令=諸宗教の信仰の自由を保証した文面になっているが、それは建前で本音はキリスト教に公式な立場を与えることであり、その後コンスタンティヌスはキリスト教優遇への道をひた走る。
ギリシャ語・ラテン語の異端はそもそも選択の意味で使われ、「塾考した末に選択した説」であって排斥まで行く「正統な解釈からはずれた説」ではなかった。それが一神教になると選択ではなく、正しいか誤りかとなる。選択ならば共生は可能だし道理さえ認めれば相手に歩み寄ることも可能だが、異端になっては共生も歩み寄りも不可能になり残るは自分が排斥されない前に相手を排斥する布かなくなってしまった。
・オリエントには、現代のイラク・イラン・アフガニスタン・パキスタンが一緒になった大国が古代のは存在していた。
・異教徒=パガヌスと言う言葉は、もともとキリスト教徒がギリシャ・ローマ教徒を
指して言った、未だに迷信を信じている田舎者、の意味をこめた蔑称であった。
・統治ないし支配の権利を君主に与えるのが「人間」ではなく「神」であるとする考え方の有効性。
・これまで国費を使ってなされてきた、教会を建造して寄贈すること・教会活動の経費の財源となる教会資産(農奴付き農耕地・工員付き手工業・店員付き商店など)の寄進や寄付は全て廃止された。[皇帝ユリアヌス]
人間を導くのが神ではなく人間を助けるのが神々の役割である多神教では、神の教えなるもの・教理が初めから存在しない。それゆえ教理を解釈する必要もないからその解釈を調整ないし統一しそれを信者に伝える人=祭司階級は必要ないし存在しない。
・投機は古代にも存在した、語源はラテン語のスペクラティオ=考えをめぐらせることの意味。
・石造りの建物は家事に強いというのは誤解で、柱・壁・梁など多くは木材が使われている。
・キリスト教の司教は自分の教区の教会資産を思い通り使える立場にあり、また司法権まで握っており、権力者である。抗争は過激さはこの権力が介在していたからだ。
宗教が現世をも支配することに反対の声を挙げたユリアヌスは、古代では唯一人一神教のもたらす弊害に気付いた人ではなかったか。古代で唯一の一神教はユダヤ教だが、選民思想を持つユダヤ教徒は自分たちの信仰に他者を引きずり込む考えからして持っていなかった。キリスト教だけが異なる考えを持つ人々への布教を重要視してきた宗教なのである。
・蛮族の精神とは日々の労苦に耐えることで生活を立てるりも他人の者を奪って生活の糧にする生き方を良しとする考え方である。
・蛮族による収奪と国家による重税の双方に攻められて農民の生活は苦しくなる一方であった。彼らは独立よりも保護を選ぶようになる。農民は農奴に変わったのであった。
この頃になって私(塩見)は、ローマの滅亡・崩壊・分解・解体とかは適切の表現ではないと思い始めている。もう存在していない、溶解が妥当と思う。ローマ人がキリスト教徒に敗れたのではなくローマ人がキリスト教徒になってしまった、のだ。
ローマ人はしねば二人の天使が両側から支えて天に昇る、と信じていた。そういう古代人にとって地獄(落ちたら責め苦しか待っていない)は新しい概念であり、恐怖であ
った。
三位一体派はこの時期以降カトリックと呼ばれるが神とその子イエスは同格であり・それに聖霊を加えての三位は一体であるとする。アリウス派はイエスは限りなく神に近いが神とは同格ではないとする。
異端の排斥
・教えを説くこと/聞くこと/集団で聞くこと/そのための場所を提供すること/それを知った司法関係者が告発しなかった者~全財産が没収され追放された。
・さらに異端者に他の人々は交渉をもってはならない。
・異端者を探し出し裁決するための特別の機関が設立された。
皇帝・グラティアヌスはこれまで兼務してきた最高神祇官の就任を拒否した。
・女祭司制度を消滅させた。
・神殿に維持費を出さず、神殿の経費を没収した。
・神殿は閉鎖された。
・神像は破壊された。
・神々に捧げられてきたオリンピックも幕を閉じた(393年)
388年テオドシウスはキリスト教をローマ帝国の国教にするよう元老院に提案し承認された。
・時代が過ぎるにつれて聖人の数も増え近現代になると寝取られ男までが守護聖人をもつと言う有様で、一年に余る聖人数となり祝日をはずれた聖人の祝祭日=万聖節=11.1という。
395年、テオドシウスは息子二人に帝国を二分し世を去った。
東ローマ帝国・西ローマ帝国とそれぞれ独立した無関係な二つの国になった。
ローマ人の物語完結である。
メモ紛失・ブログ作成ミスなどで再読、入力のやり直しと多くの時間を費やした最終巻だった。
NHKでフランス世界遺産縦断の旅があった。
「中世の面影が残る」とのコメントがたくさん流れたが、古代ローマの影響についてはほとんど触れられず、であった。
プロバンスについては、そのことに触れずには語ることはできないのにとつくずく思った。そもそもプロバンスはローマの属州(=プロバンス)の意味なのだから。
古代ローマは、秦と同じ時代であり、その同時代に秦では万里の長城が造られ、ローマでは街道・水道が造られた。
長城も街道も侵略を防ぐ目的で造られた。
それだけを見ると長城は非生産的、街道は生産的のように見えるが、
それは、中国では秦と匹敵する国が他にもたくさんあってそれらをうち破ることなしには秦の生きる道はなかった、
ローマでは、城壁に囲まれた都市国家=ポリスという形・比較的狭く国が作られたことなどが関係しているのではないだろうか。
シルクロードはまだできていないが、ローマとオリエント(ペルシャ)そして秦とは既に交流があったという。
始皇帝の兵馬俑にはその名残が残っているという。
鐙はローマでも秦でもまだ発明されていなかったらしいが、
鞍は秦では使われていたという。
ローマと秦は、今日のヨーロッパとアジアの源流であり、
その精神は今も息づいているように感じられる。
また、ローマは東方には、現代のイラク・イラン・アフガニスタン・パキスタンが一緒になった大国が存在していたこともローマの生成と発展にとっては大きな影響があった。中国にとっても北方の騎馬民族の存在は大きいが、ローマにとっては大国であるパルティア=オリエントの存在は、それとは計り知れない位置を占めていた、つまり戦争はありながらも交易はするが、お互いの地を占領することは現実的ではなかった。
ローマの全盛時は、キリストが生まれた時代でもあった。
唯一神を絶対視する一神教=キリスト教が、多神教の古代ローマ溶解させ、時代は中世へと入る。
中国もおそらく古代は多神教であったのだろう。その後、仏教・道教・儒教などの宗教が中国社会の中でも生まれるが、それらは多神教であって、一神教は起こらなかった。
中国・アジアでは一神教が生まれず、支配的宗教にならなかったのはどうしてであろうか。
これらのことは現代にも影響しているのでは無いだろうか?
キリスト教・ユダヤ教・イスラム教という一神教はたしかに、広い意味でのオリエントで生まれたのだが。
イスラム教は、今日ではアジアで広く信仰されているがインド・中国では支配的ではない。
一神教の世界では、靖国問題は理解が難しいだろう。
靖国問題は、A級戦犯が合祀されていることだけが問題・重要なのではない。
戦争で死んだ人間が神として、祀られ・信仰されているのだ。
多神教のローマでは、皇帝の何人かは、その死後、神として祀られているが、
キリスト教の世界ではそうしたことはない。
ただ、その後、信仰の対象となった聖人は無尽蔵に造られた。
古代は多神教であった。
ローマ[ヨーロッパ]は一神教のキリスト教に溶解(塩野)したが、秦・アジアはその一部はイスラム教になったが多くは多神教のままである。
一神教と多神教の共存はあり得るのだろうか。
ヘーゲルはアジアでは生まれようがない。
今日のアジアは、共通性より多様的な感じがする。
だが紛れもなくアジアには一体性・同一性があるように感じられる。
ローマは今なお多くのことを私に語りかける。
塩野さんの後書きはない。
「それは(五世紀)、皇帝の息女が蛮族の長に嫁ぐ世紀でもあった。」
で、この長い物語は閉じられた。
1.図解雑学・ローマ帝国/坂本浩
ざっと流れを整理しようとしたのだが、期待したのが無理だった。
2.中国文化故事物語/王矛(ワン・モウ)・王敏(ワン・ミン)
著者の博学はすごいのだが諸説の紹介は専門的で煩雑な感じだ。それはさらっとながして良いのでは。「黄色の信仰」「苗字」「観音様」「徐福は神武天皇か」など興味深話題がたくさん。
3.人々のかたち/塩野七生・雑誌フォーサイトに連載された映画エッセイ集
4.『映画の名画座』/橋本勝/社会思想社・現代教養文庫~259本だてイラスト・ロードショウ
=イラストが面白く、たくさんの映画を極短く紹介・絶版で古本史上でかなり高いらしいがカバーが無く廃棄した。
2.ルネサンスとは何であったのか/塩野七生ルネサンス著作集1

写真は表紙に使われたミケランジェロの「アダムの創造」
・見たい、知りたい、わかりたいという欲望の爆発が後世の人々によってルネサンスと名付けられることになる、精神運動の本質でした。
・宗教には教典をもつ宗教か、それをもたない宗教かの違いがある。教典をもつ宗教はユダヤ教、キリスト教、イスラム教でいずれもが一神教。教典をもたない方の代表はギリシャ人やローマ人が信じていた宗教でこちらは多神教。 独立した聖職者階級をもつかもたないかの違い、聖職者とは教典を解釈し一般の信者に説き聞かせる、ギリシャ・ローマには聖職者階級は存在する必要も無かったし、存在しなかった。
・中世は土地を資産とする経済構造下にありその土地を所有する封建領主が主導権をふるっていた時代、これに対し、土地は持っていないが頭脳は持っている人々が集まって作ったのが都市国家。頭脳宗団であった都市に住む住民達の一人一人の生産性は高くルネサンス盛期では封建領主や修道院の所有地で働く人の40倍にもなっていた。フレンツェ・ヴェネツィアの経済力の方がフランスやイギリスやトルコを完全に凌駕していた。
思考と表現は同一線上にあってしかも相互に働きかける関係にある。明晰で論理的に話しかけるようになれば頭脳の方も明晰で論理的になる。~自分の目で見、自分の頭で考え、自分の言葉で話し書くルネサンス、神を通して見、神の意に添って考え、聖書の言葉で話し書いた中世。
現代イタリア語の基本は14~16世紀フレンツェのダンテからマキャヴェッリ等によって完成した。イタリア語では古文が存在しない、そのまま現代に通じる。
ヴェネツィアではペストの潜伏期間とされている40日を過ぎた後でないと入港させなかった。検疫という言葉はヴェネツィアの方言40日間の意味から来ている。
デカメロンとは10日の物語の意味だが、10をあらわすギリシャ語のデカと日をあらわすhemeraの合成語。
政治とは、行き過ぎを是正することで経済の繁栄を長続きさせる人智、と言い換えても良い。
レオナルド・ダ・ヴィンチは見ることのできないものを論ずるのは意味がないと言ってプラトン・アカデミーには参加しなかった。
宗教とは信ずることであり、哲学は疑うことである。哲学では原理の樹立と破壊をくり返し行うことによって成される。
マキャヴェッリは考えた。
千年以上もの長きにわたって指導理念であったキリスト教によっても人間性は改善されなかったのだから、普遍であるのが人間性と考えるべきだと。
・十字軍とはそもそも人口が増加したヨーロッパに増えた人口を養っていけなくなってパレスチナに繰り出したのが発端。
・異なる考えも認めたのがルネサンスならば認めることを拒否したのが反動宗教改革=カトリック教会内部に生まれた危機意識の所産で異端裁判嵐が吹き荒れる時代になった。主役はスペイン人となった。
・ヴェネツィアでは、利益率の高い胡椒を初めとする香味料を運ぶ大型ガレー商船は個人の所有は許されず国家所有であった。
・ヴェネツィアでは、プラトンアカデミーのような古典の研究機関はなかったが、古典を対訳までつけて、文庫本で出版した。
ルネサンスの遺産とは、
①芸術品
②精神の独立に対する強烈な執着=自分で見、自分で考え、自分の言葉で話し表現し他者に伝える。
③二元論ではなく一元論的考え方。
~キリスト教では神は善であり、悪の方は悪魔としか言いようがない。善と悪・精神と肉体・神と悪魔というように元は二つに分かれている。
~古代のギリシャ・ローマでは神さえも善と悪の双方を持つ存在であり、まして人間では自分の内に善と悪の双方を持つ。古代を復興したルネサンスでは当然ながら人間が中心にならざるをえない。悪もまた我にあり、なのだから自己コントロールを求められる、精神も強靱でなければならない。
《とにかく一神教の害毒は計り知れない。今日のアメリカは一つの一神教と言える、世界の唯一超大国の善なのだから。金日成もしかり、スターリン主義の共産主義も、毛沢東・ヒトラーもそうであった。唯一絶対を掲げるものを一神教とすると少し世の中見えてくる。全てをこれで割るのは乱暴だが。仏教は一神教ではないが、他力本願=絶対的な仏に導かれる、は一神教につながるかもしれない。
絶対神にあこがれ・信仰する人の精神はどこから生じるのだろうか?
古代ローマの次はルネサンスか中国かと思っていたが、間をおこう。》
1.紅衛兵の時代/張承志著/岩波新書
わが友マキアヴェッリ―フィレンツェ存亡/塩野七生著
・マキアヴェッリは1469.5.3生まれ。

・15世紀後半のイタリアはミラノ公国、ヴェネツィア共和国、フィレンツェ共和国、法王庁国家、ナポリ王国が列強として連なる大国であった。
・『君主論』のモデルは、チューザレ・ボルジアであった。
・16世紀初頭の都市国家フィレンツェの人口は約50万人であった。
・プラトンやアリストテレスの時代の政治[ポリティカ]は、倫理[エティカ]と同じことであった。
・マキアヴェッリが指導者に求めた三大要素は
①ヴィルトゥ=力量・才能・器量、~元々の意味は生命力が最上の状態で発揮され た時の人間
②フォルトゥーナ=運・好運、
③ネチェシタ=時代の要求に合致すること
・真のルネサンス魂はレオナルド・ダ・ヴィンチに体現されている。
・もともとその面の素質があったからその結晶である作品が生まれるのであって、環境はその素質を自覚させる役割しかもたない。
・マキアヴェッリ作喜劇『マンドラーゴラ』
・ある制度を維持したいと思えば、時にはその制度の基本精神に反することもあえてする勇気をもたねばならぬ~マキアヴェッリ
・ローマ法王が招集して成立する同盟は、普通、神聖同盟と呼ばれる。
・『君主論』:時代が変われば統治の方式もそれに応じて変わる必要がある。1513年。
・『政略理論』:共和制を維持したければ時には共和制の精神の反することもあえてする勇気をもたねば、共和制そのものをつぶしてしまう結果になる。1516年。
・『戦略論』:市民兵制度確立の必要性を徹底して論じる。1521年。
・1527年ドイツ・スペイン連合軍はローマ(バチカン)を陥落させる。現代ローマにバロック建築が多いのは、この時の略奪でルネサンス建築の8割が破壊された。ローマの人口は9万から3万に減った。
~フィレンツェはメディチ家が追放され、共和制に復帰した。マキアヴェッリは書記官に立候補したが落選した。その10日後、マキアヴェッリは病気で死んだ。58歳。
~1530年、フィレンツェ共和国は神聖ローマ帝国の手によって滅亡した。
以降、専制君主政が始まり実質的にはスペインの支配下に入り、反動宗教改革野荒らしが吹きまくり、ルネサンス時代は終焉した。
~1559年、マキアヴェッリの全著作は良きキリスト教徒には不適当なものとされ、禁書に指定された。
最後に「これを読み終えられた今、あなたにとってもこの男は、「わが友」になったでしょうか」と書いて塩野はこの本を終えたが、私のは今ひとつマキアヴェッリが魅力ある人物には感じられなかった。
・マキアヴェッリがルネサンスのまさに時代の渦中にいて、ミケランジェロに製作代金を届けたり、政治論だけでなく演劇の脚本まで書いていたことは知らなかった。
また、フィレンツェの大統領府の書記官(ノンキャリア)=課長クラスとして外国と交渉したりしたことも知らなかった。
覚えていない/佐野洋子

楽天のポイントの締め切りが近づいたので、久しぶりに新本を買った。
1990年頃の雑多のエッセイ集だが、ちっとも古くさくない。
佐野さんの本はいつも楽しい、それでいてつらくもある。
気に入った文。
【立てば芍薬座れば牡丹、歩く姿は百合の花に人格は必要か。バラはバラだからバラなのである。
年老いて自分の役割が終わると、男達の言語も終わるのである。
今や、私の生きる目的はいかなるババアになるかということに尽きる。
私は読むはじから忘れていくので、いくら本を読んでも何の役にも立たない。読んでいる間だけ面白いのであって、読み終えるとすっかり忘れている。】
以下余談
12月に入って剣道の道場に再び通い出した。
自分では健康と暇つぶしで行っているのに、脚が曲がっているだの、腕がどうのと人の欠点を指摘し、教えたがる人がいるのは本当にヘキヘキだ。
好きにさせろっての、いかんせんこの世界は、マイナーで、保守的で古い。
でも30秒も持たないで「参りました」と休んでまた稽古。
大汗をかくほどの一生懸命にはならない。
同じく、12月に入って英会話の勉強を始めた。
もっぱらリスニングだ。
ネットは大変便利で、外国語のラジオが聞ける。
重いカセットレコーダーに録音して通勤時に聞いている。
携帯CD、MDもデジタルレコーダーも持っていないので。
VOAのスペシャルイングレッシュは初心者向けにゆっくりしゃべる。
聞き取りはできないが耳ざわりはいい。
ゆっくり過ぎる時はスピードをちょっと速めて。
だが、女性アナは、あの過剰な英語らしい発音でなんともイヤらしい。
ラジオジャパン、ABC、CNN、などいずれも早過ぎる、を通り越して聞き難い、いやそれも通り過ぎてこれはもう騒音である。
NHKのラジオジャパンは口がマイクに近すぎて息継ぎの音がとにかくうるさい。
これは日本人アナウンサーがネイティブらしく早くしゃべるために、小声でしゃべるためだと思う。
日本人を使うのはどうしてなのだろう。
VOAは文字化もされているので、翻訳ソフトで翻訳するが、日本語に全くなっていない。わからない単語の意味を調べるには一括翻訳が便利だが。
新しいソフトはもっと良くなっているのかもしれない。
さて、いつまで続くであろうか。
そのため、しばらく読書は休止。














