所謂、魏志倭人伝からみていきたい。そこには倭人は「皆徒跣」とある。つまり弥生人は裸足であると、魏志倭人伝は記す。
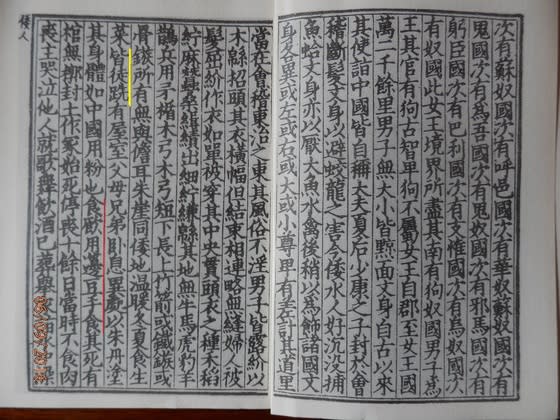
ほんまかいな?との疑問が無いわけではない。集落内では裸足であったとしても、一歩外の世界へ出るには、踏み分け道程度しかなかったであろうことを考えれば、履物は存在したであろう。
その前に、倭族と云うより弥生人と風俗が似かよっている、雲南南部や北タイ少数民族はどうであろう。北タイ少数民族といえども、近代化の波で裸足の生活など存在しないであろうと考えていたが、モン(Hmong・苗)族の老婆の足元をみると、裸足ではないか・・・う~ん、ひと昔というより20-30年前までは、切り立った切株のない集落内では、裸足は通常の姿であったろうと推測される。

してみれば、魏志倭人伝の「皆徒跣」の記述は、それなりに真実を伝えているとも思われる。
北タイの少数民族も裸足ばかりではなかったであろう。その履物は、どのようなものであったろうか? 現在は鼻緒付きのビーチサンダル(草履)を多くの少数民族が履いている。

ではひと昔前は、どーうであったろうか。ハノイ民族学博物館で黒タイ族の竹下駄を見た覚えがあり、その写真を探すがでてこない。そこでインターネット検索すると、鳥越憲三郎氏のエッセイ「下駄とワラジのルーツ」(そこの”談話室”をクリック)なるHPがヒットした。そこにはアカ族やタイ族、カレン族の下駄が紹介されている。北タイの少数民族は下駄や草鞋を履いていたのである。
そうすると、風俗の似ている我が弥生人も履物を履いていたであろう。登呂遺跡では田下駄が出土しており、この南方系の履物は稲作文化と共に伝来したであろう。また福岡の那珂久平遺跡や吉野ヶ里では、板を浅くえぐった木製の沓が出土している。
沓は別として田下駄は、北タイ少数民族の下駄と同じようなものである。魏志倭人伝を著した陳寿、記述にあたっての情報源は種々あったであろうが、その情報提供者は、実際にどこまでみたのであろうか?との疑念を覚える。
いずれにしても、裸足の生活や履物も、北タイ少数民族と弥生人は似ていたであろうと推測される。






















