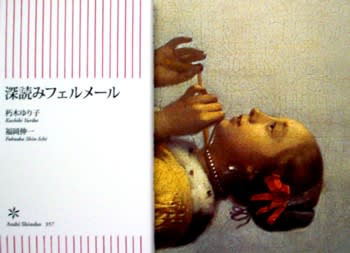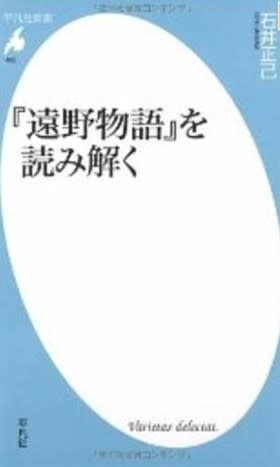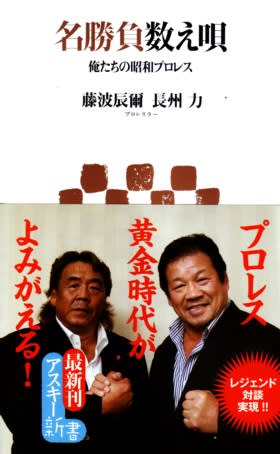「官能教育」なんて生々しいタイトルの新書であります。執筆者は宗教学者の植島啓司氏、私としては彼の本は何冊か読んだことがある比較的馴染みのある方です(大昔、大学の授業を潜りで1回だけ聞いたことがある)。宗教というものを見ていくと、トランス状態というのか、脱自というのか、私という感覚が消えていき大いなるものと遭遇、一体化を体験するという聖なる体験というものに突き当たることがあります。この聖なる体験は恍 . . . 本文を読む
よくもわるくもユニクロの服を買うことが多い私です。定番の服としてしっかりしているし、かゆいところに手が届いている服と感じているからです。気がつくと今日着ている服はパンツからシャツ、靴下からズボンまでユニクロ尽くしということもあります。若い子からオシャレですねと極たまに言われることがあるのですが、ユニクロだよというと、えっ!そうなんですか?と驚くこともあります。それだけユニクロの服は大量販売されてい . . . 本文を読む
荒木飛呂彦氏によるホラー映画に関する新書です。私は荒木氏が著名な漫画家とは知らずに購入しました。そこには彼の映画鑑賞史からくる体感的ホラー映画論が書かれているなあと感じたのですが、プロフィールを見るとほぼ私と同世代であることがわかりました(一歳違い)。なぜ本を読んでいて近しい世代と思ったか?体感的と先ほど書いたように荒木氏の内容が変なところで私と近い体験をしているように感じたからです。
&nbs . . . 本文を読む
ズバッと発言する論客の副島隆彦氏の本は読んでて気持ちがいい。はっきりしているし、言葉があやふやではない。立場や発言にブレがないのも気持ちいい。なかなかここまでの発言をしながら、それに正面から対峙している人は珍しいのではないだろうか?年月とともにその姿勢を変えていく人がいるなかで頑なにいるのは頑固とも言える。だから想像するに敵も多いかも知れない。否定派もいるだろう。しかし、そんなことを意に介さないよ . . . 本文を読む
林真理子の「野心のすすめ」が売れているといいます。私も著者名とタイトルに惹かれてその本を買ってしまいました。読んで見ると、まあ、あたりまえとは言い過ぎかもしれませんが、極端なことを書いているわけではありませんでした。むしろ、現代の若者達が野心を持って社会を生きてやろうという人が少ない印象を受けるのでハッパをかける意味で、ご自身の具体的な事例とハードルを高くせず、わかりやすく書いたという感じを持ちま . . . 本文を読む
久しぶりに読んだ新書が「職業としてのAV女優」というもの、著者はフリーライターとしてAV女優や風俗で働く女性を取材し記事にしてきたという中村淳彦氏という方。氏は事情通ではありながらも、どっぷりとその世界に足を突っ込んでいるわけではなく割とクールな視点で彼女らの実態を書いているのでした。それは興味本意感覚的手にとってしまいそうなタイトルでありながら、中味はというと正面からその実態、現状を面白おかしく . . . 本文を読む
仕事にデッドラインを設けて残業ゼロ、増収増益を連続して達成した経営者として著名な吉越浩一郎氏のリーダーに関する本を読みました。ここに書かれてあることは、いたって論理的でかつ合理的、そしてシンプルであると感じるのですが、いざ実行してみろとなると相当厳しく大変なことだと思います。目標達成のためにドライで妥協のない姿勢を貫かねばなりません。実際トリンプ時代にその噂を聞き付けて会社見学に訪れた企業は多くあ . . . 本文を読む
著者の中山康樹氏は私より9歳年上で、ジャズの専門誌「スイングジャーナル」の編集長を経て音楽評論家になり主にジャズをメインに執筆をしている方です。ジャズを聴くプロの人が書いた、肩の力を抜いたジャズの聴きかた入門。音楽音痴の私は、若い頃、ジャズの難しそうな響き(=それはどこか大人の響きに思えました)に憧れマイルス・デイビス、ジョン・コルトレーン、ソニー・ロリンズ、セロニアス・モンクといったジャズの巨人 . . . 本文を読む
書店で女優の風祭ゆきの写真が帯となっているこの本を見て思わず衝動的に買ってしまいました。新書でロマンポルノを語るというのがよかったのでしょうか。著者の寺脇研は東大法学部卒で文部省に勤務する傍ら、映画評論も書いてきたというエリートで、現在はプロととして活動している評論家です。ただ、これまでロマンポルノは語られすぎていると前置きして、ロマンポルノと題はつきながらも監督や脚本家、男優らをメインに綴ってお . . . 本文を読む
今年になって私はフェルメールの絵を6点、鑑賞したことになります。現存するフェルメールの絵が最大解釈で37点、厳しい判断で32点と言われているなかで6点とはなかなか贅沢なものだと思います。それも東京にいて1時間ちょっと電車に揺られていけばそれを拝むことができるなんて、東京は落ち目だとは言われながらも世界的にも消費が盛んな国際文化都市なんだなあとあらためて実感するわけです。それと同時に日本人はフェルメ . . . 本文を読む
この歳まで宮沢賢治に興味を持つことなくきました。しかし、宮沢賢治を読むとこんなイマジネーション豊かな作家がいたのかと心底驚かされました。どんな生涯だったのか?伝記映画を2本見てみました。大型書店の文学研究コーナー行ってみれば、あまりにも多い宮沢賢治に関する研究本、それだけ評価も高い作家だったのです。JR東日本がイーハトーヴのキャンペーンをやっていて、勢いつけて花巻の宮沢賢治関連施設も行ってみました . . . 本文を読む
「遠野物語」は明治41年、柳田国男は小説家の水野葉舟から、昔話ならいくらでも知っている珍しい男がいると遠野出身の佐々木喜善を紹介されたことから生まれたそうです。佐々木は遠野に伝わる話をお化け話と呼んでいたようですが、それを聞き書きし柳田はその時に「遠野物語」というタイトルをつけていたようで、柳田にとってみればそれは地方の発見であったということになるのでした。佐々木は訛りがひどかったそうですが、柳田 . . . 本文を読む
最近私のなかでニーチェというキーワードに触れる機会が増えてきたように思います。ひとっ飛びにニーチェの本を読むのもいいのですが、そこはまず周辺の本をと、軽い感じの本を読んでみました(昨日までの記事を参照)。今回はもう少し突っ込んだものにしようと新書に手を出してみた次第です。以下は、この手の本を読んだ時の私のスタイル、つまり私なりに、本から引用し要点や気になった箇所をまとめたものを列記しました。
◆ . . . 本文を読む
藤波辰爾と長州力、昭和プロレスの最後を飾った2大レスラーです。まさかその2人の名前で新書が出ているなんてびっくりしました。プロレスは私が中学生の時に夢中になってからのファンで、その中学生の時などはプロレス関係のメディアで仕事をしてみたいなんて真剣に思っていたこともあります。だから私はスポーツ新聞社を見学させてくださいと12、3歳くらいのとき編集部に行ってみた記憶があるくらいです。私がそのプロレスを . . . 本文を読む
現代演劇史を見ると必ず登場するのが鈴木忠志という名前を、劇団SCOTという名前を、利賀フェスティバルという名前を見ることができます。昨年末にはその鈴木忠志の劇団SCOTのお芝居を初めて見たのです。(演目は「別冊 谷崎潤一郎」)一時は一週間に一冊の読破を目標にしていたけれど、最近はあまり手にすることがめっきり少なくなってしまった新書、その鈴木忠志が岩波から「演劇とは何か」を出していて(初版は1988 . . . 本文を読む