この齢になるまで「免疫」の仕組みとか、その働きがどんなものか、きちんと知ることはなかった。「胸腺」と同じく、「脾臓」がどんな働きをし、臓器の機能をもっているのか知らない(※1)。そのいずれも免疫系に関係すると知ったのは、今回のコロナ禍による自粛中の読書による。
家の中で多くの人が何をしていたか知らないが、ウィルスと免疫、健康と免疫について、いろいろと見聞きしたのではなかろうか。
新能の作者かつ免疫学者である故多田富雄の『免疫の意味論』を読み、とりわけ「胸腺」に興味を抱いたことは前々回でふれた。で、免疫のイロハを興味本位に調べたりした。
そして、14,5歳ころをピークに次第に萎んでゆく「胸腺」に、そこはかとない愛着を感じた小生には、ちょっとした個人的理由がある。
実は、水疱瘡、蕁麻疹、ストロフルスなど様々な皮膚病に悩まされていた幼少時代(本人はカイーノだけだったかな)。たぶん、食物アレルギーのせいか、後述するが自己免疫機能の誤作動だったのかもしれない。
小学校に上がる前の頃、頸部リンパ腺が異常に腫れて、家族が大騒ぎになった。詳細は省くが、首まわりの患部にメスを入れる大手術を受けたのだ(※2)。
さらに20年後、当該部所に近い、耳の後ろに腫瘍みたいなものができ、摘出手術をすることになった。単なる脂肪等の塊だったらしいが(直径1.5㎝、紫色の完全球体)、なぜ出来たのか原因不明。医者が言うには、やはり免疫系の不具合か、詳しいことは断定できなかったとのこと。(この塊を記念にする? との問いかけに断固拒否したが、もし所有していたら・・)
現代には、医者にも原因が特定できない病気、症状は未だにある。特に難病と呼ばれるものは、その多くが免疫に関係したもので、それは治療が困難もしくは不可。たとえば、子供でも罹る老化症、糖尿病、血中の多様な疾患など、これらは特殊な例だが、自身の細胞を傷つけ、死に至らしむ「自己免疫不全」というケースが多いらしいのだ。
外界から侵入する異物(=非自己)を排除する、それが「免疫」というシステムの要諦だ。
白血球とかリンパ球、細菌やウィルスを退治するナチュラルキラー(NK)細胞、身体に侵入してきた異物を喰いつくすマクロファージ、それらの免疫用語は聞いたことがあると思う。
しかし実際のところ、それらがどう働くかというメカニズムを、詳らかに知る人は多くはないだろう。小生も同様に、健康な体なら勝手に治してくれる、自然治癒=「ザ・免疫」であろうと勝手に思っていた・・。
まず、「胸腺」について、多田富雄の『免疫の意味論』に、以下の記述がある。
文字の通り胸の中にある柔らかい白っぽい臓器である。若い動物では心臓の全面を覆うようにかなり大きな面積を占めている。人間では10代前半で最大となり、約35ℊに達する。性成熟する年齢になると、急速に小さくなるのも特徴である(前回の記事、同文を引用)。

▲人体のリンパ系の全体図。「胸腺」は、青い呼吸器官の下、茶色のニンニクのような塊だ。右下にこげ茶色の「脾臓」がある。

▲「胸腺」の詳細図。西東社から出ている『免疫学の基本がわかる事典』より。カラー図解が豊富な、医者をめざす初心者向き参考書。
胸腺を英語では「 thymus」(サァィマス?)と表記するが、この部位を焼くと、香草のタイムの匂いに似ていることから命名されたという。子羊などの小動物を、神に犠牲として捧げていたギリシャ時代、胸腺の存在は既に知られていたらしい。今日でも、フランス料理には子牛の胸腺が珍重されているとのこと。
そもそも、免疫というシステムは、以前書いたように「自己」と「非自己」を厳しく選別し、外界から侵入してくる細菌、ウィルスなどの異物を排除する生理機能だ。そのほか、ガン化する細胞を駆除したり、異物に対するアレルギー反応など、私たちの体を健全に保つ働きをする。これぐらいはざっと基本知識としてあった。こうして記述できるのも、この自粛期間のわずかな読書体験によるが・・。(※「参考」)。
免疫にかかわる基本の細胞、つまり血液の白血球(※3)やリンパ球などは、「骨髄」でつくられる。主として、胴体にある座骨、脊椎・脊髄、胸骨、鎖骨などで生成される(子供の頃には大腿骨でも生産)。そうした免疫の基本となる細胞は、幹細胞といい、免疫で重要な役割をもつ様々なB細胞、T細胞へと、まさしく教育され成長していく。(※4)
B細胞(骨髄の英語Bone narrowが由来である)は、さいしょ「幹細胞」という原初的な細胞である。それが、赤血球、白血球、血小板、あるいはリンパ球などに変化、成長していく。また、幹細胞の一部がたまたま「胸腺」( Thymus)の中に入っていくと、何段階ものプロセスを経て、特化されたリンパ球がつくられる。
ここにおいて重要なのが、それらの細胞の表面に「自己」か「非自己」かを選別するレセプター、タンパク質がつくられると免疫関係書には詳細に記述されている。そして、どの本を読んでも、これを何かしら「T細胞への教育」というコンセプトで書かれてある。
そう、未熟な幹細胞を目的に応じて、その働きを教化し、免疫細胞として叩き込んでゆく。その他にも、まだ目的が判然としない未知の「T細胞」もつくる。まったくもって、「胸腺」それ自体、解明されておらず、生命の神秘としか言いようのない臓器だ。ちなみに、T細胞のTは、胸腺「Thymus」の頭文字に由来する。
免疫において、超重要なリンパ球、T細胞だが、「抗体」をつくるB細胞を補助するヘルパーT細胞、ウィルスや細菌を殺すキラーT細胞(細胞障害性T細胞)、アレルギーに反応する制御性T細胞など、「胸腺」はそれぞれの役割に応じた教育をほどこして、体の隅々におくり出す教育機関ということは了解できた。
その「胸腺」は、思春期のころに最盛期をむかえ、必要な量のT細胞をつくったら退縮してゆく・・。80歳をむかえる老人になれば、その痕跡も見られないという。実際のところ、ここで作られるT細胞を100%だとすると、免疫で実質的に必要な量は10%ぐらい。残りの90%は自死していくように遺伝子に組込まれている。
小生はここに「無常」を感じるのだ。しかるべく役目を終えたものは、気づかれることなく退出する。まさしく鴨長明の『方丈記』の世界が現出してもおかしくない。愚生、蜂飼耳氏の現代語を読み、また新たな感慨を抱いた。
話を戻そう。「自己」の細胞を「非自己」として認め、自らの細胞を攻撃し、殺しかねない危険なT細胞に変身しないように自死させる。驚くべき自己プログラムだが、なかにはすり抜けて、いや余分に漏れ出して、体の各所で悪さをするケースもある。前述したが、稀な難病として人間を局限におき、生涯を悩ませる。その特殊な例外の病いは、百人百様といっていい。
「胸腺」についてはここまでにしておこう。免疫学は奥が深いのはもちろん、かなり複雑で専門用語が錯綜して理解するのは容易ではない。
上記の図でもふれたが、西東社さんの本は系統的に解説されており、図版が多くて頭に入りやすかった。中学生に戻ったかのように新鮮な思いで、ページをめくった。まだ、後半の「感染症とアレルギー」「自己免疫疾患」(難病の多くがこれだ)「移植免疫・がんと免疫」は未読だ。ちょっと頭を切り替えて、再チャレンジするつもりである。
いったん筆をおくが、考えたいこと、書きとめたいことがまだまだある。拙くも、それが文字化できればと密かに想う、今日この頃だ。
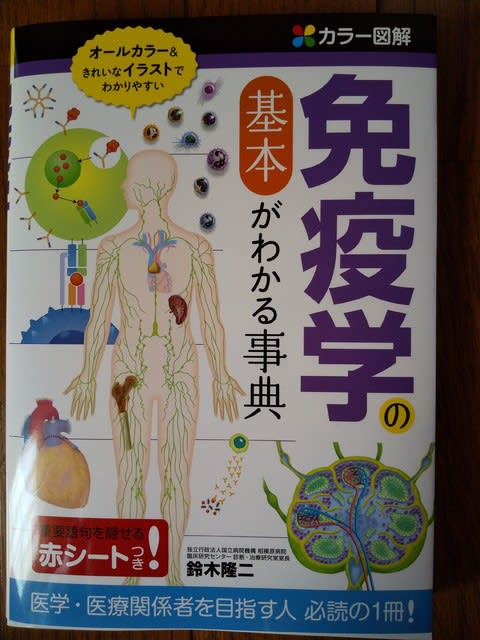
▲たまたま専門書のコーナーで発見。多田富雄の時代より、さらに進化した免疫学初歩の専門書で、そのコンテンツの充実度に驚いた。そして前半部を読み、西東社の編集部に問合わせ、記事中の図版などの掲載を願ったところ、すんなりと快諾いただいた。ここにその感謝の意を付与したい。
(※1)・・「脾臓」は、静脈つまり汚れた血液に対してフィルター作用をするリンパ臓器だ。血液中に侵入した外来異物を集積し、濃縮し、「抗原」として提示する。「抗原」ならばマクロファージなどが食い尽くすか、体外に排泄されるはずだ。
(※2)・・手術台の上に寝かされ、10人ほどの白衣の医者(ほとんどインターン医師だったんだろう)に囲まれた。大人用の全身麻酔マスクを顔全体にかぶせられる。口や鼻から甘酸っぱい空気がどんどん入ってきた。呼吸は苦しく次第に意識が遠のいてゆく。言いしれぬ闇の中の恐怖感・・。そして、首に冷たいメスが切り込まれた。痛いのに痛くない? 血が噴き出している? 「凄いな、こんなに暴れる子は初めてだ」という執刀医の声が朧げに聞こえてきた。しだいに暗黒の世界に、身体が溶けてゆくようだ・・。(ついに64,5年前の、幼き頃のわだかまっていた経験を文字化した)
(※3)白血球といっても、好中球・好酸球・好塩基球があり、リンパ球やマクロファージ、その他免疫系の細胞などが存在している。もちろん、その役割・働きは、実に適材適所というしかない。
(※4)実際には、もっと微小なタンパク質、アミノ酸など、微小レベルで変化した多種多彩な細胞が生まれる。たぶん、これらの研究において、利根川進、本庶祐さん達が授与されたノーベル生理・医学賞、それに値する研究成果があると推察される。具体的には、まったく分からないけど。
また、福岡伸一氏はじめ、この分野では日本人の研究者は多いし、薬学や化学、感染医療など多方面で活躍している。この方たちの著作を読む、そして自分なりの考えや想像力をめぐらせる、その知的興奮。今回のコロナ禍における自粛生活で、奇禍とすべきものがあるとすれば、まさにそうした読書体験だった。今後、その感想をたぶん記事にしたいのだが・・。
[追記]:今回の「Covid19 」の感染病の現場で尽力された、医療関係者への敬意と感謝の意をここに記載します。
「感染リスクと背中合わせの過酷な環境のもとで、強い使命感を持って、全力を尽くしてくださった医師、看護師、看護助手の皆さん、臨床工学技士の皆さん、そして保健所や臨床検査技師の皆さん、全ての医療従事者の皆さまに心からの敬意を表します」
[補足]:緊急事態全面解除の前日5月26日、例のマスクが宅配された。新聞によると、5月27日時点での普及率は20%程度とのこと。うちは早い方なんだ! 事あるごとに自信をもってスピーチする、決まり文句の「スピード重視」があきれる。
[参考] (免疫における)「自己」の定義 (多田富雄著 『免疫の意味論』より)
自己とは何であろうか。この問いを、生命科学を専攻している学生に聞いてみた。まず第一に返ってくる答えは、「自己」とは、自分の持っている遺伝子全体(ゲノム)の産物であるというものだった。人間では、それぞれの個体が持っている32億個ほどの塩基対によってコードされる物質の体系、それが「自己」であるという。
しかし、免疫系が見ている「自己」は少し違う。たとえば、人間に寄生しているウィルス、ことに内在性ウィルスと呼ばれるような奇生体を、免疫系は「自己」のなかに包含している。
マラリアの原虫や住血吸虫さえも、人間はしばしば「自己」と同様に扱う。それに対して、自分の遺伝子でコードされている蛋白であっても、たとえば甲状腺のコロイド蛋白とか、脳神経系のミエリンと呼ばれる蛋白などを、免疫系は「非自己」として認識し、免疫反応を起こす。その結果として、しばしば甲状腺炎や自己免疫脱髄性脳炎といった自己免疫病を起こす。遺伝子だけでは「自己」を規定できない。
もっと免疫学的な「自己」の定義として、次のような答えも返ってくる。免疫系が発生してくる環境に存在していた物質の総体が「自己」である、というのである。免疫系、ことに胸腺が発生するころの胎児期に存在していたタンパク質は、胸腺内で未熟なリンパ球の抗原レセプター(TcR)に触れることができる。未熟の状態で抗原と強く反応したT細胞には、強力なシグナルが形成され、結果的には細胞死を起こす、というのが現在の通説である。つまりT細胞発生の現場にいるタンパク質は、自分と反応するT細胞を除去するように働くのである。
それは、しかし胎児期でなければならない。なぜならば、ほとんどすべての「非自己」と反応できるT細胞のレパートリーは、出生までにすべて用意され、末梢のリンパ組織に分布し終わっているからである。
その胸腺でテストされて生き残ったT細胞は、したがって、「自己」のタンパク質抗原とは反応しない。すなわち「自己」に対する寛容が成立しているのである。この原理からいえば、胸腺が完成する胎児期、人間では5~6か月ごろ、マウスでは15~20日ごろに体の中に存在しすべてのタンパク質が免疫学的な「自己」を規定する。




















