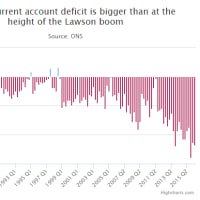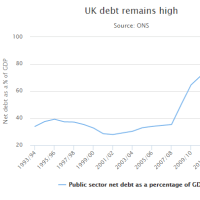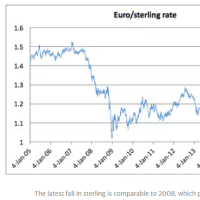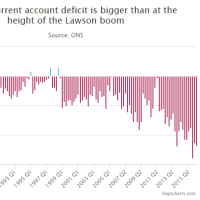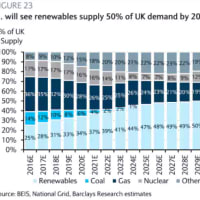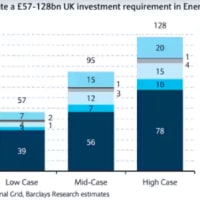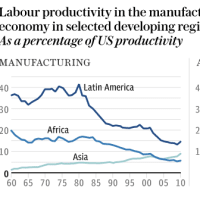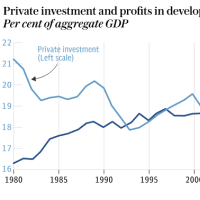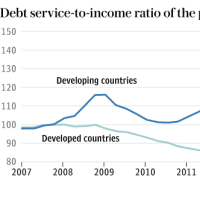知ってる人は知っている~。
The truth about Mahatma Gandhi: he was a wily operator, not India's smiling saint
(マハトマ・ガンジーの真実:狡猾なオペレーターであって、笑顔の聖人ではない)
By Patrick French
Telegraph: 7:50PM GMT 31 Jan 2013


The truth about Mahatma Gandhi: he was a wily operator, not India's smiling saint
(マハトマ・ガンジーの真実:狡猾なオペレーターであって、笑顔の聖人ではない)
By Patrick French
Telegraph: 7:50PM GMT 31 Jan 2013
The Indian nationalist leader had an eccentric attitude to sleeping habits, food and sexuality. However, his more controversial ideas have been written out of history
インドの愛国的指導者は睡眠、食事、性について奇妙な姿勢をとっていた。しかし彼のより議論を巻き起こす思想は、歴史書に記されないままだった。
This week, the National Archives here in New Delhi released a set of letters between Mohandas Karamchand Gandhi and a close friend from his South African days, Hermann Kallenbach, a German Jewish architect. Cue a set of ludicrous "Gay Gandhi" headlines across the world, wondering whether the fact the Mahatma signed some letters "Sinly yours" might be a clue (seemingly unaware that "sinly" was once a common contraction of "sincerely").
ニューデリーの国立公文書館は今週、モハンダス・カラムチャンド・ガンディーが南アフリカ時代の親しい友人であるユダヤ系ドイツ人建築家、ヘルマン・カレンバッハと交わした手紙を公開しました。
世界中に馬鹿馬鹿しい「ゲイ・ガンジー」の見出しを溢れさせ、マハトマが一部の手紙に「罪深くも君の」と署名したという事実はヒントなのかどうか考えさせる合図となりました(どうやらかつては「sincerely(敬具)」の短縮形として「sinly」が一般的に使われていたことに気付いていないようです)。
The origin of this rumour was a mischievous book review two years ago written by the historian Andrew Roberts, which speculated about the relationship between the men. On the basis of the written evidence, it seems unlikely that their friendship in the years leading up to the First World War was physical.
この噂の出所は、歴史家のアンドリュー・ロバーツ氏が2年前に記した人の悪い書評でした。
その中で同氏は2人の関係に関する憶測を記しました。
証拠文書に基づくと、第1次世界大戦まで続く長年の友情が肉体的なものになった可能性は低く思われます。
Gandhi is one of the best-documented figures of the pre-electronic age. He has innumerable biographies. If he managed to be gay without anyone noticing until now, it was a remarkable feat. The official record of his sayings and writings runs to more than 90 volumes, and reveals that his last words before being assassinated in 1948 were not an invocation to God, as is commonly reported, but the more prosaic: "It irks me if I am late for prayers even by a minute."
ガンジーは記録が最も多く残されているインドの独立前の人物の一人です。
伝記は無数にあります。
今まで誰にも気付かれることなく彼が同性愛者だったとすれば、それは驚くべき功績です。
ガンジーの発言や文章の公式記録は90巻以上に上っており、1948年に暗殺される直前の最後の言葉は、一般的に伝えられている神への祈りではなく、より退屈な「一分でもお祈りに遅刻するのはいやだなあ」という言葉だったということも明らかにされています。
That Gandhi had an eccentric attitude to sleeping habits, food and sexuality, regarding celibacy as the only way for a man to avoid draining his "vital fluid", is well known. Indeed, he spoke about it at length during his sermons, once linking a "nocturnal emission" of his own to the problems in Indian society.
ガンジーは睡眠、食事、性に対して奇妙な姿勢をとっていました。
禁欲を男性が「大事な液体」を流出しない唯一の方法と考えていたことは有名です。
そう、彼は説教の中でこれについて長々と語っており、自らの「夜間の放出」をインド社会における問題と結び付けたこともありました。
According to Jawaharlal Nehru, independent India's first prime minister, Mahatma Gandhi's pronouncements on sex were "abnormal and unnatural" and "can only lead to frustration, inhibition, neurosis, and all manner of physical and nervous ills… I do not know why he is so obsessed by this problem of sex".
インドの初代首相、ジャワハルラール・ネルーによれば、マハトマ・ガンジーのセックスに関する判決は「異常かつ不自然」であり「落胆、抑制、ノイローゼ、およびありとあらゆる身体的および神経的疾患しかもたらさないというものだった。私は彼が何故セックスのこのような問題にあれほど執着していたのかわからない」そうです。
Although some of Gandhi's unconventional ideas were rooted in ancient Hindu philosophy, he was more tellingly a figure of the late Victorian age, both in his puritanism and in his kooky theories about health, diet and communal living. Like other epic figures from the not too distant past, such as Leo Tolstoy and Queen Victoria, he is increasingly perceived in ways that would have surprised his contemporaries. Certainly no contemporary Indian politician would dare to speak about him in the frank tone that his ally Nehru did.
ガンジーの異例の考えの一部は古代ヒンズー教の教えに根付くものですが、どちらかといえば、ピューリタン主義や健康、食事、集団生活における奇妙な理論の両方において、ビクトリア朝終盤の人物です。
レオ・トルストイやヴィクトリア女王といった、割と最近の重要人物と同じく、ガンジーは現代人を驚かせるような考え方を深めていました。
現代のインドの政治家で、ネルー首相のように単刀直入に彼について語る勇気のある人は勿論いません。
Gandhi has become, in India and around the globe, a simplified version of what he was: a smiling saint who wore a white loincloth and John Lennon spectacles, who ate little and succeeded in bringing down the greatest empire the world has ever known through non-violent civil disobedience. President Obama, who kept a portrait of Gandhi hanging on the wall of his Senate office, likes to cite him.
ガンジーはインドと世界で、真実の彼の簡素化バージョンで知られるようになりました。
つまり、真っ白な布とジョン・レノンのような眼鏡を身に着け、余り物を食べず、非暴力的で文明的な非服従によって世界最大の帝国を倒すことに成功した笑顔の聖人として有名になりました。
ガンジーの肖像画を上院議会のオフィスに飾っていたオバマ大統領は、ガンジーの言葉を好んで引用します。
An important origin of the myth was Richard Attenborough's 1982 film Gandhi. Take the episode when the newly arrived Gandhi is ejected from a first-class railway carriage at Pietermaritzburg after a white passenger objects to sharing space with a "coolie" (an Indian indentured laborer). In fact, Gandhi's demand to be allowed to travel first-class was accepted by the railway company. Rather than marking the start of a campaign against racial oppression, as legend has it, this episode was the start of a campaign to extend racial segregation in South Africa. Gandhi was adamant that "respectable Indians" should not be obliged to use the same facilities as "raw Kaffirs". He petitioned the authorities in the port city of Durban, where he practised law, to end the indignity of making Indians use the same entrance to the post office as blacks, and counted it a victory when three doors were introduced: one for Europeans, one for Asiatics and one for Natives.
この神話の重要な出所は、リチャード・アッテンボロー監督の映画『ガンジー』です(1982年)。
例えば、
南アフリカに到着したばかりのガンジーは、白人の乗客が「クーリー(インド人の契約労働者)」と一緒に乗ることに反対した後、ピーターマリッツバーグで列車の一等車両から降ろされてしまうというエピソードがあります。
実際には、一等車両に乗りたい、というガンジーの要求は列車会社に認められたのです。
伝説のように、人種的抑圧に反対するキャンペーンの始まりではなく、このエピソードは南アフリカで人種的分離を拡大するためのキャンペーンの始まりでした。
ガンジーは「立派なインド人」が「野蛮な黒人」と同じ施設の利用を余儀なくされることなどあってはならない、として譲りませんでした。
彼は弁護士をしていた港町ダーバンで、インド人に郵便局で黒人と同じ出入口を使わせるという侮辱を終わらせるべく当局に署名を集めて提出し、3つの出入口(欧米人用、アジア人用、原住民用)が出来た時はこれを勝利としました。
Gandhi's genuine achievement as a political leader in India was to create a new form of protest, a mass public assertion which could, in the right circumstances, change history. It depended ultimately on a responsive government. He figured, from what he knew of British democracy, that the House of Commons would only be willing to suppress uprisings to a limited degree before conceding. If he had faced a different opponent, he would have had a different fate. When the former Viceroy of India, Lord Halifax, saw Adolf Hitler in 1938, the Fuhrer suggested that he have Gandhi shot; and that if nationalist protests continued, members of the Indian National Congress should be killed in increments of 200.
ガンジーのインドにおける政治的リーダーとしての本当の実績は、正しい状況においては歴史を変え得る、一般人による大人数での主張という、抗議の新しい形を生み出したことでした。
それも最終的には統治政府次第でした。
彼は英国の民主主義に関する知識から、英下院は妥協する前に蜂起を或る程度までは抑圧する気があるだろうが、そこまでだと推測しました。
違う相手であれば、異なる運命に見舞われたことでしょう。
インド総督を務めたロード・ハリファクスが1938年にアドルフ・ヒトラーに会見した際、ヒトラーは自分ならガンジーを打ち殺した、民族主義抗議運動が続くのならインド国民会議派も200人単位で殺しただろうと言いました。
For other Indian leaders who opposed Gandhi, he could be a fiendish opponent. His claim to represent "in his person" all the oppressed castes of India outraged the Dalit leader Dr BR Ambedkar. Gandhi even told him that they were not permitted to join his association to abolish untouchability. "You owe nothing to the debtors, and therefore, so far as this board is concerned, the initiative has to come from the debtors." Who could argue with Gandhi the lawyer? The whole object of this proposal, Ambedkar responded angrily, "is to create a slave mentality among the Untouchables towards their Hindu masters".
ガンジーに反対した他のインドの指導者にしてみれば、ガンジーは狡猾な敵にもなりました
インドのカースト制度で虐げられた全ての人々を「彼自ら」代表しているというガンジーの主張は、被抑圧労働者農民党の党首、ビームラーオ・ラームジー・アンベードカル博士を激怒させました。
なんとガンジーは博士に、自分達は不可触民制度廃止のために博士に与することは許されないと告げました。
「債務者には何も負わないものだから、この委員会が考えるに、イニシアチブは債務者から出されなければならない」
弁護士ガンジーと誰が議論出来るでしょう?
この提案の全ての目的は「ヒンズーのご主人様への奴隷根性を不可触民に植え付けることだ」とアンベードカル博士は怒って応じました。
Although Gandhi may have looked like a saint, in an outfit designed to represent the poor of rural India, he was above all a wily operator and tactician. Having lived in Britain and South Africa, he was familiar with the system that he was attempting to subvert. He knew how to undermine the British, when to press an advantage and when to withdraw. Little wonder that one British provincial governor described Mr Gandhi as being as "cunning as a cartload of monkeys".
ガンジーはインドの地方の貧者を代表すべくデザインされた衣装に身を包み、聖人のように見えたかもしれませんが、彼は何にもまして狡猾なオペレーター、戦術家でした。
英国と南アフリカで生活した彼は、自分が倒そうとしているシステムに精通していました。
ガンジーは英国を倒す方法、押すタイミング、退くタイミングを知っていまいた。
英国のインド総督がガンジー氏を「押し車一杯のサルほど狡猾だ」と評したのも無理はないのです。
Patrick French is the author of 'India: A Portrait' (Vintage)