
船戸与一『満洲国演義』の7巻は「雷の波濤」。
敷島太郎が官僚、次郎が馬賊、三郎が軍人、四郎がアナーキストという立場を異にし、「追従」「無関心」「肯定」「否定」という四つの機軸でストーリーを展開する、とある人は本書をまとめている。満州国を多角的描くことで満州国の存在感をよりリアルに感じさせる。
太郎、三郎が満洲国にアクティヴにかかわるのに対して、次郎と四郎は受け身。特に無政府主義の演劇集団にいた四郎は特高に弱みを握られて、したくもない汚い仕事を多々やらされる。
その境遇を次郎が助ける。馬賊上りで暗殺者となった次郎は特高を銃で脅して弟の満洲映画への就職斡旋と、以後付きまとわないことを約束させる。
満洲映画で脚本家となった四郎はハルビンを取材する。
ここで「大観園」が登場する。要するにアヘン中毒患者がたむろする街。安い買収宿もあり、アヘン中毒者が死ぬのが日常茶飯事。死体は全裸。衣服はほかの人に剥がれる。死体を見て四郎が「埋葬しないのか」と言うと連れが「棺桶に金がかかる。誰がそんな負担をするのだ」と言う。
別の死体現場で四郎は夜、放置死体が犬に齧られる音を聞いた。しかし大観園では静か。わけを聞くと連れは「犬がいるわけがない。いれば鍋料理にして食われる」と言う。
死体は腐ると職員が来て「万人坑」に投げ捨てる。「屍姦」という言葉は知っていたが、それが白昼堂々行われる。満人の母が死んだ売春婦の娘の体を男たちに供するでのある。硬直しない前に。これは船戸の想像力の所産であろうが、大観園を象徴する出来事として異彩を放ち、無頼派、船戸の面目躍如といえる。
ぼくはインドの貧民窟を見たことがあるがそれとは比較にならない世界である。
満洲というと満洲映画映理事長甘粕正彦が有名だが、彼を船戸は超現実主義者と描く。
すなわち、四郎が理想主義的なストーリーを書くと、
アヘン地獄に陥った満人たちを救うために日本人青年が大活躍するなんて嘘っぱちを満人が信用するはずがない、と企画課長を怒鳴りつける。
「主義者殺し」の異名をとる甘粕正彦は欺瞞を徹底的に嫌う現実主義者なのかもしれない、と四郎は思い直す。
満洲という虚構の国家が必然的に大観園と呼ばれるこの夜の地獄を創りあげた、と船戸は断じる。満洲国を維持するのに膨大な金が要り、それはアヘン売買が支えた。
さらなる資本導入としてユダヤ人の満洲移民も考えられた。同時に戦争をしていたドイツや欧州全域で白い目で見られていたユダヤ人の資本力は魅力であった。ユダヤ人移民は実現しなかったが、これは教科書では学べなかったことであり、はっとした。
拉致、監禁、拷問、殺人、放火、爆発、謀略、強盗、強姦、売春、アヘン中毒、賭博、酔っ払い、行き倒れ……船戸の筆は冴える。
7巻で3000ページ以上になる。あと2巻でさらに900ページ。船戸はこれを書き下ろした。時間制限のなく自由の効く中で書いた。よほど書きたかったと思うが、それは読めばリアルに伝わってくる。
佐藤慎一郎「魔窟・大観園の解剖」
(満州国警務総局保安局、原書房、1982年)
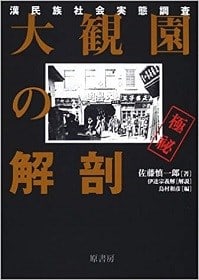
(満州国警務総局保安局、原書房、1982年)
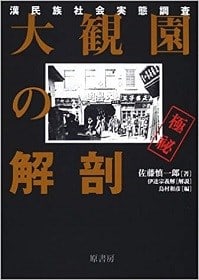


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます