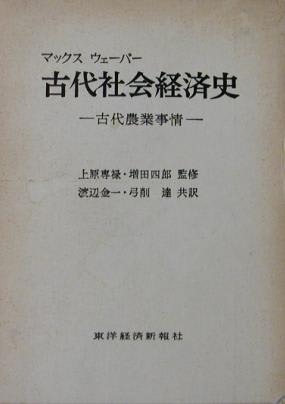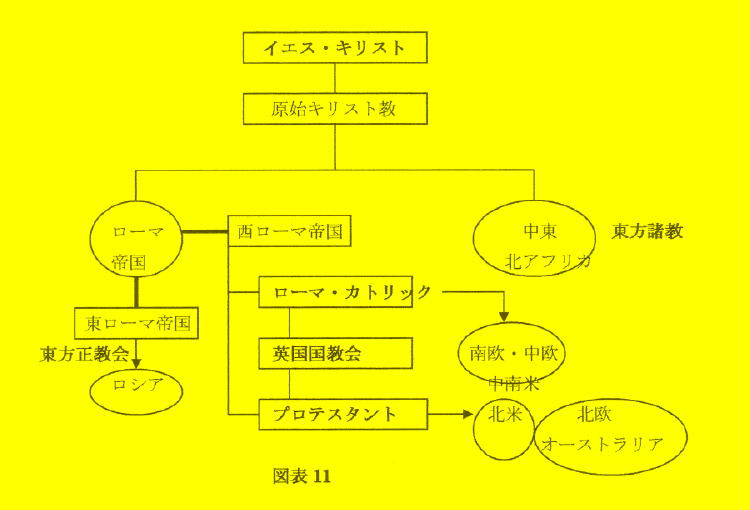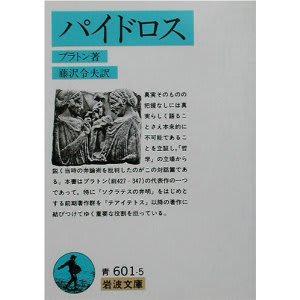森 有正(1911年11月30日 - 1976年10月18日)は、日本の哲学者、フランス文学者。
『森有正全集 (全14巻・補巻1)』 筑摩書房、1978年-82年
- 第1巻 バビロンの流れのほとりにて/流れのほとりにて
- 第2巻 城門のかたわらにて/砂漠に向かって
- 第3巻 遥かなノートル・ダム
- 第4巻 旅の空の下で
- 第5巻 木々は光を浴びて
- 第6巻 現代フランス思想の展望
- 第7巻 近代精神とキリスト教
- 第8巻 ドストエーフスキー覚書
- 第9巻 デカルトの人間像ほか論考
- 第10巻 パスカルの方法
- 第11巻 パスカルにおける「愛」の構造
- 第12巻 経験と思想 雑纂
- 第13巻 日記I
- 第14巻 日記II・アリアンヌへの手紙
- 補巻 補遺(随想・書評ほか)
これみよがしのおべっか使いが相手なら話は単純だ。本当に厄介なのは、見え透いたやり口は使わずにすり寄ってくる連中である。ではどうすればこの手合いを真の友人から見分けられるか?こう説き起こしてプルタルコスは彼らの手口のあの手この手を実例をあげて紹介する。よく人間を知る者ならではの観察眼がひかるエッセイ4篇。
《収録作品》饒舌について いかに敵から利益を得るか 知りたがりについて 弱気について 人から憎まれずに自分をほめること 借金をしてはならぬこと
ソクラテスの精神に触れる手掛かりは、プラトンの残した著作品以外にありません。
しかし、彼の作品は質・量ともに群を抜いています。そのすべてに目を通すなんて、想像するだけで目眩がします。でも、その必要はありません。芸術的天才プラトンの執筆動機が、ソクラテスその人にあったのです。一篇は全編に通じます。少なくとも、ソクラテスに関する四福音書と言われている対話編、
「ソクラテスの弁明」 : 法廷におけるソクラテスの弁論、無知の知、魂の世話
「クリトン」 : 獄舎におけるソクラテス、遵法の正義
「パイドン」 : ソクラテスの死、イデア論 、霊魂不滅論
「シュンポジュウム(饗宴)」 : エロスについて
田中美知太郎著『ソクラテス』(岩波新書)
中野幸次著『ソクラテス』(清水書院)
ジャン・ブラン著『ソクラテス』(文庫クセジュ)
テイラー著『ソクラテス』(桜井書店)
Desiderius Erasmus Roterodamus (27 October 1466 ? 12 July 1536), known as Erasmus of Rotterdam, or simply Erasmus, was a Dutch Renaissance humanist, Catholic priest, social critic, teacher, and theologian.
Erasmus was a classical scholar who wrote in a pure Latin style. He was a proponent of religious toleration, and enjoyed the sobriquet "Prince of the Humanists"; he has been called "the crowning glory of the Christian humanists". Using humanist techniques for working on texts, he prepared important new Latin and Greek editions of the New Testament. These raised questions that would be influential in the Protestant Reformation and Catholic Counter-Reformation. He also wrote On Free Will, The Praise of Folly, Handbook of a Christian Knight, On Civility in Children, Copia: Foundations of the Abundant Style, Julius Exclusus, and many other works.
Erasmus lived against the backdrop of the growing European religious Reformation; but while he was critical of the abuses within the Church and called for reform, he kept his distance from Luther and Melanchthon and continued to recognise the authority of the pope. Erasmus emphasized a middle way, with a deep respect for traditional faith, piety and grace, and rejected Luther's emphasis on faith alone. Erasmus therefore remained a member of the Catholic Church all his life. Erasmus remained committed to reforming the Church and its clerics' abuses from within. He also held to Catholic doctrines such as that of free will, which some Reformers rejected in favour of the doctrine of predestination. His middle road approach disappointed and even angered scholars in both camps.
Marcus Tullius Cicero (/?s?s?ro?/; Classical Latin: [mark?s tul.lj?s ?k?k?ro?]; Ancient Greek: Κικέρων Kikerōn; 3 January 106 BC ? 7 December 43 BC; sometimes anglicized as Tully /?t?li/), was a Roman philosopher, politician, lawyer, orator, political theorist, consul and constitutionalist. He came from a wealthy municipal family of the Roman equestrian order, and is widely considered one of Rome's greatest orators and prose stylists.
His influence on the Latin language was so immense that the subsequent history of prose in not only Latin but European languages up to the 19th century was said to be either a reaction against or a return to his style. According to Michael Grant, "the influence of Cicero upon the history of European literature and ideas greatly exceeds that of any other prose writer in any language". Cicero introduced the Romans to the chief schools of Greek philosophy and created a Latin philosophical vocabulary (with neologisms such as humanitas, qualitas, quantitas, and essentia) distinguishing himself as a linguist, translator, and philosopher.
Augustine of Hippo (/?????st?n/ or /?????st?n/; Latin: Aurelius Augustinus Hipponensis;13 November 354 ? 28 August 430), also known as Saint Augustine or Saint Austin, was an early Christian theologian whose writings were very influential in the development of Western Christianity and Western philosophy. He was bishop of Hippo Regius (present-day Annaba, Algeria) located in the Roman province of Africa. Writing during the Patristic Era, he is viewed as one of the most important Church Fathers. Among his most important works are City of God and Confessions, which continue to be read widely today.
竹田 青嗣(1947年10月29日 - )は、大阪府出身の、在日韓国人の哲学者、早稲田大学国際教養学部教授
早大政治経済学部卒業、文芸評論などでデビューし、1986年加藤典洋とともに明治学院大学国際学部助教授、教授を経て、2005年早大国際教養学部教授。通常用いている韓国名は、姜修次(カン・スチャ、???)。戸籍名は、姜正秀(カン・ジョンス、???)。「竹田青嗣」とは、太宰治の小説「竹青」から付けた筆名であり、日本名ではない。
http://www.phenomenology-japan.com/takeda.htm
フッサールは晩年に、「現象学入門」という副題のついた二冊の本を書いています。『デカルト的省察』(1931)と『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』(1936)です。この講座では一年間をかけて、この二冊の書物をていねいに解読していきます。四月からの春期講座では、『デカルト的省察』を取り上げます。デカルトの「われ思う、ゆえにわれあり」という命題の正しさは、だれもが自分で確かめることができますが、このような「だれもが確かめうる」方法を発展させたものとして、フッサールは現象学を提示しようとします。現象学の強みは、価値や感情や認識について、独断ではなく「共通了解」をつくっていける点にありますが、そうした現象学の方法とその特質を理解するうえで、この本はもっとも基本的な文献といえます。また、この本では、あらゆる物事を「意識における確信」(意識において〝妥当〟してくるもの)とみなす超越論的現象学の姿勢がきわめて明確に打ち出されています。そのような発想をすることの必要性とその意義について、あらためてテクストにあたりつつ考えることができるでしょう。間主観性について詳細に語った「第五省察」が含まれているのも見逃せません。現象学に関心のある方の参加をお待ちしています。(西講師・記)
<参考文献>竹田青嗣「超解読!はじめてのフッサール『現象学の理念』」講談社現代新書、竹田青嗣「現象学入門」NHKブックス、竹田青嗣「現象学は〈思考の原理〉である」ちくま新書
西研「哲学的思考――フッサール現象学の核心」ちくま学芸文庫、西研「哲学の練習問題」河出文庫。
David Hume (/?hju?m/; 7 May [O.S. 26 April] 1711 ? 25 August 1776) was a Scottish philosopher, historian, economist, and essayist known especially for his philosophical empiricism and skepticism. He was one of the most important figures in the history of Western philosophy and the Scottish Enlightenment. Hume is often grouped with John Locke, George Berkeley, and a handful of others as a British Empiricist.
George Berkeley (/?b?rkl??/; 12 March 1685 ? 14 January 1753), also known as Bishop Berkeley (Bishop of Cloyne), was an Anglo-Irish philosopher whose primary achievement was the advancement of a theory he called "immaterialism" (later referred to as "subjective idealism" by others). This theory denies the existence of material substance and instead contends that familiar objects like tables and chairs are only ideas in the minds of perceivers, and as a result cannot exist without being perceived. Berkeley is also known for his critique of abstraction, an important premise in his argument for immaterialism.
John Locke FRS (/?l?k/; 29 August 1632 ? 28 October 1704), widely known as the Father of Classical Liberalism, was an English philosopher and physician regarded as one of the most influential of Enlightenment thinkers. Considered one of the first of the British empiricists, following the tradition of Francis Bacon, he is equally important to social contract theory. His work greatly affected the development of epistemology and political philosophy. His writings influenced Voltaire and Rousseau, many Scottish Enlightenment thinkers, as well as the American revolutionaries. His contributions to classical republicanism and liberal theory are reflected in the United States Declaration of Independence.
Sir Francis Bacon, 1st Viscount St. Alban, Kt., QC (22 January 1561 ? 9 April 1626) was an English philosopher, statesman, scientist, jurist, orator, essayist, and author. He served both as Attorney General and Lord Chancellor of England. After his death, he remained extremely influential through his works, especially as philosophical advocate and practitioner of the scientific method during the scientific revolution.
古い科学では、観察を重視し、実験を行いませんでした。人間の手を加えないものが自然であるという考えを持っていたからです。アリストテレスは、「人間は自然を模倣するもの」と考えていました。自然の方が、人間よりも優れていると考えていたのです。古い科学では、技術を使って自然に介入し、自然を変えることは神を真似る人間のおごりだと考えられていました。
ベーコンはこのような古い考え方を捨て、実験を行い、人間の手で自然に介入し、パラメタを変えて、結果の変化を見る、ということをはじめました(たとえばガリレイの実験を思い出してみてください。坂の傾きを変えて、落ちる時間の変化を調べましたね)。
このように、ベーコン以降にはじめて、人間が手を加えたものも自然科学で扱えるという考え方が生まれたのです。