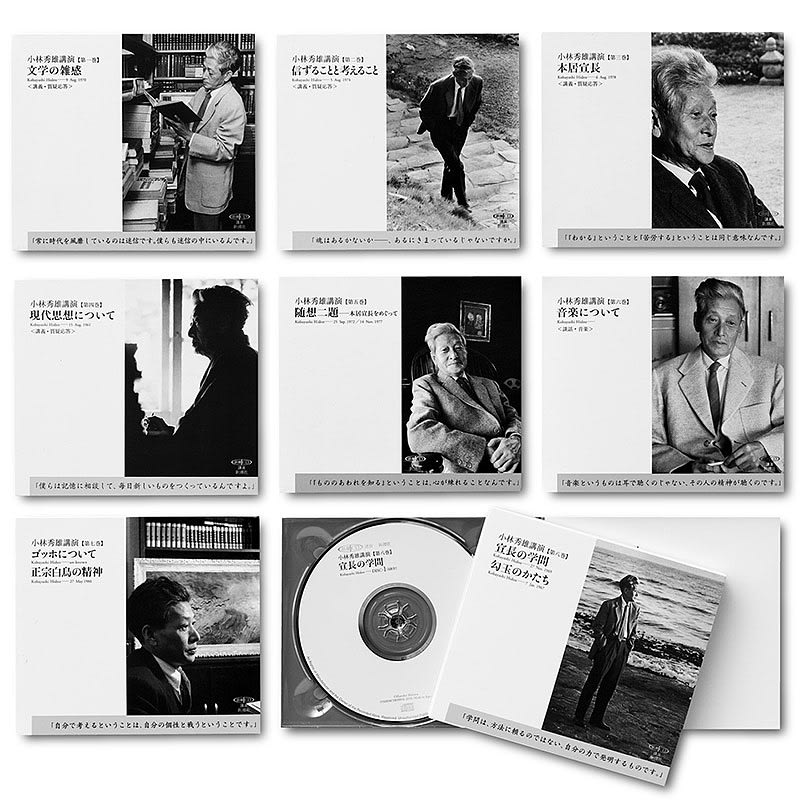大阪府出身。私立追手門学院小学校、同中学校を卒業。大阪府立大手前高等学校で岩脇正人、佐々木幹郎、山崎博昭らの学生運動に参加する。2年生のとき不登校となり、1年間休学し、読書と思索の日々を送っていたとき書いた小説『Mの世界』で文藝学生小説コンクール佳作入選し、18歳の誕生日を前にして文壇にデビュー。早稲田大学第一文学部演劇専修卒業後、広告プロダクションでのサラリーマン生活を経て1977年、『僕って何』で芥川賞受賞。1988年から早稲田大学で教鞭をとり、1997年~2001年と2005年~2007年には早稲田大学文学部客員教授を務めた。その後2009年~2011年武蔵野大学客員教授、2011年から武蔵野大学教授。
芥川賞受賞作『僕って何』は早稲田大学在学当時に経験した学生運動をモチーフにした作品だが、当時本人は特定のセクトに属さずクラス単位での活動に参加。既に学生結婚しており家庭を持つ身であったためバリケードに泊まり込むことはせず「日帰り」で活動していた(『都の西北』)。また、『僕って何』という小説は、従来の「社会主義を絶対的な正義として、正義のために闘おうとしながら結局は挫折してしまう人物をセンチメンタルに描いた」生真面目な学生運動小説に対して、作品の中に絶対的な価値基準を置かず、学生運動自体に批判的な視点をもっており(本人ホームページ)、ユーモアと恋愛小説風の軽やかな筆致で、学生運動を客観的・通俗的に描いたため、その新しさが評価された一方で、政治的には左右の一部から批判の的とされた。
芥川賞受賞以来「団塊世代の旗手」と称されることも多く、それに呼応するように「ニューファミリー世代」「団塊世代」としての家族のあり方をテーマに随筆・小説を多く手がけている。『僕の赤ちゃんたち』『トマトケチャップの青春』『パパは塾長さん』『息子の教育』『父親学入門』『ぼくのリビングルーム』など、家族の関わりの中でも子育て・教育に関する著作が多かったが、近年では『団塊老人』『団塊-再生世代の底力』『夫婦って何? おふたり様の老後』など団塊世代の老後の生き方への提言・指南を多く著している。
2009年に上梓した『新釈罪と罰』の「あとがき」では、「僕はドストエフスキーを読むことで小説の魅力に触れ、小説家の人生を始めることになった」と述べている。初の新聞連載『龍をみたか』は、『白痴』のパロディー化ということを意識して書いたと述べている。
また、キリスト教・仏教への造詣が深く、『地に火を放つ者/双児のトマスによる第五の福音』『迷宮のラビア』『釈迦と維摩/小説維摩経』『空海』『日蓮』といった深遠な宗教小説が近年を代表する創作である。
さらに、『聖書の謎を解く』『般若心経の謎を解く』『謎の空海』『はじめての宗教 キリストと釈迦』などの入門書・エッセーも旺盛に執筆している。本人のホームページによると、ライフワークとしての小説作品とその「解説書」を並行して次々に発表する「すごいパラノイア的構想」によると述べており、「21世紀はパラノイアの時代だ」としている。
中学までは理系志向であったというが、自然科学分野の本格的な著作も多く、相対性理論や宇宙論についての解説書を多々手がけている。宗教をさらに拡大した「宇宙論」こそ、自らの「究極のライフワークである」としており、小説『デイドリーム・ビリーバー』はその系譜にある大作といえよう。また2003年、小惑星11921がMitamasahiroと命名される。
他にも、青春小説、小説入門、女帝や武将といった歴史上の為政者などを主人公とする歴史小説など、幅広く執筆している。
2007年頃から著作権ロビーにも尽力しており、著作権保護期間の延長を訴えている。その一方で『星の王子さま』の翻訳出版権が2005年1月に消失すると2006年11月には講談社から『星の王子さま』を訳出している。
なお、実家は一世を風靡した「コピーの三田」で知られた三田工業(現京セラドキュメントソリューションズ)を経営していた。実家の住まいは会社の近辺であった。長男はピアニストの三田貴広。女優の三田和代は実姉。実兄は三田工業元社長の三田順啓。
宮本輝夫人とは幼馴染(『龍をみたか』文庫版での平岡篤頼との対談)