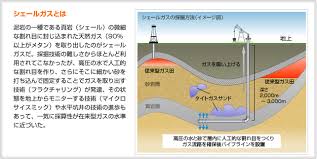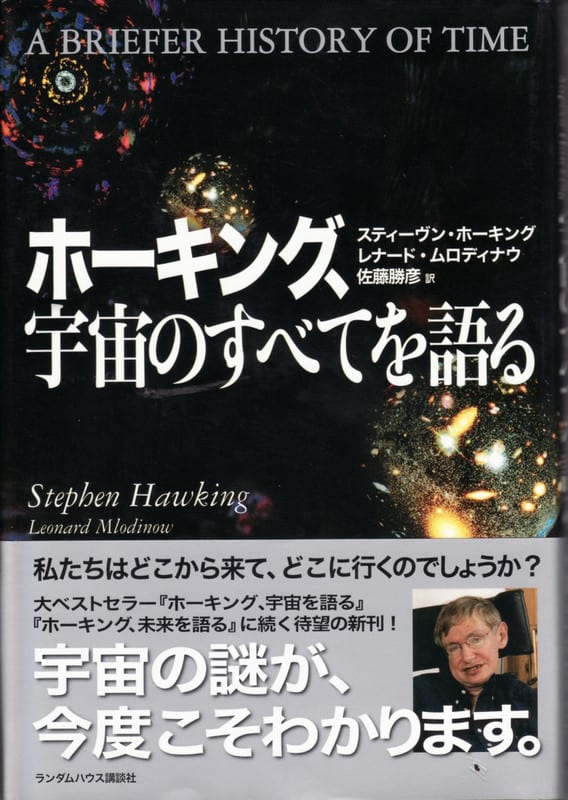戸塚 洋二(とつか ようじ、1942年3月6日 - 2008年7月10日)は日本の物理学者。東京大学特別栄誉教授。静岡県富士市出身。


1987年2月23日、スーパーカミオカンデの前身であるカミオカンデにおいて大マゼラン星雲で発生した超新星爆発に伴うニュートリノ11例を世界で初めて観測しました。これにより、超新星爆発の理論が正しいことが証明され、ニュートリノを観測手段とするニュートリノ天文学の幕開けともなりました。


「がんと闘った科学者の記録」(2009)
宇宙線研究所から |
戸塚先生は1942年に静岡県でお生まれになり、本学理学部を卒業、同大学院理学系研究科を修了されました。理学博士の学位を取得後、本学理学部の教官として小柴昌俊先生のもとで当時の西ドイツでの電子陽電子衝突実験に参加されました。1988年にスーパーカミオカンデを実現するために宇宙線研究所に移られました。戸塚先生のご努力でスーパーカミオカンデの建設が認められ、1996年にスーパーカミオカンデ実験開始、1998年に宇宙線が大気中で生成するニュートリノを観測してニュートリノ振動(質量)を発見、2001年にはカナダのSNO実験のデータと共に、太陽ニュートリノ問題もニュートリノ振動によるものだということを突き止められました。これらの発見によって、素粒子の標準理論を超えてより深く自然法則を理解するための実験的な手がかりがはじめて得られました。これらは科学史に残る偉大な成果です。また、宇宙線研究所長として、宇宙線研究所と日本の宇宙線研究の発展のためにもご尽力されました。
戸塚先生の達成した科学的成果については多くのところで語られていますので、ここでは戸塚先生にまつわるいくつかのエピソードを紹介します。スーパーカミオカンデの建設は1991年度から始まり、1995年度末に完成の計画でした。そこで戸塚先生は広く世界の研究者仲間に1996年4月1日に観測を開始すると宣言し、約100人の全共同研究者を結束してこの目標に向かって進ませました。こう書くのは簡単ですが、とても大変なことです。本来研究者というのは自分の好きなことをやるという習性があり、さらにこの習性は全共同研究者の約4割を占めるアメリカ人には強いので。これは戸塚先生の強い決意とリーダーシップによってはじめてなしえたものですが、それと共に忘れてならない、あるいは忘れられないのは、戸塚先生の人柄です。写真に示した戸塚先生のお顔は2000年に撮影したものですが、この写真から想像していただける通り、戸塚先生と話しているだけで心が温まるような人柄でした。この人柄に惹かれて多数の共同研究者が共通の目標に向かって進むことができたのです。
戸塚先生は強いリーダーシップでニュートリノ研究と宇宙線研究所を引っ張ってこられましたが、我々に特別に強いインパクトを与えたのは、2001年秋のスーパーカミオカンデの事故に際しての戸塚先生のリーダーシップです。戸塚先生は2001年の春には宇宙線研究所長としての任期を終えられ、またこの年の夏前には太陽ニュートリノ問題も解決してスーパーカミオカンデの当初の目的を概ね達成されたとして、このあとは定年までゆっくり物理を楽しもうと思われていたのかもしれません。そこに起きたのがあの事故でした。この時の戸塚先生の対応は本当に見事なもので、事故の翌日には装置を再建すると宣言され、全共同研究者を再び同一の目標に向かって進ませました。この時の戸塚先生の献身的かつ強力なリーダーシップがなければ、現在のスーパーカミオカンデも宇宙線研究所も考えられません。いくら感謝してもしきれない思いです。それと共に、戸塚先生が2000年の暮れにガンの手術をされてから1年ほどで、その時期にこのような極限状態で過酷な仕事をしていただくことになってしまったということに関して、本当に申し訳ない気持ちです。
最後に戸塚先生が日頃我々に話されたことをここに書かせていただきます。戸塚先生がドイツで研究をされていた1970年代、研究仲間のハイデルベルク大学の教授の研究室を訪問されたとき、古びた棚のなかに古い道具が置いてあり、それについて聞いてみると、これはヘルムホルツが使った道具だ、こちらは誰々の装置だと説明してくれたそうです。戸塚先生はこのときショックを受けたと仰っていました。つまり、我々日本人にはどこかの歴史上の偉い科学者のものとしか考えられないものが、まさにその場所にある、つまり、ハイデルベルグ大学の研究者にとっては科学の歴史が日常にあり、ひいては科学を切り開いて行くということがあたりまえの環境にいるという、日本の環境との違いにショックを受けたとのことでした。そして我々に、将来の日本の科学の発展のためには、我々も若い日本の学生や研究者が、科学の成果を身近なものとして受け止められるような日本の科学の伝統をつくらねばならないと仰っていました。戸塚先生は大きな科学上の成果を残され、まさにこの言葉通りの壮大な夢の実現に向かって生きてこられました。あとに残された我々がなすべきことは戸塚先生が我々に話して下さった大きな夢に向かってたゆみない努力を続けて行くことだと思います。心より戸塚先生のご冥福をお祈りいたします。