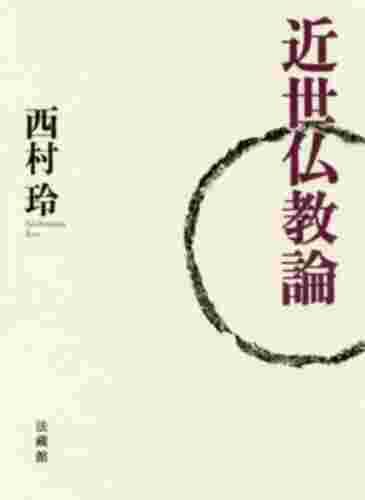世界中が欺かれていた!
これはエコではない、エゴだ。
地球温暖化はCO2のせいではない。
地球の温暖化は人為的な二酸化炭素排出が原因とされ、ノーベル平和賞を受賞したIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が主導して、世界中でCO2の排出規制が叫ばれてきた。しかし、その論拠となった基礎データが捏造されていたことが二〇〇九年に露見する。このことは欧米ではクライメートゲート事件として大問題となっているが、なぜか日本ではほとんど報道されていない。
本書は、地球の気候に関するさまざまなデータを科学的に読み解くことで、二酸化炭素の冤罪を晴らし、温暖化の実態とその真の原因を追い、エネルギーの正しい使い方を示す。
[著者情報]
広瀬 隆(ひろせ たかし)
一九四三年東京生まれ。作家。早稲田大学卒業。長年、エネルギー問題について原発から燃料電池まで精力的に分析・研究している。『アメリカの経済支配者たち』『アメリカの巨大軍需産業』『アメリカの保守本流』『資本主義崩壊の首謀者たち』(以上集英社新書)、『赤い楯』(集英社文庫)、『世界金融戦争』『世界石油戦争』(以上NHK出版)、『一本の鎖』(ダイヤモンド社)など著書多数。
これはエコではない、エゴだ。
地球温暖化はCO2のせいではない。
地球の温暖化は人為的な二酸化炭素排出が原因とされ、ノーベル平和賞を受賞したIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が主導して、世界中でCO2の排出規制が叫ばれてきた。しかし、その論拠となった基礎データが捏造されていたことが二〇〇九年に露見する。このことは欧米ではクライメートゲート事件として大問題となっているが、なぜか日本ではほとんど報道されていない。
本書は、地球の気候に関するさまざまなデータを科学的に読み解くことで、二酸化炭素の冤罪を晴らし、温暖化の実態とその真の原因を追い、エネルギーの正しい使い方を示す。
[著者情報]
広瀬 隆(ひろせ たかし)
一九四三年東京生まれ。作家。早稲田大学卒業。長年、エネルギー問題について原発から燃料電池まで精力的に分析・研究している。『アメリカの経済支配者たち』『アメリカの巨大軍需産業』『アメリカの保守本流』『資本主義崩壊の首謀者たち』(以上集英社新書)、『赤い楯』(集英社文庫)、『世界金融戦争』『世界石油戦争』(以上NHK出版)、『一本の鎖』(ダイヤモンド社)など著書多数。