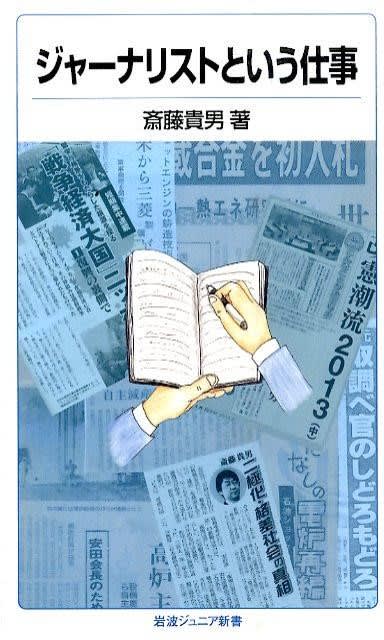10月消費税10%ストップ! ネットワーク
【呼びかけ人】 有田芳子(主婦連合会会長)
斎藤貴男(ジャーナリスト)
庄司正俊(全国FC加盟店協会会長)
住江憲勇(全国保険医団体連合会会長)
醍醐聰(東京大学名誉教授)
富岡幸雄(中央大学名誉教授)
浜矩子(同志社大学大学院教授)
本田宏(NPO法人医療制度研究会副理事長)
室井佑月(小説家・タレント)
山田洋次(映画監督)
「10%ストップ!」
5・24 日比谷野音に響かせましょう
5月24日(金)13時から、東京・日比谷野外音楽堂で「消費税 いま上げるべきではない 5・24中央集会」を開きます。
全国のネットワークのみなさん、「10月消費税10%増税はストップを」と願うみなさん、ぜひご参加ください。
集会終了後は、銀座、東京駅方面にサウンドデモを行います。
「10月消費税10%ストップ!ネットワーク」アピール
14日、「10月消費税10%ストップ!ネットワーク」の結成記者会見で発表されたアピールは次のとおりです。
◇ ◇
国民のみなさん
政府は予定通り、2019年10月から消費税率を10%に引き上げようとしています。
家計消費は低迷し、深刻な消費不況が続いています。実質賃金は伸びず、年金受給額はさらに削られようとしています。金融資産を持たない世帯が全世帯の3割を超えるなど、格差と貧困は拡大する一方です。
このまま税率が引き上げられれば、地域経済をさらに疲弊させ、中小企業や小規模事業者の営業を脅かし、雇用不安を招くなど国民生活は大変な影響を受けることになります。
国民のみなさん
政府が行おうとしている消費税増税のための景気対策は、一時的で対象も限定され、富裕層ほど大きな恩恵を受けるものです。「軽減」と宣伝されている複数税率による混乱も心配されています。
消費税率引き上げのために莫大(ばくだい)な予算をつぎ込むなど本末転倒であり、本気で景気対策を行うというのなら、消費税10%への増税こそ中止すべきではないでしょうか。
国民のみなさん
景気悪化を招き、低所得者ほど負担が重いのが消費税の特徴です。「いま、消費税を上げる時なのか」といった疑問の声が大きく広がっています。
私たちは「10月消費税10%ストップ!ネットワーク」を立ち上げ、2019年10月からの消費税増税を中止させるために、あらゆる手段を尽くして活動します。
こうした趣旨に賛同いただき、ともに声をあげていただくことを呼び掛けます。
【呼びかけ人】 有田芳子(主婦連合会会長)
斎藤貴男(ジャーナリスト)
庄司正俊(全国FC加盟店協会会長)
住江憲勇(全国保険医団体連合会会長)
醍醐聰(東京大学名誉教授)
富岡幸雄(中央大学名誉教授)
浜矩子(同志社大学大学院教授)
本田宏(NPO法人医療制度研究会副理事長)
室井佑月(小説家・タレント)
山田洋次(映画監督)
「10%ストップ!」
5・24 日比谷野音に響かせましょう
5月24日(金)13時から、東京・日比谷野外音楽堂で「消費税 いま上げるべきではない 5・24中央集会」を開きます。
全国のネットワークのみなさん、「10月消費税10%増税はストップを」と願うみなさん、ぜひご参加ください。
集会終了後は、銀座、東京駅方面にサウンドデモを行います。
「10月消費税10%ストップ!ネットワーク」アピール
14日、「10月消費税10%ストップ!ネットワーク」の結成記者会見で発表されたアピールは次のとおりです。
◇ ◇
国民のみなさん
政府は予定通り、2019年10月から消費税率を10%に引き上げようとしています。
家計消費は低迷し、深刻な消費不況が続いています。実質賃金は伸びず、年金受給額はさらに削られようとしています。金融資産を持たない世帯が全世帯の3割を超えるなど、格差と貧困は拡大する一方です。
このまま税率が引き上げられれば、地域経済をさらに疲弊させ、中小企業や小規模事業者の営業を脅かし、雇用不安を招くなど国民生活は大変な影響を受けることになります。
国民のみなさん
政府が行おうとしている消費税増税のための景気対策は、一時的で対象も限定され、富裕層ほど大きな恩恵を受けるものです。「軽減」と宣伝されている複数税率による混乱も心配されています。
消費税率引き上げのために莫大(ばくだい)な予算をつぎ込むなど本末転倒であり、本気で景気対策を行うというのなら、消費税10%への増税こそ中止すべきではないでしょうか。
国民のみなさん
景気悪化を招き、低所得者ほど負担が重いのが消費税の特徴です。「いま、消費税を上げる時なのか」といった疑問の声が大きく広がっています。
私たちは「10月消費税10%ストップ!ネットワーク」を立ち上げ、2019年10月からの消費税増税を中止させるために、あらゆる手段を尽くして活動します。
こうした趣旨に賛同いただき、ともに声をあげていただくことを呼び掛けます。