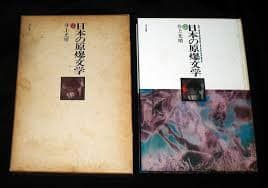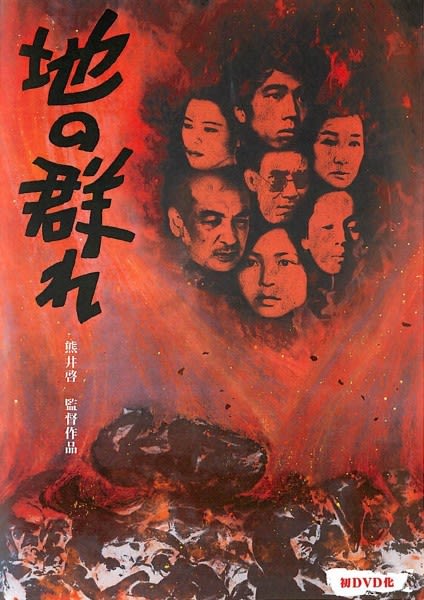(2)「IT イット ”それ”が見えたら、終わり。」を観る。
スティーブン・キングの小説を映画化したものだ。
観始めて15分で一旦停止した。更に10分観て、「このまま返してしまおうか」
と思った。それほど怖かった。(歳をとるとビビり度が増します)
だが試練だと思い、何度も心臓が止まりそうになりながら観た。
何なのだ、観終わった後のこの爽快感は!
「スタンド・バイ・ミー」を観た時のように切なく、また心がほっこりした。
登場する少年たちは、それぞれトラウマを抱えている。
その心の闇に、ペニー・ワイズ(クラウンの姿をした悪霊)が付け入る。
恐怖を膨らませ、破壊へと追いやろうとする。
いじめを受けている黒人の少年は、火事で両親を失った恐怖と呵責(かしゃく)を。
もう一人の少年もまた、弟を死なせてしまった後悔と呵責を。
だが私が一番興味を持ったのは喘息の少年と、父と二人で暮らす少女だ。
少年は発作が起きないようにと、生活のすべてを母親に支配されている。
その母親というのが、身動きするもしんどいくらいに太っていて、
家の中の椅子にすわって多くの時間を過ごしている。
そして「不潔なものは発作を起こす」、「外で仲間と遊ぶと発作を起こす」、と
少年を洗脳する。
”発作”という恐怖で少年をがんじがらめにして、自分の一部にしているようだ。
後に偽の喘息薬を飲ませていたことが分かる。
少女は父親に怯えている。
父親は少女に、「今も自分だけのものか」と常に問い詰める。
恐怖から、洗面所の排水口から髪の毛が逆流し、洗面所を一面真っ赤に
染め上げてしまう。だがこれは少女には見えても、父親には見えない。
その後、父親は少女に性的虐待をしていたことが分かる。
少女の恐怖が、洗面所を血の海にしてしまったのだ。
恐怖を具現化する映像は見事だ。
恐怖に付け入るペニー・ワイズに打ち勝つには、自らの恐怖と向き合って
闘わなければならない。
少年たちと少女は、それをやり抜いたのだ。
(3)夏物語
川上未映子著『夏物語』を読む。
543頁の、その1ページ、1ページが隙間のないほどぎっしり文字で
埋まっている。その分量に圧倒された。
だがのめり込むように読んでいくと、無駄な言葉が一語もないことに気づく。
祖母、母、姉、姪、そして主人公の貧しい暮らしが、まるで目の前で繰り広げられて
いるように感じる。
状況が想像を絶するものであっても、話の進行が普通では考えられないことであっても、
細部を緻密に描くことで、読者はぐいぐい話の中に引き込まれる。
すべての言葉に血が通っている。言葉に生活が宿っている。
『乳と卵』を読んだ時は分からなかったが、今回は川上さんの筆致に
度肝を抜かれ、すっかりファンになっていた。
(4)バイス
ジョージ・W・ブッシュ(子)の下で副大統領を務めた「ディック・チェイニー」を通して
9・11に続く【イラク戦争が間違いだった】ことを訴えている。
たとえ役者が扮しているとはいえ、実在の人物をこれほど赤裸々に描くことの出来る
アメリカ映画の懐の深さに感銘を覚えた。
(5)記者たち 衝撃と畏怖の真実
ロブ・ライナー監督のこの映画も、イラク戦争の大義名分であったはずの
【大量破壊兵器の保有】は間違いだった、という真相を追い詰める
記者たちの物語だ。
アメリカに追随した日本は、イラク戦争に対してどのような検証を行い、
どのように責任を取り、また今後に活かしたのだろうか!
アメリカは、ベトナム戦争を題材にした映画も数多く作っている。
トランプの出現があるとは言え、日本とアメリカの民主主義の違いを
まざまざと見せつけられた映画だ。
恣意的に間違った情報を流し、愛国心に訴えて国民を扇動すれば、
戦争は簡単に起こり得る、このことをイラク戦争を描いた
二つの映画は訴えている。




(画像はお借りしました)
スティーブン・キングの小説を映画化したものだ。
観始めて15分で一旦停止した。更に10分観て、「このまま返してしまおうか」
と思った。それほど怖かった。(歳をとるとビビり度が増します)
だが試練だと思い、何度も心臓が止まりそうになりながら観た。
何なのだ、観終わった後のこの爽快感は!
「スタンド・バイ・ミー」を観た時のように切なく、また心がほっこりした。
登場する少年たちは、それぞれトラウマを抱えている。
その心の闇に、ペニー・ワイズ(クラウンの姿をした悪霊)が付け入る。
恐怖を膨らませ、破壊へと追いやろうとする。
いじめを受けている黒人の少年は、火事で両親を失った恐怖と呵責(かしゃく)を。
もう一人の少年もまた、弟を死なせてしまった後悔と呵責を。
だが私が一番興味を持ったのは喘息の少年と、父と二人で暮らす少女だ。
少年は発作が起きないようにと、生活のすべてを母親に支配されている。
その母親というのが、身動きするもしんどいくらいに太っていて、
家の中の椅子にすわって多くの時間を過ごしている。
そして「不潔なものは発作を起こす」、「外で仲間と遊ぶと発作を起こす」、と
少年を洗脳する。
”発作”という恐怖で少年をがんじがらめにして、自分の一部にしているようだ。
後に偽の喘息薬を飲ませていたことが分かる。
少女は父親に怯えている。
父親は少女に、「今も自分だけのものか」と常に問い詰める。
恐怖から、洗面所の排水口から髪の毛が逆流し、洗面所を一面真っ赤に
染め上げてしまう。だがこれは少女には見えても、父親には見えない。
その後、父親は少女に性的虐待をしていたことが分かる。
少女の恐怖が、洗面所を血の海にしてしまったのだ。
恐怖を具現化する映像は見事だ。
恐怖に付け入るペニー・ワイズに打ち勝つには、自らの恐怖と向き合って
闘わなければならない。
少年たちと少女は、それをやり抜いたのだ。
(3)夏物語
川上未映子著『夏物語』を読む。
543頁の、その1ページ、1ページが隙間のないほどぎっしり文字で
埋まっている。その分量に圧倒された。
だがのめり込むように読んでいくと、無駄な言葉が一語もないことに気づく。
祖母、母、姉、姪、そして主人公の貧しい暮らしが、まるで目の前で繰り広げられて
いるように感じる。
状況が想像を絶するものであっても、話の進行が普通では考えられないことであっても、
細部を緻密に描くことで、読者はぐいぐい話の中に引き込まれる。
すべての言葉に血が通っている。言葉に生活が宿っている。
『乳と卵』を読んだ時は分からなかったが、今回は川上さんの筆致に
度肝を抜かれ、すっかりファンになっていた。
(4)バイス
ジョージ・W・ブッシュ(子)の下で副大統領を務めた「ディック・チェイニー」を通して
9・11に続く【イラク戦争が間違いだった】ことを訴えている。
たとえ役者が扮しているとはいえ、実在の人物をこれほど赤裸々に描くことの出来る
アメリカ映画の懐の深さに感銘を覚えた。
(5)記者たち 衝撃と畏怖の真実
ロブ・ライナー監督のこの映画も、イラク戦争の大義名分であったはずの
【大量破壊兵器の保有】は間違いだった、という真相を追い詰める
記者たちの物語だ。
アメリカに追随した日本は、イラク戦争に対してどのような検証を行い、
どのように責任を取り、また今後に活かしたのだろうか!
アメリカは、ベトナム戦争を題材にした映画も数多く作っている。
トランプの出現があるとは言え、日本とアメリカの民主主義の違いを
まざまざと見せつけられた映画だ。
恣意的に間違った情報を流し、愛国心に訴えて国民を扇動すれば、
戦争は簡単に起こり得る、このことをイラク戦争を描いた
二つの映画は訴えている。




(画像はお借りしました)