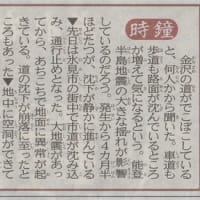都の僧は讃岐の国八嶋に着きました。あたりが暗くなったので土地の漁師に一夜の宿を頼みました。「とても人を泊められるような家ではない」と断られてしまいました。

旅の僧(ワキ)が漁翁(前シテ)に一夜の宿を頼む時、シテに向かって直接話が出来ません。漁夫(ツレ)に取り次いでもらいます。
ツレ詞「暫く御待ち候へ」。と言ってシテの所へ行って「主のその由申し候べし」。「いかに申し候」。「諸国一見の御僧の一夜の宿と仰せ候」。と区切りがありそうだが、テキストではいっぺんでしゃべってしまいます。能を見ていれば役者の立ち回りで様子が分かりますが素謡では続けて出てくるのでよく分かりません。どこで誰に向かって言っているのか考えさせられます。謡は役者が誰に向かってしゃべっているのかいちいち考えながら謡わなければなりません。言葉が難しい上にそこまで考えるのはなかなか大変です。
始めは訝っていた漁翁が僧が都から来たと聞くと途端に態度が変わり、合戦の様子を語ります。

三保乃谷の四郎(源氏方)と悪七兵衛(平家方)が一騎打ちする場面。お互いに相手の兜の錏(しころ)をひっぱりっこするってまるで子供の遊びみたい。
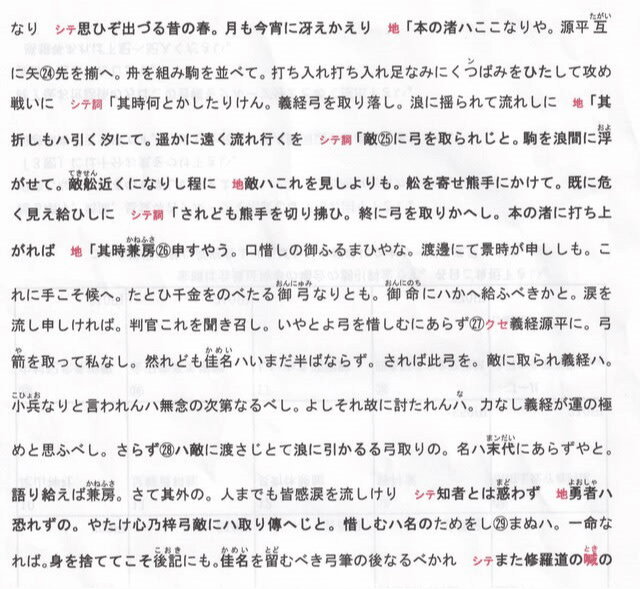
義経が矢を取り落としてしまい平家方にその矢が渡るのを嫌って部下が止めるのも聞かずに拾いに行く。おそまつな自分の矢が敵に笑われては武門の恥だと。立派な甲冑を付けていてそんな恥ずかしい弓を持っていたのだろうか。

キリの部分です。八嶋と聞いてもどんな曲だったかなとちょっと思い出せないが、この部分だけはよく覚えている。能楽堂ではいつも掛る仕舞の部分だ。
仕舞とは謡のいい部分だけ取り出して紋付き袴姿でその部分だけ舞う。
仕舞で思い出したが、舞手の後ろで地謡に人が4人並んで声の伴奏を入れるのだが、何の仕舞だったか覚えていないが、謡っている最中にぷつんと声が切れて静かになったことがある。
セリフを忘れたのかな。と始めは思った。だが、違うのだね。
仕舞の振り付けはきちっと決まっている。誰がやっても同じ舞い方をする。
ところが、時々合わない時がある。舞が終わっても地が謡っていたり、地がおわっても舞手が舞っていたりすると、みっともない。同時に終わらないといけない。なのでどこでどんな舞い方をするか熟知している人が地頭になって謡う。その地頭が声が小さいと横に座っている人がよく聞き取れない。それで一時的に謡うのを止める。地頭さんは舞に合わせて謡っているのでずれることがあるのだ。その地頭さんが喉を痛めて大きな声が出なくなっているのだ。
その地頭さんが大先生だったとしたら今日は地頭を下りてくださいとは言えない。それでこんなトラブルが起きる。めったにないことだが。
昨日金沢能楽会館で写謡の会があった。謡の一部だけ筆ペンで書き写すのだ。
どんな人が来ているのだろうと思ったら、女の人ばかりで男はほとんどおらず恥ずかしかった。今や能は男性の芸能でなく女性の芸能となったようだ。

お手本を下に敷いて薄紙に写すのだがなかなか上手くいかない。
能楽師の講師の発音がよく耳の悪い私でもよく聞き取れて勉強になった。