

東京オリンピック 朝日新聞社説批判 「中止の決断を」に反論する 「五輪開催」支持

朝日新聞社説 2021年5月26日
5月26日朝刊 朝日新聞社説 「東京五輪 中止の決断を求める」(全文)

8月8日 2020東京五輪大会は閉会式 日本の獲得メダル数 金メダル27 銀メダル14 銅メダル17 過去最高 五輪のバトンは北京冬季五輪2022とパリ夏季五輪2024に 出典 TOKYO2020

大竹しのぶさんが子供たちと一緒に登場し、宮沢賢治作曲作詞の「星めぐりの歌」を合唱し,聖火が消える場面を飾った。
閉会式終了後にInstagramに投稿した大竹さんのコメントはまさに筆者のTOKYO2020への思いと重なる。
北京冬季五輪最新情報はこちら
深層情報 北京冬季五輪2022 競技会場 国際放送センター(IBC)・4K8K 5G ・高速新幹線 最新情報
東京オリパラ閉幕 朝日新聞は東京オリパラに対する報道姿勢を検証せよ
9月5日、東京パラリンピックの閉会式が、13日間の熱戦に幕を閉じた。大会では22競技539種目が開催され、日本は前回リオデジャネイロ大会でゼロだった金メダルを13個獲得。銀は15個、銅23個で、総メダル数は51と過去3大会を大きく上回り、史上最多だった2004年アテネ大会の52個に迫り、パラアスリートの活躍で、多くの「感動」と「勇気」をもらった。
閉会式は、「多様性の街」をテーマにした演出だったが、なにか雑然とパーフォーマンスが続き、開会式の「片翼のない飛行機」のようなインパクトはなかった印象を持った。
その中で強烈なインパクトがあったのは「Paris2024」のパラ・アスリートたちのパーフォーマンス、五輪の閉会式に引き続き、「Paris2024」の圧勝。さすが「文化と芸術」の国、フランスには脱帽。
五輪・パラの閉幕を迎え、最大の問題はメディアの報道姿勢である。五輪に対しては徹底的なバッシングを浴びせ、パラリンピックに対してはまったく沈黙する。その「手のひら返し」姿勢には唖然である。
コロナ感染状況は、五輪開催時よりパラリンピック開催時の方がはるかに悪化、東京の感染者数は、パラリンピック開催直前には5000人(8月18日)を突破、医療逼迫は現実化して、感染しても治療も受けられない状況に陥っていた。五輪開催時に朝日新聞は、繰り返し医療逼迫の懸念を唱えていた。パラリンピック開催については医療逼迫は黙認するのか。
パラリンピックの参加者は約4400人、規模は五輪の約半分以下だが、超ビックな国際イベントには変わりはない。
障害者の祭典、「共生社会」の実現という大義名分があれば、コロナ感染拡大のリスクを黙認していいのか。五輪バッシングに奔走したメディアは、パラリンピック開催に沈黙した「手のひら返し」報道姿勢を明快に説明すると共に、報道対応を冷静に検証すべきだろう。
朝日新聞は、一面で東京本社社会部長・隅田佳孝の署名記事で「大会を通して突きつけられた社会の自画像から目を背けず、選手たちがまいてくれた気づきの種を育てよう。その先に大会のレガシーはある」と五輪レガシーについて言及する始末。
また社説では、「パラ大会閉幕 将来に何をどう残すか」と見出しで、「障害の内容や程度は違っても、自らが秘めている能力に気づき、伸ばすことによって、新たな世界が開ける。13日間にわたる選手たちの躍動を通じて、人間のもつ可能性を肌で感じ取った人は多いだろう」として、「選手のプレーに感動し、それをただ消費して終わるのではなく、次代につながる、まさにレガシー(遺産)を残すことに英知を集めねばならない」とレガシー論を述べている。
まさに「なにをかいわんや」である。朝日新聞は、東京オリンピック・パラリンピックを全否定して「開催中止」を主張したのではないか。
女子マラソンの道下美里選手やボッチャ個人での杉本英孝選手は、メディアのインタビューで、涙を流して、悲願の金メダルを勝ち取った喜びとコロナ禍で1年延期された上に、開催されるかどうかわからないという不安に包まれる中で、苦悶しながら大会に向けてトレーニングを積んだ苦しさにさいなまれた日々を語った。
メディアの五輪バッシングが激しく浴びせされる中で、アスリートの五輪大会開催を願う声は完全に封殺された。
BBCニュースは、「東京五輪、国民が支持を表明しにくい日本」と見出しを掲げ、「アスリートが五輪に出たいと言えない、やってほしいという声があげられなくなっている」と「異論が許されない」日本の異常さを指摘している。
競技後のインタビューで、アスリートは、口々に、この1年、コロナ禍で練習の場の確保もままならず、歯をくいしばって大会を目標にしてトレーニングを続けた苦悶の日々を語っている。アスリートたちを追い詰めたのはメディアの激しい五輪バッシング報道だ。
こうしたアスリートたちの活躍で、メダルラッシュに沸き、大きな「感動」と「勇気」がもたらされた。コロナ禍で閉塞した社会に陥っていた日本にほっとする「清涼剤」になったのは間違いない。
産経新聞は、パラリンピックが閉幕した9月6日の「主張」で、「開催は間違っていなかった。可能性を示した選手に拍手を」と述べた。筆者はこの「主張」を全面的に支持する。
東京オリンピック・パラリンピック大会については、消え去った「復興五輪」、開催経費の肥大化、女性蔑視発言、開会式演出担当者の相次ぐ辞任など多くの問題点を抱え、批判されてしかるべきである。
しかしながら、東京オリンピック・パラリンピック大会を全否定をするメディアの報道姿勢には納得できない。
東京パラリンピック大会終了を待たずに、菅首相は突如、退陣表明。日本は一転して政局の季節に突入した。安倍長期政権とそれ引き継いだ菅政権、日本の政治は節目を迎える。
いずれにしてもコロナ禍で開催された2020東京オリンピック・パラリンピックは、1964大会に並ぶ、「歴史に残る」大会になったのは間違いない。

9月6日 朝日新聞社説 「パラ大会閉幕 将来に何をどう残すか」
東京パラリンピック開幕 パンデミックの中での「強行」ではないのか?
朝日新聞は、五輪開会式の日(7月23日)の朝刊で、「五輪きょう開会式 分断と不信、漂流する祭典」という見出しで社説を掲載、「東京五輪の開会式の日を迎えた。鍛え抜かれたアスリートたちがどんな力と技を披露してくれるか。本来ならば期待に胸躍るときだが、コロナ禍に加え、直前になって式典担当者の辞任や解任が伝えられ、まちには高揚感も祝祭気分もない。(中略)
社説はパンデミック下で五輪を強行する意義を繰り返し問うてきた。だが主催する側から返ってくるのは中身のない美辞麗句ばかりで、人々の間に理解と共感はついに広がらなかった。分断と不信のなかで幕を開ける、異例で異様な五輪である」とした。
そして、「感染防止を最優先で この1年4カ月は、肥大化・商業化が進んで原点を見失った五輪の新しい形を探る好機だった。実際、大会組織委員会にもその機運があったという。ところがいざ実行に移そうとなると、関係者の思惑が絡み合い、何より国際オリンピック委員会(IOC)と、その背後にいる米国のテレビ局や巨大スポンサーの意向が壁となって、将来につながる挑戦にはほとんど手をつけられなかった」と厳しく批判した。
これに対して、パラリンピックの開催式が行われた翌日、朝日新聞は、1面で「<視点>共生社会へ、人々つなぐ大会に」という見出しの記事を掲載した。
パラリンピック・アスリートに対しては、「大会延期決定から1年。選手たちは自国開催への思いを声高に語ることはできず、もどかしさを抱く」としてアスリートを思いやるコメントをのせた。
そして、「残された体の機能を最大限に生かし、競技で表現する選手の姿は、たしかに心に響くものがある。それでも、新型コロナウイルスの感染拡大が収まらないなか、大会を開く意義は何か。記者も問い直す日々が続く。この大会が、違いを認め合い、わたしたちが生きる希望を見いだせるきっかけになれば、と願う。(中略)4400人の選手たちがそれぞれの思いを胸に臨む。人々がつながるための気づきがきっとある」とパラリンピック開催を「歓迎」し「賛美」するコメントで締めくくった。
「五輪」と「パラリンピック」に対するこの違いは一体、どうなっているのだろうか。まったく納得できない。「五輪」のアスリートの思いにはまったく「無視」して、「パラリンピック」のアスリートには「共感」を寄せる、朝日新聞はその姿勢の違いを論理的に説明すべきだ。
「五輪」に対する批判記事を執筆した朝日新聞の記者や論説委員、それに有識者や外部評論家は、パラリンピック開催についてどう考えているかコメントすべきだ。沈黙するのはあまりにもお粗末な対応だろう。
パラリンピックもさらに深刻化したコロナ・パンデミックの中で「強行」された国際スポーツイベントなのである。
朝日新聞社説 パラリンピック開催は支持「安全対策に万全期して」
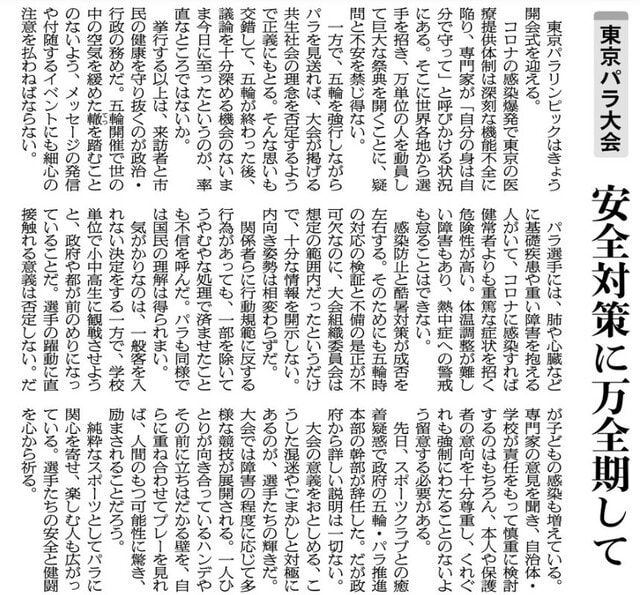
朝日新聞社説(8月24日) 「東京パラ大会 安全対策に万全期して」 上記の「東京五輪 中止の決断を求める」の社説と読み比べて欲しい
今日(8月24)、東京パラリンピックは開会式を開催する。
朝日新聞は、五輪開催については激しく攻撃を繰り返していたが、パラリンピック開催についてこれまで沈黙を続けていた。
新型コロナウイルスの「感染爆発」という危機的な状況の中で、「世界各地から選手を招き、万単位の人を動員して巨大な祭典を開くことに、疑問と不安を禁じ得ない」としたが、開催については、「手のひら返し」をして「延期」や「中止」を主張せず、「安全対策に万全期して」して開催して欲しいとする。
その一方で、「五輪を強行しながらパラを見送れば、大会が掲げる共生社会の理念を否定するようで正義にもとる。そんな思いも交錯して、五輪が終わった後、議論を十分深める機会のないまま今日に至ったというのが、率直なところではないか」と「言い訳」をした。
「議論を十分深める機会」がなかったとして、世論の責任に転嫁しているが、朝日新聞はパラリンピック開催については「議論を十分深める」ことを行ったのか。これまで沈黙していたのではないか。メディアとしての責任を問う。
そして、パラリンピック大会開催意義として「選手たちの輝き」を上げ、「大会では障害の程度に応じて多様な競技が展開される。一人ひとりが向き合っているハンデやその前に立ちはだかる壁を、自らに重ね合わせてプレーを見れば、人間のもつ可能性に驚き、励まされることだろう」とし、「純粋なスポーツとしてパラに関心を寄せ、楽しむ人も広がっている。選手たちの安全と健闘を心から祈る」と締めくくった。「五輪」とは一変して「暖かさ」にあふれたコメントだ。
五輪大会中止を掲げた社説と読み比べて、五輪大会とパラリンピック大会に対する報道姿勢の違いに唖然とする。五輪のアスリートには「輝き」や「人間のもつ可能性に驚き、励まされる」ことはないのか。偏見に満ち溢れた不公正な論評に対して筆者はまったく納得しない。朝日新聞は五輪大会でのアスリートの姿に「感動」や「勇気」を感じ取っていないのか。
繰り返すが筆者は、障害者の世界最大のスポーツの祭典であるパラリンピックの開催意義は高く評価し、コロナ禍でもその開催を強く支持している。コロナ禍だからこそ「感動」と「勇気」がもらえる大会開催は極めて大きな意味がある。
朝日新聞は、朝日新聞のコマーシャルで、「スポーツは希望になる」として、1964東京大会の開催に尽力した朝日新聞記者の田畑政治氏を取り上げ、「若者が世界に挑戦する舞台を作り続けた」とし、「憧れを絶やすな」「スポーツのすそ野を広げていく」と宣言している。五輪バッシングを激しく続けた姿勢はどこにいったのか。
しかし、新型コロナウイルスの感染状況は五輪開催時より更に深刻化して、「感染爆発」、「災害クラス」、医療崩壊は現実化して中での開催を批判しない朝日新聞などのメディアは糾弾に値する。
パラリンピック明日開幕 朝日新聞は、パラリンピックの開催中止をなぜ主張しない
明日8月24日から、8月8日に閉幕した2020東京五輪大会に引き続き、8月24日から9月5日まで、パラリンピックが開催される。22競技、539種目が1都3県の21の競技会場で開催され、約4400人が参加する世界最大の障害者スポーツの祭典である。
コロナ禍の大会開催となり、一般観客はすべての会場で受け入れないが、「学校連携プログラム」による小中高生の感染は認めることになった。
五輪閉幕後も新型コロナウイルスの感染拡大は、更に加速し、「感染爆発」、「制御不能」、「災害レベルの感染猛威」という事態を迎えている。
全国の新規感染者数(8月20日)は2万5876人、五輪が開幕した時は4377人(7月23日)は4377人、約6倍増、東京では1359人に対して5405人で約4倍と感染爆発が止まらない。
8月22日、組織委員会は、東京パラリンピックの選手2人を含む、大会関係者30人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表した。パラリンピック関係者の1日の陽性者数としては、過去最多を記録した。
医療逼迫の懸念は五輪時よりはるかに高まっている。
東京の入院者数(軽傷中等症)は3968人に達し、病床使用率は66.5%、重症者数は271人に重症床使用率は69.1%、入院が必要な患者が病床が足らなくて入院できないケースが常態化している。医療崩壊が現実化しているのである。
競技会場で大会関係者に傷病者が出た場合に受け入れる「指定病院」の都立墨東病院が、救急で重症者を受け入れは行うが、「新型コロナウイルス感染症を最優先としながら対応する」という。苦渋の選択である。こうした動きは他の病院にもあるという。都立墨東病院は「開催の是非」を議論すべきだとした。(8月19/20日 朝日新聞)
こうした状況の中で、朝日新聞はパラリンピック開催の是非を論評する記事を掲載しない。唯一、「パラ学校観戦 割れる判断」(8月18日朝刊)だけが論評記事である。
あれだけ、五輪開催については激しく批判していた報道姿勢とは一変をしたのには唖然とする。
五輪開催時には、医療崩壊を理由に五輪開催を激しく批判したに対し、パラリンピック開催については、医療崩壊が現実化しているにも関わらす、開催を一切批判しない。
朝日新聞はメディアとしての責任をどう考えているか。パラリンピック開催に関する批判をファクトを踏まえて掲載すべきだ。
新型コロナウイルスの感染状況は、五輪開催を直前に控えた7月上旬より、今の方がはるかに深刻化している。もはや「感染爆発」、「制御不能」、「災害レベル」の感染猛威なのである。
「オリンピック」と「パラリンピック」とでは開催の理念が異なり、「パラリンピック」は障害者スポーツの祭典であることは十分理解した上で、その開催意義は高く評価したい。
にもかかわらず、残念だが、今の深刻なコロナ禍の中では、五輪大会以上に、アスリートや大会関係者の感染拡大リスクは「制御不能」と言わざるを得ない。
また五輪開催で、国民の感染対策に「気の緩み」が生じると激しく批判したが、パラリンピック大会の開催で「気の緩み」は懸念しなくてよいのか。論理的に説明して欲しい。
朝日新聞は、こうした状況を踏まえて、「パラリンピック」開催是非について、社説などで見解を表明すべきだろう。「沈黙」はメディアとしての責任放棄である。
宮崎商業 東北学院 試合を辞退 大阪桐蔭ブラスバンド 部員感染、甲子園での応援断念
8月17日、高校野球大会本部は、選手ら5人の新型コロナウイルス陽性が確認された宮崎商業と東北学院が試合を辞退し、これを受理したと発表した。
宮崎商業では今月14日の夕方、選手1人が発熱し、PCR検査で陽性反応を示していましたが、宿舎に入っているチーム関係者35人が医療機関で検査を受けた結果、発熱した選手を含め13人の感染がわかり、さらに保健所から8人が濃厚接触者と判断された。東北学院は、選手1人の陽性が確認され、選手3人と朝日新聞社の記者1人が濃厚接触者となった。
高野連と朝日新聞社は、今大会で出場の可否を判断する際「個別感染」か「集団感染」かを重要視していて、宮崎商業については「集団感染」に該当すると判断し学校側に伝え、17日午前、宮崎商業から19日の初戦を前に出場を辞退するという申し出があり受理したとした。東北学院については、大会本部は「個別感染」としたが、東北学院は、出場するれば感染者や濃厚接触者が特定される恐れがありり、生徒の将来に影響を及ぼす可能性を懸念して「辞退」という判断に至ったという。東北学院副校長は「大変残念だが、生徒のプライバシーを守りたい」と述べた。
宮崎商業と東北学園の対戦予定校は不戦勝になる。宮崎商は13年ぶり5回目の出場、東北学院が初出場だった。
朝日新聞は、五輪大会では、コロナ感染で棄権した選手が出たことに言及し、「コロナ禍で涙をのんだ選手たちにとって、この五輪は公平だったと言えるのか。悩みながら出場した選手たちの思いは、報われたのだろうか」と主張した。高校野球については同じ主張はしないのか。高校野球の選手たちの思いは受け止めないのか。
一方、大阪桐蔭吹奏楽部はブラスバンド演奏による応援を予定していたが、同部内に新型コロナウイルス感染者が発生したため、急きょ応援を取りやめた。同部OB会の公式ツイッターが「大切なお知らせ」と題し、「この度、吹奏楽部で新型コロナウイルス感染者が判明したため、本日予定していた甲子園での応援を取りやめる事になりました。楽しみにして頂いていた皆様には大変申し訳ございません」と投稿した。
ついにコロナ感染は、選手や学校関係者に及び、前代未聞の2校の出場校辞退という状況に追い込まれた。
更に悪天候の影響で、今日(8月18日)の試合開催も中止、史上最多の6度目の「延期」となり、選手の健康を守るために設けられた「休息日」も3日が設定されていたが、準々決勝後の1日だけに削減された。「強硬日程」に対しての批判記事は一切ない。
こうした状況の中で、朝日新聞は高校野球の開催をこのまま継続することが適切なのか、論評する記事を一切掲載していない。五輪開催を激しく批判した報道姿勢はどこにいったのか。メディアとしての責任が問われる。
東海大菅生-大阪桐蔭 豪雨に見舞われ8回表でコールドゲーム 7対4で大坂桐蔭が勝利
大会3日目の第一試合、東海大菅生-大阪桐蔭の試合は8回の表、東海大菅生の攻撃の最中に中断、甲子園球場は豪雨でグランドは水浸しになっていた。 雨は降りやまず、その後、ノーゲームが宣告され、8回表でコールドゲームとなり7対4で大坂桐蔭の勝利となった。しかし問題は、「中断」の判断は遅すぎたことだ。雨は5回頃から激しさを増し、中継映像を見ていても雨で明らかに視界がなくなり、グランドは水たまりになっていた。なぜ試合が成立する7回前に判断してノーゲームとして再試合にしなかったのだろうか。雨で延期が相次いでいる中で、強引に試合消化を優先させた運営姿勢は非難されてしかるべきだろう。とくかく大会本部は、なにがなんでも「開催ありき」、明らかにアンフェアな判断だった。
NHKは、生中継番組で、「続行やむなし」を言い続けて、7回に入る前に「中断」について言及しなかったNHKアナウンサーと解説者の責任も問われる。
甲子園に入場認める学校関係者の範囲を制限
8月20日、高野連と朝日新聞社は、阪神甲子園球場に来場できる代表校の学校関係者を、野球部員とその家族らに制限すると発表した。新型コロナウイルス感染の急拡大や、球場がある兵庫県が緊急事態宣言の対象になったことを受けた措置で、22日から適用する。
来場者は代表校の校長が健康状態を管理できる野球部員や家族(選手・指導者1人につき3人まで)、教職員のみとする。吹奏楽部員やチアリーダー、一般の生徒らは来場できなくなる。
これに先立って大会本部は16日に、学校関係者を生徒、保護者、教職員、野球部OB・OGらに限定し、それ以外の卒業生などを対象から外し、入場を認めている学校関係者の範囲を大会第5日(17日)から制限すると発表した。学校関係者の定義を生徒、保護者、教職員、野球部員だった卒業生とし、校長が氏名、連絡先などを管理できる人にした。
第7日(19日)までについては返券に応じ、この措置に伴っての移動、宿泊のキャンセル料は主催者が負担するとした。
しかし、「校長が氏名、連絡先などを管理できる人に限る」としたことで、これまでの「学校関係者」とは一体何だったのかという疑問がわく。学校が甲子園で観戦したいという人を募って、一般市民でも幅広く観戦が可能だったのではという疑念が生まれる。だとすればなんとも杜撰な「制限」と言わざるを得ない。
また、代表校の関係者の感染者が出ても、「個別感染」か「集団感染」かを見極めて「個別感染」と見なされれば、チームとしての試合の出場は認められる可能性があるとしている。しかし、代表校の関係者は同じ宿舎に宿泊をしていて、練習、移動などは常に同一行動、マスク着用で「密」は避けるにしても、感染者が発生したら、「個別感染」か「集団感染」にかかわらず、感染リスクは極めて高くなるのは明らかだろう。朝日新聞は五輪大会で「個別感染」か「集団感染」の区別について言及したのか。高校野球だけなぜ特別扱いするのか説明を求めたい。
「開催ありき」の姿勢はまさに高校野球にある。
朝日新聞は高校野球関係者のコロナ感染者を公表せよ 選手1人陽性 朝日新聞記者も濃厚接触者で待機
速報 宮崎商業の選手ら5人がコロナ感染
高野連=日本高校野球連盟や朝日新聞は、宮崎商業の選手1人が14日夕方に発熱し、15日に病院でPCR検査を受けたところ陽性反応を示し、これを受けてほかの選手などもPCR検査を受けた結果、16日朝までに新たに選手など4人の感染が確認されたことを明らかにした。
感染が確認された5人を含むチームの関係者は濃厚接触者について保健所の判断が出るまで宿舎の個室でそれぞれ待機している。
宮崎商業は18日、第1試合で智弁和歌山高校との初戦に臨む予定になっている。
大会主催者は、出場の可否について、濃厚接触者についての保健所の判断を待って緊急対策本部の会議を開き決定するとしている。
一方、政府は今月31日までを期限に「蔓延(まんえん)防止等重点措置」を適用している兵庫、京都、福岡にも新たに「緊急事態宣言」を発令する方向で検討が進められている。朝日新聞は、「緊急事態宣言」のが発令された東京で、五輪開催を行うことに対して強く批判をした。兵庫に「緊急事態宣言」が発令されたら、朝日新聞は「高校野球開催」を予定通り無批判に続けるのだろうか。主催者として、メディアとしての説明を強く求める。
朝日新聞社は「高校野球大会中止」を検討しないのか
日本人選手のメダルラッシュで沸いている五輪大会の開催中の7月27日、東京都の新型コロナ新規感染者数が過去最多となったことを受け、菅首相は、オリンピックを中止するという選択肢はあるかとの質問に対して、オリンピック中止の可能性を否定した。
菅首相は、コロナ感染の再拡大が進む中で、朝日新聞社を始め、メディア各社から、オリンピック中止の可能性を再三に渡って問われていた。
8月12日、朝日新聞は、一面トップで「31都道府県『感染爆発』」とい見出しを掲げ、厚労省の専門家組織は首都圏を中心に「もはや災害時の状況に近い局面」だと強い危機感を示したと伝えた。最早、日本は「感染爆発」の危機に立たされているのである。
こうした中で8月10日に朝日新聞社と高野連が主催する夏の甲子園大会が開催されている。今日は雨のために中止となり、試合は明日以降に順延となった。
朝日新聞などメディアは、五輪開催については、コロナ感染者が急速に増加している中、「中止の可能性」について、必要に菅首相に迫った。
しかし、「感染爆発」の危機に突入したという局面の中でも、主催者である朝日新聞社は「高校野球中止」問題について言及をしない。開催を懸念する記事すら一切ない。
筆者はこうした朝日新聞の報道姿勢にまったく納得しない。
朝日新聞やメディアが五輪に対しては「中止の可能性」について菅首相に迫ったと同様に、高校野球の「中止」の可能性を朝日新聞社に問いたい。メディアとしての良心と正義が問われている。
コロナ感染者爆発の危機は、明らかに五輪開催時を上回っている。

8月12日 朝日新聞1面 「31都道府県『感染爆発』」
朝日新聞は「高校野球」だけを特別扱いするな!
8月10日、夏の高校野球大会が開幕した。開会式の選手宣誓で、小松大谷(石川)の木下仁緒主将は、「1年前、甲子園という夢がなくなり、泣き崩れる先輩たちの姿がありました。しかし、私たちはくじけませんでした。友の笑顔に励まされ、家族の深い愛情に包まれ、世界のアスリートから刺激を受け、一歩一歩歩んできました」と述べ、「人々に夢を追いかけることの素晴らしさを思いだしてもらうために、気力、体力を尽くしたプレーで、この夢の甲子園で高校球児のまことの姿を見せることを誓います」力強く締めくくった。
「夢の甲子園」で高校球児が見せる「感動」と「勇気」そして、「希望」は、コロナ禍の中で閉塞感が溢れている今の日本の中で、後世に残るレガシーになる大会になることは間違いない。
しかし、筆者は、朝日新聞の「五輪」に対する激しい批判と「高校野球」に対する報道姿勢に大きな疑問を抱く。
五輪大会を目指したアスリートへの思いは無視して、高校球児の思いはしっかり受け止める、五輪あるリートの思いと高校球児の思いに違いはあるのか、朝日新聞に問いたい。
五輪大会を社説で「中止勧告」をしたり、五輪バッシングを執拗に繰り返した姿勢への反省が一切ない。五輪は開催反対で、高校野球はなぜ開催なのか明快な説明が欲しい。
夏の甲子園大会は、夏のスポーツビックイベントして全国的に絶大な人気がある。甲子園大会の関心の高まりは、出場校のある地域などを中心に、「人流」が増え、市民のコロナ対策への「気の緩み」を誘発するのは間違いない。
朝日新聞は、五輪開催で市民の「気の緩み」が生まれ、「人流」が増加して、コロナ感染が増加する懸念を繰り返し指摘した。しかし、夏の甲子園大会ではその懸念がないのか。朝日新聞は明快な説明をすべきだ。五輪大会だけ、批判をして高校野球の悪影響には眼をつぶる報道姿勢には、まったく唖然とする。
新型コロナウイルスの新規感染者は、高校野球が開幕した8月9日、全国で1万2073人、重症者は1190人と五輪が開催された7月23日に比べて倍以上になり、感染状況は更に悪化している。地元大阪や兵庫の新規感染者数は、大阪で995人、兵庫で275人に及び、病床占有率は40%を超えている。コロナのパンデミックは、五輪開催の時よりも更に悪化している。
朝日新聞は、五輪開催による医療体制逼迫を厳しく警告した。しかし、夏の甲子園大会の開催で、地元の大坂、神戸の医療体制逼迫を警告する記事は一切ない。大坂、神戸の医療体制は崩壊寸前であろう。なぜ医療体制に言及しないのか朝日新聞は説明するべきだ。ちなみに五輪関係者で、コロナ感染で入院した人は、わずか4人で、五輪関係者のコロナ感染による「医療崩壊」は起きなかった。また、海外から来日した選手や大会関係者から、日本の市民にコロナの感染が広まったというファクトは今の所はない。
また、多くの専門家やメディアは、五輪開催で「気の緩み」が生じて、「人流」が増して感染拡大に輪をかけたとしているが、印象論に基づいた発言、エビデンスがない。五輪開催で本当に「人流」は増えたのか。むしろ「巣ごもり観戦」で外出は減ったのではないかと筆者は分析する。
8月10日、東京都医学総合研究所は、GPS の移動パターンからレジャー目的の人流・滞留を推定して、主要繁華街にレジャー目的で移動・滞留したデータを抽出して、主要繁華街 滞留人口を推定した。
その結果によると、夜間滞留人口は、前週より 4.5 % 減少、6週連続の減少となった。7週前(6/20-26)と比較すると 30.2 % 減 となる。昼間滞留人口や、前週より 2.5% 減少、5週連続の減少となった。6週前(6/27-7/3)に比較して:19.7% 減 である。このデータを見ると、五輪開催が「人流増」につながったとするエビデンスはない。
五輪と「人流増」の関係は、印象論でなく、エビデンスで論議するべきだろう。
今年の夏の甲子園大会では、一般の観客は入れないが、参加各校の関係者や応援団などは1校当たり2000人を限度に入場を認めた。全国から選手や学校関係者が、交通機関や貸し切りバスを連ねて甲子園に集まる。
政府や専門家は、感染防止策としてお盆を迎える中で「県境超える移動」の自粛を強く要請している。高校野球の開催はこうした要請に明らかに背反していることは間違いない。主催者の朝日新聞はこれをどう説明するのか。
朝日新聞の論説委員・郷富佐子氏は「日曜に想う 『パラレルワールド』で起きたこと」とタイトルで、ボート競技のイタリア男子代表、ブルーノ・ロゼッティ選手
がコロナ検査で陽性となり試合への出場ができなくなったり、サーフィン男子のポルトガル代表など、コロナ感染で棄権した選手が複数いたことに言及し、「おそらく今晩の閉会式で、バッハ会長は、高らかに「困難を乗り越えた東京五輪の成功」を宣言するだろう。 だが、いま一度、問いたい。コロナ禍で涙をのんだ選手たちにとって、この五輪は公平だったと言えるのか。悩みながら出場した選手たちの思いは、報われたのだろうか」と結論づけた。
筆者は、郷富佐子氏に問いたい。
今年の高校野球大会では、優勝候補筆頭の東海大相模高校で関係者31人が感染するというクラスターが発生し、県大会の出場を辞退、強豪校の福井商業や星稜(金沢市)、中越(長岡市)も感染者を出して県大会の出場を辞退している。
こうした状況の中で、今年の高校野球は、「公平」だと言えるのか。
朝日新聞の、ファクトを無視したアンフェアな五輪バッシング報道姿勢には唖然とする。
さらに問題なのは、社説で「五輪反対」を唱えながら、五輪大会を支援するオフイシャル・サポーターを辞退せず、「経営と記事は別」として、スポンサーとしての営業活動を続けたことだろう。日本選手のメダルラッシュに沸くと、朝日新聞は、「手のひら返し」で五輪批判記事を引っ込めて、アスリートの「感動」と「称賛」の記事で紙面は溢れかえった。開催期間中は連日号外を発行し、日本選手の活躍を讃えている。号外には、しっかりスポンサーの広告も掲載、広告料収入もしっかり得ている。五輪を激しく批判しておきながら、アスリートへの「感動」を「売り物」にしている営業姿勢は問われてしかるべきだ。
ライバルの読売新聞が7~9日に実施した全国世論調査では、東京五輪が開催されてよかったと「思う」は64%に上り、「思わない」の28%を大きく上回った。
朝日新聞は、8月9日の1面で、東京本社スポーツ部長・志方浩文氏は「確かな理念を伝えられぬまま、東京五輪は終わった。でも、まだできることはある。組織委がすべての反省点を洗い出し、持続可能な五輪につなげる提案ができたなら、レガシーと言えるものになる」と述べた。
しかし、検証しなければならいのは、組織委だけでなく、五輪ネガティブ報道に終始した朝日新聞の報道姿勢にある。朝日新聞の記者はすべて五輪ネガティブ報道を支持したのか。異論はなかったのか。社内で、五輪ネガティブ報道に対して、「ものを言えない」雰囲気がなかったのか。
激しく五輪開催を批判する記事を執筆した記者の人たちに問いたい。
五輪開催時よりより深刻になっているコロナの感染状況の中で、高校野球を開催することに何の疑問も持たないのか? 朝日新聞が主催するイベントだから批判はしないのか。ジャーナリストとしての正義が微塵も感じられない。
朝日新聞を中心とするメディアの激しい五輪バッシング報道で、社会全体に、「五輪開催支持」だがそれを唱えられないという雰囲気が蔓延した。メディアに登場する評論家や有識者の多くは、ほとんど盲目的に五輪反対に追随した。まるで五輪反対を主張しないとまづいのではと思っているがごとくの無節操な大合唱を繰り返した。冷静にファクトを見つめる姿勢がない。
こうした五輪バッシング報道で、追い詰められたのは、五輪を目指してきたアスリートたちである。
競泳日本代表の池江璃花子選手は、ツイッターで「(東京五輪代表を)辞退してほしい」「(五輪の開催に対して)反対の声をあげてほしい」といったメッセージが複数寄せられていることを明かした。
池江選手は「このコロナ禍でオリンピックの中止を求める声が多いことは仕方なく、当然のことだと思っています」としながら、2019年2月に白血病と診断されたことを受けて、「持病を持ってる私も開催され無くても今、目の前にある重症化リスクに日々不安な生活も送っています」と書いた。
そして、「私に反対の声を求めても、私は何も変えることができません」とコメント。「この暗い世の中をいち早く変えたい、そんな気持ちは皆さんと同じように強く持っています。ですが、それを選手個人に当てるのはとても苦しいです。わたしに限らず、頑張っている選手をどんな状況になっても暖かく見守ってほしいなと思います」と苦しい胸を内を明らかにした。
アスリートの多くは、「五輪開催」を唱えたくても唱えられない状況に追い込まれたいただろう。社会全体に「ものを言えない」閉塞状況が覆った。まさに五輪反対ファシズム、冷静な議論の場を確保するデモクラシー社会を放棄した。
こうした状況を生み出したのは朝日新聞を中心とするメディアの責任だ。メディアの責任は極めて重い。
筆者は、改めて明快にしておきたいのは、熱烈は高校野球ファン、毎年、テレビ中継に1日中かじりついている。去年は中止になり本当にがっかりした。コロナ禍の中でも、感染防止対策を進めながら開催する姿勢を支持したい。コロナとの戦いは長期戦になるのは間違いない。コロナ禍だからこそ、スポーツイベントの開催を簡単に諦めるのではなくて、なんとか開催して、国民に「感動」と「勇気」を与えていくことが必須だろう。
「五輪」も「高校野球」もまったく同じだ。
一方で、筆者は五輪の在り方に全面的に賛同しているわけではない。
止まることを知らない肥大化、膨大に膨れ上がる開催経費と地元負担の重圧、過度な商業主義、国際オリンピック委員会(IOC)の閉鎖的な体質や「浪費」体質、賄賂が横行する腐敗体質など厳しく批判を続けてきた。
また完全に吹き飛んだ「復興五輪」の開催理念や招致を巡る贈収賄疑惑、放射能汚染水を巡る安倍前首相の発言問題も問い続けたい。この姿勢は変わることはない。
しかし、筆者はオリンピックの開催理念、「多様性」と「調和」は支持したい。
「分断」と「対立」を超えるツールとして「スポーツの力」を信じたい。

7月27日 朝日新聞号外
メダリストの涙の裏に「追い詰められた1年」の苦悶を見た
五輪開催に対してメディアは連日のように激しい「五輪バッシング」を浴びせ続けた。
BBCニュース(6月12日)は、「(日本)国内の議論は極めて感情的なものとなった。異なる意見は許されず、開催に前向きな思いをもつ人はそれを表明するのを恐れた。その影響はアスリートにも及んだ。白血病から復帰して競泳の東京五輪代表に内定し、多くの人に感動を与えた池江璃花子選手には、出場辞退を求める声がソーシャルメディアで寄せられた。彼女は、『このコロナ禍でオリンピックの中止を求める声が多いことは仕方なく、当然の事』である反面、『それを選手個人に当てるのはとても苦しい』とツイートした。中村知春選手も、『東京オリンピック・パラリンピックをやりたい、と声を大にして言えないのは、それはアスリートのエゴだとわかってるから。 別に何も考えてない訳じゃない』とツイッターに投稿した」と伝えた。
アスリートが五輪に出たいと言えない、開催してほしいいう声が上げられなくなっていた。
アスリートを追い詰めたのは、メディアの激しい「五輪バッシング」だったのは間違いない。
メダルを獲得して表彰台に上がったアスリートには、笑顔と同時に涙があった。筆者は、涙の裏に、コロナ化で練習もできない一方で、目標としている五輪大会開催に激しい批判が浴びせられて苦悶し続けていた姿をアスリートの姿を見た。
柔道、競泳、卓球、ソフトボール、そして史上最年少の金メダリストが出たスケートボード、五輪大会には、「感動」と「勇気」がもらえる。
朝日新聞は、五輪大会の「感動」と「勇気」を伝える資格がない。
「金メダルラッシュ」 コロナ禍の中で「感動」と「勇気」を与えてくれるアスリート
2020東京五輪大会は、開会式のNHK中継番組が、56・4%(ビデオリサーチ調べ 関東地区)という「驚異的」視聴率を獲得し、1964年東京五輪の61・2%に迫った。瞬間最高は61・0%に達したという。
序盤戦の日本人選手の活躍は目覚ましく、「金メダル」ラッシュである。柔道では阿部詩選手と阿部一二三選手の兄妹が揃って金メダルに輝く。兄妹の同時金メダルは初の快挙である。競泳400メートル個人メドレーでは大橋悠依選手が完勝して金メダル、新種目のスケートボードでは堀米雄斗選手も金メダルを獲得した。
そして、今日(7月26日)は、スケートボード女子ストリートで13歳の西矢椛選手が日本選手で史上最年少となる金メダルを獲得、また、16歳の中山楓奈選手が銅メダルを獲得した。五輪大会の新競技で2人の10代のメダリストが誕生した。夜になって柔道男子73キロ級で、大野将平選手が二連覇を達成した。
こうした日本人選手の大健闘で、東京五輪大会の熱気は一気に高まった。アスリートの活躍は、コロナ禍で閉塞感が溢れる中で、ひときわ感動と勇気をもたらしてくれる。
朝日新聞は、7月26日の朝刊の1面トップで初めて、「大橋 堀米 阿部一 阿部詩 金 兄妹で『金』 家族とともに」という見出しで、五輪大会での選手の活躍を讃える記事を掲載した。スポーツ面でも同様な趣旨の特集記事を掲載している。五輪大会に対する「熱気」を明らかに高める記事だ。
これまで、朝日新聞は、五輪大会に対して痛烈な批判を繰り返してきた。その姿勢はどこにいったのか? 金メダルラッシュが続けば五輪批判はやめるのか? 余りにも節操がない「手のひら返し」のお粗末な報道姿勢である。
朝日新聞は「五輪開催中止」を声高に社説に掲げて、五輪開催の意義すら否定したことを忘れたのだろうか。
メディアは姿勢の一貫性が求められる。さもないとメディアとして最も重要な「信頼性」を失うだろう。

「大橋 堀米 阿部一 阿部詩 金 兄妹で『金』 家族とともに」 一転して日本選手の活躍を1面トップで報道 朝日新聞 7月26日 朝刊1面
夏の高校野球大会 一般観客はなし 学校関係者は入場は認める
7月22日、朝日新聞社と日本高等学校野球連盟は、第103回全国高等学校野球選手権大会を8月9日から25日まで(雨天順延)、北海道、東京から2校ずつ、45府県から1校ずつの計49代表校が出場して、阪神甲子園球場(西宮市)で開催すると発表した。選手や大会役員・スタッフらがPCR検査を複数回受けるなどの新型コロナウイルス感染防止対策に万全を期すとしている。
焦点の観客の受け入れについては、一般の観客の入場は止めて、代表校の学校関係者に限り受け入れることとした。
観客受け入れの可否については、政府や兵庫県などの大規模イベント実施の指針、「観客上限1万人」を踏まえた上で、入場者数を大幅に制限するケースを検討してきたが、全国各地から観客が来場し、長時間観戦することで感染リスクが高まる恐れがあることから、今回の判断になったという。
なお、各代表校の生徒や保護者らについては当該試合に限り、入場可能とした。
朝日新聞社は「五輪中止」と主張して「高校野球」は「開催」するのか
新型コロナウイルスの新規感染者は、東京で約2000人、全国で約5000人と爆発的増加が止まらない。お盆が終わる8月末には、更に増えるという予測がされている。
状況は更に悪化しているのは間違いない。
「五輪中止」の根拠として、大会を開催すると、県境を越えて全国からの「人流」が増加することを上げている。高校野球を開催したら、全国各都道府県から49代表校が甲子園に集まる。さらに1校当たり約2000人の学校関係者の入場を認めるために、全国から延べ10万人近い人が甲子園にやってくる。参加者の満載した専用バスを何十台も連ねて、甲子園から遠い地域では12時間以上かけて往復する光景が繰り広げられる。狭い社内に缶詰状態になり感染リスクは極めて高い。
政府や感染が拡大している首都圏は、「県境をまたぐ不要不急の移動は控える」、「ステイホーム」を訴えている。
高校野球の開催は、こうした方針に明らかに背くもものである。
「五輪開催」は、こうした「人流」増は、感染者の増加を招き、医療の逼迫を招くと主張していたのではないか。
また、「五輪開催」で、大会の雰囲気が高まり、気が緩むのが問題とする論拠も出された。高校野球は夏のスポーツイベントとして、絶大な人気を誇る。地元の高校が勝ち進めば、熱気が沸き上がるのは当然であろう。高校野球で熱気が沸き上がるのは許されて、五輪大会ではなぜだめなのか。納得のいく説明が欲しい。
また高校野球の宿舎は、西宮周辺の旅館やホテルだが、選手たちは個室ではなく、「大部屋」と宿泊となる。五輪の選手村の環境よりはるかに悪い。
筆者は、高校野球を「中止」を主張しない。高校球児の夢と希望をかなえるために是非開催すべきだと考える。学校関係者を受け入れるのも賛成である。
同様に、五輪開催は支持、無観客ではなくて限定的ではあるが有観客で開催すべきだ。
五輪に参加する世界のアスリートの夢と希望は、高校野球球児と同様に大切にすべきだろう。
朝日新聞は、五輪報道、そして高校野球報道で、こうした疑問に答えて欲しい。
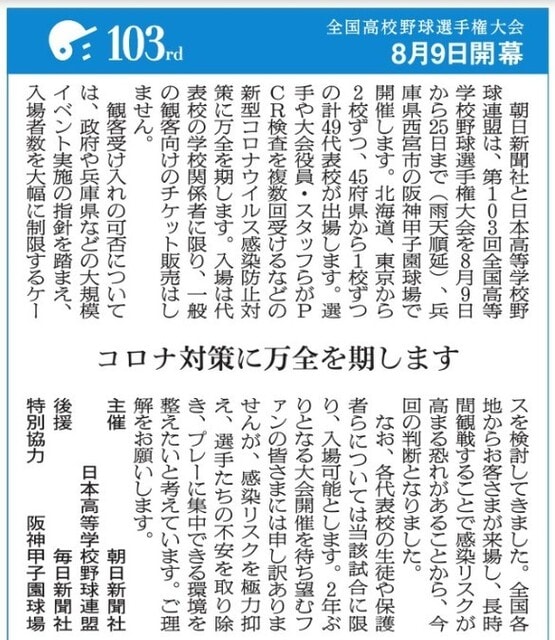
朝日新聞 7月22日 「全国高校野球選手権大会 8月9日開幕 ころな対策に万全を期します」

「前例なき五輪、光も影も報じます」 朝日新聞表明
7月21日、朝日新聞は、「前例なき五輪、光も影も報じます」という見出しで、ゼネラルエディター兼東京本社編集局長の坂尻信義氏の署名入り記事を1面で掲載した。
「緊急事態宣言下の東京を主な舞台に、過去に例のない五輪が始まろうとしています。(中略)選手や関係者たちは、延期が決まってからの1年4カ月間、不安や葛藤にさいなまれてきたはずです。今日から始まる競技では、選手たちが重ねてきた努力の成果を存分に発揮してほしいと心から願っています」とした。
一方で、選手や関係者は、外部との接触が制限される「バブル」の状況にほころびが目立ち、クラスター(感染者集団)が発生する恐れがあるとして、医療体制に負担をかけ、「平和の祭典」が、人々の健康や生命を脅かしかねないとした。
五輪開催による感染拡大の批判は、当初は、大量の観客がスタジアムに押し寄せることに感染リスクに対してであった。しかし、「無観客」となって、「1万人」ともされた大会関係者の参加に批判が向けられたが、大会関係者が大幅に縮減されることになり、五輪リスクを主張する根拠がなくなった。そもそも、国立競技場などスタジアムの感染リスクはほとんどない。プロ野球やJリーグで観客のパンデミックが発生したことはない。科学的なファクトを無視している。
そうすると、今度は、五輪開催で国民の間に高揚感が高まり、「人流」増可や、気が緩んで感染防止対策が甘くなり感染リスクが増すと主張が変わった。まさに、感情的な印象論での批判で、科学的なファクトの裏付けがない。
問題は、五輪ではなくで、全国で3758人、東京で1387人に達した新規感染者の「爆発」だろう。渋谷や新宿の繁華街の「人流」は緊急事態宣言が出されたにも拘わらず、減少する様子はない。この「感染爆発」は、五輪は関係なく、五輪はむしろ「感染爆発」の被害者なのである。
選手や大会関係者の「バブル体制」には、確かに「ほころび」があるが、それが原因でパンデミックが広がっている状況はない。選手や大会関係者の陽性者連日のように報告され、計67人(内選手3人、7月20現在)が出ているが、連日検査体制を実施すればある程度の陽性者が出るのは「想定内」だろう。
2012ロンドン大会で公衆衛生ディレクターを務めたブライアン・ライアン氏は、IOCの会見で、「感染者は想定より少ない。選手村は安全だ」と語った。
無症状感染者は有症症状感染者の数割以上は存在すると考えるのが常識だ。東京で検査体制を充実させたら、連日300人近い、陽性者が新たに検出されるに違いない。
五輪開催で医療体制の崩壊を指摘しているが、今の所、選手や大会関係者で入院している人はいない。医療体制に対する負荷はない。
医療体制の逼迫は、全国で3758人、東京で1387人の新規感染者で引き起こされるのである。五輪のせいにするのは筋違いだ。
坂尻氏は、「無謀な続行は、五輪の精神にもとる」として、「パンデミックのさなかに再延期や中止を選択しなかったことの是非は、問われ続ける」と明言した。
筆者は、コロナ禍で社会全体を覆っている閉塞感を拭いさるため、少しでも「感動」と「勇気」がもらえる五輪大会は開催すべきと考える。勿論、感染防止対策は、最大限、実施するのは条件だ。
新型コロナウイルスとの闘いは、長期間になることは必至の情勢だ。そこで必要になるのは、「withコロナの時代のニューノーマル」への模索である。五輪大会も、スポーツイベントも「中止」ではなくて開催の道を模索すべきだろう。感染防止策を講じながら、飲食店、酒類の提供、ショッピングセンター、劇場、コンサートの再開を目指し、市民生活を極力もとに戻すための知恵が求められる。
「緊急事態宣言」、「重点措置」、「人流」の抑制、飲食店規制の手法では、最早、国民の支持は得られず、「コロナに打ち勝つ」ことはできない。
コロナ・パンデミックの中で、開催をやり遂げることで、感染症の脅威にさらされ続ける時代へのレガシーにして欲しい。
それにしても「大会中止」を主張した朝日新聞は、五輪報道を自粛して、スポンサーを辞退すべきだ。

7月21日朝刊 朝日新聞 「前例なき五輪、光も影も報じます」
朝日新聞は「大会を盛り上げる」記事の掲載は止めるべきだ
いよいよ23日には、開会式を迎え、五輪大会が始まる。
朝日新聞を始め、各紙やテレビは、「反五輪」の主張を繰り返し、その論拠として、五輪開催期間中に日本選手の活躍などがあると五輪大会の機運醸成が巻き起こり、「人流」が増えたり、市民の気が緩んで感染対策が甘くなり、感染者が急増して医療崩壊が起きることを上げている。尾身茂政府分科会の論拠も同じである。
しかし、大会の雰囲気を盛り上げるのは新聞各紙やテレビなどのメディアであろう。片方で懸念を示しながら、片方で「雰囲気を盛り上げ報道」に加担するのは納得がいかない。「反五輪」の主張を繰り返した筋を是非貫いて、五輪の「雰囲気を盛り上げ報道」は止めるべきだろう。
日本人選手が金メダルをとろうが、日本代表チームが大健闘しようが、大会の雰囲気を盛り上げる報道は、自粛してほしい。
社説で、「五輪開催反対」を唱えたことを忘れるべきでなない。
東京オリンピック メディア批判 「五輪開催」すべき 盲目的に「中止」唱えるメディアのお粗末
開催実現で「Withコロナの時代のニューノルマル」をレガシーに
羽鳥慎一モーニングショー批判 玉川徹批判 ファクトチェック 検証五輪バッシング報道 五輪ポピュリズムを廃す

朝日新聞「夏の東京五輪 中止の決断を首相に求める」 社説掲載。
5月26日掲載された社説では「冷静に、客観的に周囲の状況を見極め、今夏の開催の中止を決断するよう菅首相に求める」主張した。
これまで、朝日新聞は、五輪開催に関しては「疑問」は提起したが、「中止」を明確に掲げることはなかった。
しかし、この社説は、「冷静」に事実を認識する姿勢に欠ける思考停止状態のメディアの典型で、納得できない。
五輪を中止すれば、コロナ感染拡大は収まる、すべては五輪が「悪者」とする単純化した構図が透けて見える。
しかし、五輪を中止しても感染は収まらない。感染拡大が収まらないのは、未だに「三密回避」、「マスク着用」、「人流抑制」に頼る前世紀型のコロナ対策のお粗末さである。ワクチンや検査体制で、世界で圧倒的に遅れたツケである。批判すべきなのは、政府の感染防止対策の失敗だろう。
筆者はあくまで「開催支持」、TOKYO2020を開催して「Withコロナの時代のニューノルマル」を示すべきだと考える。
社説では、「生命・健康が最優先」を掲げ、「国際オリンピック委員会(IOC)のコーツ副会長が先週、宣言下でも五輪は開けるとの認識を記者会見で述べた。
だが、ただ競技が無事成立すればよいという話ではない。国民の感覚とのずれは明らかで、明確な根拠を示さないまま「イエス」と言い切るその様子は、IOCの独善的な体質を改めて印象づける形となった」とする。
「生命・健康が最優先」は当然だが、五輪開催が引き金になって「生命・健康」が脅かされる可能性はどの位のリスクがあるか印象論ではなく、科学的に冷静に分析してほしい。
4月下旬に国際オリンピック委員会(IOC)と大会組織委員会が発表した「プレイブックV2」はこれまでにない厳格なコロナ対策が示された。さらに、来日する選手などの約80%はワクチン接種を終えているという。
こうした対策で感染拡大が発生するリスクは少ないと考える。印象論で五輪開催を批判するのは誤りだ。
5月23日に発表された東大院准教授のグループの「感染者試算」によれば、海外の選手や関係者ら入国者数は10万5千人、ワクチン接種率が50%として試算した結果、都内における1週間平均の新規感染者数で約15人、重症患者数で約1人、上昇させる程度にとどまり、「入国・滞在の影響は限定的」と結論づけた。
こうした分析を朝日新聞はどう分析しているのか。
「開催中止」を主張しながら、「五輪のレガシー」論を展開した支離滅裂の紙面
朝日新聞社が社説で、「中止の決断を首相に求める」という記事を掲載した同じ日の朝刊では、「ジェンダー平等を五輪のレガシーに 橋本聖子・大会組織委会長に聞く」という朝日新聞が開催してフォーラムを元にした記事を掲載している。フォーラムには大会組織委ジェンダー平等推進チームの小谷実可子氏や元女子サッカー日本代表の大滝麻未氏なども加わっている。
社説で「開催中止」を主張しておきながら、もう一方で、「ジェンダー平等」を2020東京五輪大会開催のレガシーにしようと訴える記事を掲載するのは、どう考えても矛盾する。大会を中止するなら。レガシー論はまったく不要である。東京2020大会の開催経費は、組織委の予算だけでも1兆6440億円、開催を中止すれば、この膨大な金額が吹き飛ぶ。まさに空前の「負のレガシー」となるのは必須である。「開催中止」を主張するなら、「ジェンダー平等を五輪のレガシーに」ではなくて、次世代に重くのしかかる「負のレガシー」を検証する記事を掲載すべきだろう。
今後、朝日新聞は、紙面で「開催中止」を念頭に置いた五輪報道紙面を構成すべきだ。さもないとジャーナリズムとしての信頼は喪失するだろう。
社説とコラムなどの評論記事は基本的に違う。コラムなどの評論記事は、さまざまな意見を持つ人々が活発に議論を展開する場である。五輪開催支持論、中止論、双方が記事されるのが望ましい。読者は多角的な主張を期待している。
一方、社説は、「新聞社」としての主張である。コラムなどの評論記事とは位置づけが違う。朝日新聞社は社説の重みを理解しているのだろうか。
東京オリンピック 朝日新聞は東京五輪の「オフイシャルパートナー」を返上せよ
朝日新聞社は、2020東京五輪大会の「オフイシャルパートナー」になり、東京五輪大会の協賛社に名を連ねている。朝日新聞社が大会組織委員会に支払う協賛金は、約60億円(推定)以上とされ、昨年末、「1年延期」に伴い、追加の協賛金を支払うことに合意している。
朝日新聞社は、「tier2」の「オフイシャルパートナー」になることで、呼称の使用権(東京2020オリンピック競技大会、東京2020パラリンピック競技大会など)やマーク類の使用権(東京2020大会エンブレム、東京2020大会マスコット)を得て、朝日新聞のPRに利用することができる。
60億円以上支払って五輪開催をサポートをすることで、五輪のブランド力を利用して部数拡大やメディアとしてのプレゼンスに寄与させるのがその狙いであろう。
ライバルの読売新聞社、毎日新聞社、産経新聞社もいずれもスポンサーに加わっており、朝日新聞社としても五輪で遅れをとるわけにはいかない。
5月26日、朝日新聞は「中止の決断を首相に求める」という社説を掲載。「誰もが安全・安心を確信できる状況にはほど遠い」として、「五輪を開く意義はどこにあるのか」と疑問を投げかけ、「そもそも五輪とは何か。社会に分断を残し、万人に祝福されない祭典を強行したとき、何を得て、何を失うのか。首相はよくよく考えねばならない」として、五輪開催をほぼ全否定した。
しかし、朝日新聞社は「オフイシャルパートナー」を続けて、五輪のブランド力をフルに活用することで営業力の強化につなげる一方で「五輪中止」を社説で掲げるのは、まったく納得できない。
朝日新聞社は、社としての方針と紙面は違うと釈明するが、「見識」が求めらるジャーナリズムとしては、余りにも恥ずべき発言だろう。
朝日新聞は、今後、紙面で五輪開催を後押しするようなポジティブな内容の記事は掲載するべきでない。社説の主張と相反する記事も排除してほしい。
「オフイシャルパートナー」は即刻、撤退すべきだ。
テレビや新聞は、連日のように「五輪中止」の大合唱を繰り広げて、選手や大会関係者の感染防止対策「頑や五輪の観客問題などで徹底したネガティブ報道を重ねているが、五輪大会が始まり、日本選手の活躍が目覚ましくなってきたら、手の平を返したように「頑張れ!日本」と報道するのだろうか。筆者はまったく納得がいかない。テレビや新聞で五輪批判を続けるコメンテーター、ジャーナリスト、評論家は、五輪大会でのアスリートの活躍を見る資格がない。道理が通らない。
とりわけ、五輪のスポンサーでありながら、五輪中止を唱えた朝日新聞はどうするのか。「頑張れ!日本」、「日本、金メダル獲得!」を掲げた紙面が踊るようだったら、無節操の誹りは免れない。メディアとしての信頼感を喪失する。それ位の覚悟を持った上で、「五輪中止」、「五輪バッシング」の大合唱を繰り広げるべきだ。
「東京2020オフィシャルパートナーとして」(朝日新聞 5月26日)
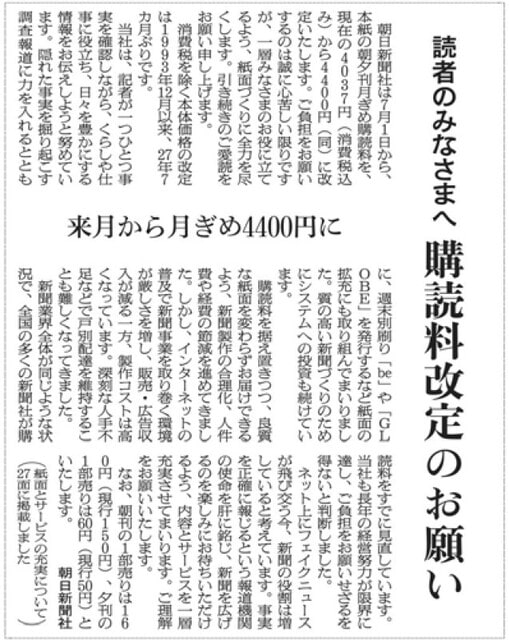
購読料値上げを明らかにした朝日新聞(6月10日) 五輪「オフイシャルパートナー」の60億円問題を放置して読者へ負担増をしいる姿勢は疑問
「Withコロナの時代のニューノルマル」を示せ
コロナとの長期戦で、世界はコロナ感染リスクをある程度抱えながら、社会・経済活動を維持していかなければならない。
Withコロナの時代のニューノルマルの確立が、社会全体に求められる。スポーツイベントやコンサート、飲食産業、ショッピングセンター、どうやって維持していくか、その知恵と努力が問われている。
TOKYO2020は。「安全・安心な大会」を達成して、「Withコロナの時代のニューノルマル」を世界に示すべきた。五輪開催で得るものはある。
2020東京五輪大会開催のレガシーは「Withコロナの時代のニューノルマル」に違いない。
東京オリンピック 尾身会長批判 五輪リスク 「ワクチン」「検査体制」「医療体制」一体何を提言したのか
「ぼったくり」は米国五輪委員会 バッハ会長は「ぼったくり男爵」ではない メディアはファクトを凝視せよ

国際メディアサービスシステム研究所 International Media Service System Research Institute(IMSSR)
2021年5月26日
Copyright (C) 2021 IMSSR
******************************************************
廣谷 徹
Toru Hiroya
国際メディアサービスシステム研究所
代表
International Media Service System Research Institute(IMSSR)
President
thiroya@r03.itscom.net
imssr@a09.itscom.net
******************************************************














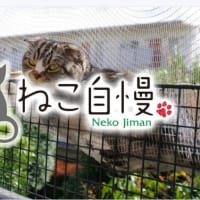












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます