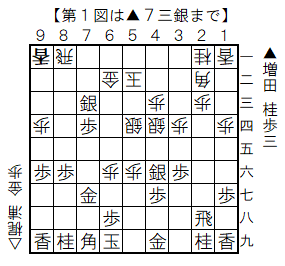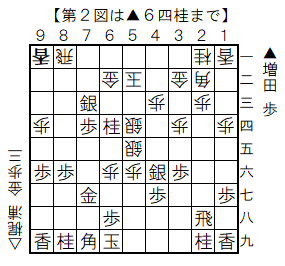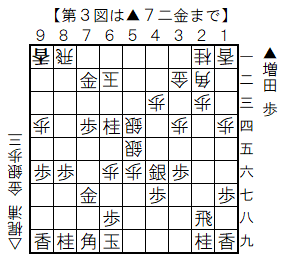昨年12月22日の当ブログに、「藤井聡太竜王・名人は年度勝率8割を達成できるか」という記事を書いた。
当時藤井竜王・名人は今年度27勝9敗、勝率.750だった。
そのときの残り棋戦と、最大勝数は以下のごとくだった。
第10期叡王戦本戦 ○○○○
第74期王将戦七番勝負・永瀬拓矢九段 ○○○○
第18回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメント ○○○○
第50期棋王戦五番勝負・増田康宏八段 ○○○
第74回NHK杯 ○○○
最大18勝で、全勝で切り抜ければもちろん8割越えとなるが、さすがにそれは無理。
問題は負け方で、タイトル戦の1敗なら傷は浅いが、トーナメント戦の中途で負けると勝数が少なくなり、黄信号となる。
実際、今年1月19日の朝日杯では、本戦2回戦で服部慎一郎六段(当時)に敗れ、エライことになった。最大4勝を見込めたのが、1勝で終わってしまったからだ。
しかし藤井竜王・名人は頑張った。これ以外の棋戦は。王将戦、棋王戦のタイトル戦をはじめとして、全勝で乗り切っているのだ。
第10期叡王戦本戦 ○
第74期王将戦七番勝負・永瀬拓矢九段 ○○○
第18回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメント ○●
第50期棋王戦五番勝負・増田康宏八段 ○
第74回NHK杯 ○
これで34勝10敗。しかも、NHK杯では優勝したのではないか、という噂もあり、それを信じれば「36勝10敗.783」となる。
では、残りの対局での最大勝数を改めて確認してみよう。
第10期叡王戦本戦 ○○○
第74期王将戦七番勝負・永瀬拓矢九段 ○
第50期棋王戦五番勝負・増田康宏八段 ○○
最大6勝。よって年度最大も42勝となり、勝率8割をクリアするためには、もう一番も負けられないことになる。
そしてあす12日は、叡王戦本戦2回戦・戸辺誠七段戦が行われる。戸辺七段は中飛車の名手。さすがの藤井竜王・名人も対振り飛車はそこまで研究していないはず。また両者は初対局であることから、この条件は戸辺七段のほうに有利に働くと思う。
あすはABEMAで中継があるが有料なので、私は見られない(課金はしない)。ネットでのチャットを楽しみにしたい。
当時藤井竜王・名人は今年度27勝9敗、勝率.750だった。
そのときの残り棋戦と、最大勝数は以下のごとくだった。
第10期叡王戦本戦 ○○○○
第74期王将戦七番勝負・永瀬拓矢九段 ○○○○
第18回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメント ○○○○
第50期棋王戦五番勝負・増田康宏八段 ○○○
第74回NHK杯 ○○○
最大18勝で、全勝で切り抜ければもちろん8割越えとなるが、さすがにそれは無理。
問題は負け方で、タイトル戦の1敗なら傷は浅いが、トーナメント戦の中途で負けると勝数が少なくなり、黄信号となる。
実際、今年1月19日の朝日杯では、本戦2回戦で服部慎一郎六段(当時)に敗れ、エライことになった。最大4勝を見込めたのが、1勝で終わってしまったからだ。
しかし藤井竜王・名人は頑張った。これ以外の棋戦は。王将戦、棋王戦のタイトル戦をはじめとして、全勝で乗り切っているのだ。
第10期叡王戦本戦 ○
第74期王将戦七番勝負・永瀬拓矢九段 ○○○
第18回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメント ○●
第50期棋王戦五番勝負・増田康宏八段 ○
第74回NHK杯 ○
これで34勝10敗。しかも、NHK杯では優勝したのではないか、という噂もあり、それを信じれば「36勝10敗.783」となる。
では、残りの対局での最大勝数を改めて確認してみよう。
第10期叡王戦本戦 ○○○
第74期王将戦七番勝負・永瀬拓矢九段 ○
第50期棋王戦五番勝負・増田康宏八段 ○○
最大6勝。よって年度最大も42勝となり、勝率8割をクリアするためには、もう一番も負けられないことになる。
そしてあす12日は、叡王戦本戦2回戦・戸辺誠七段戦が行われる。戸辺七段は中飛車の名手。さすがの藤井竜王・名人も対振り飛車はそこまで研究していないはず。また両者は初対局であることから、この条件は戸辺七段のほうに有利に働くと思う。
あすはABEMAで中継があるが有料なので、私は見られない(課金はしない)。ネットでのチャットを楽しみにしたい。