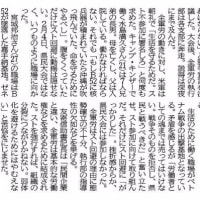長い間ずっと探していたある食べ物を先日スコットランドで見つけた。最初にこれに出会ったのはインドで、30年以上も昔のこと。こんなにおいしいものがあるかと感動したのをよく覚えている。
それに再会したのが12年前のネパール。昔を思い出して二重の感動を
味わった。
どちらのときもレストランや食堂のカレー系の定食の隅に添えてあった。
本当にうまくて、しかも店ごとに作るのではなく瓶詰めからひょいとス
プーンで出して置いたという感じ。
だから、食堂を出るや否や食料品店に行って、こういうものが欲しいと
説明するのだが、そんなものは無いと言われる。
ネパールの時はけっこう必死で、カトマンドゥーの下町で何軒もの店を
回ったのに、本当に無いのか説明が伝わらないのか、出会えなかった。
あまりもったいぶらないで言えば、ライムのチャツネである。
チャツネないしチャトニはインド料理の薬味で、野菜や果物や香草を材
料に作り、ジャムのように甘いのと、塩と唐辛子で辛いのがある。
最もよく知られているのはマンゴーのチャツネだろう。
ぼくが惚れ込んだライムのチャツネは酸味が強く、塩が濃く、とても辛
く、香りが高くて、うまい。
それがスコットランドの田舎町の小さな、ほとんどコンビニ・レベルの
店にあったのだ。
ぼくがインドで予想したとおり瓶詰めで、商品名はLime Picklesとある。
ピクルズだからあるいは違うかなと思いながら買ってみたら正にあの味
だった。
同じ店にカレー・ソースの瓶詰めがあった。
肉類などのいわゆる具は入っていなくて、ソースだけ。
これも試そうと思って買って、とりあえずジャガイモを電子レンジで調
理し、鍋にあけたソースの中に入れて味が馴染むまでゆっくり加熱する。
ジャガイモを茹でてしまっては水っぽくなるから、この場合は電子レン
ジが正解。ジャガイモのカレーは少しごりごりと歯ごたえが残るくらいが
いいのだ。
このソースもうまかった。
匂いが立っていて辛みも正しく、本格的な味だった。
ルーを使う日本のカレーはあまりに日本化してしまってインドのカレー
とはまったく別種のものである。
それに比べるとイギリスのカレーにはインド直伝の強烈さが残っている。
ロンドンのちゃんとしたインド料理の店に行けばもちろんだが、田舎を
巡っていてひょいと飛び込んだパブの日替わり定食がカレーで、それが相
当にうまかったりする。
どこでこの差が生じたのだろう?
日本にはカレーはイギリス経由で来たはずだ。
明治の初期に入ったというけれど、その時期にインドから直接到来した
とは思えない。
漱石の『三四郎』に出てくるのが象徴的で、その作者と同じようにやは
り間にはイギリスが関わっていたに違いない。
その結果、日本におけるカレーは蕎麦屋のカレー南蛮にまで馴化された。
しかし、日本にはあらかじめ配合されたカレー粉は入ってきてもインド
人の料理人は来なかった。
それに対してイギリスには、なんといっても植民地と本国の関係なのだ
から、インド人がたくさん来た。
たぶん彼らは妥協のないカレーを作って自分たちで食べ、イギリス人に
も提供したのだろう。
ぼくは太平洋の真ん中、ミッドウェイ島のアメリカ海軍の食堂で数日に
亘って本格的なカレーを食べ続けたことがある。
あの島で働く軍属の半分はインド系で、料理人もインド人。
アメリカ風のファスト・フードの横にエスニックの一角があったので通
い詰めた。
イギリスのカレーはイギリス化しなかった。
ローストビーフに合うカレー風味のソースは開発されなかった。
イギリスは当時から多文化主義だったと言えるかどうか、それはまた別
の問題だが。
同じような例をフランスで探すと、クスクスがある。
本来は北アフリカ諸国、いわゆるマグレブの料理だがフランスでも広く
普及している。
ぼくの住む町にも専門店があってとてもおいしいし、朝市でも買える。
缶詰はスーパーにあり、冷凍のもある。
子供たちの給食にさえ登場するから、本当にこの国の食生活に溶け込ん
でいると言っていい。
カレーからクスクスへ連想が走ったのは、まずどちらも植民地の料理だ
ということと、一品の料理として構成がカレーと似ているからだ。
カレーは炊いた米ないしナンというあのパンと、香辛料の利いた肉や野
菜のシチューを一緒に食べるものであり、クスクスもまた香辛料の利いた
鶏やソーセージや豆のシチューと蒸した粒状のパスタを一緒に食べる。
クスクスに使われるスパイスはクミンとコリアンダー、パプリカ、サフ
ランが少し入って、それにハリッサないしアリッサと呼ばれる赤唐辛子の
ペースト。
フランスで食べるクスクスがどこまで本来の味を維持しているか、ぼく
はまだマグレブ諸国に行ったことがないのでわからない。
でも、そんなに違ってはいないと類推していいだろうと思う。
モロッコやチュニジアやアルジェリアはかつてフランスの植民地で、今
のフランスにはこれらの土地から来た人々とその子孫がたくさんいる。
同じような例を日本で求めれば、いちばん似ているのが韓国・朝鮮系の
料理だ。(言うまでもないことだが、1910年の日韓併合から1945
年の敗戦までの間、今の大韓民国ならびに朝鮮民主共和国にあたる地域は
日本の植民地だった)
最初のころはプルコギばかりだったが、しばらく前から家庭料理や宮廷
料理など、本来のものが味わえるようになった。
この場合も、本源の地とあまり変わらない味が再現されているとすれば、
それは素材だけでなく人も渡ってきたことの結果だろう。
人と共に文化も運ばれる。
ちなみにインターネットというのは便利すぎて味気ないもので、この原
稿を書きはじめて3分後にぼくはライムのチャツネが日本でも簡単に買え
ることを発見した。この30年の探索は何だったのだ?
NiLon’sというブランドの品は次のサイトに案内がある。
値段は200グラムで390円。
http://www.spinfoods.net/pickles.htm
スコットランドから帰って来ると、フランスは大荒れだった。
パリ周辺の住宅地で路上に駐めた車が次々に燃やされている。
毎夜、何百台という車が炎上している。
日本を含めて各国のメディアが大きく報道したし、夜空を背景に炎上す
る車は派手な絵になるから、日本の友人たちからは「そこは大丈夫?」と
いうメールが次々に入った。
まるでフランス全体が燃え上がっているかのようだ。
きっかけはパリ郊外のクリシー・スー・ボアという町で、2人の少年が
警察官に追われて変電所に逃げ込み、高圧線に触れて感電死したことだっ
た。
事故ではあるが象徴的な意味づけがあまりに濃い事故。
可燃材が山積みされたところに火が放たれたように、パリを取り巻く一
帯、郵便番号でいえば92、93、94あたりの地域で車への放火が相次
ぎ、他の大きな都市へも飛び火した。
それが毎晩百台単位、ピークには千台を超えたのだからたしかに尋常で
はない。
可燃材は何か、火を点けたのは誰か?
3週間以上たった今になって振り返ってみると、まず初期の報道はいか
にもセンセーショナルだった。
『パリは燃えているか?』というのはラピエールとコリンズの名著のタイ
トルで、ヨーロッパではよく知られている。
第2次大戦の末期、ヒトラーは退却しながらパリ全体を燃やせという指
令を出した。この指令がなぜ実行されなかったかを描いたノンフィクショ
ン。
映画化もされていたし、新聞の見出しがみなこれをなぞったのは当然だ
ったのかもしれない。「パリは燃えている!」
しかし違うのだ。
場所はパリではなく周辺だったし、燃えているのは住宅ではなく、路上
の車やターミナルに帰ったバスだった。
日本の法律では現住建造物放火罪と非現住建造物放火罪は区別されてい
る。
フランスの法のことは知らないけれど、路上に駐めてある車は日本風に
言えば後者だろう。
また、車への放火は今に始まったことではなく、このような地域でずっ
と続いている反抗の延長上にあることだった。
今年に入ってから燃やされた車は28000台、毎晩百台近い。
その内の6000台ほどが数日の間に集中したのが今回の事件。
イギリスの新聞の中には、あれだけの人を殺したロンドンのテロよりは
ずっと平和的という論調もあった。
前にこの連載でフランス人がグレーヴ(ストライキ)やマニフ(デモン
ストレーション)による意思表示を好むことを書いた。
今年の3月、政府が企図した教育制度の改革に反対してフランス全土の
高校生がデモをした。
今回の事態はむしろあれに似ているのではないか、とぼくは考えた。
放火は言うまでもなく乱暴な手段だが、1992年のロサンジェルスの
暴動のような過激さはない。
あの時はたしか50人以上の死者が出たが、今回は一人だけで、この一
人の犠牲はある程度まで偶発的と言っていいだろう。
バスを停めて、乗客全員を降ろしてから火を放ったという例もあったら
しい。
ともかく犯人たちが若い。
逮捕された者の半分以上が18歳以下で、中には10歳の子もいたとい
う。彼らは証拠不十分ということですぐに釈放されている。
要するに警察がとりあえず夜の町に出ている子供たちを片っ端から捕ま
えたということだ。
参加者のこの年齢もまた高校生のデモへの連想を誘うものだった。
しかし、今回の争乱・暴動・蜂起・示威(立場によって呼称はこれくら
い変わるはずだ)の真の原因は、フィヨンの教育制度の改革などよりずっ
と深いところにある。
フランスという共和国の基本理念が揺らいでいる。
この2週間、日本にいてはなかなか理解できないことだったと思いなが
ら、日々の報道や論評に接した。
一見したところ、騒いだ若い連中の動機はわかりやすい。
職がなく、将来の希望がなく、不満に満ちた毎日という状態がずっと続
いていて、改善の兆しが見えない。
ここ数年、事態は悪くなるばかり。
そこへ仲間が死んだという知らせが入る。
事故死とはいえ警察官に追われた果てのことだ。
それをきっかけに普段からの不満が一気に爆発し、正に燎原の火の如く
燃え広がった。
それに模倣犯が便乗し、夜ごとの解放区があちらこちらに出現した。
騒ぎが起こったのはどこも大都市周辺の事実上のゲットーである(だか
らと言っていいかどうか、パリからだいぶ離れた我が町では何の騒ぎもな
かった)。
もっぱら北アフリカ系の、ムスリムの人々がまとまって住む地域。
騒動の主役は移民の2世3世。
どこの国でもそうだが、移民の一世は苦労してフランスに渡って市民権
を得たから、少々待遇が悪くても文句は言わない。
前にいたところの暮らしよりはずっとよくなったと思って、たいていの
ことは我慢する。
しかしその子や孫の世代はフランスで生まれてフランスで育った。
人権についても学校で教えられた。
フランスの建前としての平等をそのまま受け止めれば、現実の不平等が
嫌でも目に付く。
もともとフランスは移民の多い国だ。
労働力の不足を移民で補うのは昔からのことで、だからフランス人の3、
4人に一人は祖父か祖母の一人が外国人だという。
そしてフランス革命でジャコバン派の人権思想が国の基本方針として採
択され、国籍についてもフランスで生まれればフランス人という出生地主
義が確立した。
つい先日まで血統主義だったドイツや、今もそれを貫き、まったくと言
っていいほど移民を入れない日本とは国の成り立ちが違う。
フランスは国民の要件として出自や信仰は問わない。
だから、フランスの公式の統計では国民のどれだけがムスリムであるか、
わからない。
6000万の人口のうち500万くらい、という推測があるばかりだ。
移民は次々にやってくる。年間十万人単位で増えているという。
一定の間この国に住んでいると国籍が与えられて移民から国民に昇格す
ることが多い。
そうなるとその人たちはもう統計の上の数字としては出てこないのだが、
それでも今のフランスでは人口の六パーセントが外国人だという。
しばらく前、たとえばアメリカ合衆国の人種問題を論じるのに、坩堝(る
つぼ)かサラダ・ボウルかという議論があった。
多くの人種が混じり合い溶け合って一つの社会を作るから「人種の坩堝」
だという素朴な比喩が最初にあり、やがて混じり合っても溶け合いはしな
いことが明らかになって、異質のままの素材が混在するという意味でサラ
ダ・ボウルという新しい表現が生まれた。
アメリカ合衆国やイギリスなどアングロ・サクソン系はもっぱらこの方
針で、エスニックな集団に社会的な地位が与えられる。
しかしフランスは理念として坩堝論を立ててきた。
集団としてのエスニックの存在を認めない。
フランス語を話し、フランス文化を受け入れればフランス人。
それ以上の分類はしない。
この国の基本は血統や土地ではなく理念だ、と言い張ってきた。
それはそれで立派なことかもしれない。
「自由、平等、博愛」は今でも美しいスローガンだとぼくは思う。
しかし、現実には差別はある。
最も目に見える形では、ゲットーの存在。
収入が低くて家が得にくい人々のために政府が団地を作る。
それは悪いことではないが、社会的なふるいを通過してそこに住み着い
た人々を見れば結果としては旧植民地の北アフリカ諸国の出身者ばかり。
そこに住む芸人が国立のテレビ局に職を得ようと履歴書を送ったという
話がある。
2通作って、一方は正直にその地域の住所を使い、名前もアフリカ系の
本名のまま。
もう一方はフランスっぽい名にして住所も評判のいい地域にした。
すると、後者の方にだけ面接の通知がきた。
フランスで成功したモロッコ生まれの実業家が書いた自伝のタイトルが
『社会のエスカレーターが壊れていたので、私は階段を登った』、という
例もある。
自分たちのためのエスカレーターが壊れていることを今回、若い人々は
車に火を放つことで指摘したのだ。
サルコジ内相の発言が騒ぎの初期にまさに火に油を注ぐ結果になったこ
とは広く報道されたようだ。
彼は荒れる若者を「くず racaille」と呼び、箒で掃き出すと言った。
普通、フランスの政治家はこういう露骨な表現は使わない。
直後のアンケートによればこの発言にはフランス人の6割以上が反発を
覚えたという。
しかし彼の発言はある程度まで計算ずくのものだ。
異質の文化からフランスを守れという思いもフランス人の中にはあって、
だから数年前、極右の国民戦線を代表するルペンの台頭に世界は驚いたの
だった。
2007年の選挙で大統領の席を窺うサルコジはフランスの保守層に訴
えることで支持者を増やせると読んだ。
彼自身がハンガリー系移民の2世であることを考えると、彼を巡る状況
はずいぶんねじれたものだ。
彼はアメリカ合衆国のコンドリーサ・ライス国務長官と同じようにマイ
ノリティー出身者たちの出世頭で、だから出自と体制の間でデリケート・
バランスを保っている。
東と南の違いもある。
去年の今ごろパリで会ったモロッコ人のジャーナリストのムハンマドは、
「1990年代になってソ連の崩壊で東欧系の移民が増えたので、ヨーロ
ッパは全体として南からの移民を制限するようになった」と言っていた。
労働力の不足を補うには移民が必要。
それならば文化的にも人種的にも近い東ヨーロッパの人の方が好ましい
ーーーそういう意図が移民政策に読み取れるというのだ。
この分析とサルコジの立場を重ねると、明日のフランスのある面が見え
るような気がする。
彼は移民の子といっても、ヨーロッパ系だから今の地位に就けたのでは
ないか。
この9月までフランス人は移民の存在にあまり不安感を覚えていなかっ
た、というアンケート結果がある。
騒ぎの3週間前に全ヨーロッパ的に行われた調査で、「移民は文化やア
イデンティティーや宗教にとって危険か?」という問いに、ドイツでは
29.2パーセントが危険だと答えた。
イタリアでは26,6パーセント。
そしてフランスでは22,6パーセントと最も低かった。
またこの数字はドイツでは前回の調査の時より4ポイント上昇している
のに対して、フランスでは逆に3,2ポイント減っていた。
「移民は就職の障害になるか?」という問いに肯定的な答えをしたのは
ドイツで40パーセント、イタリアで35パーセントに対して、フランス
では26,7パーセントだった。
前回書いた聖マルタンの夜に、知人と再会した。
彼女とは去年この町で親しくなったのだが、引っ越して今はパリ郊外の
別の町にいる。
とても知的で、フランス以外の国もよく知っていて、アジアや中東、ア
フリカで暮らした経験がある。
今住むところがパリ近郊と聞いて、騒ぎのことを聞いてみたが、自分の
ところでは何もなかったという。
それはそれとして、この一連の事態に関する彼女の意見がなかなか意味
のあるものだった――
私はやはりあの人たち、アフリカ系と呼ぶか、有色というか、黒い人と
するか、ムスリムというか、それはともかく、彼らには問題があると思う。
フランスには中国系の人もヴェトナム出身の人もたくさんいるけれど、
そういう人たちを巡って騒ぎにはならない。
でもあの人たちとフランス社会との間には埋めがたい溝がある。
例えば、ムスリムの人々の間では女性の地位は極端に低い。
女には社会に出る機会も権利もないというのはフランス人として認知で
きることではない。
実際、彼らは自分たちの文化の中にこもっている。
一人の夫が狭いアパルトマンで妻4人と子供十数人と一緒に暮らしてい
るのは、フランス的ではないと私は思う。
しかしそれでも、あるいはだからこそ、私たちはあの人たちに手を貸さ
なければならない。追い出すのではなく、お互いに許容できる範囲まで歩
み寄って、こちら側に招き寄せて、共にこの先のフランスを築いていかな
ければならない……というのが彼女の意見。
そうなのだろうとぼくは思った。
このあたりがフランスの良識の基本なのだろう。
しかしこの問題の根は深い。
前に論じた公立学校における女生徒のスカーフ着用の件がいい例だった
が、イスラム教とキリスト教の違いはやはり大きな障害なのだ。
なぜならばこの2つはよく似ているくせに決定的に違うから。
どちらも契約の宗教であり、一個の神を信じ、その神が微妙に、しかし絶
対的に違う。
東アジアの人々とはまったく違う。
そういう人たちが今や人口の1割近くいる。
一夫多妻の件は例えばこういう形で議論に入ってくる――今度の騒動の理
由の一つとして、騒いだ子供たちの親の責任を問う論があった。
小さなアパルトマンに父と母たちやたくさんの兄弟がひしめきあっている
から、子供は街頭で遊ぶしかなく、だから非行には走る。
この論法はある閣僚の口からも漏れた。
騒いだのが子供たちだったし、途中からは愉快犯の模倣も多かったので、
それを鎮めるべく発令された夜間外出禁止令は功を奏し、国民の73パーセ
ントの賛成を得た。
騒ぐ者は国外追放などという一連のサルコジの強硬策にも63パーセント
の支持が集まった。
実際には最初百数十人と言われた国外追放は10人程度に減じられたよう
だが。
11月の18日、ド・ヴィルパン首相はエリート校の一つであるストラス
ブールのENA(国立行政学院)の創立60周年の式典に出てスピーチをし
た。
その中で彼は、今回の事件は「価値観の危機」だと語り、「非人間的な都
市計画」と「失業」と「公共事業の非効率」を原因として挙げ、これらの解
決がまず必要だと言った。
また、騒動の起こった地域の人々を同一視してはいけないとも言った。
ムスリムをムスリムであるというだけでトラブルの元というレッテルを貼
ってはいけない。
共和国の原理を回復することが大事だと語り、機会の均等を実現しなけれ
ばならないと述べた。
1905年の法が男女の差別をなくしたように、今はライシテの原理によ
ってもう一つの差別をなくさなければならない(このライシテすなわちフラ
ンス流の政教分離の原理については、前にスカーフ問題のところで論じた)。
この後、首相はENAを出て、この町の郊外、つまりここでも騒動があっ
た地域をひそかに訪れ、あるレストランで福祉団体の代表や教育者の訴えを
聞いた。
そこで商業学校に通うという20歳の女性が言った言葉がなかなか印象的
だ――「郊外を変えるだけではなく、フランスを変えなければいけないと思
います」
去年すなわち2004年12月、それまで穏やかな地方都市と思われてい
たレンヌで、音楽フェスティバルに集まった若者が暴れて、警察が催涙弾2
50発を使うという騒ぎがあった。
その前にはこの町の名物だった回転木馬への放火という蛮行が2度あった
という。
この場合は特にマイノリティーが主体ということではなかったようだ。
北アフリカ系だけでなく、若い人々ぜんたいが就職難や先行きの不安を感
じているから、何かきっかけがあると騒ぎ出す。
またレンヌではベルナデット・マルゴールという女性の知事(市長ではな
い)の強権主義が却って反発を招いたという意見もある。
この点はサルコジの発言の影響に似ている。
この問題に関する日本の報道にはどこか冷ややかなものがあった。
移民なんか入れるからそういうことになるのだと言わんばかり。
しかし、日本だっていつまでも今のような鎖国をしているわけにはいかな
いだろう。
移民はおろか難民さえ受け入れないという姿勢がいつまで続くか。
開放せざるを得なくなった時に、日本は今のフランスその他ヨーロッパ諸
国の苦しみを身をもって理解するだろう。
世界の至るところで人と文化と言語は混じりあい、ぶつかり、その渦の中
から新しい価値が生まれている。
ド・ヴィルパンの演説はあまりに理想主義的で、あるいは空疎に響いたか
もしれない。
しかし、ぜんたいとしてフランスはやはりこの方向に進まなければいけな
いのだろうとぼくは思う。
<聖マルタン、愛知万博、植民地の料理、車を燃やす おわり>
(池澤夏樹 執筆:2005‐11‐25)
それに再会したのが12年前のネパール。昔を思い出して二重の感動を
味わった。
どちらのときもレストランや食堂のカレー系の定食の隅に添えてあった。
本当にうまくて、しかも店ごとに作るのではなく瓶詰めからひょいとス
プーンで出して置いたという感じ。
だから、食堂を出るや否や食料品店に行って、こういうものが欲しいと
説明するのだが、そんなものは無いと言われる。
ネパールの時はけっこう必死で、カトマンドゥーの下町で何軒もの店を
回ったのに、本当に無いのか説明が伝わらないのか、出会えなかった。
あまりもったいぶらないで言えば、ライムのチャツネである。
チャツネないしチャトニはインド料理の薬味で、野菜や果物や香草を材
料に作り、ジャムのように甘いのと、塩と唐辛子で辛いのがある。
最もよく知られているのはマンゴーのチャツネだろう。
ぼくが惚れ込んだライムのチャツネは酸味が強く、塩が濃く、とても辛
く、香りが高くて、うまい。
それがスコットランドの田舎町の小さな、ほとんどコンビニ・レベルの
店にあったのだ。
ぼくがインドで予想したとおり瓶詰めで、商品名はLime Picklesとある。
ピクルズだからあるいは違うかなと思いながら買ってみたら正にあの味
だった。
同じ店にカレー・ソースの瓶詰めがあった。
肉類などのいわゆる具は入っていなくて、ソースだけ。
これも試そうと思って買って、とりあえずジャガイモを電子レンジで調
理し、鍋にあけたソースの中に入れて味が馴染むまでゆっくり加熱する。
ジャガイモを茹でてしまっては水っぽくなるから、この場合は電子レン
ジが正解。ジャガイモのカレーは少しごりごりと歯ごたえが残るくらいが
いいのだ。
このソースもうまかった。
匂いが立っていて辛みも正しく、本格的な味だった。
ルーを使う日本のカレーはあまりに日本化してしまってインドのカレー
とはまったく別種のものである。
それに比べるとイギリスのカレーにはインド直伝の強烈さが残っている。
ロンドンのちゃんとしたインド料理の店に行けばもちろんだが、田舎を
巡っていてひょいと飛び込んだパブの日替わり定食がカレーで、それが相
当にうまかったりする。
どこでこの差が生じたのだろう?
日本にはカレーはイギリス経由で来たはずだ。
明治の初期に入ったというけれど、その時期にインドから直接到来した
とは思えない。
漱石の『三四郎』に出てくるのが象徴的で、その作者と同じようにやは
り間にはイギリスが関わっていたに違いない。
その結果、日本におけるカレーは蕎麦屋のカレー南蛮にまで馴化された。
しかし、日本にはあらかじめ配合されたカレー粉は入ってきてもインド
人の料理人は来なかった。
それに対してイギリスには、なんといっても植民地と本国の関係なのだ
から、インド人がたくさん来た。
たぶん彼らは妥協のないカレーを作って自分たちで食べ、イギリス人に
も提供したのだろう。
ぼくは太平洋の真ん中、ミッドウェイ島のアメリカ海軍の食堂で数日に
亘って本格的なカレーを食べ続けたことがある。
あの島で働く軍属の半分はインド系で、料理人もインド人。
アメリカ風のファスト・フードの横にエスニックの一角があったので通
い詰めた。
イギリスのカレーはイギリス化しなかった。
ローストビーフに合うカレー風味のソースは開発されなかった。
イギリスは当時から多文化主義だったと言えるかどうか、それはまた別
の問題だが。
同じような例をフランスで探すと、クスクスがある。
本来は北アフリカ諸国、いわゆるマグレブの料理だがフランスでも広く
普及している。
ぼくの住む町にも専門店があってとてもおいしいし、朝市でも買える。
缶詰はスーパーにあり、冷凍のもある。
子供たちの給食にさえ登場するから、本当にこの国の食生活に溶け込ん
でいると言っていい。
カレーからクスクスへ連想が走ったのは、まずどちらも植民地の料理だ
ということと、一品の料理として構成がカレーと似ているからだ。
カレーは炊いた米ないしナンというあのパンと、香辛料の利いた肉や野
菜のシチューを一緒に食べるものであり、クスクスもまた香辛料の利いた
鶏やソーセージや豆のシチューと蒸した粒状のパスタを一緒に食べる。
クスクスに使われるスパイスはクミンとコリアンダー、パプリカ、サフ
ランが少し入って、それにハリッサないしアリッサと呼ばれる赤唐辛子の
ペースト。
フランスで食べるクスクスがどこまで本来の味を維持しているか、ぼく
はまだマグレブ諸国に行ったことがないのでわからない。
でも、そんなに違ってはいないと類推していいだろうと思う。
モロッコやチュニジアやアルジェリアはかつてフランスの植民地で、今
のフランスにはこれらの土地から来た人々とその子孫がたくさんいる。
同じような例を日本で求めれば、いちばん似ているのが韓国・朝鮮系の
料理だ。(言うまでもないことだが、1910年の日韓併合から1945
年の敗戦までの間、今の大韓民国ならびに朝鮮民主共和国にあたる地域は
日本の植民地だった)
最初のころはプルコギばかりだったが、しばらく前から家庭料理や宮廷
料理など、本来のものが味わえるようになった。
この場合も、本源の地とあまり変わらない味が再現されているとすれば、
それは素材だけでなく人も渡ってきたことの結果だろう。
人と共に文化も運ばれる。
ちなみにインターネットというのは便利すぎて味気ないもので、この原
稿を書きはじめて3分後にぼくはライムのチャツネが日本でも簡単に買え
ることを発見した。この30年の探索は何だったのだ?
NiLon’sというブランドの品は次のサイトに案内がある。
値段は200グラムで390円。
http://www.spinfoods.net/pickles.htm
スコットランドから帰って来ると、フランスは大荒れだった。
パリ周辺の住宅地で路上に駐めた車が次々に燃やされている。
毎夜、何百台という車が炎上している。
日本を含めて各国のメディアが大きく報道したし、夜空を背景に炎上す
る車は派手な絵になるから、日本の友人たちからは「そこは大丈夫?」と
いうメールが次々に入った。
まるでフランス全体が燃え上がっているかのようだ。
きっかけはパリ郊外のクリシー・スー・ボアという町で、2人の少年が
警察官に追われて変電所に逃げ込み、高圧線に触れて感電死したことだっ
た。
事故ではあるが象徴的な意味づけがあまりに濃い事故。
可燃材が山積みされたところに火が放たれたように、パリを取り巻く一
帯、郵便番号でいえば92、93、94あたりの地域で車への放火が相次
ぎ、他の大きな都市へも飛び火した。
それが毎晩百台単位、ピークには千台を超えたのだからたしかに尋常で
はない。
可燃材は何か、火を点けたのは誰か?
3週間以上たった今になって振り返ってみると、まず初期の報道はいか
にもセンセーショナルだった。
『パリは燃えているか?』というのはラピエールとコリンズの名著のタイ
トルで、ヨーロッパではよく知られている。
第2次大戦の末期、ヒトラーは退却しながらパリ全体を燃やせという指
令を出した。この指令がなぜ実行されなかったかを描いたノンフィクショ
ン。
映画化もされていたし、新聞の見出しがみなこれをなぞったのは当然だ
ったのかもしれない。「パリは燃えている!」
しかし違うのだ。
場所はパリではなく周辺だったし、燃えているのは住宅ではなく、路上
の車やターミナルに帰ったバスだった。
日本の法律では現住建造物放火罪と非現住建造物放火罪は区別されてい
る。
フランスの法のことは知らないけれど、路上に駐めてある車は日本風に
言えば後者だろう。
また、車への放火は今に始まったことではなく、このような地域でずっ
と続いている反抗の延長上にあることだった。
今年に入ってから燃やされた車は28000台、毎晩百台近い。
その内の6000台ほどが数日の間に集中したのが今回の事件。
イギリスの新聞の中には、あれだけの人を殺したロンドンのテロよりは
ずっと平和的という論調もあった。
前にこの連載でフランス人がグレーヴ(ストライキ)やマニフ(デモン
ストレーション)による意思表示を好むことを書いた。
今年の3月、政府が企図した教育制度の改革に反対してフランス全土の
高校生がデモをした。
今回の事態はむしろあれに似ているのではないか、とぼくは考えた。
放火は言うまでもなく乱暴な手段だが、1992年のロサンジェルスの
暴動のような過激さはない。
あの時はたしか50人以上の死者が出たが、今回は一人だけで、この一
人の犠牲はある程度まで偶発的と言っていいだろう。
バスを停めて、乗客全員を降ろしてから火を放ったという例もあったら
しい。
ともかく犯人たちが若い。
逮捕された者の半分以上が18歳以下で、中には10歳の子もいたとい
う。彼らは証拠不十分ということですぐに釈放されている。
要するに警察がとりあえず夜の町に出ている子供たちを片っ端から捕ま
えたということだ。
参加者のこの年齢もまた高校生のデモへの連想を誘うものだった。
しかし、今回の争乱・暴動・蜂起・示威(立場によって呼称はこれくら
い変わるはずだ)の真の原因は、フィヨンの教育制度の改革などよりずっ
と深いところにある。
フランスという共和国の基本理念が揺らいでいる。
この2週間、日本にいてはなかなか理解できないことだったと思いなが
ら、日々の報道や論評に接した。
一見したところ、騒いだ若い連中の動機はわかりやすい。
職がなく、将来の希望がなく、不満に満ちた毎日という状態がずっと続
いていて、改善の兆しが見えない。
ここ数年、事態は悪くなるばかり。
そこへ仲間が死んだという知らせが入る。
事故死とはいえ警察官に追われた果てのことだ。
それをきっかけに普段からの不満が一気に爆発し、正に燎原の火の如く
燃え広がった。
それに模倣犯が便乗し、夜ごとの解放区があちらこちらに出現した。
騒ぎが起こったのはどこも大都市周辺の事実上のゲットーである(だか
らと言っていいかどうか、パリからだいぶ離れた我が町では何の騒ぎもな
かった)。
もっぱら北アフリカ系の、ムスリムの人々がまとまって住む地域。
騒動の主役は移民の2世3世。
どこの国でもそうだが、移民の一世は苦労してフランスに渡って市民権
を得たから、少々待遇が悪くても文句は言わない。
前にいたところの暮らしよりはずっとよくなったと思って、たいていの
ことは我慢する。
しかしその子や孫の世代はフランスで生まれてフランスで育った。
人権についても学校で教えられた。
フランスの建前としての平等をそのまま受け止めれば、現実の不平等が
嫌でも目に付く。
もともとフランスは移民の多い国だ。
労働力の不足を移民で補うのは昔からのことで、だからフランス人の3、
4人に一人は祖父か祖母の一人が外国人だという。
そしてフランス革命でジャコバン派の人権思想が国の基本方針として採
択され、国籍についてもフランスで生まれればフランス人という出生地主
義が確立した。
つい先日まで血統主義だったドイツや、今もそれを貫き、まったくと言
っていいほど移民を入れない日本とは国の成り立ちが違う。
フランスは国民の要件として出自や信仰は問わない。
だから、フランスの公式の統計では国民のどれだけがムスリムであるか、
わからない。
6000万の人口のうち500万くらい、という推測があるばかりだ。
移民は次々にやってくる。年間十万人単位で増えているという。
一定の間この国に住んでいると国籍が与えられて移民から国民に昇格す
ることが多い。
そうなるとその人たちはもう統計の上の数字としては出てこないのだが、
それでも今のフランスでは人口の六パーセントが外国人だという。
しばらく前、たとえばアメリカ合衆国の人種問題を論じるのに、坩堝(る
つぼ)かサラダ・ボウルかという議論があった。
多くの人種が混じり合い溶け合って一つの社会を作るから「人種の坩堝」
だという素朴な比喩が最初にあり、やがて混じり合っても溶け合いはしな
いことが明らかになって、異質のままの素材が混在するという意味でサラ
ダ・ボウルという新しい表現が生まれた。
アメリカ合衆国やイギリスなどアングロ・サクソン系はもっぱらこの方
針で、エスニックな集団に社会的な地位が与えられる。
しかしフランスは理念として坩堝論を立ててきた。
集団としてのエスニックの存在を認めない。
フランス語を話し、フランス文化を受け入れればフランス人。
それ以上の分類はしない。
この国の基本は血統や土地ではなく理念だ、と言い張ってきた。
それはそれで立派なことかもしれない。
「自由、平等、博愛」は今でも美しいスローガンだとぼくは思う。
しかし、現実には差別はある。
最も目に見える形では、ゲットーの存在。
収入が低くて家が得にくい人々のために政府が団地を作る。
それは悪いことではないが、社会的なふるいを通過してそこに住み着い
た人々を見れば結果としては旧植民地の北アフリカ諸国の出身者ばかり。
そこに住む芸人が国立のテレビ局に職を得ようと履歴書を送ったという
話がある。
2通作って、一方は正直にその地域の住所を使い、名前もアフリカ系の
本名のまま。
もう一方はフランスっぽい名にして住所も評判のいい地域にした。
すると、後者の方にだけ面接の通知がきた。
フランスで成功したモロッコ生まれの実業家が書いた自伝のタイトルが
『社会のエスカレーターが壊れていたので、私は階段を登った』、という
例もある。
自分たちのためのエスカレーターが壊れていることを今回、若い人々は
車に火を放つことで指摘したのだ。
サルコジ内相の発言が騒ぎの初期にまさに火に油を注ぐ結果になったこ
とは広く報道されたようだ。
彼は荒れる若者を「くず racaille」と呼び、箒で掃き出すと言った。
普通、フランスの政治家はこういう露骨な表現は使わない。
直後のアンケートによればこの発言にはフランス人の6割以上が反発を
覚えたという。
しかし彼の発言はある程度まで計算ずくのものだ。
異質の文化からフランスを守れという思いもフランス人の中にはあって、
だから数年前、極右の国民戦線を代表するルペンの台頭に世界は驚いたの
だった。
2007年の選挙で大統領の席を窺うサルコジはフランスの保守層に訴
えることで支持者を増やせると読んだ。
彼自身がハンガリー系移民の2世であることを考えると、彼を巡る状況
はずいぶんねじれたものだ。
彼はアメリカ合衆国のコンドリーサ・ライス国務長官と同じようにマイ
ノリティー出身者たちの出世頭で、だから出自と体制の間でデリケート・
バランスを保っている。
東と南の違いもある。
去年の今ごろパリで会ったモロッコ人のジャーナリストのムハンマドは、
「1990年代になってソ連の崩壊で東欧系の移民が増えたので、ヨーロ
ッパは全体として南からの移民を制限するようになった」と言っていた。
労働力の不足を補うには移民が必要。
それならば文化的にも人種的にも近い東ヨーロッパの人の方が好ましい
ーーーそういう意図が移民政策に読み取れるというのだ。
この分析とサルコジの立場を重ねると、明日のフランスのある面が見え
るような気がする。
彼は移民の子といっても、ヨーロッパ系だから今の地位に就けたのでは
ないか。
この9月までフランス人は移民の存在にあまり不安感を覚えていなかっ
た、というアンケート結果がある。
騒ぎの3週間前に全ヨーロッパ的に行われた調査で、「移民は文化やア
イデンティティーや宗教にとって危険か?」という問いに、ドイツでは
29.2パーセントが危険だと答えた。
イタリアでは26,6パーセント。
そしてフランスでは22,6パーセントと最も低かった。
またこの数字はドイツでは前回の調査の時より4ポイント上昇している
のに対して、フランスでは逆に3,2ポイント減っていた。
「移民は就職の障害になるか?」という問いに肯定的な答えをしたのは
ドイツで40パーセント、イタリアで35パーセントに対して、フランス
では26,7パーセントだった。
前回書いた聖マルタンの夜に、知人と再会した。
彼女とは去年この町で親しくなったのだが、引っ越して今はパリ郊外の
別の町にいる。
とても知的で、フランス以外の国もよく知っていて、アジアや中東、ア
フリカで暮らした経験がある。
今住むところがパリ近郊と聞いて、騒ぎのことを聞いてみたが、自分の
ところでは何もなかったという。
それはそれとして、この一連の事態に関する彼女の意見がなかなか意味
のあるものだった――
私はやはりあの人たち、アフリカ系と呼ぶか、有色というか、黒い人と
するか、ムスリムというか、それはともかく、彼らには問題があると思う。
フランスには中国系の人もヴェトナム出身の人もたくさんいるけれど、
そういう人たちを巡って騒ぎにはならない。
でもあの人たちとフランス社会との間には埋めがたい溝がある。
例えば、ムスリムの人々の間では女性の地位は極端に低い。
女には社会に出る機会も権利もないというのはフランス人として認知で
きることではない。
実際、彼らは自分たちの文化の中にこもっている。
一人の夫が狭いアパルトマンで妻4人と子供十数人と一緒に暮らしてい
るのは、フランス的ではないと私は思う。
しかしそれでも、あるいはだからこそ、私たちはあの人たちに手を貸さ
なければならない。追い出すのではなく、お互いに許容できる範囲まで歩
み寄って、こちら側に招き寄せて、共にこの先のフランスを築いていかな
ければならない……というのが彼女の意見。
そうなのだろうとぼくは思った。
このあたりがフランスの良識の基本なのだろう。
しかしこの問題の根は深い。
前に論じた公立学校における女生徒のスカーフ着用の件がいい例だった
が、イスラム教とキリスト教の違いはやはり大きな障害なのだ。
なぜならばこの2つはよく似ているくせに決定的に違うから。
どちらも契約の宗教であり、一個の神を信じ、その神が微妙に、しかし絶
対的に違う。
東アジアの人々とはまったく違う。
そういう人たちが今や人口の1割近くいる。
一夫多妻の件は例えばこういう形で議論に入ってくる――今度の騒動の理
由の一つとして、騒いだ子供たちの親の責任を問う論があった。
小さなアパルトマンに父と母たちやたくさんの兄弟がひしめきあっている
から、子供は街頭で遊ぶしかなく、だから非行には走る。
この論法はある閣僚の口からも漏れた。
騒いだのが子供たちだったし、途中からは愉快犯の模倣も多かったので、
それを鎮めるべく発令された夜間外出禁止令は功を奏し、国民の73パーセ
ントの賛成を得た。
騒ぐ者は国外追放などという一連のサルコジの強硬策にも63パーセント
の支持が集まった。
実際には最初百数十人と言われた国外追放は10人程度に減じられたよう
だが。
11月の18日、ド・ヴィルパン首相はエリート校の一つであるストラス
ブールのENA(国立行政学院)の創立60周年の式典に出てスピーチをし
た。
その中で彼は、今回の事件は「価値観の危機」だと語り、「非人間的な都
市計画」と「失業」と「公共事業の非効率」を原因として挙げ、これらの解
決がまず必要だと言った。
また、騒動の起こった地域の人々を同一視してはいけないとも言った。
ムスリムをムスリムであるというだけでトラブルの元というレッテルを貼
ってはいけない。
共和国の原理を回復することが大事だと語り、機会の均等を実現しなけれ
ばならないと述べた。
1905年の法が男女の差別をなくしたように、今はライシテの原理によ
ってもう一つの差別をなくさなければならない(このライシテすなわちフラ
ンス流の政教分離の原理については、前にスカーフ問題のところで論じた)。
この後、首相はENAを出て、この町の郊外、つまりここでも騒動があっ
た地域をひそかに訪れ、あるレストランで福祉団体の代表や教育者の訴えを
聞いた。
そこで商業学校に通うという20歳の女性が言った言葉がなかなか印象的
だ――「郊外を変えるだけではなく、フランスを変えなければいけないと思
います」
去年すなわち2004年12月、それまで穏やかな地方都市と思われてい
たレンヌで、音楽フェスティバルに集まった若者が暴れて、警察が催涙弾2
50発を使うという騒ぎがあった。
その前にはこの町の名物だった回転木馬への放火という蛮行が2度あった
という。
この場合は特にマイノリティーが主体ということではなかったようだ。
北アフリカ系だけでなく、若い人々ぜんたいが就職難や先行きの不安を感
じているから、何かきっかけがあると騒ぎ出す。
またレンヌではベルナデット・マルゴールという女性の知事(市長ではな
い)の強権主義が却って反発を招いたという意見もある。
この点はサルコジの発言の影響に似ている。
この問題に関する日本の報道にはどこか冷ややかなものがあった。
移民なんか入れるからそういうことになるのだと言わんばかり。
しかし、日本だっていつまでも今のような鎖国をしているわけにはいかな
いだろう。
移民はおろか難民さえ受け入れないという姿勢がいつまで続くか。
開放せざるを得なくなった時に、日本は今のフランスその他ヨーロッパ諸
国の苦しみを身をもって理解するだろう。
世界の至るところで人と文化と言語は混じりあい、ぶつかり、その渦の中
から新しい価値が生まれている。
ド・ヴィルパンの演説はあまりに理想主義的で、あるいは空疎に響いたか
もしれない。
しかし、ぜんたいとしてフランスはやはりこの方向に進まなければいけな
いのだろうとぼくは思う。
<聖マルタン、愛知万博、植民地の料理、車を燃やす おわり>
(池澤夏樹 執筆:2005‐11‐25)