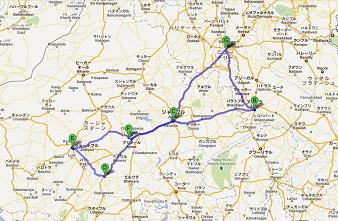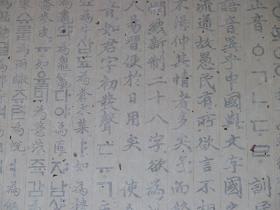当社の工場がある、フィリピン・スービック工業団地の敷地内にはフィリピンの原住民であるアニタ族の旧集落があります。上の写真は、アニタ族の子供達と。

1991年のピナツボ火山大噴火により集落は失われ、現在アニタ族は新たな集落に移っていますが、今でもここパムラクラキン・フォレストでは、観光スポットとして森の民、アニタ族の風俗を知ることができます。

ですから、元はこんな格好をしていたわけですが、今では普通にTシャツやジーンズを着用しています。しかし、森の恵みで生活の全てを営んできたアニタ族には、森に関する驚くべき知恵があり、今回はその一部をご紹介したいと思います。
台湾の原住民である高砂族の知恵が旧日本軍の南方進出の為に役立ったという話は知っていましたが、同様にアニタ族のジャングルで生き残るための知恵も、アメリカ軍に活用されたそうです。

まず、こちらは東南アジアでよく見られるジャックフルーツの木です。この木は果実が食べられるというだけでなく、葉の汁が沼のヒルを避けるのに有効だそうです。

アニャタンの木。樹皮が腹痛に効くそうです。食べてみましたが、非常に苦い皮です。まさしく「良薬口に苦し」といったところ。

ティビックの木。「水の木」とも呼ばれ、乾季で水が不足した場合、木の根に傷をつけ、その周りに穴を掘っておきます。すると夜の間に水がたまるということです。


デリタの木。樹液はマラリアの薬になります。ただし、妊娠中は避けなければならないとのこと。

パムラクラキンの木。この森の名を冠した木。葉が関節痛に効き、予防接種の代わりにもなるそうです。さらに花からは蜜が採れるという、万能の木といえます。
<つづく>
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

ブログをご覧いただいたすべての皆様に感謝を込めて。
よろしければクリックおねがいします!
↓