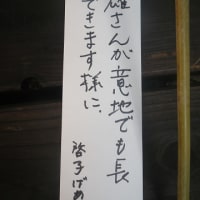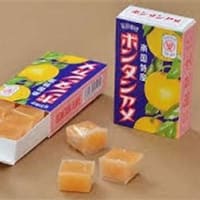さぬき市地方は概ね晴れていたが、冬型の気圧配置となっているため、雲が広がっている処もあった。気温は0度から7度、湿度は74%から56%、風は1mから3mの北北西の風が少し。明日の9日は、冬型の気圧配置が続くため、雲が広がりやすく、昼過ぎまで雪や雨の降る所があるらしい。

奥方のけいこばぁは朝の5時から起きて赤飯造り。お仏飯と昼食の赤飯用である。

私は仏間の準備。和室のふすまを取り外したり、座布団を並べたり・・・。

仏前のお供えを盛ったりする。お客さんが来るのは9時過ぎからぼつぼつと。

今日の導師は英海さん。脇は私と兄弟子の弘昭さん。今回は母の三回忌と祖母の25回忌の法要である。

一席目は「初夜礼讃」。二席目は「四十八願」と「阿弥陀経」、それに「現世利益和讃」。

最後は「御勧章拝読」。そして法話があって、ちょうど2時間。直後にお迎えのバスがやってきた。みんなは大急ぎでバスに乗り込んで「おとき(齊)会場」に向かう。例年、この時期には雪があって大騒ぎするのだが、今回はさわやかな春のような空だが、空気は冷たかった。

「プレッソ古川」さんというお店での「おとき」である。ここは結婚式場でもあり、一般の宴会場でもあって重宝なお店。毎年、ここのお世話になっている。

予定参加者は22人だったが、当日のお参りは18名になった。少し前には30人・40人という数になったが、叔父さんやおばさんらがいなくなって、めっきりと淋しくなった。それに子や孫や・・というのもいなくなって、「なぎちゃん」一人になった。

最初のおときはこうしたものから。「献杯」は唯一の叔父さんの発声をお願いした。あと、天ぷらだの茶碗蒸しだのおすましなどが出て来る。左下のお茶碗の中に、けいこばぁの作ったお赤飯が入っている。

ご婦人方はしっかりと食べて、話してとにぎやか。一方。男性陣はビールだ、酒だ、と、こちらは飲んで騒いで・・・。「六甲おろし」まで飛び出したりして・・・。

楽しいときはあっという間。時間制ではないのだが、女性陣がパックに残り物を詰め出すと、仕方なく男性陣もお銚子やビール瓶の中身を飲み干してしまう。およそ二時間・・・。

おみやげを手にして、みんなはバスに乗り込んでわが家に戻る。そのまま、車で帰る人もあれば、コーヒーやお茶で休憩する女性陣や、またもビールで二次会をする男性陣なども。

私はようやくに和装から平服に着替えて、早速に座布団や椅子などを片付け、経机や焼香盆などを片付けて平常の仏間に戻す。

今日の掲示板はこれ。「災難が来ぬように祈るのが信心ではない。どんな災難が来ても引き受けてゆける力を得るのが信心です」というもの。この世は無常である。常なるものは何もない。「ゆく川の流れは絶えずして、もとの水にあらず」と言われるように常に変化している。「時間よとまれ」ということはありえない。無常なるがゆえに、一寸先は何が起こるかわからない。一寸先は闇。いくら一生懸命努力しても、勉強しても、頑張っても、結果はどうなるかはわからない。どっちに転ぶかわからないのが現実。どっちに転んでも大丈夫といえるものを身につけていなかったら、結果が悪かった時とても苦しい。仏法を聞くとは、どっちに転んでも、災難がきても、思い通りにいかなくても大丈夫というものを得ることである。災難が来ないように祈るのが信心ではない。この世は必ず、生老病死の苦しみに出会うのである。祈って無くなるものでは決してない。生きていれば必ず別れや死が来る。与えられたことを引き受け、それを乗り越えていくしかないのである。その乗り越えていく力を得ることが信心であると言うているのである。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。