
もう既に四月の初旬も過ぎようと云うのに明日は真冬並みの氷雨か
雪かもーーとの予報が出たので桜が終わってしまう前に又、一回り。
今日は3/31の桜祭りが蕾のままで終わってしまった小幡方面。
R-254の福島から南進して小幡の街中を目指すと沿道は桜満開。
だが、上空には風雲が張り付き冷たい強風で花日和とはいかない。
人影も少ない沿道の桜を観てから総合公園を縦断する幅広の
雄川の河川敷で土手の桜見物。
城下町小幡の桜
小幡から県道を西進して「織田七代の墓地」に寄る。最近整備された
らしく県道の入口から墓地前まで車道が完備。
先ず西側の織田家菩提寺の「崇福寺」。実は旧領主小幡氏の菩提寺は
宝積寺で格式も高かったため、織田氏も三代までこの寺を菩提寺として
いたのだが四代・織田信久は急に、廃寺であった崇福寺を改築し、
臨済宗に改めて菩提寺として、宝積寺から三代の墓石をここへ移した
と伝わっている。
どうやら宝積寺の住職交代の儀式に際しての織田家の席次に不満を
持ったのが原因とされるが真実か風聞伝説かは分からない。
山号は「小畑山」だが1758年と1871年に大火に拠って焼失している。

隣には織田家の位牌堂。歴代藩主の位牌は二度の火災にも難を逃れ
檀徒によって大切に守られて位牌堂内で安置・保存されているとか、
但し二代信良と七代信富を除く十代信美までの位牌と、四代小幡藩主
信久の実父でもある織田高長の位牌が祀られているそうだ。

位牌堂内部の様子。

町指定文化財の「石造聖観音座像」の前を通って

七代の墓地に向かう。光線の関係で七代側からの様子。

小幡と織田の関係は大坂の陣後の1615年から152年間の事であり
それ以前は地名の小幡が示すように主に小幡氏の支配下だった。
鎌倉時代には既に児玉党の一派として小幡氏の活躍がみられ13世紀
初頭には小幡の地に居住し、勢力を確立していたと推考されている。
南北朝時代以降、上杉氏が上野国守護となりその支配力が強固になると、
西上野の拠点の一つとして甘楽の地が重要視される。
今の甘楽町地域には白倉城、国峯城、庭谷城、天引城などが築城。
小幡氏は居城の国峯城に拠り後に信玄の幕下に加わり、武田軍団
の先陣として武勇をはせ「朱備え」着用を許され、上州の朱武者として
恐れられた。武田24将絵図にも常連で入っている。
武田氏滅亡後は一瞬だけ信長配下の滝川一益に従い、本能寺の変以後は
小田原北条氏の勢力下に入ったが、1590年秀吉の小田原城攻めに際して、
国峯城も前田利家隊などの北陸秀吉軍により落城した。そして
甘楽の地を徳川家康に明け渡し、真田氏をたよって信州へ去っている。
この1590年から関ケ原直後の1601年までの11年間は、小幡領2万石で
奥平信昌が領主となり、国峯城の支城であった富岡の宮崎城に入った。
1601年から1602年は、信昌四男・松平忠明、
1602年から1615年までは水野忠清。そして1615年7月、信長の二男信雄に
大和国宇陀郡3万石・上州小幡2万石が与えられ、1616年に信雄の子
信良が福島の陣屋に入り、織田氏による小幡支配が開始されたのである。
そして150年が過ぎ、8代信邦の1766年に内紛が勃発、明和事件にも
連座して。1767年に信邦蟄居、弟・信浮は養子として出羽高畠2万石に
移封。跡に座ったのは松平忠恒。4代忠恕は、小幡藩最後の藩主として
1869年に版籍奉還。
七代の墓には信邦は入っていない。正面からは逆光になるので裏から。
(左クリックで拡大、元の画面に戻すには画面左上の左向き矢印クリック)







墓地を辞して更に県道を西南進、小幡氏菩提寺の花の寺として名高い
宝積寺。
名物の枝垂れ桜はもう勢いはないが境内は桜で一杯。再び観桜満喫。
(左クリックで拡大、元の画面に戻すには画面左上の左向き矢印クリック)













この寺は見所も満載。
(左クリックで拡大、元の画面に戻すには画面左上の左向き矢印クリック)









境内散策を切り上げて4/7に開始されたという秋畑の鯉のぼり見物。
曲がりくねった県道を山手に向かって約7K,雄川の左岸を延々と進む。
やがて目の前にいきなり鯉のぼりが現れた。橋を渡って右岸を行くと
堰堤の所で鯉のぼりに出会った。

更に県道の前方に次のものが見えたので前進。

だが、近くに寄る前に県道は左の山手に向かって南進し日野方面に
行ってしまう。その角で確認しながら居合わせた地元の方に聞いたら
橋を渡らずに左岸の道だと教えられた。どうやら最初に見つけたものに
惑わされて右岸を進んで来たようだ。

戻って橋を渡りなおして進むとトイレ付きの駐車場。ここからも
良く見える。

更に近寄るとその奥にも未だ鯉のぼりが続いている。だが急斜面を
蛇行する山道なので自重して終わりにした。五月までやっている
との事なので時間に余裕のある時に再度来てみたい。

尚、この文中で「国峰城」と「明和事件」の文字を色変わりさせていますが
そこをクリックすると爺イの過去の夫々の詳細記事がご覧いただけます。
御用とお急ぎの無い方?は暇つぶしにご覧ください。
ご来訪の序に下のバナーをポチッと。
 登山・キャンプランキング
登山・キャンプランキング
雪かもーーとの予報が出たので桜が終わってしまう前に又、一回り。
今日は3/31の桜祭りが蕾のままで終わってしまった小幡方面。
R-254の福島から南進して小幡の街中を目指すと沿道は桜満開。
だが、上空には風雲が張り付き冷たい強風で花日和とはいかない。
人影も少ない沿道の桜を観てから総合公園を縦断する幅広の
雄川の河川敷で土手の桜見物。
城下町小幡の桜
小幡から県道を西進して「織田七代の墓地」に寄る。最近整備された
らしく県道の入口から墓地前まで車道が完備。
先ず西側の織田家菩提寺の「崇福寺」。実は旧領主小幡氏の菩提寺は
宝積寺で格式も高かったため、織田氏も三代までこの寺を菩提寺として
いたのだが四代・織田信久は急に、廃寺であった崇福寺を改築し、
臨済宗に改めて菩提寺として、宝積寺から三代の墓石をここへ移した
と伝わっている。
どうやら宝積寺の住職交代の儀式に際しての織田家の席次に不満を
持ったのが原因とされるが真実か風聞伝説かは分からない。
山号は「小畑山」だが1758年と1871年に大火に拠って焼失している。

隣には織田家の位牌堂。歴代藩主の位牌は二度の火災にも難を逃れ
檀徒によって大切に守られて位牌堂内で安置・保存されているとか、
但し二代信良と七代信富を除く十代信美までの位牌と、四代小幡藩主
信久の実父でもある織田高長の位牌が祀られているそうだ。

位牌堂内部の様子。

町指定文化財の「石造聖観音座像」の前を通って

七代の墓地に向かう。光線の関係で七代側からの様子。

小幡と織田の関係は大坂の陣後の1615年から152年間の事であり
それ以前は地名の小幡が示すように主に小幡氏の支配下だった。
鎌倉時代には既に児玉党の一派として小幡氏の活躍がみられ13世紀
初頭には小幡の地に居住し、勢力を確立していたと推考されている。
南北朝時代以降、上杉氏が上野国守護となりその支配力が強固になると、
西上野の拠点の一つとして甘楽の地が重要視される。
今の甘楽町地域には白倉城、国峯城、庭谷城、天引城などが築城。
小幡氏は居城の国峯城に拠り後に信玄の幕下に加わり、武田軍団
の先陣として武勇をはせ「朱備え」着用を許され、上州の朱武者として
恐れられた。武田24将絵図にも常連で入っている。
武田氏滅亡後は一瞬だけ信長配下の滝川一益に従い、本能寺の変以後は
小田原北条氏の勢力下に入ったが、1590年秀吉の小田原城攻めに際して、
国峯城も前田利家隊などの北陸秀吉軍により落城した。そして
甘楽の地を徳川家康に明け渡し、真田氏をたよって信州へ去っている。
この1590年から関ケ原直後の1601年までの11年間は、小幡領2万石で
奥平信昌が領主となり、国峯城の支城であった富岡の宮崎城に入った。
1601年から1602年は、信昌四男・松平忠明、
1602年から1615年までは水野忠清。そして1615年7月、信長の二男信雄に
大和国宇陀郡3万石・上州小幡2万石が与えられ、1616年に信雄の子
信良が福島の陣屋に入り、織田氏による小幡支配が開始されたのである。
そして150年が過ぎ、8代信邦の1766年に内紛が勃発、明和事件にも
連座して。1767年に信邦蟄居、弟・信浮は養子として出羽高畠2万石に
移封。跡に座ったのは松平忠恒。4代忠恕は、小幡藩最後の藩主として
1869年に版籍奉還。
七代の墓には信邦は入っていない。正面からは逆光になるので裏から。
(左クリックで拡大、元の画面に戻すには画面左上の左向き矢印クリック)







墓地を辞して更に県道を西南進、小幡氏菩提寺の花の寺として名高い
宝積寺。
名物の枝垂れ桜はもう勢いはないが境内は桜で一杯。再び観桜満喫。
(左クリックで拡大、元の画面に戻すには画面左上の左向き矢印クリック)













この寺は見所も満載。
(左クリックで拡大、元の画面に戻すには画面左上の左向き矢印クリック)









境内散策を切り上げて4/7に開始されたという秋畑の鯉のぼり見物。
曲がりくねった県道を山手に向かって約7K,雄川の左岸を延々と進む。
やがて目の前にいきなり鯉のぼりが現れた。橋を渡って右岸を行くと
堰堤の所で鯉のぼりに出会った。

更に県道の前方に次のものが見えたので前進。

だが、近くに寄る前に県道は左の山手に向かって南進し日野方面に
行ってしまう。その角で確認しながら居合わせた地元の方に聞いたら
橋を渡らずに左岸の道だと教えられた。どうやら最初に見つけたものに
惑わされて右岸を進んで来たようだ。

戻って橋を渡りなおして進むとトイレ付きの駐車場。ここからも
良く見える。

更に近寄るとその奥にも未だ鯉のぼりが続いている。だが急斜面を
蛇行する山道なので自重して終わりにした。五月までやっている
との事なので時間に余裕のある時に再度来てみたい。

尚、この文中で「国峰城」と「明和事件」の文字を色変わりさせていますが
そこをクリックすると爺イの過去の夫々の詳細記事がご覧いただけます。
御用とお急ぎの無い方?は暇つぶしにご覧ください。
ご来訪の序に下のバナーをポチッと。
















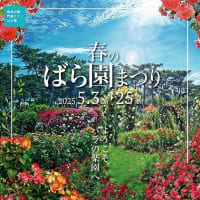



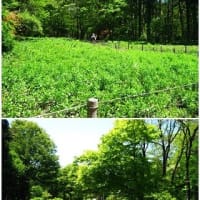





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます