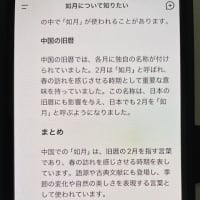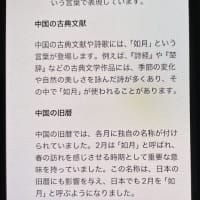語について 日本語の文法について その49
語は詞辞による構成を考える。これは学説を踏まえることになる。詞辞の二大別はどのように行われてきたであろうか。これによって時枝学説の言語過程説が生まれた。その理論は詳細を心的過程とするので現代の言語学の流派には即さない。批判が出された多くはまた時枝流の言語解釈である。学説そのものも国語解釈を打ち出すので古典文学作品に依拠する文献資料の証明にとどまる。それをあえて学説を踏まえるとするのはいずれ語を捉え文章を見ることになるとまさに学説が辿る作品論にもおよび文学と言語の境界が定かでなくなる。
しかしこれから述べようとするところはその理論の換骨奪胎であるべきかと戒めつつ、いつかはその学説を超えたくも思う。それはできるかできないかはわからないが国語にふさわしく見て言語現象をそれによって振り返ることはその亜流にあっても潮流になってもさらには必要な超流のようなことを考える。できるだけ心的過程を言語事実に合わせたとらえ方をしたい。
しかしこの考えに至るには松下学説の言辞の捉え方、それを詞と原辞とした分析にも負う。松下学説の文法論を進めると連詞にあって断句でひとまずの理論となる。原辞、連詞、断句はまた統治を捉えようとしている。いわば漢文法を据えて言語の現象をそのままに受け止めたものである。そこには詞という組み合わせがいわば句を作るという合理的な分析である。
その学説の及ぶところ、ほかにはないが長くそれを行う文法の考え方があるのも事実であってそれは歌の解釈を心情的に捉えるための分析と総合であったろうと思う。学説はその後の学界において時を経て再論されようとしたが、形態論の先駆としてだけの位置づけで、そこに現われた炯眼のいくつかを取り込む現代語の現象の解説になっているに過ぎない。
いずれにせよ、松下文法の吟味は言語学足り得るか、それは西洋語学の視点に対して東洋語学という、それがあるならばのことで、再び水平線を見せるかどうかである。その水準点は境界を示す。語については詞と見た考え方を、詞は原辞を基にする見方を持つ。ここでその理論を紹介するわけではないので、その発想のもとに語を考えたいということである。
語は詞辞による構成を考える。これは学説を踏まえることになる。詞辞の二大別はどのように行われてきたであろうか。これによって時枝学説の言語過程説が生まれた。その理論は詳細を心的過程とするので現代の言語学の流派には即さない。批判が出された多くはまた時枝流の言語解釈である。学説そのものも国語解釈を打ち出すので古典文学作品に依拠する文献資料の証明にとどまる。それをあえて学説を踏まえるとするのはいずれ語を捉え文章を見ることになるとまさに学説が辿る作品論にもおよび文学と言語の境界が定かでなくなる。
しかしこれから述べようとするところはその理論の換骨奪胎であるべきかと戒めつつ、いつかはその学説を超えたくも思う。それはできるかできないかはわからないが国語にふさわしく見て言語現象をそれによって振り返ることはその亜流にあっても潮流になってもさらには必要な超流のようなことを考える。できるだけ心的過程を言語事実に合わせたとらえ方をしたい。
しかしこの考えに至るには松下学説の言辞の捉え方、それを詞と原辞とした分析にも負う。松下学説の文法論を進めると連詞にあって断句でひとまずの理論となる。原辞、連詞、断句はまた統治を捉えようとしている。いわば漢文法を据えて言語の現象をそのままに受け止めたものである。そこには詞という組み合わせがいわば句を作るという合理的な分析である。
その学説の及ぶところ、ほかにはないが長くそれを行う文法の考え方があるのも事実であってそれは歌の解釈を心情的に捉えるための分析と総合であったろうと思う。学説はその後の学界において時を経て再論されようとしたが、形態論の先駆としてだけの位置づけで、そこに現われた炯眼のいくつかを取り込む現代語の現象の解説になっているに過ぎない。
いずれにせよ、松下文法の吟味は言語学足り得るか、それは西洋語学の視点に対して東洋語学という、それがあるならばのことで、再び水平線を見せるかどうかである。その水準点は境界を示す。語については詞と見た考え方を、詞は原辞を基にする見方を持つ。ここでその理論を紹介するわけではないので、その発想のもとに語を考えたいということである。