2月27日月曜日、晴天に恵まれた鼓ヶ浦海岸で、白砂青松100選に選ばれていながらここ2年間で250本余の松がマツクイムシの被害で枯れてしまった松林を再生しようという鈴鹿市、ベイロータリークラブ、鼓ヶ浦観光協会の共催事業のプロジェクトに白子小学校6年生約100名と鼓ヶ浦中学校3年生約170名が、卒業記念として参加してくれた。
主催者挨拶ののち、樹木医さんからのマツクイムシによる松枯れの仕組みの説明、松の苗木の植え方の説明があり、小学生のブロックと中学生のブロックに分かれて海岸林再生のために300本の黒松を植樹した。
大きく育った松を、自分が植えた松が大きく育った姿を見に来てほしい。という思いはどうやら中学校の先生方には伝わらなかったようだ。
30㎝ほどの穴を掘り、藁を敷き、根を広げ下方に伸びるように苗木を置いて砂を戻し、添え木を刺してゴムで苗木を固定する作業をしてもらった。が、明らかに大人が付き添ったとはいえ小学生の植え方の方が上手であった。つまり、中学生は、何故そうしなければならないのか、とりあえず松を砂浜に差し込んだらこのイベントは終わり、松が根付くかどうかには興味もない。という風にみえた。一生懸命してくれた子には申し訳ないが、先生たちが何も言わず(整列時だけは命令口調だったが)何もせずに時間の経過を過ごしている姿からは、子どもの自立という義務教育の最大の使命を果たそうとする気配は皆無であった。
彫る深さは、苗木の長さや土壌の状況によって変わるものだし、藁を敷くのも保水性の問題を考えたものだし、根を上向きに押し込んだのでは根付くはずもなく、根が機能を発揮し続けるために幹が風に動かされないように添え木をするわけだし、止めゴムを使うのもゴムの寿命や根付く時間を考えたものであるという事をいったいどのくらいの子どもたちが考えたのであろう。
学校で植え方のプリントを配布していただいて会場に来てもらっているので事前に説明があったのか、配られただけだったのかはわからないが、少なくとも、卒業記念に植えた松を数年後に見に来てほしいという気持ちが先生方にあれば子どもたちの動きが違ったであろうし、見守る先生たちの態度も変わったでしょう。校長先生が「小学生より植え方が下手だ」といった言葉がむなしい。
義務教育が終わって、巣立っていくという事は、高校への進学を選ばない生き方も可能なわけで、守られた環境での義務教育の世界から子どもが巣立つために、何を子どもに伝えようとしているのかが、先生たちの態度からはうかがえなかった。時間を過ごせば給与がもらえる、どうしようもない公務員の姿でしかない姿を子どもたちに見せつけている状況で、学力向上も生徒たちの自立も望めない。今現在の子どもたちの立ち位置を気づかしてあげなければ、指示待ち人間で大切な青春時代を送ってしまいかねないことに考えが回らないのだろうか。
たった2時間の作業で松が命を受け継いだとしたら有意義な時間だったといえるけれど,根付かなくても、懸命に行えば次につながる時間であったと思うけれど、意味も狙いも考えずに過ごした2時間は全く無意味になってしまうことを、教師として見過ごしていいのだろうか。
植えた状況をチェックし、手を加えながら近くの生徒たちにも確認とやり直しをさせている主催者側の大人たちの姿をどんな気持ちで見ていたのだろう。
今日一日を生きていることに感謝することや、残り少ない時間を懸命に生きている人の存在なども子どもに気づかせられる立場の教員の意識を聞いてみたいなぁと思わされた松林再生プロジェクトでした。
もちろん一生懸命自分の与えられた場所で、教師の使命に燃えて闘っている先生の存在を否定しているわけではありません。
親が我が子を思うように、クラス、学校の子どもを見てほしいと願っているのです。
主催者挨拶ののち、樹木医さんからのマツクイムシによる松枯れの仕組みの説明、松の苗木の植え方の説明があり、小学生のブロックと中学生のブロックに分かれて海岸林再生のために300本の黒松を植樹した。
大きく育った松を、自分が植えた松が大きく育った姿を見に来てほしい。という思いはどうやら中学校の先生方には伝わらなかったようだ。
30㎝ほどの穴を掘り、藁を敷き、根を広げ下方に伸びるように苗木を置いて砂を戻し、添え木を刺してゴムで苗木を固定する作業をしてもらった。が、明らかに大人が付き添ったとはいえ小学生の植え方の方が上手であった。つまり、中学生は、何故そうしなければならないのか、とりあえず松を砂浜に差し込んだらこのイベントは終わり、松が根付くかどうかには興味もない。という風にみえた。一生懸命してくれた子には申し訳ないが、先生たちが何も言わず(整列時だけは命令口調だったが)何もせずに時間の経過を過ごしている姿からは、子どもの自立という義務教育の最大の使命を果たそうとする気配は皆無であった。
彫る深さは、苗木の長さや土壌の状況によって変わるものだし、藁を敷くのも保水性の問題を考えたものだし、根を上向きに押し込んだのでは根付くはずもなく、根が機能を発揮し続けるために幹が風に動かされないように添え木をするわけだし、止めゴムを使うのもゴムの寿命や根付く時間を考えたものであるという事をいったいどのくらいの子どもたちが考えたのであろう。
学校で植え方のプリントを配布していただいて会場に来てもらっているので事前に説明があったのか、配られただけだったのかはわからないが、少なくとも、卒業記念に植えた松を数年後に見に来てほしいという気持ちが先生方にあれば子どもたちの動きが違ったであろうし、見守る先生たちの態度も変わったでしょう。校長先生が「小学生より植え方が下手だ」といった言葉がむなしい。
義務教育が終わって、巣立っていくという事は、高校への進学を選ばない生き方も可能なわけで、守られた環境での義務教育の世界から子どもが巣立つために、何を子どもに伝えようとしているのかが、先生たちの態度からはうかがえなかった。時間を過ごせば給与がもらえる、どうしようもない公務員の姿でしかない姿を子どもたちに見せつけている状況で、学力向上も生徒たちの自立も望めない。今現在の子どもたちの立ち位置を気づかしてあげなければ、指示待ち人間で大切な青春時代を送ってしまいかねないことに考えが回らないのだろうか。
たった2時間の作業で松が命を受け継いだとしたら有意義な時間だったといえるけれど,根付かなくても、懸命に行えば次につながる時間であったと思うけれど、意味も狙いも考えずに過ごした2時間は全く無意味になってしまうことを、教師として見過ごしていいのだろうか。
植えた状況をチェックし、手を加えながら近くの生徒たちにも確認とやり直しをさせている主催者側の大人たちの姿をどんな気持ちで見ていたのだろう。
今日一日を生きていることに感謝することや、残り少ない時間を懸命に生きている人の存在なども子どもに気づかせられる立場の教員の意識を聞いてみたいなぁと思わされた松林再生プロジェクトでした。
もちろん一生懸命自分の与えられた場所で、教師の使命に燃えて闘っている先生の存在を否定しているわけではありません。
親が我が子を思うように、クラス、学校の子どもを見てほしいと願っているのです。










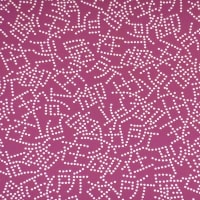



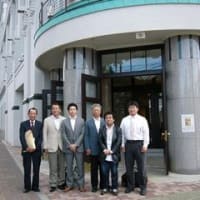
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます