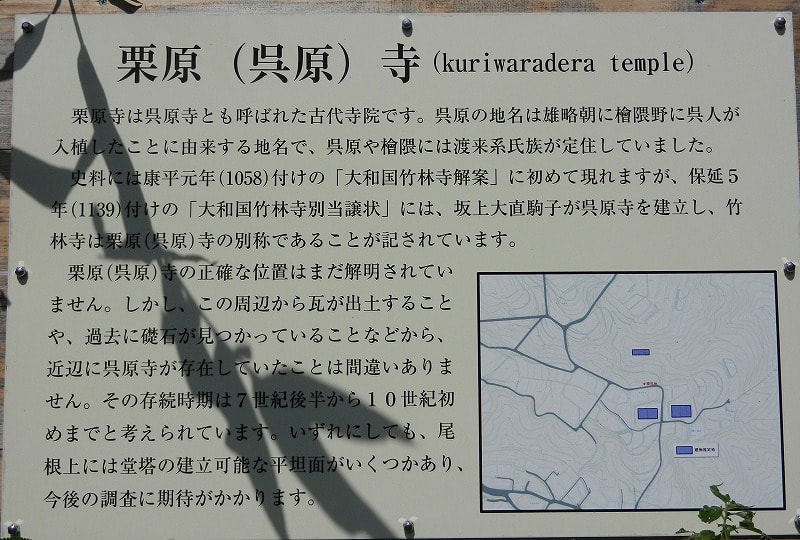三つの磐座で『古事記』神話の「天の岩戸」の段を再現していると考えられています 撮影日;2011.11.13
裏参道側の神域左方下に三つの磐座が有ります
右上段は「掌石」(斎神:太玉命)、手のひらのような形をしている
左下段は「沓形石」(斎神:天児屋根命)、神官が履く沓(くつ)のような形をしている
手前にある「鵝形石」(斎神:天照大神)、鵝鳥(がちょう)のような形をしている


與喜山は、古くは大泊瀬山と呼ばれ、古代大和の国では最初に太陽の昇る神聖な山としてあがめられました
『万葉集』では初瀬にかかる枕詞「隠り国」(山に囲まれ隠っているような地)は、この自然の姿から生まれたそうです
万物の生命のみなもとである太陽と、母なる慈愛を神としてあがめたのがアマテラスという女性神で、天上からこの御山に初めて降臨されたと伝えられています
本殿の向かって左に古代信仰のままに磐座(鵝形石)に祭られているのが天照大神で、女性の守護神として信仰されています
673年4月、天武天皇は伊勢に出発する斎王・大来皇女の潔斎のために、與喜山に施設「泊瀬斎宮」を設けたと伝わります
後方の鍋倉山には、延喜式式内社の「鍋倉神社」が磐座に祭られているそうです
磐座の左方には「鍋倉神社」へ奉納された灯篭2基が有り、その後方広場は連歌会所の「菅明院」跡だそうです
★所在地;桜井市初瀬14
★交通;近鉄 長谷寺駅下車 徒歩20分
長谷寺駅下車 徒歩20分
★駐車場;有ります(有料)
★入場料;見学自由
★問合せ;0744-55-2300(與喜天満神社)
裏参道側の神域左方下に三つの磐座が有ります
右上段は「掌石」(斎神:太玉命)、手のひらのような形をしている
左下段は「沓形石」(斎神:天児屋根命)、神官が履く沓(くつ)のような形をしている
手前にある「鵝形石」(斎神:天照大神)、鵝鳥(がちょう)のような形をしている


與喜山は、古くは大泊瀬山と呼ばれ、古代大和の国では最初に太陽の昇る神聖な山としてあがめられました
『万葉集』では初瀬にかかる枕詞「隠り国」(山に囲まれ隠っているような地)は、この自然の姿から生まれたそうです
万物の生命のみなもとである太陽と、母なる慈愛を神としてあがめたのがアマテラスという女性神で、天上からこの御山に初めて降臨されたと伝えられています
本殿の向かって左に古代信仰のままに磐座(鵝形石)に祭られているのが天照大神で、女性の守護神として信仰されています
673年4月、天武天皇は伊勢に出発する斎王・大来皇女の潔斎のために、與喜山に施設「泊瀬斎宮」を設けたと伝わります
後方の鍋倉山には、延喜式式内社の「鍋倉神社」が磐座に祭られているそうです
磐座の左方には「鍋倉神社」へ奉納された灯篭2基が有り、その後方広場は連歌会所の「菅明院」跡だそうです
★所在地;桜井市初瀬14
★交通;近鉄
 長谷寺駅下車 徒歩20分
長谷寺駅下車 徒歩20分★駐車場;有ります(有料)
★入場料;見学自由
★問合せ;0744-55-2300(與喜天満神社)