
幽霊トンネルとしても有名 撮影日;2014.01.04
かつて近鉄奈良線の孔舎衛坂駅⇔生駒駅間にあった鉄道トンネル(全長3,388m)
(日本初の標準軌複線トンネルです)
奈良線の生駒トンネルは大正3年(1914)に、近畿日本鉄道の前身である大阪電気軌道により開通しました
開通当時は日本で2番目の長さだったそうです
新生駒トンネル(全長3,494m)の開通により、昭和39年に鉄道トンネルとしての使用を終えました
その後、奈良線の旧トンネルを一部再利用する形でけいはんな線の生駒トンネルが昭和61年に開通しています
このトンネルは、現在のようなコンクリートではなくレンガにより作られています
使用されているレンガの数は約3,000万個に及ぶそうです
イギリス工法という、小口のみの段と長手のみの段を交互に積み重ねた技法を採用
当時は強度的にも優れた積み方として推奨されていたそうです
工事は明治44年(1911)に大林組が請け負い着工されました
建設は地質の変化や湧水等に悩まされ、予想外の難工事となった
工事費用が見込みを上まわり、岩下清周(当時の大軌社長)が私財を叩いて建設を続行させたそうです
大正2年1月26日に発生した落盤事故では、152名が生き埋めとなり20名の犠牲者が出ています
工事には朝鮮半島からの出稼ぎ労働者も従事しており、この事故でも犠牲となった者がいました
開通後も何度と無く大事故が有り、幽霊説がうわさされたようです
現在は、高圧電流の通る電力設備が設置されています
また、新生駒トンネル及びけいはんな線生駒トンネルの緊急避難通路になっています
平成21年2月23日、経済産業省より「近代化産業遺産」に認定されました

孔舎衛坂駅は新生駒トンネル開通時まで大阪側出入口に有りました
大正3年7月17日、日下駅(くさかえき)として開業
大正7年、鷲尾駅と改称
昭和15年6月、孔舎衛坂駅(くさえざかえき)と改称
昭和39年7月23日、新生駒トンネル開通の路線変更により廃駅
駅名の由来は、『日本書紀』の神武東征伝説で、神武天皇が生駒山の豪族・長髄彦と刃を交えた峠「孔舎衛坂」に比定される尾根が近くにあることによる
「白龍神社」が祀られています
工事中の落盤事故や開通後に起きた車両火災及び衝突事故などの犠牲者を慰霊する目的と、生駒トンネルの安全を祈願して建立されたものだそうです
旧生駒トンネルに向かって右のホームにはお地蔵さん、左のホームには石碑が建っており、事件で犠牲になった人を祀ってあるとのこと
★所在地;東大阪市日下町1丁目
★交通;近鉄

石切駅下車 徒歩5分
★駐車場;なし
★見学;通常は見学できません
★問合せ;

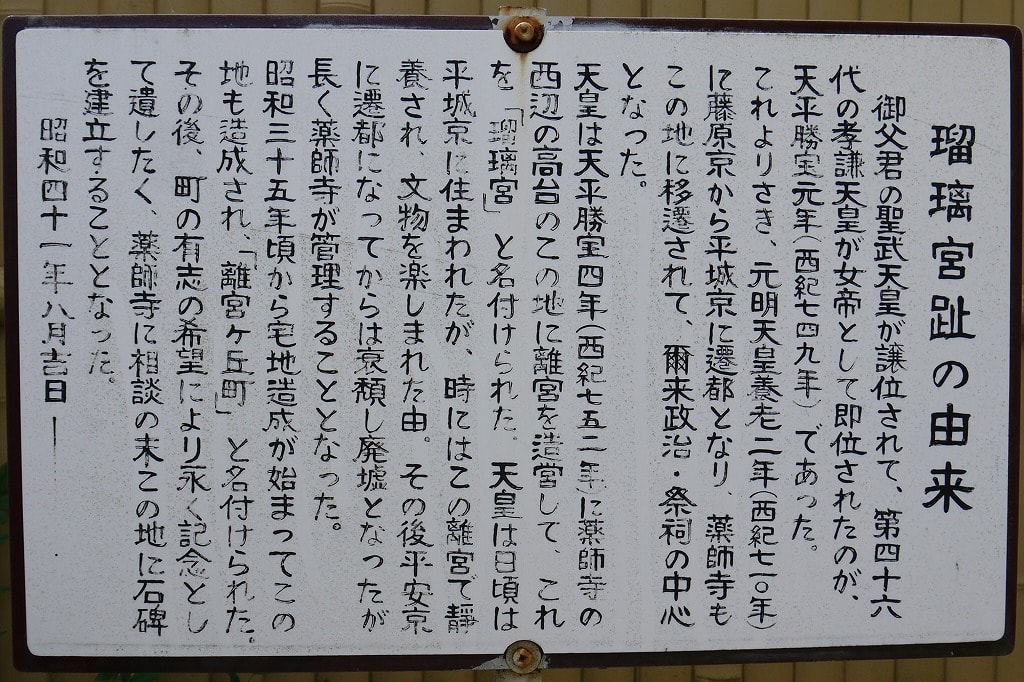

 西の京駅下車 徒歩15分
西の京駅下車 徒歩15分




































