日本メキシコ学院はメキシコ・シティの南部にある。私立学校なので、ある程度以上の家庭でないと、とても子供をやれない。子供だけで徒歩や自転車で通学することはあり得ない。親がついていれば安心かというとそうでもない。富裕層の子供を狙った誘拐ビジネスもあるくらいである。路線バスでもやっぱり危ない。バスの中はいいとしても、バスを降りて歩いている間に狙われるのである。
スクールバスもあったような気もするが、通学は親が自家用車で送り迎えするのが普通だった。学校の正門の前で降ろすのもだめで、敷地内に降車場所があるので、そこで降ろす。車が次々に来るので、さっさと場所を空けなければならないのだが、メキシコでは「行っていらっしゃい」程度のちょっとした別れの挨拶でも、キスをするのが習慣である。中には念入りにキスする親子もいて、ますます混雑に拍車がかかるのである。
ポチッとクリックすると、何かが起きる(かも)。
↓↓↓
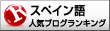 スペイン語 ブログランキングへ
スペイン語 ブログランキングへ


スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 (開拓社言語・文化選書)
天界航路―天野芳太郎とその時代 (1984年)

 インディアスの破壊についての簡潔な報告 (岩波文庫)
インディアスの破壊についての簡潔な報告 (岩波文庫)

 はじめてのスペイン語 (講談社現代新書)
はじめてのスペイン語 (講談社現代新書)


コスタリカの歴史 (世界の教科書シリーズ)

 人名の世界地図 (文春新書)
人名の世界地図 (文春新書)
スクールバスもあったような気もするが、通学は親が自家用車で送り迎えするのが普通だった。学校の正門の前で降ろすのもだめで、敷地内に降車場所があるので、そこで降ろす。車が次々に来るので、さっさと場所を空けなければならないのだが、メキシコでは「行っていらっしゃい」程度のちょっとした別れの挨拶でも、キスをするのが習慣である。中には念入りにキスする親子もいて、ますます混雑に拍車がかかるのである。
ポチッとクリックすると、何かが起きる(かも)。
↓↓↓

スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 (開拓社言語・文化選書)
天界航路―天野芳太郎とその時代 (1984年)



コスタリカの歴史 (世界の教科書シリーズ)




























