
カフカを読むなら「審判」は外せないでしょう。
と以前から思っていた私ですが、ことはそう簡単には済みません。
何しろ「審判」は、著者に放り出された作品でありますから、やはり慎重にならざるおえない。
カフカがどのような作家で、どのような作品を書いているのか、そこのところを少しでも汲み取れるぐらいになってから読むべきかと思います。
結末がしっかりと描かれていますが、完成形ではないのです。
カフカが完成をどのような形でイメージしていたのかは知る由もありません。
神のみぞ知るといったところですね。
そういったこともあり、「審判」について何が言えるかといえば、読者がカフカの世界を体験する、それに尽きるのではないかと思います。
「審判」は、銀行の支配人であるヨーゼフ・Kが、30歳の誕生日の朝逮捕されるのですが、
告訴の理由は全く分かりません。
それでも、訴訟は現にあるわけで、奇妙な審理も開かれる。
逮捕されているとはいえ、Kは拘束されているわけではなく、仕事に支障のないように、
日曜日に審理が行われるという気の使いよう。
下っ端の役人は、自分のする仕事は熟知していても、関係する他の仕事に関しては全く知らず、裁判所での弁護士の扱いは酷く、地位も低い。
予審判事をする判事だって、下位の判事で、上位に比べるべくもない。
訴訟に大事なのは、強力な人間関係を関係者と築けるかであり、
膨大な書類を提出したとしても、その書類は意味をなさない。
こういった、役所、役人のありようは、大げさではあるけれど、全然違っているということもないわけで、公務員やそれに準ずる職業についている方や、その関係者などは、苦笑を禁じえないのではないかと思います。
特に、変なところに気を使うあたりが。
カフカは、プラハ大学法学部を卒業して、司法研修を受けていますので、
カフカの体験が基になっていると考えてよさそうです。
不条理といわれるカフカですが、私はそれほど不条理であるとは思えません。
それは、現実世界を大げさにもじっているだけで、不条理は現実に、
私たちの側にこそあるのではないでしょうか。
では、少し細かいところを見ていきましょう。
私が、面白いなと思ったところは、最初の審理で、
右半分と左半分という聴衆の分け方をしているところです。
これは、脳を暗示しているのかしら?
そして、その後の裁判所事務局。
細い階段を上った屋根裏部屋が事務局で、そこでの息苦しさは、まるで臨死体験のようです。
画家ティトレリのベットに隠されているドアが、事務局につながっているのは、
「不思議の国のアリス」を彷彿とさせます。
そう、迷宮めいているのです。
訴訟がはかばかしくなく、日常の職務に支障をきたし始めるKは、
「大聖堂にて」で、時間のズレが決定的となります。
「掟の門」をはさんだやり取りのなんと奇妙なことか。
裁判所とは、いったい何なのか?
ところで、Kの罪とはいったいなんでしょう。
Kは罪あるものとして最期をむかえますが、その罪が何であるのかは、
さっぱり言及されません。
当時のユダヤの世界では、30歳を過ぎても結婚しないというのは、大変由々しき事態であったらしいですし、婚約しては破棄するという一連の出来事とその葛藤に、カフカは罪を感じていたのかもしれません。
原罪を持ち出す人もいるようですが、そういったことよりも、
罪自体を裁こうという目的があったのではないでしょうか。
「逮捕」と対象をなす「最期」ですが、「流刑地にて」と同じような感触を覚えます。
Kは将校でもあり、囚人でもある。
関係ない旅行者は、私たち読者なのかもしれません。
審判

と以前から思っていた私ですが、ことはそう簡単には済みません。
何しろ「審判」は、著者に放り出された作品でありますから、やはり慎重にならざるおえない。
カフカがどのような作家で、どのような作品を書いているのか、そこのところを少しでも汲み取れるぐらいになってから読むべきかと思います。
結末がしっかりと描かれていますが、完成形ではないのです。
カフカが完成をどのような形でイメージしていたのかは知る由もありません。
神のみぞ知るといったところですね。
そういったこともあり、「審判」について何が言えるかといえば、読者がカフカの世界を体験する、それに尽きるのではないかと思います。
「審判」は、銀行の支配人であるヨーゼフ・Kが、30歳の誕生日の朝逮捕されるのですが、
告訴の理由は全く分かりません。
それでも、訴訟は現にあるわけで、奇妙な審理も開かれる。
逮捕されているとはいえ、Kは拘束されているわけではなく、仕事に支障のないように、
日曜日に審理が行われるという気の使いよう。
下っ端の役人は、自分のする仕事は熟知していても、関係する他の仕事に関しては全く知らず、裁判所での弁護士の扱いは酷く、地位も低い。
予審判事をする判事だって、下位の判事で、上位に比べるべくもない。
訴訟に大事なのは、強力な人間関係を関係者と築けるかであり、
膨大な書類を提出したとしても、その書類は意味をなさない。
こういった、役所、役人のありようは、大げさではあるけれど、全然違っているということもないわけで、公務員やそれに準ずる職業についている方や、その関係者などは、苦笑を禁じえないのではないかと思います。
特に、変なところに気を使うあたりが。
カフカは、プラハ大学法学部を卒業して、司法研修を受けていますので、
カフカの体験が基になっていると考えてよさそうです。
不条理といわれるカフカですが、私はそれほど不条理であるとは思えません。
それは、現実世界を大げさにもじっているだけで、不条理は現実に、
私たちの側にこそあるのではないでしょうか。
では、少し細かいところを見ていきましょう。
私が、面白いなと思ったところは、最初の審理で、
右半分と左半分という聴衆の分け方をしているところです。
これは、脳を暗示しているのかしら?
そして、その後の裁判所事務局。
細い階段を上った屋根裏部屋が事務局で、そこでの息苦しさは、まるで臨死体験のようです。
画家ティトレリのベットに隠されているドアが、事務局につながっているのは、
「不思議の国のアリス」を彷彿とさせます。
そう、迷宮めいているのです。
訴訟がはかばかしくなく、日常の職務に支障をきたし始めるKは、
「大聖堂にて」で、時間のズレが決定的となります。
「掟の門」をはさんだやり取りのなんと奇妙なことか。
裁判所とは、いったい何なのか?
ところで、Kの罪とはいったいなんでしょう。
Kは罪あるものとして最期をむかえますが、その罪が何であるのかは、
さっぱり言及されません。
当時のユダヤの世界では、30歳を過ぎても結婚しないというのは、大変由々しき事態であったらしいですし、婚約しては破棄するという一連の出来事とその葛藤に、カフカは罪を感じていたのかもしれません。
原罪を持ち出す人もいるようですが、そういったことよりも、
罪自体を裁こうという目的があったのではないでしょうか。
「逮捕」と対象をなす「最期」ですが、「流刑地にて」と同じような感触を覚えます。
Kは将校でもあり、囚人でもある。
関係ない旅行者は、私たち読者なのかもしれません。
審判










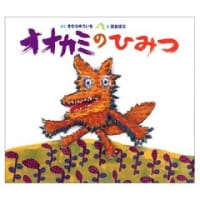
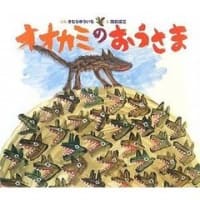
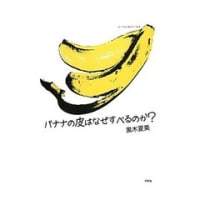
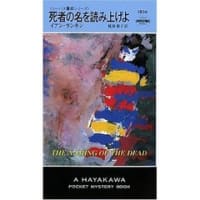
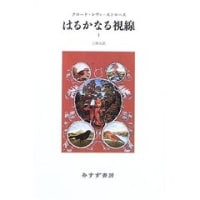
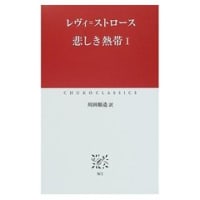
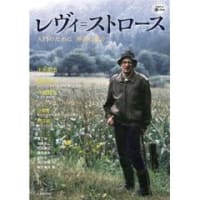
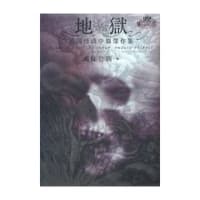
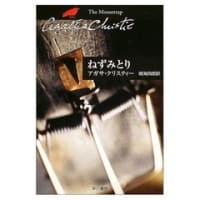
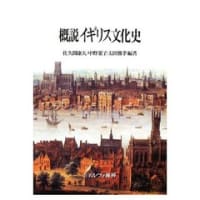
全体の筋立てはもちろん、どの章も見事にヘンです。終章はちょっと取ってつけたような感じがしますが。
わけのわからない作品が読みたい人向けの作品ですが、私の好みではなかったですね。
ヘンテコな作品が巷で流布している現在では、その感覚に慣れてしまっているということもあるかもしれませんが、カフカの不条理にはリアリズムを感じるところがあるように思います。
実存主義というのも、私が考えているものとは全く違うように感じます。
研究者ではなく、感覚でものを言っているので、その辺はご容赦ください。
カフカは、Kの30歳の誕生日である「逮捕」と31歳の誕生日である「最期」をほぼ同時期に書いたらしく、あとは、その間隙を埋めるだけだったはずが、そうはならなかったんですね。
「失踪者」が途中でにっちもさっちも行かなくなったことの反省のようですが、どちらにしても完成は見なかったわけです。
カフカの作品をそれほど多く読んではいませんが、どれも著者であるカフカ自身を感じます。
カフカの内的世界に付き合えるかどうかは、確かに好みが分かれるところですね。
ちなみに私は嫌いじゃないです。
積極的に好きというわけでもないですけど。
審理での聴衆の雰囲気や、事務室の息苦しさに嫌な汗をかいては、またつぎの迷路に迷い込んでゆく、どこまでもつづく悪夢を描いています。その悪夢的なことに比べたら、逮捕の理由がわからないことくらいはたいしたことではないように思えてしまいます。
中学生のころこの本を読んで、汗をかきつつも、自分のいる世界自体の不明瞭さと共感するところがあったせいか、面白く読んだことを思い出します。カフカには、ある意味、世界のある面におけるリアルをじんわりと指し示すようなリアリズムがあるのだろうと私も思います。
かなりの数を読んだのですが、リアリズムを感じるという記事は一つしかありませんでした。
manimaniさまにそういっていただいたことで、三人になりましたね。
力強い。
未完である「審判」ですが、カフカの世界は悪夢のようなものですから、尻切れトンボであっても、どこかが欠落していても、別にどうってことはない。
むしろ、カフカの魅力が味わえる作品だと思います。
文学におけるリアリズムとは何も日常生活を綿密に、日本の私小説のように書くものではないのだとカフカをあらためて読んで知りました。現実を現実のように書こうとする意志は意に反して現実離れをします。当たり前です。だって「現実のように」書かれたものは現実ではないのですから。ドキュメンタリーはノンフィクションと分類されますがこれも実はフィクションにより近いと感じます。
非現実的な表象を描いていながら、これは現実以外の何者でもないと感じられるところに文学におけるリアリズムが立ち上ってくるのではないかと思っています。カフカの作品はどれも意図的に書かれたフィクションでありながら、そこには人間の現実が描かれている、と50を過ぎた過去の文学青年が感じたのです。そう思って過去に読んだ本を思い起こすと、たとえば安部公房の作品や大江健三郎の初期の作品にはリアリズムを感じるのです。まだお読みでなかったなら安部公房の「砂の女」を読んでみてください。
私は今、源氏物語にはまってしまっていて頭が平安中期を漂っています。歳をとると一つの世界に入ってしまうとその前に集中して読んだ世界から次の世界へワープしたまま、なかなか元へ戻れません。
文学を愉しむよい指標を新しく見つけることができ、うれしく思っています。ときどき遊びに来ます。
リアリズムに触れているレビューに出会ったのはEUGENEさまだけでしたので、つい嬉しくて、
コメント入れてしまいました。
この白水社の帯に次のようなことが書いてありました。
「カフカの小説を読んではじめてわれわれは世界が不条理であることに気づく」
読む前は、カフカの小説の不条理性を指してそういっているんだと思っていましたが、
そうではなかったんですね。
カフカの不条理文学から、リアリズムを感じることは、私としては大きな発見でした。
年齢や経験があってこそなのだと思います。
安倍公房はチラッとしか読んだことがないんです。
「砂の女」チェックしておきますね。
大江健三郎も読みたい作家リストに入っています。
「遅れてきた青年」はなぜか上巻だけ読んでます。
ダイナミックな描写が鮮やかで、さすがノーベル賞作家は違うと感心した記憶があります。
私は、時々、無性に古典が読みたくなることがあります。
お気に入りは雨月です。
源氏物語、きらびやかでいいですよね。
いつでも、遊びにいらしてください