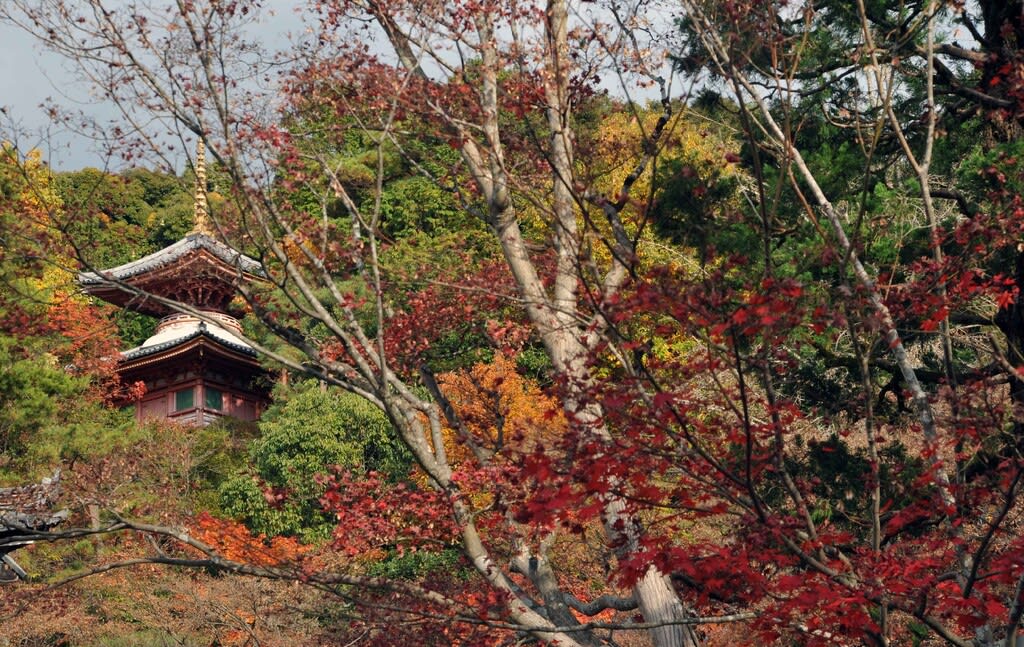12月も明日で20日になり、今年もあと10日あまり・・・
暑かった秋も、急に寒気の到来で冬に突入しました!
蔵出し画像の紅葉のトリは、嵯峨野の小倉山の麓にある「常寂光寺」です!
自転車で嵯峨野を巡り行くとその奥に常寂光寺にたどり着き、多くの観光客が山門で佇んで
盛んにスマホ撮影の横をすり抜けて奥にある自転車起き場に愛車?を駐車・・・
入口で多くの観光客と一緒に山門を入ると、長い石段がお出迎!

本殿横の小径を行くと、
多宝塔を仰ぎながらが紅葉が照る光景が好きでいろいろと
角度を変えながらの撮影!

さらに小径を登ると、
先程の多宝塔を眼下に
京都市内の町並みが眺望できます!

坂の石段を下ると、
仁王門と散紅葉が望める景観が・・・


本殿よこの池には、
散りもみじが浮かびます!

モミジ風景を見ながら
息を切れせながら石段を登ると、
本殿が紅葉に映えます!


山門は
観光客の長蛇の列、
頭超しにカメラを・・・
このお寺は、慶長年間(1596〜1614)に大本山本圀寺第16世究竟院日禛上人により開創され、
本堂は慶長年間に小早川秀秋公の助力を得て、伏見桃山城客殿を移築し造営するとあります。
仁王門は、元和二年(1616)に大本山本圀寺客殿の南門(貞和年間の建立)を移築、仁王像は運慶作と伝えられています!。
小倉山
平安時代より嵯峨野の地は、皇族や貴族の離宮、山荘をかまえる景勝地として有名でありました。
特に小倉山、亀岡、嵐山の山麓は、後嵯峨上皇の亀山殿、兼明親王の雄倉殿、藤原定家の小倉山荘などがあり
今で言うリゾート地、別荘地でしよう!