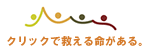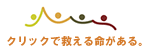(一昨年書き置いたもので
放流同意問題 その6 の続きです。なおこの話題はこれで終了いたします。)
都会に住むとインフラが整備されているので気にもかけないだろうが、上水・下水道は生活に密接に関わり、田舎暮らしを始めるとそれらはすべて居住(移住)者個人に直接の負担となってくる。
もちろんそのために補助金制度もあるのだが、今回のような合併浄化槽放流同意に関して、民事トラブルと言うべきものは何ら行政からの支援はない。
現に法務省からは”放流同意書添付を強要されたら行政指導するが、放流水路の維持整備のために農家からお金を請求されることは不適切とは言えない”との返事をもらった。
そもそも同意書添付を禁止したのは、暗にこのような同意金問題を含んでいるからやめるようになったのではないのか。単独浄化槽ならいざしらず、合併浄化槽になっても裏ではお金を積む古い因習とも言うべきことこそ、行政指導の対象ではないのか。
その昔、日照権でもめる建物があったが、建築基準法法改正によって建築主は一定の基準を守れば争議の嵐に見舞われることはなくなった。浄化槽もしかり、合併浄化槽が一定の基準をクリアーでき、かつ後々の法定検査義務も科せられるのであるからして、民事だからと知らぬ顔をしてほしくない。
以前も書いたが、農水省が進める”緑と”政策は、農村の老齢化に対して環境維持のために非農家も含めて推進されるよう提唱している。簡単にいえば、お互い助け合いましょうということではないか。
放流同意するから金を出せ。ついでに水路の泥上げを手伝え、草も刈れ。
これでは非農家はやってられない。
環境省のサイトで”合併浄化槽”と検索すると以下のような資料を見つけることができた。
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
浄化槽専門委員会第 21 回 平成18 年11 月27 日(午前10:00~12:00)
かいつまんで転記すると
〔浄化槽の今後の在り方について〕
1.効率的な汚水処理施設における浄化槽の位置づけについて
1)地方公共団体の厳しい財政的な面から、汚水処理施設整備の費用対効果
を考えた効率化が一層求められている。
2)全国的に見れば、人口5 万人未満の市町村の汚水処理人口普及率は62.
9%であり、今後の整備を必要とする地域は、中山間地域等の人口散在
地域でのウエイトが高いことから、費用対効果の面からも、合併処理浄
化槽が重要な柱となる。
2.汚水処理施設の整備における浄化槽の展開について
3)少子高齢化などの社会状況の変化により、現在は下水道整備計画区域内
であっても過疎化が進み、費用対効果の面からも、集合処理整備計画が
実情にそぐわないこと等が考えられることから、今後、社会状況の変化
を踏まえた効率的な整備手法について、住民を交えて策定する必要がある。
3.単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換について
1)全国で約620万基とも言われている単独処理浄化槽の環境への汚濁
負荷は、合併処理浄化槽の約8倍と大きいため、対応策が必要。
2)すでに単独処理浄化槽で、水洗化が行われている使用者にとっては、転換
メリットが少ないという考えから、転換に応じないケースがあると聞いている。
特に近隣に単独処理浄化槽を設置した使用者が複数いるケースほど転換
意欲が少なく、ひいては地域全体へ環境保全上からも悪影響を及ぼす。
3)また、市町村にとっても、単独処理浄化槽の存在のために、地域全体の
事業の達成が難しい状況になっている。
4)合併浄化槽への転換施策を押し進めるには、単独処理浄化槽撤去助成の
拡充等を行い転換への支援を行っていただきたい。
5)設置条件など個々の住民ごとに異なるため、撤去と浄化槽の設置だけで
なく、単独処理浄化槽を合併浄化槽に改造する開発の推進をするなど、
使用者が様々な方法を選べるようにすると、転換が大きく前進する。
4.水の再利用
浄化槽は、その場で放流することから、水不足の解消等健全な水環境に反
映され、循環型社会の一翼を担っている。
つまり合併式浄化槽を設置することは行政に協力していることになる。
それを土地や農業用水の権利を盾に、設置者を悪者扱いにされるのはどこかおかしいではないか。
 ←押してくれると励みになります
←押してくれると励みになります