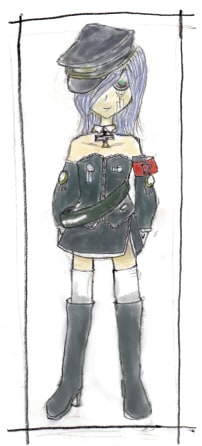神宮橋に背を持たしてアノン達がカラフルな頭を並べていた。ミドリは欄干の上に座って、アカは地面にあぐらをかいて、アノンは立ったまま背を持たせて棒のついたアメをくわえてる。他のスフィアや路上バンドみたいなのも数多くいるけど、ことさら多くの見物人達がアノンの前にたむろっていた。大げさなカメラを抱えた人や、携帯を持ったまだ十代の若い学生達がレンズを向けている。
「…いっぱいいますね」
アカは少し気後れする。
「ショーウィンドウに並べられてずっと笑ってたいよ。あ、雑誌の人だ。こんにちは」とアノンはまるで動じてない。
「アノンちゃん、自分の名前で歌手デビューする気ないの?」
見物人達をかき分けて入ってきたのは、いつもの雑誌『ベント』の女の人。
「ないよ?私はマキーナの端末でしかないから」
「だからよ。自分自身を表現したくならない?」
「はは、そういうのよく分からないよ」
アノンが周りを見渡すと、色とりどりに着飾った人達がまるで巡礼者みたいに見えた。ここはもうひとつの聖地になった。デウ・エクス・マキーナに魅せられた人達が足を向けて、そして祝ってくれてる。ああこの中に埋もれて人の波に押し流され透明になって私を支えてるこの心の現象を終わりにしたい。
「あっオトナだ」とミドリがつぶやく。
人ごみの間から覗くと遠くの方から横一列に並んだ制服姿の警備員たちがこちらに向かってくるのが見えた。それがハチの集団が波打つように伝わると、ざわざわと騒ぎが起こる。急いで置いてある荷物を手に取って、こうなるとめんどくさいからみんな散り散りになって逃げてしまう。
「さあ行こ」
そう言って私はアカの手を取る。
「じゃあ、またね!」
そう言って私達はさっきまで馴染んだ風景を後にする。
「今度、いつ!?」
誰かが後ろから大声で呼びかける。
「分かんない!でも、会えるといいね!」
「最近ちょっと多くないですか?」
走りながら息を切らせてアカが言う。
「確かにね。ちょっと変だよね…」
近頃は特に取締りが厳しくなって来てる。それも初めから知ってたみたいにみんなが集ったところですぐにやってくる。その疑いもまだ言葉で定義できるほどははっきりと意識には上ってきていなかった。大人達を巻くと、スフィアの仲間たちも数人私達と一緒に人通りのある通りまで歩いている。奇抜なファッションばかりが目につくこの場所でも私達はひときわ目立っていた。
「…どうします?」アカがアノンに聞く。
「ま、解散でいいんじゃない?」とミドリが言う
「アノンは?」
「うーん…」
アノンがアイディアでも探すように辺りを見渡すと、ふと人ごみに紛れて一瞬、砂漠の中から宝石を見つけた時みたいに小さく見えた人の顔が目に止まった。
「…イナギ?」
「え?イナギ?イナギがどうしたの?」
「ううん、なんでもない」
アノンは自分でも分かるくらいちぐはぐな笑いを浮かべた。
「イナギと初めて会ったのがここだったなって…」
アノン遠巻きからもう一度同じ場所に目をやったが、そこには既に誰も立ってはいなかった。そこの空間が人型に切り抜かれてなくなったようにも思えた。
確かに私はイナギを見たんだ。やっぱりイナギは生きてる。 息を潜めてどこかで私達を見てるんだ。イナギ、また私を殺しに来たの?そしたら次で三度目になるんだ。