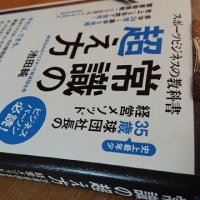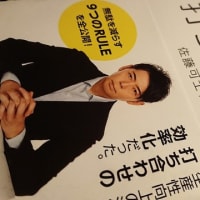サブタイトルに「戦略マネジメント・ガイドブック」とある。
原題でも類似の表現のようだが、これはガイドブックではなく、明らかにミンツバーグらのファイルターを通したある種の経営戦略論の本である。
その戦略論を展開するために経営戦略論や人的資源管理論、リーダーシップ論などを10の分類に集めているにすぎないともいえる。
ミンツバーグによる10のスクール(これは学派あるいは潮流と訳すべきか?)とは次の名称と代表する理論家などである。
1.デザイン 代表的なのは、セルズニック
2.プランニング アンゾフ
3.ポジショニング ポーター、BCGなど
4.アントンプレナー シュムペーター
5.コグニティブ サイモン
6.ラーニング センゲ、野中郁次郎もこの分類
7.パワー アリソンら
8.カルチャー レンマン、ノーマン
9.エンバイロンメント ハナンとフリーマン
10.コンフィギレーション チャンドラー、ミンツバーグら
ポーターとシュムペーター、センゲらを同じ戦略論の一分類とするのは無理があると思うが、これもミンツバーグの考える戦略論の全体だということならそれもわかる。
もし仮にこれが戦略論のガイドブックとしたら公平な編集の仕方ではないと思う。
古くはディドロの百科全書がそうであったように百科事典はある目的をもって編纂されるものであり、このガイドブックも実は同じなのだということがよくわかる。
戦略論を「群盲象を撫でる」の言葉に例えて、ミンツバーグはこの本でそれぞれの戦略論が撫でているに過ぎない象の全体像を描く目的だったらしい。
しかし、実際にはミンツバーグが10に分類したスクール(学派・潮流)の紹介と批判を通して、ミンツバーグがこれまで展開した理論との位置関係を確認しているに過ぎないと思う。
とくに厳しい批判はミンツバーグが「ポジショニング・スクール」という檻に押し込めているマイケル・ポーターの戦略論とBCGの事業ポートフォリオに向けられている。この系統は古くは孫子、クラウゼビッツなどの軍師家の潮流であるそうだ。
ポジショニング・スクールの特徴は、CEOが戦略家にとどまり、プランナー(多くはコンサルタント)がアナリストとなり、包括的戦略を提言するために膨大な計算と分析をする。アナリストは戦略をデザインしない。木になる実を取るように戦略を選ぶだけである。このあたりはミンツバーグが『MBAが世界を滅ぼす』のなかで今のビジネススクールを批判しているのと同じような視点である。
ミンツバーグがポジショニングスクールと呼んでいるポーターやBCGのフレームワークは「戦略そのものが焦点を狭くする傾向がある」と言い、「戦略はユニークなパースペクティブとしてではなく、包括的なポジションとして見られている」ことを批判する。
戦略形成において事象を静的に枠組みで捉えるところがいけないのだそうだ。
BCGのPPMマトリクスについて、ホンダがバイクで米国に進出したときの例ではBCGマトリクスでは「負け犬」になるが、実際には成功した。これはポジショニングスクールの勝利ではなく、ラーニング・スクール(学習重視学派?)に関係しているという。創発的戦略の例でミンツバーグが好んでこのホンダの小型バイクの例を使う。
たしかにBCGのこのマトリクスは縦軸に成長率、横軸にシェアをとるマトリクスであるが、大企業のポートフォリオなど当てはまる条件は限られていると思う。それに事業を続けるかどうかは企業の中核的な競争力の源泉であるのかどうかの検討も必要だが、その判断バランスを欠く傾向があるのかもしれない。
ポーターへの批判はいくつかある。考えさせられるのは3つの基本戦略で、ポーターは「コストリーダーシップと差別化はトレードオフの関係にある」と言い切っているが、ミラーが「超越したときに大きな見返りがある」としてキャタピラーやベネトンの例を出していることだ。ベネトンが低コストとファッション性を両立させたと言っていいのかどうかは疑問だが、ポーターの本を読んでいてもこの2つの背反性については疑問だった。ある条件が揃えばトレードオフにならないかもしれないという視点を与えてくれる。
もう一つの批判こそ、ミンツバーグの戦略論の本質を表しているといえる。
それは「ポーターによる『戦略の本質』がなぜ戦略でないのか」と題した節だ(p.123~)。ポーターは『戦略の本質』という1996年の論文で持続的な競争優位を達成するための6つのポイントをリストアップし、6つめに「業務効率化は当然の前提」と書いた。このことをミンツバーグは業務改善が戦略を大きく変えるきっかけにもなるとし、「ポーターは戦略を演繹的で計画的なものとしており、あたかも戦略的学習や創発的な戦略が存在しないかのように捉えている」と批判している。ミンツバーグは、自分の批判の趣旨を「戦略をポジションというよりパースペクティブと捉えているだけなのだ」と解説している。
戦略をパースペクティブ(観点・視点)と考えると、あらかじめ考える計画ばかりではなく後から修正したり、追加することも戦略だし、認知心理学的な視点や組織学習的な視点から眺めることも戦略といえる。
センゲの組織学習や野中郁次郎のナレッジマネジメントなどの重要さは分かるが、それは戦略論とは別の人的資源管理や組織行動などの視点から活かすべき理論だろう。
ミンツバーグ自身の戦略論としては、創発戦略は「ラーニング・スクール」に属し、包括的な組織変革のマネジメントは「コンフィギュレーション・スクール」に属することになっている。自らのスクールへの批判は、マギロニア(マギル大学学派狂)とラベル化され、現実にはありえない簡素化された風刺画のようだという意見があることを紹介している。
この本の帯には「ポーターを超えるための決定版テキスト」とある。
しかしこの本を読んで、ますますポーターの戦略論の卓越性がよくわかった。
そして、ポーターの理論を応用するには前提条件を吟味する必要性や組織変革論などとのセットで考える大切さをあらためて感じた。
原題でも類似の表現のようだが、これはガイドブックではなく、明らかにミンツバーグらのファイルターを通したある種の経営戦略論の本である。
その戦略論を展開するために経営戦略論や人的資源管理論、リーダーシップ論などを10の分類に集めているにすぎないともいえる。
ミンツバーグによる10のスクール(これは学派あるいは潮流と訳すべきか?)とは次の名称と代表する理論家などである。
1.デザイン 代表的なのは、セルズニック
2.プランニング アンゾフ
3.ポジショニング ポーター、BCGなど
4.アントンプレナー シュムペーター
5.コグニティブ サイモン
6.ラーニング センゲ、野中郁次郎もこの分類
7.パワー アリソンら
8.カルチャー レンマン、ノーマン
9.エンバイロンメント ハナンとフリーマン
10.コンフィギレーション チャンドラー、ミンツバーグら
ポーターとシュムペーター、センゲらを同じ戦略論の一分類とするのは無理があると思うが、これもミンツバーグの考える戦略論の全体だということならそれもわかる。
もし仮にこれが戦略論のガイドブックとしたら公平な編集の仕方ではないと思う。
古くはディドロの百科全書がそうであったように百科事典はある目的をもって編纂されるものであり、このガイドブックも実は同じなのだということがよくわかる。
戦略論を「群盲象を撫でる」の言葉に例えて、ミンツバーグはこの本でそれぞれの戦略論が撫でているに過ぎない象の全体像を描く目的だったらしい。
しかし、実際にはミンツバーグが10に分類したスクール(学派・潮流)の紹介と批判を通して、ミンツバーグがこれまで展開した理論との位置関係を確認しているに過ぎないと思う。
とくに厳しい批判はミンツバーグが「ポジショニング・スクール」という檻に押し込めているマイケル・ポーターの戦略論とBCGの事業ポートフォリオに向けられている。この系統は古くは孫子、クラウゼビッツなどの軍師家の潮流であるそうだ。
ポジショニング・スクールの特徴は、CEOが戦略家にとどまり、プランナー(多くはコンサルタント)がアナリストとなり、包括的戦略を提言するために膨大な計算と分析をする。アナリストは戦略をデザインしない。木になる実を取るように戦略を選ぶだけである。このあたりはミンツバーグが『MBAが世界を滅ぼす』のなかで今のビジネススクールを批判しているのと同じような視点である。
ミンツバーグがポジショニングスクールと呼んでいるポーターやBCGのフレームワークは「戦略そのものが焦点を狭くする傾向がある」と言い、「戦略はユニークなパースペクティブとしてではなく、包括的なポジションとして見られている」ことを批判する。
戦略形成において事象を静的に枠組みで捉えるところがいけないのだそうだ。
BCGのPPMマトリクスについて、ホンダがバイクで米国に進出したときの例ではBCGマトリクスでは「負け犬」になるが、実際には成功した。これはポジショニングスクールの勝利ではなく、ラーニング・スクール(学習重視学派?)に関係しているという。創発的戦略の例でミンツバーグが好んでこのホンダの小型バイクの例を使う。
たしかにBCGのこのマトリクスは縦軸に成長率、横軸にシェアをとるマトリクスであるが、大企業のポートフォリオなど当てはまる条件は限られていると思う。それに事業を続けるかどうかは企業の中核的な競争力の源泉であるのかどうかの検討も必要だが、その判断バランスを欠く傾向があるのかもしれない。
ポーターへの批判はいくつかある。考えさせられるのは3つの基本戦略で、ポーターは「コストリーダーシップと差別化はトレードオフの関係にある」と言い切っているが、ミラーが「超越したときに大きな見返りがある」としてキャタピラーやベネトンの例を出していることだ。ベネトンが低コストとファッション性を両立させたと言っていいのかどうかは疑問だが、ポーターの本を読んでいてもこの2つの背反性については疑問だった。ある条件が揃えばトレードオフにならないかもしれないという視点を与えてくれる。
もう一つの批判こそ、ミンツバーグの戦略論の本質を表しているといえる。
それは「ポーターによる『戦略の本質』がなぜ戦略でないのか」と題した節だ(p.123~)。ポーターは『戦略の本質』という1996年の論文で持続的な競争優位を達成するための6つのポイントをリストアップし、6つめに「業務効率化は当然の前提」と書いた。このことをミンツバーグは業務改善が戦略を大きく変えるきっかけにもなるとし、「ポーターは戦略を演繹的で計画的なものとしており、あたかも戦略的学習や創発的な戦略が存在しないかのように捉えている」と批判している。ミンツバーグは、自分の批判の趣旨を「戦略をポジションというよりパースペクティブと捉えているだけなのだ」と解説している。
戦略をパースペクティブ(観点・視点)と考えると、あらかじめ考える計画ばかりではなく後から修正したり、追加することも戦略だし、認知心理学的な視点や組織学習的な視点から眺めることも戦略といえる。
センゲの組織学習や野中郁次郎のナレッジマネジメントなどの重要さは分かるが、それは戦略論とは別の人的資源管理や組織行動などの視点から活かすべき理論だろう。
ミンツバーグ自身の戦略論としては、創発戦略は「ラーニング・スクール」に属し、包括的な組織変革のマネジメントは「コンフィギュレーション・スクール」に属することになっている。自らのスクールへの批判は、マギロニア(マギル大学学派狂)とラベル化され、現実にはありえない簡素化された風刺画のようだという意見があることを紹介している。
この本の帯には「ポーターを超えるための決定版テキスト」とある。
しかしこの本を読んで、ますますポーターの戦略論の卓越性がよくわかった。
そして、ポーターの理論を応用するには前提条件を吟味する必要性や組織変革論などとのセットで考える大切さをあらためて感じた。