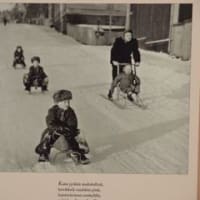この大会は社会言語学の大会としては最大のものになっているそうで、じつに600人以上の発表者が集まったそうです。今日が最終日で、夜遅くまで内容を修正するのに忙しかったのですが、雨の中、タクシーで朝9時に始まるワークショップに出かけました。
language planning, managementのワークショップで6組の発表がありましたが、いわゆる言語政策研究の人が4組で、言語管理については第1部の最初に理論を紹介したNekvapilさん、そして第2部の私とファンの発表だけでした。あとはSpolskyさんのグループというわけです。SpolskyさんはLanguage Managementというタイトルの本を書き上げて出版を前にしているそうで、その宣伝でもあったようです。しかしこのタイトルはじつはいただけないというか、すでに20年前からこちらで使っている理論の名前ですから、納得できないですね。
その他の発表では、ウェールズ語維持委員会の話であったり、リンガフランカと経済の関係であったり、オーストリア・ハンガリー二重帝国時代の言語政策のミクロとマクロであったり(ただし、このウィーン大の2人の発表は面白かった)で、ミクロなディスコースの言語問題という視点はまったくないのです。ウェールズ語やリンガフランカの話を聞いていると、なるほど言語政策研究とは役人の間の研究なのだなと思いました。ある政府のセクターはこう考えていて、他のセクターではべつな方向を向いているといった政府機関の事情通というのがこうした研究の秘訣になっているのです。
40人ほど集まった出席者からの質問は、Nekvapil教授と我々の言語管理の発表に関するものが多く、どちらが魅力的だったかはそれで判断してもよいのかなと思いました。(自画自賛?)
最後の特別講演はLabovで、まる1時間、例の変異理論の枠組による、発音のバリエーションと年代の関係についての具体的な研究発表でした。もう80歳になると言うのに、早口でしかもまだまだデータを収集しての研究をしているのには驚きました。背はその時代の人で低いのですが、太ってもいず、偉ぶるわけでもなく、ただ言語研究に従事する研究者といった風情でした。
すべてが終わり、Nekvapilさんと3人で外に出て、食事をすることにしました。ずっと雨模様だったのに、大会が終わると同時に空が澄み渡りました。Labovの講演について、Nekvapilさんはじつに正直に、In fact, it is very boring, and I am almost sleepingとか言ったので笑ってしまいました。私もすかさず、I was absent for 20 minutesと告白してしまいましたが。
最後にひとつ、付け加えておきたいのは、欧米の社会言語学の世界で言語管理を主張していくためにはMACRO→MICROの方向での議論や研究だけでなく、MICRO→MACRO、つまりミクロな言語問題の研究からマクロな言語政策への方向でも積極的に言及していかなければならないというNekvapilさんの言葉です。これは考えなければならない点だと思います。MICROにだけ言語管理理論を使うと、それは一種の文化適応(acculturation)の理論と区別がつかなくなるというわけです。
みなさんの感覚ではどうでしょうか?
language planning, managementのワークショップで6組の発表がありましたが、いわゆる言語政策研究の人が4組で、言語管理については第1部の最初に理論を紹介したNekvapilさん、そして第2部の私とファンの発表だけでした。あとはSpolskyさんのグループというわけです。SpolskyさんはLanguage Managementというタイトルの本を書き上げて出版を前にしているそうで、その宣伝でもあったようです。しかしこのタイトルはじつはいただけないというか、すでに20年前からこちらで使っている理論の名前ですから、納得できないですね。
その他の発表では、ウェールズ語維持委員会の話であったり、リンガフランカと経済の関係であったり、オーストリア・ハンガリー二重帝国時代の言語政策のミクロとマクロであったり(ただし、このウィーン大の2人の発表は面白かった)で、ミクロなディスコースの言語問題という視点はまったくないのです。ウェールズ語やリンガフランカの話を聞いていると、なるほど言語政策研究とは役人の間の研究なのだなと思いました。ある政府のセクターはこう考えていて、他のセクターではべつな方向を向いているといった政府機関の事情通というのがこうした研究の秘訣になっているのです。
40人ほど集まった出席者からの質問は、Nekvapil教授と我々の言語管理の発表に関するものが多く、どちらが魅力的だったかはそれで判断してもよいのかなと思いました。(自画自賛?)
最後の特別講演はLabovで、まる1時間、例の変異理論の枠組による、発音のバリエーションと年代の関係についての具体的な研究発表でした。もう80歳になると言うのに、早口でしかもまだまだデータを収集しての研究をしているのには驚きました。背はその時代の人で低いのですが、太ってもいず、偉ぶるわけでもなく、ただ言語研究に従事する研究者といった風情でした。
すべてが終わり、Nekvapilさんと3人で外に出て、食事をすることにしました。ずっと雨模様だったのに、大会が終わると同時に空が澄み渡りました。Labovの講演について、Nekvapilさんはじつに正直に、In fact, it is very boring, and I am almost sleepingとか言ったので笑ってしまいました。私もすかさず、I was absent for 20 minutesと告白してしまいましたが。
最後にひとつ、付け加えておきたいのは、欧米の社会言語学の世界で言語管理を主張していくためにはMACRO→MICROの方向での議論や研究だけでなく、MICRO→MACRO、つまりミクロな言語問題の研究からマクロな言語政策への方向でも積極的に言及していかなければならないというNekvapilさんの言葉です。これは考えなければならない点だと思います。MICROにだけ言語管理理論を使うと、それは一種の文化適応(acculturation)の理論と区別がつかなくなるというわけです。
みなさんの感覚ではどうでしょうか?