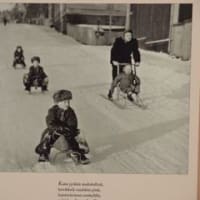前日の晩ご飯はホテルで紹介された近くの中華レストランに行きましたが、メニューをみるとどうも香港風です。支配人のおじさんと息子さん(?)がすぐに広東語にスイッチして別メニューを準備してくれました。30年前に香港の元朗から移民できた人で、息子さんはアムステルダム生まれだそうです。つれあいの話では、単語が少し足りないけど、ちゃんと広東語を話せるそうです。思わぬところで、移民第1世代と第2世代の多言語話者にであったわけです。
30日は一転、雨模様で一日中降ったり止んだりです。
そんなわけで、同じトラム2の沿線にあるゴッホ美術館と国立博物館を訪問しました。
ゴッホ美術館は、ゴッホの弟テオが使命としたビンセントの絵を広める仕事を引き継いだ、奥さんと息子によって永久期間アムステルダム市に貸し出されている絵をもとに建てられたもので、多くのすばらしい作品が展示されていました。ゴッホの説明を見ると、色の実験という面が強調されていて、そういうふうに見れば確かにじつに鮮やかな色の対照を作り出していることがわかります。売店でもゴッホの黄色や青を使ったカサやスカーフを売っています。しかし、ゴッホ以後の印象派から現在のCMまで広がる色の実験に目を汚されている人間から見ると、ゴッホにはむしろ構成の強さを感じてしまいます。
国立博物館は言わずとしれたレンブラントとフェルメールです。とにかく「夜警」が巨大。ここにあるレンブラントはどちらかというとオランダの国宝としてのレンブラントが多い気がします。卓越した絵の技術とか、アムステルダムを称揚するような絵が多いのです。むかしプラド美術館で見たレンブラントには、ゴヤの友人のような絵が結構あったんですけど。
なんかすごい絵ばかり見て視覚が飽和してしまったので、ちょっと息抜きにビンセント・ヴァン・ゴッホを娘と一緒になんて言い換えられるか考えていました。で、出てきたのが「えびせんとばんごっはん」。声に出して言ってみると笑えます。
発表の話は、トップダウン・アプローチをとる言語政策と、ボトムアップ・アプローチで当事者の問題から出発する言語管理とのかかわりを多言語使用者の事例から考察するというものになります。
マクロな言語政策では外国人居住者は、ある言語の母語話者として見なされるか、日本語の非母語話者として見なされるか、のどちらかしかなく、政策立案もまたある言語の母語話者に対する言語サービスか、日本語支援と生活支援しかないというところが議論の出発点です。
昨年から発表を始めている多言語使用者の事例には、そのどちらでもない外国人居住者がじつは少なくないというところに、マクロな政策との矛盾が見えてくるのだと思います。そして現在すすめられつつある「多文化共生」のスローガンもまた、こうしたトップダウンの政策的な前提から一歩も踏み出していない、ということも言えるのかもしれません。
30日は一転、雨模様で一日中降ったり止んだりです。
そんなわけで、同じトラム2の沿線にあるゴッホ美術館と国立博物館を訪問しました。
ゴッホ美術館は、ゴッホの弟テオが使命としたビンセントの絵を広める仕事を引き継いだ、奥さんと息子によって永久期間アムステルダム市に貸し出されている絵をもとに建てられたもので、多くのすばらしい作品が展示されていました。ゴッホの説明を見ると、色の実験という面が強調されていて、そういうふうに見れば確かにじつに鮮やかな色の対照を作り出していることがわかります。売店でもゴッホの黄色や青を使ったカサやスカーフを売っています。しかし、ゴッホ以後の印象派から現在のCMまで広がる色の実験に目を汚されている人間から見ると、ゴッホにはむしろ構成の強さを感じてしまいます。
国立博物館は言わずとしれたレンブラントとフェルメールです。とにかく「夜警」が巨大。ここにあるレンブラントはどちらかというとオランダの国宝としてのレンブラントが多い気がします。卓越した絵の技術とか、アムステルダムを称揚するような絵が多いのです。むかしプラド美術館で見たレンブラントには、ゴヤの友人のような絵が結構あったんですけど。
なんかすごい絵ばかり見て視覚が飽和してしまったので、ちょっと息抜きにビンセント・ヴァン・ゴッホを娘と一緒になんて言い換えられるか考えていました。で、出てきたのが「えびせんとばんごっはん」。声に出して言ってみると笑えます。
発表の話は、トップダウン・アプローチをとる言語政策と、ボトムアップ・アプローチで当事者の問題から出発する言語管理とのかかわりを多言語使用者の事例から考察するというものになります。
マクロな言語政策では外国人居住者は、ある言語の母語話者として見なされるか、日本語の非母語話者として見なされるか、のどちらかしかなく、政策立案もまたある言語の母語話者に対する言語サービスか、日本語支援と生活支援しかないというところが議論の出発点です。
昨年から発表を始めている多言語使用者の事例には、そのどちらでもない外国人居住者がじつは少なくないというところに、マクロな政策との矛盾が見えてくるのだと思います。そして現在すすめられつつある「多文化共生」のスローガンもまた、こうしたトップダウンの政策的な前提から一歩も踏み出していない、ということも言えるのかもしれません。