先日、立命館大学の環境教育の授業で
ナラ枯れの話をしました。
Kさんからの質問が面白かった。
「カシノナガキクイムシが、そもそもそこに土着している虫なら、
里山が放置され、そこでコナラなどがどんどん太ってくる過程で、
それに比例してカシナガも増えてくるのではないですか?」
ほんとにそうです。
”太い木を好む”というなら、なぜ太い木がだんだんと増えてくる過程で、カシナガも増えてこなかったか?
そうした経過をたどれば、大量発生、大量枯死が一気に起こることはなく、
”太い木”が増える中で、釣り合いのとれた関係が続いたはず。
しかし、そうではなかった。
”太い木を好む”と言うが、カシナガのアタックは
吉田山での観察では、明らかに樹種によって異なります。
ナラ枯れの本質的な問題は、
カシノナガキクイムシが大量に発生し、異常な規模でミズナラやコナラが大量枯死していることです。
なぜそれが起こっているのか?
枯死率は、明らかにミズナラとコナラ、アラカシやシイでは(京都の吉田山では)異なります。
ここにミスナラやコナラなどの大量枯死を考える重要なヒントがあると考えています。
ナラ枯れの話をしました。
Kさんからの質問が面白かった。
「カシノナガキクイムシが、そもそもそこに土着している虫なら、
里山が放置され、そこでコナラなどがどんどん太ってくる過程で、
それに比例してカシナガも増えてくるのではないですか?」
ほんとにそうです。
”太い木を好む”というなら、なぜ太い木がだんだんと増えてくる過程で、カシナガも増えてこなかったか?
そうした経過をたどれば、大量発生、大量枯死が一気に起こることはなく、
”太い木”が増える中で、釣り合いのとれた関係が続いたはず。
しかし、そうではなかった。
”太い木を好む”と言うが、カシナガのアタックは
吉田山での観察では、明らかに樹種によって異なります。
ナラ枯れの本質的な問題は、
カシノナガキクイムシが大量に発生し、異常な規模でミズナラやコナラが大量枯死していることです。
なぜそれが起こっているのか?
枯死率は、明らかにミズナラとコナラ、アラカシやシイでは(京都の吉田山では)異なります。
ここにミスナラやコナラなどの大量枯死を考える重要なヒントがあると考えています。















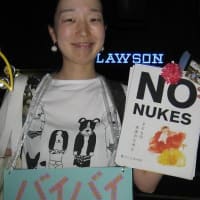



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます