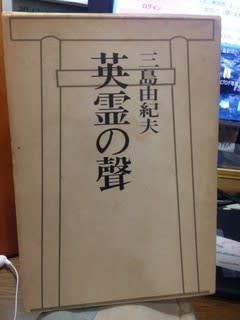平成29年7月12日、東京麻布賢崇寺で、15士祥月命日、22士の命日の法要が行われた。
以下、ご報告申し上げます。
高齢化が進み、御便りは次の一通のみであった。
相変わらず東京は、暑い日が続いていると思います。こちらは静かな雨が降っています。
明日、穏やかな一日であってほしいものです。
諸士のご冥福をお祈りします。(北海道の方から)
私は、池田少尉が、昭和62年に出版された「生きている二・二六」から次の文章を読ませていただいた。
池田さんは林さん、竹島さん、栗原さん、安田さん、渋川さん、坂井さんの遺書に言及された後、坂井中尉の遺書に触れられた。
(以下文中より)
「、、宏大無辺の御仏の御慈悲に浸り、唯忠を念じて名目致します。前途を祝福して下さい。 天皇陛下 万々歳」
何という純な心であろうか。秩父宮のことや恨みがましいことなど一言も言わずにあの世へ逝ったのだ。
香田さん、丹生さん、安藤さん、對馬さん、高橋さん、田中さん、中島さんもみな無量の思いを遺書に認めて亡くなった。村中さんと磯部さんの手記は、現在事件究明の一つの鍵ともなっている歴史的価値あるものだが、両人の性格が実によく表現されていると思う。
私は今日まで、何回もなくなった同志の人々の遺書を読んだ。そして凄まじい気迫の中に、何とも言えぬ真の人間性、人としての心の温かさを感じている。
あの人達は、人一倍君を思い、国を思い、人を愛し、兵を愛し、正義の迸(ほとばし)るところ、このような行動に身を投じて死んでゆかねばならなかった。
皆心優しき人々であった。西田税は同志の処刑後、次の歌を詠んでいる。
かの子等はあをぐもの涯(はて)にゆきにけり
涯なるくにを日ねもすおもふ
涯なる国はどこにあるのであろうか。私はひとり、君に対して不忠の臣、親に対して不幸の子として生き残った。」
香田代表理事からは、8月に公開予定といわれていた、裁判記録の公開が、さらに遅れる見込みであるとの報告があった。
弘前ご在住の、對馬中尉の妹様の波多江たまさま(102歳)より、リンゴジュースのお供え物があった。皆様にお分けした。
出席者は、炎天にも関わらず、40名近くの参列があった。北海道、湯河原、大阪、また、熱海からのご参加を頂き、衷心より感謝でいっぱいであった。
法要がすっかり終わり、本堂の前立った時、突然、私は、以前、賢萗寺の本堂の前で、杖をついた、背の大きな方にお目にかかったことを思い出した。その方は、いきなり私の顔見て「君は今泉君の息子か。」といわれた。父はその時はすでに亡くなっていた。その方は父と同期の常盤少尉であった。
暫く話をした後に、「泉下の皆は涙を流して喜んでいるよ。みんなは、本当に心の優しい人だった。」といわれたことを思い出した。常盤さんは、無期禁固。しかし常盤さんももうずいぶん前に鬼籍に入られた。
 (2010年、坂木原レム氏画のコピー、同氏より頂いたもの)
(2010年、坂木原レム氏画のコピー、同氏より頂いたもの)
以下、ご報告申し上げます。
高齢化が進み、御便りは次の一通のみであった。
相変わらず東京は、暑い日が続いていると思います。こちらは静かな雨が降っています。
明日、穏やかな一日であってほしいものです。
諸士のご冥福をお祈りします。(北海道の方から)
私は、池田少尉が、昭和62年に出版された「生きている二・二六」から次の文章を読ませていただいた。
池田さんは林さん、竹島さん、栗原さん、安田さん、渋川さん、坂井さんの遺書に言及された後、坂井中尉の遺書に触れられた。
(以下文中より)
「、、宏大無辺の御仏の御慈悲に浸り、唯忠を念じて名目致します。前途を祝福して下さい。 天皇陛下 万々歳」
何という純な心であろうか。秩父宮のことや恨みがましいことなど一言も言わずにあの世へ逝ったのだ。
香田さん、丹生さん、安藤さん、對馬さん、高橋さん、田中さん、中島さんもみな無量の思いを遺書に認めて亡くなった。村中さんと磯部さんの手記は、現在事件究明の一つの鍵ともなっている歴史的価値あるものだが、両人の性格が実によく表現されていると思う。
私は今日まで、何回もなくなった同志の人々の遺書を読んだ。そして凄まじい気迫の中に、何とも言えぬ真の人間性、人としての心の温かさを感じている。
あの人達は、人一倍君を思い、国を思い、人を愛し、兵を愛し、正義の迸(ほとばし)るところ、このような行動に身を投じて死んでゆかねばならなかった。
皆心優しき人々であった。西田税は同志の処刑後、次の歌を詠んでいる。
かの子等はあをぐもの涯(はて)にゆきにけり
涯なるくにを日ねもすおもふ
涯なる国はどこにあるのであろうか。私はひとり、君に対して不忠の臣、親に対して不幸の子として生き残った。」
香田代表理事からは、8月に公開予定といわれていた、裁判記録の公開が、さらに遅れる見込みであるとの報告があった。
弘前ご在住の、對馬中尉の妹様の波多江たまさま(102歳)より、リンゴジュースのお供え物があった。皆様にお分けした。
出席者は、炎天にも関わらず、40名近くの参列があった。北海道、湯河原、大阪、また、熱海からのご参加を頂き、衷心より感謝でいっぱいであった。
法要がすっかり終わり、本堂の前立った時、突然、私は、以前、賢萗寺の本堂の前で、杖をついた、背の大きな方にお目にかかったことを思い出した。その方は、いきなり私の顔見て「君は今泉君の息子か。」といわれた。父はその時はすでに亡くなっていた。その方は父と同期の常盤少尉であった。
暫く話をした後に、「泉下の皆は涙を流して喜んでいるよ。みんなは、本当に心の優しい人だった。」といわれたことを思い出した。常盤さんは、無期禁固。しかし常盤さんももうずいぶん前に鬼籍に入られた。
 (2010年、坂木原レム氏画のコピー、同氏より頂いたもの)
(2010年、坂木原レム氏画のコピー、同氏より頂いたもの)











 近衛歩兵三聯隊(今の赤坂TBSの場所)
近衛歩兵三聯隊(今の赤坂TBSの場所)