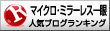村上春樹 文春文庫2016
文芸春秋に最初の「ドライブ・マイ・カー」が発表されたのが2013年。作中の地名について、地元議員の講義を受けたという事件や、僕は知らなかったが、「イエスタディ」の訳詞についてもひと悶着遭ったという記述が、さいしょの「まえがき」に書かれている。
氏にはめずらしく「まえがき」が書かれているのは、上記のことがあるからかもしれない。
いずれにしても、数年前におきたこの事件はちょっと心に引っかかるものがあり、単行本が発売されたときもなんとなく手に取る気になれなかった。
そんな話はこの辺にして・・。
なんとなく、過去の同氏の作品をほうふつとさせるような人物やエピソードがそこかしこに出てくる。みさきはちょっと青豆風、高槻は雰囲気五反田君を連想する。イエスタディは「ノルウェイの森」とは全然違うが、どこかでつながっているような気もする。「カミタ」は、ねじまき鳥の顔のない男のことを思い出させた。一角獣も出てくる。「シェエラザード」の寝物語は、いかにも村上氏の作品、という感じだ。
たぶん意識はされているのだろうけど、主人公はいずれも「男たち」なのは共通として、世代は学生(のちに30台になってからのシーンも出てくるが)から、50代後半まで、様々だ。「カローラ」じゃないので、若くて新しい読者もついてきているとはもうが、初期の頃からの熱心な読者をはじめ、全体に年齢層は上がってきているというか、幅広くなっては来ているのでしょうね。
個人的には家福の、一歩下がって冷静に人生を見つめているような姿に惹かれるものを感じる。「木野」の冷めた生き方は、自分にはまねのできない道だが、最後に彼が自分を振り返る様子には納得ができる。こうしたことは、自分が若い頃には読み取れなかった感覚かもしれない。もっとも、若ければ若いなりに「感じ取って」しまえるものなのかもしれないけど。若者の感受性というのは、侮れないものだから。
女性はこの本を、どのように捉えるものなのか、僕には想像がつかない。村上氏はここでは、女性の描写をそれほど追及しているようには思えない。文章量に制約があり、主人公である男性に筆を割く必要があったということもあるとは思うが。代わりに、その女を失った本人や、その本人から話を聞いた相手が、失われていった女や、その女の取った態度を語る。
とりわけ、「ドライブ・マイ・カー」のみさきが語る言葉がいちばん印象的だ。家福も、彼女の言葉を受け止めることができたようだ。
「女の人にはそういうところがあるんです。そういうのって、病のようなものなんです。・・頭で考えても仕方ありません。こちらでやりくりして、呑み込んで、ただやっていくしかないんです」
「そして僕らはみな演技をする」と家福は言った。
「そういうことだと思います。多かれ少なかれ」
この作品が、今回の短編集の中では一番まとまっていると思う。