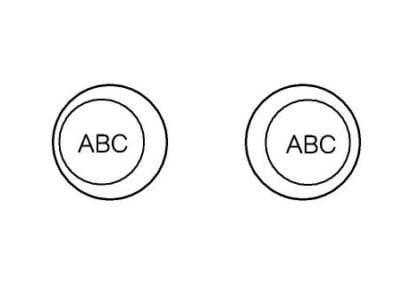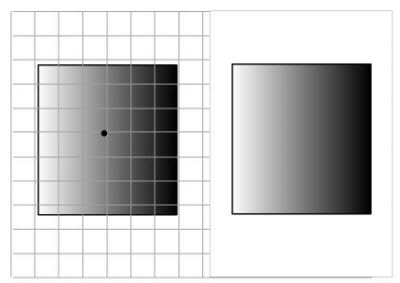「利き目」というものががあるというふうに思ってしまうのはなぜでしょうか。
a図のように目標に向かって両手で指の輪をつくって、そこから目標を見ると、目標は二つに見えます。
焦点距離を指に合わせてみると、遠くにある目標物は二重に見える、つまり目標物は二つに見えてしまいます。
このとき左の目を閉じれば右側の輪の中にだけ目標物が見え、左側の輪の中には見えません。
そうすると右の眼が「利き目」のように感じられますが、今度は右目を閉じて左の目で見れば目標物は左側の輪の中に見え、右の輪の中には見えなくなります。
要するにどちらも同じように見えるということで、とくに「利き目」というものはないということが分かります。
ここで片方の指の輪を残し、もう片方の手を下ろすとどうなるでしょうか。
b図の例では左側の指を残していますが、この状態で両目で見ると、指の輪の中に目標物が見えます。
ここで左目を閉じれば目標物は見えなくなり、右目を閉じて左眼で見れば見えます。
やはり、左目が「利き目」かと思うでしょうが、もう一度両目で見てみます。
目標物は左指の輪の中に見えるのですが、輪の外側にも見えることに気がつきます。
要するに目標物は二つに見えるのですが、指の輪の中に注意を向けると、二重に見えているもう一つの像に気がつかないでいたのです。
指の輪でなく目標物のほうを両眼で見ると、目標物はひとつに見えます。
このとき、指の輪は左によっていて、親指と人差し指が合わさっているところが顔の正面にあることに気がつきます。
つまり、指の輪の中から見ようとするときは無意識のうちに見ようとする眼の側に輪を寄せていたということになります。
たまたま右の指で輪を作り、目標物が右目で見えたから「利き目」が右目であると思い込んで、左目ばかりを強化するなどということをすればかえっておかしくなります。
もし目標物が左目を閉じたときに見え、替わりに右目を閉じたときも見えるならそれは指を気がつかないうちに動かしてしまっているのです。
「利き目」ということを信じ込んでむやみに片側を強化するというようなことは考え物です。
もし左右の眼がアンバランスであるということであるならば、医師の診断を受けるのが安全だということになります。
a図のように目標に向かって両手で指の輪をつくって、そこから目標を見ると、目標は二つに見えます。
焦点距離を指に合わせてみると、遠くにある目標物は二重に見える、つまり目標物は二つに見えてしまいます。
このとき左の目を閉じれば右側の輪の中にだけ目標物が見え、左側の輪の中には見えません。
そうすると右の眼が「利き目」のように感じられますが、今度は右目を閉じて左の目で見れば目標物は左側の輪の中に見え、右の輪の中には見えなくなります。
要するにどちらも同じように見えるということで、とくに「利き目」というものはないということが分かります。
ここで片方の指の輪を残し、もう片方の手を下ろすとどうなるでしょうか。
b図の例では左側の指を残していますが、この状態で両目で見ると、指の輪の中に目標物が見えます。
ここで左目を閉じれば目標物は見えなくなり、右目を閉じて左眼で見れば見えます。
やはり、左目が「利き目」かと思うでしょうが、もう一度両目で見てみます。
目標物は左指の輪の中に見えるのですが、輪の外側にも見えることに気がつきます。
要するに目標物は二つに見えるのですが、指の輪の中に注意を向けると、二重に見えているもう一つの像に気がつかないでいたのです。
指の輪でなく目標物のほうを両眼で見ると、目標物はひとつに見えます。
このとき、指の輪は左によっていて、親指と人差し指が合わさっているところが顔の正面にあることに気がつきます。
つまり、指の輪の中から見ようとするときは無意識のうちに見ようとする眼の側に輪を寄せていたということになります。
たまたま右の指で輪を作り、目標物が右目で見えたから「利き目」が右目であると思い込んで、左目ばかりを強化するなどということをすればかえっておかしくなります。
もし目標物が左目を閉じたときに見え、替わりに右目を閉じたときも見えるならそれは指を気がつかないうちに動かしてしまっているのです。
「利き目」ということを信じ込んでむやみに片側を強化するというようなことは考え物です。
もし左右の眼がアンバランスであるということであるならば、医師の診断を受けるのが安全だということになります。