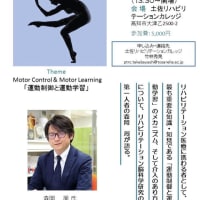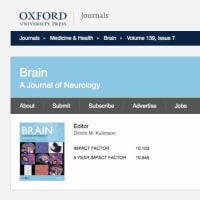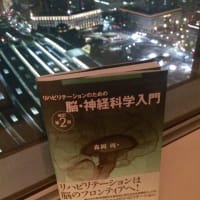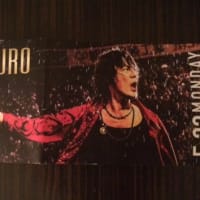昨日は大学で会議の後、
近鉄、新幹線、山手線、つくばエクスプレスを乗り継ぎ、5時間半かかり、つくばへ
科学都市、つくばへの上陸ははじめてである。
しかし、遠かった。
栃木、群馬、長野へ行くときも、それを感じたが、
それよりも遠く感じたのはなぜだろう。
乗り継ぎの問題か、時間帯の問題か、はたまた乗り心地の問題か、
いやいや、私の体調の問題か、いずれにしても、そういう意識が発生した。
ホテルに遅く着くなり、
高知の時の後輩、教え子ら5名と懇親に。
そのメンバーは、高田、吉田、山岡、田中、今泉である。
茨城メンバーが揃い、いろんな話をした。
決して、否定的、懐疑的、そして建設的な話ではなかった。
だから、楽しい時間が過ぎ去った。
会話というものはそういうものである。
今年から、全国学術研修大会は、座席の半分を予約制にしたらしい。
うれしいことに、私の明日の講演の座席のチケットが一番早く売り切れたらしい。
座席の量にも影響しているが・・・
こういうところからも「脳ブーム」を感じるし、
他の講演を見てみると、知覚、神経科学、認知運動療法、運動学習、脳イメージングなどのキーワードがてんこ盛りである。
時代が少し変わりつつあるのかな。
ただ、危惧すべきことはそれが表面だけに終わらないことだ。
熟れたリンゴにはならず。
青いリンゴをペンキで塗ったに過ぎない。
薄い思考の集団にしてはならない。
これは自省を含めてであるが、なかなかそれも厳しい。
しかし、完売はうれしいことだ。
大学の講義ではそんなことはないだろう。
大学の講義も選択性にしようか・・・と懐疑的になってもしょうがない。
まだ、インタラクションできていないのだと思う。
大学の講義、あるいはコース、講習会での講義・演習は原則視聴覚を使わない。
それは、一人称的な訴えとしての講義であり、自分を見て、そして内容を聞いて、そして、アクションをみて、模倣してもらいたいという意図がある。
一方、学会講演では、限られた時間内で、情報を与えないといけなく、
スライドでの三人称的報告になる。
その情報を聴衆者は求めている場合があるから。
後者のほうはできばえの標準偏差は減る。
安定はしているが、面白くもない。
面白いのは講義前にスライドを操作しているときのシミュレーション活動であり、
本番では、それが流れるだけである。
前者はライブであり、スライドがない分、頼れるのは私の脳のなかの記憶、市myレーションだけである。
だから、バラつきもみられるが、突然、ことばが生み出され、文脈として成立する。
なんで、そのような流れになったのかは、これも意識の問題になるが、もう1回その講義をやれといわれてもできないし、1週間もたてば、間で何を話し方も覚えていない。
リスクを伴う講義だが、自分を発見できる、自己成長の場である。
学生には申し訳ないが、自己成長のための講義だし、それに自らが能動的接触をはかってくれれば、インタラクションが生まれるだろう。
今は、どんな大きな講演よりも、大学の講義が気になる。
教育者として成長したのか、それほど、現代若者が悩ませる存在、つまりギャップが生じているのか、わからないが、いずれにしても、○回生のおかげだ。
気づきは、ずれがないと発生できない。
情報化されるには、何かと何かの差異が必要である。
私の経験(記憶)と今の求心性フィードバック(感覚)に差異があるのだろう。
成長したいが、ときには無意識でもいたい。
こんな気持ちに患者さんもなる場合があるだろう。
さて、二日酔いだが、会場へ行くとするか。
近鉄、新幹線、山手線、つくばエクスプレスを乗り継ぎ、5時間半かかり、つくばへ
科学都市、つくばへの上陸ははじめてである。
しかし、遠かった。
栃木、群馬、長野へ行くときも、それを感じたが、
それよりも遠く感じたのはなぜだろう。
乗り継ぎの問題か、時間帯の問題か、はたまた乗り心地の問題か、
いやいや、私の体調の問題か、いずれにしても、そういう意識が発生した。
ホテルに遅く着くなり、
高知の時の後輩、教え子ら5名と懇親に。
そのメンバーは、高田、吉田、山岡、田中、今泉である。
茨城メンバーが揃い、いろんな話をした。
決して、否定的、懐疑的、そして建設的な話ではなかった。
だから、楽しい時間が過ぎ去った。
会話というものはそういうものである。
今年から、全国学術研修大会は、座席の半分を予約制にしたらしい。
うれしいことに、私の明日の講演の座席のチケットが一番早く売り切れたらしい。
座席の量にも影響しているが・・・
こういうところからも「脳ブーム」を感じるし、
他の講演を見てみると、知覚、神経科学、認知運動療法、運動学習、脳イメージングなどのキーワードがてんこ盛りである。
時代が少し変わりつつあるのかな。
ただ、危惧すべきことはそれが表面だけに終わらないことだ。
熟れたリンゴにはならず。
青いリンゴをペンキで塗ったに過ぎない。
薄い思考の集団にしてはならない。
これは自省を含めてであるが、なかなかそれも厳しい。
しかし、完売はうれしいことだ。
大学の講義ではそんなことはないだろう。
大学の講義も選択性にしようか・・・と懐疑的になってもしょうがない。
まだ、インタラクションできていないのだと思う。
大学の講義、あるいはコース、講習会での講義・演習は原則視聴覚を使わない。
それは、一人称的な訴えとしての講義であり、自分を見て、そして内容を聞いて、そして、アクションをみて、模倣してもらいたいという意図がある。
一方、学会講演では、限られた時間内で、情報を与えないといけなく、
スライドでの三人称的報告になる。
その情報を聴衆者は求めている場合があるから。
後者のほうはできばえの標準偏差は減る。
安定はしているが、面白くもない。
面白いのは講義前にスライドを操作しているときのシミュレーション活動であり、
本番では、それが流れるだけである。
前者はライブであり、スライドがない分、頼れるのは私の脳のなかの記憶、市myレーションだけである。
だから、バラつきもみられるが、突然、ことばが生み出され、文脈として成立する。
なんで、そのような流れになったのかは、これも意識の問題になるが、もう1回その講義をやれといわれてもできないし、1週間もたてば、間で何を話し方も覚えていない。
リスクを伴う講義だが、自分を発見できる、自己成長の場である。
学生には申し訳ないが、自己成長のための講義だし、それに自らが能動的接触をはかってくれれば、インタラクションが生まれるだろう。
今は、どんな大きな講演よりも、大学の講義が気になる。
教育者として成長したのか、それほど、現代若者が悩ませる存在、つまりギャップが生じているのか、わからないが、いずれにしても、○回生のおかげだ。
気づきは、ずれがないと発生できない。
情報化されるには、何かと何かの差異が必要である。
私の経験(記憶)と今の求心性フィードバック(感覚)に差異があるのだろう。
成長したいが、ときには無意識でもいたい。
こんな気持ちに患者さんもなる場合があるだろう。
さて、二日酔いだが、会場へ行くとするか。