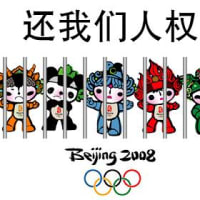王力雄:チベットの選択――チベットと中国の歴史的関係(12)
これは連鎖反応である。西洋の主権基準によるチベットに対する介入が中国のチベットにおける主権確立行動を刺激し、中国の行動がチベットの中国支配からの完全離脱の願いを刺激した。東洋的なあいまい関係の中では、チベットは「骨抜き」により実質的な独立を保持し、表面的な臣服と引き換えに実質的な利益を手に入れることができたが、いったん中国の明確な主権構造に組み込まれたら、それは本当の臣服であり、権力は奪われる。それはチベットの統治者にとっては最大の利益を失うことであり、いかなる別の利益とも交換不能である。
まして、日増しに没落する末期清国がチベットにどんな利益をもたらすことができるだろう? チベットの北京への臣服の理由――保護と仲裁の追求――は既に存在しない。一方で、外交面では、当時の中国は国際紛争で辱めを受け続けており、自分を守るのさえ難しいのに、どうやってチベットを守れよう。イギリスとの2回の戦争の敗北によって、チベットはこの点について身をもって知っていた。もう一方、チベットの内政の面では、ダライラマ十三世のチベットの政治宗教の最高権威の地位は当時すでにかなり安定しており、もう北京の仲裁と支持は必要としなくなっていた。
1900年、中国政府が許可したパスポートを所持するロシアの視察団がチベット東部チャムド地区ソツ村でチベット人に阻まれた。中国のパスポートはチベット人に道を開けるよう説得することはできなかった。視察団の団長コズロフの言葉によれば「射撃手はどんな中国パスポートよりも頼りになる」(注1)。チベット人との衝突で、ロシア人はチベット人21人を射殺し、19人を負傷させ、建物を焼き払い、馬を略奪し、少しの損害も出さずに大手を振って去って行った。事件発生後、ロシア人はいかなる処分も受けず、むしろ中国側に護衛されて出国した。清朝の役所に処分を依頼したチベット人に対しては、三年も引き延ばし、最後に新政府が死者一人当たり80両の銀貨、負傷者に16両の銀貨、あわせて2003両の銀貨の給付でことを済ませた。当時の駐チベット大臣裕鋼は事件処理後上奏文を一通書いた。その上奏文(注2)を見ただけでも、チベット人がなぜ中国を見限って別の後ろ盾を探したのかが十分理解できる。
西洋、とりわけ英露の勢力はアジアで迅速に拡張し、もともと中国だけの活動領域だったチベットは、中英露三か国の三角地帯になった。中国はすでにチベットにとって唯一の強者ではなく、むしろ中国は他の二つの大国にはるかに及ばないことが明らかになった。ダライラマ十三世は新しい後ろ盾の希望を当初ロシアに寄せた。彼はロシアを仏教を信仰する国だと思ったので、元朝のような構造――チベット人が精神的リーダーとなり、強大な世俗帝国が信者、施主兼軍事上の保護者となる――の再現を願った。彼は1904年にイギリス人から逃れるためにラサを脱出した。そのときあるいはロシア人と連絡を取り、ロシアを後ろ盾にイギリスに抵抗する願望があったのかもしれない。しかし、当時ロシアに非常に近いクーロン(今日のモンゴル共和国の首都ウランバートル)に至ったとき、ロシアは対外的には対日戦争に負け、ロシア国内では1905年の革命が発生し、国中が混乱していた。ダライラマ十三世の幻想も水泡に帰した。
このダライラマ十三世を苦しませたさすらいの旅では、住まいさえ問題だった。彼の宗教的地位はクーロンのモンゴル人大ラマを凌駕しており、後者は見劣りがする。そのため多くの信徒がダライラマに寄進し、モンゴル大ラマは損害を被った。クーロンの大ラマは当初の歓迎の態度を改めて、徐々に無礼になっていき、ダライラマの玉座を壊し、さらにダライラマの目の前でたばこを吸った(注3)。人情は移ろいやすく、宗教界もまた浄土ではなかった。ダライラマ十三世がチベットに帰ろうとしても様々な妨害にあい、実現できなかった。彼は中国の支配から抜け出すことができなかった。彼が北京の慈禧太后の誕生祝いに召し出された時、彼には清朝と合意に至る一筋の希望があったかもしれない。多くの歴史書が彼と中国の最終的な決裂は、慈禧太后が彼に面会の時にひざまずくよう要求したからだという。チベットは世俗権力では中国に臣服しているが、ダライラマは自分の宗教的地位は至高だと思っている。ましてかつてダライラマ五世が北京に行ったときは、ひざまずかなかったばかりか、清国皇帝は城門を出て出迎えた。しかし、時がたって状況は変わっていた。かつての清朝はモンゴルを抑え込むためにチベットを籠絡する必要があったが、いま清朝はチベットに対する主権を表現しなければならなかった。チベットの政教一致のもとではダライラマは宗教リーダーであるだけでなく、チベット世俗権力の最高代表であり、ゆえに彼はひざまずかなければならない。この争いを解決するために、ダライラマ十三世の謁見の時間は半月後に延ばされ、最終的にダライラマが慈禧太后と光緒皇帝に片膝でひざまずくことで妥協した。これまで神と自任していたダライラマにとって、その屈辱は想像に難くない。この種の屈辱は前途なき民族の非力さゆえであり、苦しみはいっそう深く、当然彼に強烈な反逆心を呼び起こす。
慈禧太后と光緒皇帝はダライラマ十三世に謁見した後、わずか1カ月のうちに相次いで死亡した。すでに破綻百出だった末期清王朝はさらに不安定化し、明日をも知れない状態になった。この時期にダライラマは北京に滞在し、間近に清王朝の腐敗と没落を目撃した。彼は必ずや中国の支配から脱する決意を一層強めたであろう。彼の今回の亡命は5年間に及び、視野を大きく広げ、意志を鍛練し、関係を築き、彼を雪山の奥深くの神王から民族リーダー兼政治家に変えた。
趙爾豊、聯豫らがカムとチベットで行った新政もまた、ダライラマ十三世を強く刺激した。新政はチベットの自由と伝統、ダライラマ自身の支配的地位を脅かし、根本からチベット社会が壊滅するに等しかった。慈禧と光緒が死んでから、ダライラマ十三世はただちにチベットへの帰途に就き、しかも旅の途中からチベット人の闘争を指揮し始めた。
(脚注は原文を参照)
原文:http://observechina.net/info/artshow.asp?ID=49029
関係文章:
趙爾豊の直轄統治――チベットと中国の歴史的関係(11)
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/a599d7ca72593668ab8604632adce601
辛亥革命後のチベット独立――チベットと中国の歴史的関係(13)(1/2)
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d7e57edb3011e87f38553c5c32dcaaef
これは連鎖反応である。西洋の主権基準によるチベットに対する介入が中国のチベットにおける主権確立行動を刺激し、中国の行動がチベットの中国支配からの完全離脱の願いを刺激した。東洋的なあいまい関係の中では、チベットは「骨抜き」により実質的な独立を保持し、表面的な臣服と引き換えに実質的な利益を手に入れることができたが、いったん中国の明確な主権構造に組み込まれたら、それは本当の臣服であり、権力は奪われる。それはチベットの統治者にとっては最大の利益を失うことであり、いかなる別の利益とも交換不能である。
まして、日増しに没落する末期清国がチベットにどんな利益をもたらすことができるだろう? チベットの北京への臣服の理由――保護と仲裁の追求――は既に存在しない。一方で、外交面では、当時の中国は国際紛争で辱めを受け続けており、自分を守るのさえ難しいのに、どうやってチベットを守れよう。イギリスとの2回の戦争の敗北によって、チベットはこの点について身をもって知っていた。もう一方、チベットの内政の面では、ダライラマ十三世のチベットの政治宗教の最高権威の地位は当時すでにかなり安定しており、もう北京の仲裁と支持は必要としなくなっていた。
1900年、中国政府が許可したパスポートを所持するロシアの視察団がチベット東部チャムド地区ソツ村でチベット人に阻まれた。中国のパスポートはチベット人に道を開けるよう説得することはできなかった。視察団の団長コズロフの言葉によれば「射撃手はどんな中国パスポートよりも頼りになる」(注1)。チベット人との衝突で、ロシア人はチベット人21人を射殺し、19人を負傷させ、建物を焼き払い、馬を略奪し、少しの損害も出さずに大手を振って去って行った。事件発生後、ロシア人はいかなる処分も受けず、むしろ中国側に護衛されて出国した。清朝の役所に処分を依頼したチベット人に対しては、三年も引き延ばし、最後に新政府が死者一人当たり80両の銀貨、負傷者に16両の銀貨、あわせて2003両の銀貨の給付でことを済ませた。当時の駐チベット大臣裕鋼は事件処理後上奏文を一通書いた。その上奏文(注2)を見ただけでも、チベット人がなぜ中国を見限って別の後ろ盾を探したのかが十分理解できる。
西洋、とりわけ英露の勢力はアジアで迅速に拡張し、もともと中国だけの活動領域だったチベットは、中英露三か国の三角地帯になった。中国はすでにチベットにとって唯一の強者ではなく、むしろ中国は他の二つの大国にはるかに及ばないことが明らかになった。ダライラマ十三世は新しい後ろ盾の希望を当初ロシアに寄せた。彼はロシアを仏教を信仰する国だと思ったので、元朝のような構造――チベット人が精神的リーダーとなり、強大な世俗帝国が信者、施主兼軍事上の保護者となる――の再現を願った。彼は1904年にイギリス人から逃れるためにラサを脱出した。そのときあるいはロシア人と連絡を取り、ロシアを後ろ盾にイギリスに抵抗する願望があったのかもしれない。しかし、当時ロシアに非常に近いクーロン(今日のモンゴル共和国の首都ウランバートル)に至ったとき、ロシアは対外的には対日戦争に負け、ロシア国内では1905年の革命が発生し、国中が混乱していた。ダライラマ十三世の幻想も水泡に帰した。
このダライラマ十三世を苦しませたさすらいの旅では、住まいさえ問題だった。彼の宗教的地位はクーロンのモンゴル人大ラマを凌駕しており、後者は見劣りがする。そのため多くの信徒がダライラマに寄進し、モンゴル大ラマは損害を被った。クーロンの大ラマは当初の歓迎の態度を改めて、徐々に無礼になっていき、ダライラマの玉座を壊し、さらにダライラマの目の前でたばこを吸った(注3)。人情は移ろいやすく、宗教界もまた浄土ではなかった。ダライラマ十三世がチベットに帰ろうとしても様々な妨害にあい、実現できなかった。彼は中国の支配から抜け出すことができなかった。彼が北京の慈禧太后の誕生祝いに召し出された時、彼には清朝と合意に至る一筋の希望があったかもしれない。多くの歴史書が彼と中国の最終的な決裂は、慈禧太后が彼に面会の時にひざまずくよう要求したからだという。チベットは世俗権力では中国に臣服しているが、ダライラマは自分の宗教的地位は至高だと思っている。ましてかつてダライラマ五世が北京に行ったときは、ひざまずかなかったばかりか、清国皇帝は城門を出て出迎えた。しかし、時がたって状況は変わっていた。かつての清朝はモンゴルを抑え込むためにチベットを籠絡する必要があったが、いま清朝はチベットに対する主権を表現しなければならなかった。チベットの政教一致のもとではダライラマは宗教リーダーであるだけでなく、チベット世俗権力の最高代表であり、ゆえに彼はひざまずかなければならない。この争いを解決するために、ダライラマ十三世の謁見の時間は半月後に延ばされ、最終的にダライラマが慈禧太后と光緒皇帝に片膝でひざまずくことで妥協した。これまで神と自任していたダライラマにとって、その屈辱は想像に難くない。この種の屈辱は前途なき民族の非力さゆえであり、苦しみはいっそう深く、当然彼に強烈な反逆心を呼び起こす。
慈禧太后と光緒皇帝はダライラマ十三世に謁見した後、わずか1カ月のうちに相次いで死亡した。すでに破綻百出だった末期清王朝はさらに不安定化し、明日をも知れない状態になった。この時期にダライラマは北京に滞在し、間近に清王朝の腐敗と没落を目撃した。彼は必ずや中国の支配から脱する決意を一層強めたであろう。彼の今回の亡命は5年間に及び、視野を大きく広げ、意志を鍛練し、関係を築き、彼を雪山の奥深くの神王から民族リーダー兼政治家に変えた。
趙爾豊、聯豫らがカムとチベットで行った新政もまた、ダライラマ十三世を強く刺激した。新政はチベットの自由と伝統、ダライラマ自身の支配的地位を脅かし、根本からチベット社会が壊滅するに等しかった。慈禧と光緒が死んでから、ダライラマ十三世はただちにチベットへの帰途に就き、しかも旅の途中からチベット人の闘争を指揮し始めた。
(脚注は原文を参照)
原文:http://observechina.net/info/artshow.asp?ID=49029
関係文章:
趙爾豊の直轄統治――チベットと中国の歴史的関係(11)
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/a599d7ca72593668ab8604632adce601
辛亥革命後のチベット独立――チベットと中国の歴史的関係(13)(1/2)
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d7e57edb3011e87f38553c5c32dcaaef