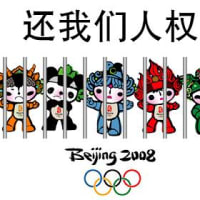王力雄:東洋的関係――チベットと中国の歴史的関係(8)
今日、ダライラマの海外亡命政府は西洋の人を国際公法顧問に招いて、国際法の視点からチベットが中国に隷属したことがないという法的根拠を探している。西洋の学者も次のような結論を出している。たとえ清朝が最も勢力の大きかった時代でも、中国のチベットに対する宗主権は「これまで形式化されたことはなく、いかなる条約もしくはその他の交渉によって双方の権利義務を確定させたこともない」(注1)。北京側も大勢の法律、歴史分野の専門家を飼って、「二十九条章程」のような証拠をたくさん探し出し、国際法の視点からその中の主権表現を分析し、中国のチベットに対する主権の歴史的合法性を証明している。
上述の文章の中の国際法・法的根拠・形式化・条約・権利義務・合法性といったキーワードを抜き出すと、双方が使っているのは東洋の歴史概念ではないことが分かる。中国であれチベットであれ、歴史上近代的主権概念によって相互の関係を決めてきたことはない。西洋の概念が世界的な国際秩序となり、東洋に受け入れられ、中国チベット関係の中で強烈に意識され、奪い合われるようになったのは、わずかに19世紀末からのことである。両者の間の似て非なる結論と、もつれて定かでない是非、その根源は西洋の概念を無理に東洋の歴史にあてはめようとするところにある。
もし、必ず主権・宗主権の概念を用いて清代の中国チベット関係を判断しなければならないのなら、私は中国の当時のチベットに対する支配は宗主権により近く、主権の性質は欠けていたと思う。チベットは中国の朝廷に対して臣服していたとはいえ、多くの時間と多くの問題についてはこの臣服は名義的なものにとどまり、あるいは見せかけのゲームにすぎなかった。表面上、駐チベット大臣は重要な位置に置かれた。前に引用したベンガルの校長が描写したように、駐チベット大臣は威風堂々と行進することができたし、チベット官吏を正式な席では副次的な地位に置くことができた。さらには駐チベット大臣はチベット人の族長を拘禁したり、路上のチベット民衆を鞭打ちにしたりすることもできた。しかし、チベットの実際の統治の中では、駐チベット大臣は実質的な役割は余り発揮できなかった。チベットの統治者はその独特なずる賢さと辛抱強さで駐チベット大臣を骨抜きにすることによって、実質的な独立を維持した。
しかし、私はそれを支配と反支配の闘争に中での勝敗の結果だとは思わない。むしろ、それは当時の中国とチベットがともに追求したものであり、双方が満足していたのであり、最も自然で合理的な結果だったのかもしれない。
確かに、駐チベット大臣は骨抜きにされたことに恨みごとを言っているし、清朝皇帝もしばしば不満を漏らしているが、それらはチベットで大きな問題が持ち上がったり、正常な運営軌道をはずれたりした時にはじめて重視され解決された。たとえば、1788年と1791年の2回、グルカがチベットを侵略した。きっかけは、パンチェン6世の弟のシャマルパがチベットから離反し、グルカにチベットのタシルンポ寺の財宝を奪うようそそのかしたことだった。当時チベット側は駐チベット大臣にシャマルパの離反を報告しなかった。グルカが最初に侵入した後、ダライは自分だけでグルカに賠償と土地の割譲を承諾し、駐チベット大臣に相談しなかった。のちには、賠償を払いきれなかったのでグルカの二回目の侵入を招いた。清朝はやむなく大軍をチベットに出兵させてやっと平定した。この人力物力の濫用に乾隆は怒り、チベット事務の粛正を厳命し、「二十九条章程」が制定された。その他の大部分の期間、清朝が駐チベット大臣を設置した目的は、チベット統治の象徴を維持することだけであり、実質的な統治を行うことではなかった。
この点を理解するには、中国古代の政治観と西洋の政治観の違いを知る必要がある。
「米国カリフォルニア大学デービス校のゲイリー・ハミルトン教授は、中国古代国家に関する論説は、啓蒙時代の思想家から現代の政治史・政治学・社会学の学者まで、例外なく西洋国家構造の概念によって、たとえば官僚制、世襲官僚制、専制政治、独裁政治およびその中で活動する各種の役割概念によって、中国国家の属性を描写してきた。このやり方は彼からみると、しばしば確認のしようもなく、かつ誤解を招く結果になった。ハミルトン氏のまとめによると、西洋の政治構造は二つの基本的特徴がある。すなわち、集中的な権力観と行政的な政治組織観である。そこでは、政治権力は意志に基づき、かつ抽象的な中心から四方に広がる。いわゆる「行政官僚制」こそ、その種の命令構造の中で生まれた組織類型である。上に述べた各種の概念、たとえば官僚制・官僚・統治者そして「国家」は、いずれもこの種の政治組織と国家の合法性の中心主義の観念に導かれてきた。しかし、中国の政治組織の中では、こうした観念は成り立たない。そこでは、権力は意志から生まれるわけではなく、服従も命令に基づくものではない。ハミルトン氏は、中国人の権力観は秩序を形成するために調和の中で活動する役割および礼によって画定された役割関係の上に築かれていると考える。このように築かれた政治組織は階層化された役割組織によって構成され、役割組織は基本的に自己維持的であり、命令構造との明らかな関連はない」。(注2)
後ろの数行の語気は私が強めた。古代中国とチベットの関係理解の助けになると思う。古代中国の世界観の中では、「天下」は中国を中心としていた。そのころ中国周辺にはほかに進んだ文明はなく、中国は一貫して強烈な文化的優越感を保持して、ほかの民族を「化外の邦」の「夷」「狄」「蛮」「番」とみなすことができた。古代中国は政治共同体によって国家を画定するのではなく、一族一姓の王朝にだけ注目した。そして王朝の合法性は中国文化の「正統な後継者」(原文「正朔=暦法の基礎」)であることであった。梁漱溟が言ったように「それは文化の統一に基づき政治の統一があり、天下をもって国家を兼ねていた」(注3)。
「中央の国」の君主として、中国の歴代皇帝が周辺民族に対する統治において最も重視したのは領土・資源・辺境などの「物」ではなく、「礼」だった。「夷」「狄」「蛮」「番」が中国文化に対して臣服と尊崇を示し、「中央帝国」の尊厳が満足されれば、ほかは全て些細なことに過ぎず、あまり気にかける必要はない。
それゆえ、古代中国は法律で自国の領土を画定したことがなく、文化あるいは政治的に臣服すれば、中国に属するとみなした。加えて、「無為にして治まる」の伝統的政治哲学(道家の思想)により、むしろ「化外の邦」が自分で自分を管理するよう望んだ。ゆえに、古代中国の辺境はいつも非常にあいまいだった。
「内を重んじ外を軽んじ、近くは詳しく遠くは大まかに、四方を並び挙げて以て政権の帰一を示し、すなわち天下は地理上政治上いずれもすでに無欠であるとみなされ、『四方』の細部については、昔の人の主な関心事ではなかった。もし、西洋人のように明確さを求める方法で検証したら、昔の人の『天下』は地図に再現するのは難しい。歴代の中国の辺境の拡大縮小は常に千里単位であり、西洋人の辺境の確定を国家の要素とする概念でこれを考量したら、中国は近代の多くの売国条約によって土地を割譲して国境を確定したあとに初めて『国』になるだろう。しかし、昔の中国の朝廷と民間にとって、本土(main body of homeland)さえ安定していれば、辺境の変動は『中国』概念の無欠性を妨げるものではなかった」。(注4)
西洋の観念の中の「大」は「小」によって構成され、「大」は明確な事実であり、正確に画定された細部によって説明し決定される。東洋の観念の中の「大」はむしろムードに近く、「小」に拘泥するとむしろ損なわれるので、しばしば「小」を捨てて「大」を求める。中国の皇帝には「空の下、王土にあらざるはなし」という意識があった(注5)が、しばしば土地を封じて恩賞とした。いったん怒ると、万里離れていても出兵して討伐し、意にかなうときは何でも認め、あるいは気を配りきれないときは、宋の太宗のように文鎮で地図に線を引いて、大渡河以西を捨て去り――「度外に置き、有っても論じな」かった。
国力の上からみると、古代中国は周辺民族を征服支配できなかったわけではなく、必要がなかった。それが脅威とならず、「礼」の秩序に合えば――臣服を示せば――それでよかった。古代中国の周辺にはいつも朝廷に認められたさまざまな藩王がおり、またしばしば諸侯に封じた。清代の中国皇帝の眼中では、チベットはまさにそのようなものだったと思う。これは一種の統治方式とみなすことができるが、完全に現代の主権あるいは宗主権概念によって解釈することはできない。
中国皇帝は「礼」によってきめられた尊厳――「これだけが大きい」。この「大」を満足すれば、その他の細部はあいまいでよかった。あるいはその細部を尊厳を満足させる交換物とした。一方、中国周辺の弱小民族にとって、より重要な「大」はまず生存の安全と実質的な利益だった。そのためには尊厳はあいまいでよかった。これもまた東洋的思考である。尊厳が重要でないというのではなく、それを価値の大きな資源とし、実質的利益と交換した。当時のチベットが中国に名義上臣服していたのは、かなりの程度この種の需要のためであった。清代中国はチベットを元以降のモンゴルカーンの統治から抜け出させ、ゲルグ派を支配的地位に就かせ、世俗権力との闘争においてダライを主とする宗教権力が勝利するのを助けた。北京はさらにチベットに手厚い恩賞と必要な仲裁、対外防衛の保証を与えた。チベットはこれほど多くの利益を受けながら、払った代価は表面的な中国に対する臣服の姿勢だけだった。この種の臣服は名義上にとどまり、見せかけのゲームで、中国皇帝に「君臨天下」の心理的満足を与えるものにすぎず、チベットはそれによって実質的な独立を失うことはなかった。むしろ、強硬な態度を堅持して中国皇帝を怒らせたら、チベットは大軍に攻められ、統治者は地位を失い、人民も苦しむ。この種の得失の対比を前にして、賢明な選択は何かは非常にはっきりしている。
前述した駐チベット大臣の行進の場面に「ランバの死」の故事を加えると、清代中国とチベットの関係の縮図になると私は思う。
原文:http://www.minzhuzhongguo.org/Article/wl/sj/200804/20080428085224.shtml
(脚注は原文参照)
関連文章:
骨抜き――チベットと中国の歴史的関係(7)
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/458be72eb12dfb3e581aa933e0f078e4
主権確立の相互作用――チベットと中国の歴史的関係(9)
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/a477aa095a4b290168e4d29dfe07a155
今日、ダライラマの海外亡命政府は西洋の人を国際公法顧問に招いて、国際法の視点からチベットが中国に隷属したことがないという法的根拠を探している。西洋の学者も次のような結論を出している。たとえ清朝が最も勢力の大きかった時代でも、中国のチベットに対する宗主権は「これまで形式化されたことはなく、いかなる条約もしくはその他の交渉によって双方の権利義務を確定させたこともない」(注1)。北京側も大勢の法律、歴史分野の専門家を飼って、「二十九条章程」のような証拠をたくさん探し出し、国際法の視点からその中の主権表現を分析し、中国のチベットに対する主権の歴史的合法性を証明している。
上述の文章の中の国際法・法的根拠・形式化・条約・権利義務・合法性といったキーワードを抜き出すと、双方が使っているのは東洋の歴史概念ではないことが分かる。中国であれチベットであれ、歴史上近代的主権概念によって相互の関係を決めてきたことはない。西洋の概念が世界的な国際秩序となり、東洋に受け入れられ、中国チベット関係の中で強烈に意識され、奪い合われるようになったのは、わずかに19世紀末からのことである。両者の間の似て非なる結論と、もつれて定かでない是非、その根源は西洋の概念を無理に東洋の歴史にあてはめようとするところにある。
もし、必ず主権・宗主権の概念を用いて清代の中国チベット関係を判断しなければならないのなら、私は中国の当時のチベットに対する支配は宗主権により近く、主権の性質は欠けていたと思う。チベットは中国の朝廷に対して臣服していたとはいえ、多くの時間と多くの問題についてはこの臣服は名義的なものにとどまり、あるいは見せかけのゲームにすぎなかった。表面上、駐チベット大臣は重要な位置に置かれた。前に引用したベンガルの校長が描写したように、駐チベット大臣は威風堂々と行進することができたし、チベット官吏を正式な席では副次的な地位に置くことができた。さらには駐チベット大臣はチベット人の族長を拘禁したり、路上のチベット民衆を鞭打ちにしたりすることもできた。しかし、チベットの実際の統治の中では、駐チベット大臣は実質的な役割は余り発揮できなかった。チベットの統治者はその独特なずる賢さと辛抱強さで駐チベット大臣を骨抜きにすることによって、実質的な独立を維持した。
しかし、私はそれを支配と反支配の闘争に中での勝敗の結果だとは思わない。むしろ、それは当時の中国とチベットがともに追求したものであり、双方が満足していたのであり、最も自然で合理的な結果だったのかもしれない。
確かに、駐チベット大臣は骨抜きにされたことに恨みごとを言っているし、清朝皇帝もしばしば不満を漏らしているが、それらはチベットで大きな問題が持ち上がったり、正常な運営軌道をはずれたりした時にはじめて重視され解決された。たとえば、1788年と1791年の2回、グルカがチベットを侵略した。きっかけは、パンチェン6世の弟のシャマルパがチベットから離反し、グルカにチベットのタシルンポ寺の財宝を奪うようそそのかしたことだった。当時チベット側は駐チベット大臣にシャマルパの離反を報告しなかった。グルカが最初に侵入した後、ダライは自分だけでグルカに賠償と土地の割譲を承諾し、駐チベット大臣に相談しなかった。のちには、賠償を払いきれなかったのでグルカの二回目の侵入を招いた。清朝はやむなく大軍をチベットに出兵させてやっと平定した。この人力物力の濫用に乾隆は怒り、チベット事務の粛正を厳命し、「二十九条章程」が制定された。その他の大部分の期間、清朝が駐チベット大臣を設置した目的は、チベット統治の象徴を維持することだけであり、実質的な統治を行うことではなかった。
この点を理解するには、中国古代の政治観と西洋の政治観の違いを知る必要がある。
「米国カリフォルニア大学デービス校のゲイリー・ハミルトン教授は、中国古代国家に関する論説は、啓蒙時代の思想家から現代の政治史・政治学・社会学の学者まで、例外なく西洋国家構造の概念によって、たとえば官僚制、世襲官僚制、専制政治、独裁政治およびその中で活動する各種の役割概念によって、中国国家の属性を描写してきた。このやり方は彼からみると、しばしば確認のしようもなく、かつ誤解を招く結果になった。ハミルトン氏のまとめによると、西洋の政治構造は二つの基本的特徴がある。すなわち、集中的な権力観と行政的な政治組織観である。そこでは、政治権力は意志に基づき、かつ抽象的な中心から四方に広がる。いわゆる「行政官僚制」こそ、その種の命令構造の中で生まれた組織類型である。上に述べた各種の概念、たとえば官僚制・官僚・統治者そして「国家」は、いずれもこの種の政治組織と国家の合法性の中心主義の観念に導かれてきた。しかし、中国の政治組織の中では、こうした観念は成り立たない。そこでは、権力は意志から生まれるわけではなく、服従も命令に基づくものではない。ハミルトン氏は、中国人の権力観は秩序を形成するために調和の中で活動する役割および礼によって画定された役割関係の上に築かれていると考える。このように築かれた政治組織は階層化された役割組織によって構成され、役割組織は基本的に自己維持的であり、命令構造との明らかな関連はない」。(注2)
後ろの数行の語気は私が強めた。古代中国とチベットの関係理解の助けになると思う。古代中国の世界観の中では、「天下」は中国を中心としていた。そのころ中国周辺にはほかに進んだ文明はなく、中国は一貫して強烈な文化的優越感を保持して、ほかの民族を「化外の邦」の「夷」「狄」「蛮」「番」とみなすことができた。古代中国は政治共同体によって国家を画定するのではなく、一族一姓の王朝にだけ注目した。そして王朝の合法性は中国文化の「正統な後継者」(原文「正朔=暦法の基礎」)であることであった。梁漱溟が言ったように「それは文化の統一に基づき政治の統一があり、天下をもって国家を兼ねていた」(注3)。
「中央の国」の君主として、中国の歴代皇帝が周辺民族に対する統治において最も重視したのは領土・資源・辺境などの「物」ではなく、「礼」だった。「夷」「狄」「蛮」「番」が中国文化に対して臣服と尊崇を示し、「中央帝国」の尊厳が満足されれば、ほかは全て些細なことに過ぎず、あまり気にかける必要はない。
それゆえ、古代中国は法律で自国の領土を画定したことがなく、文化あるいは政治的に臣服すれば、中国に属するとみなした。加えて、「無為にして治まる」の伝統的政治哲学(道家の思想)により、むしろ「化外の邦」が自分で自分を管理するよう望んだ。ゆえに、古代中国の辺境はいつも非常にあいまいだった。
「内を重んじ外を軽んじ、近くは詳しく遠くは大まかに、四方を並び挙げて以て政権の帰一を示し、すなわち天下は地理上政治上いずれもすでに無欠であるとみなされ、『四方』の細部については、昔の人の主な関心事ではなかった。もし、西洋人のように明確さを求める方法で検証したら、昔の人の『天下』は地図に再現するのは難しい。歴代の中国の辺境の拡大縮小は常に千里単位であり、西洋人の辺境の確定を国家の要素とする概念でこれを考量したら、中国は近代の多くの売国条約によって土地を割譲して国境を確定したあとに初めて『国』になるだろう。しかし、昔の中国の朝廷と民間にとって、本土(main body of homeland)さえ安定していれば、辺境の変動は『中国』概念の無欠性を妨げるものではなかった」。(注4)
西洋の観念の中の「大」は「小」によって構成され、「大」は明確な事実であり、正確に画定された細部によって説明し決定される。東洋の観念の中の「大」はむしろムードに近く、「小」に拘泥するとむしろ損なわれるので、しばしば「小」を捨てて「大」を求める。中国の皇帝には「空の下、王土にあらざるはなし」という意識があった(注5)が、しばしば土地を封じて恩賞とした。いったん怒ると、万里離れていても出兵して討伐し、意にかなうときは何でも認め、あるいは気を配りきれないときは、宋の太宗のように文鎮で地図に線を引いて、大渡河以西を捨て去り――「度外に置き、有っても論じな」かった。
国力の上からみると、古代中国は周辺民族を征服支配できなかったわけではなく、必要がなかった。それが脅威とならず、「礼」の秩序に合えば――臣服を示せば――それでよかった。古代中国の周辺にはいつも朝廷に認められたさまざまな藩王がおり、またしばしば諸侯に封じた。清代の中国皇帝の眼中では、チベットはまさにそのようなものだったと思う。これは一種の統治方式とみなすことができるが、完全に現代の主権あるいは宗主権概念によって解釈することはできない。
中国皇帝は「礼」によってきめられた尊厳――「これだけが大きい」。この「大」を満足すれば、その他の細部はあいまいでよかった。あるいはその細部を尊厳を満足させる交換物とした。一方、中国周辺の弱小民族にとって、より重要な「大」はまず生存の安全と実質的な利益だった。そのためには尊厳はあいまいでよかった。これもまた東洋的思考である。尊厳が重要でないというのではなく、それを価値の大きな資源とし、実質的利益と交換した。当時のチベットが中国に名義上臣服していたのは、かなりの程度この種の需要のためであった。清代中国はチベットを元以降のモンゴルカーンの統治から抜け出させ、ゲルグ派を支配的地位に就かせ、世俗権力との闘争においてダライを主とする宗教権力が勝利するのを助けた。北京はさらにチベットに手厚い恩賞と必要な仲裁、対外防衛の保証を与えた。チベットはこれほど多くの利益を受けながら、払った代価は表面的な中国に対する臣服の姿勢だけだった。この種の臣服は名義上にとどまり、見せかけのゲームで、中国皇帝に「君臨天下」の心理的満足を与えるものにすぎず、チベットはそれによって実質的な独立を失うことはなかった。むしろ、強硬な態度を堅持して中国皇帝を怒らせたら、チベットは大軍に攻められ、統治者は地位を失い、人民も苦しむ。この種の得失の対比を前にして、賢明な選択は何かは非常にはっきりしている。
前述した駐チベット大臣の行進の場面に「ランバの死」の故事を加えると、清代中国とチベットの関係の縮図になると私は思う。
原文:http://www.minzhuzhongguo.org/Article/wl/sj/200804/20080428085224.shtml
(脚注は原文参照)
関連文章:
骨抜き――チベットと中国の歴史的関係(7)
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/458be72eb12dfb3e581aa933e0f078e4
主権確立の相互作用――チベットと中国の歴史的関係(9)
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/a477aa095a4b290168e4d29dfe07a155