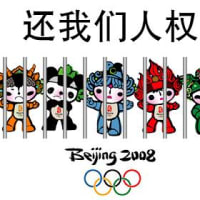王力雄:超越者連盟(4)
出典:http://boxun.com/hero/2006/wanglx/6_4.shtml
そうなればエリート連盟も民衆をコントロールしやすい。民衆に選挙権があり、自由に表現できるので、政治的な地位がないといって嘆きようがない。政権に対する不満も自分の選択が間違っていたことに帰するしかない。こうしてブルジョア階級は政権を操縦できるだけでなく、民主理念からあらさがしをされる心配もない。代議制政権の階級属性はこのようにして覆い隠される。
エリート連盟は人類の昔からの現象である。昔は限られた狭い領地に分割されていた。各領地のエリート連盟は独裁政権の主導下に一体となり、連盟同士がお互いに争い、頻繁に戦争が起きた。資本主義のグローバル化に伴い、障壁が打破され、ブルジョア階級を盟主とする世界エリート連盟が形成された。連盟の基礎はグローバル化する資本のルールであり、共同で貧富二元世界を維持することにある(?)。このような背景の下で、国際資本は中国が代議制に転換するのを必ずや支持する。なぜなら中国のエリート連盟が独裁政権に主導される限り、世界と闘争し続け、資本主導となってはじめて、中国のエリート連盟はグローバルエリート連盟の信頼しえる一員となるからだ。これは国際要素が中国の政治変革に影響を与えるおもな方向である。
民衆はブルジョア階級革命に利用できる同盟者に過ぎず、決着がつけばまた被統治の地位に戻る。人口と資源の制限が資本主義が中国において恩恵をもたらす対象を制限するので(?)、貧富の格差は避けがたい(?前後の結びつきは必然か?)。したがって、たとえ古いエリート連盟が新しいエリート連盟に地位を譲ったとしても、民衆に対しては形は変わっても依然として本質は変わらない。
政権と民衆の連合――ファシズムに向かう
一般的に、政権は自分から自ら主導するエリート連盟を打破することはない。なぜなら政権の分け前が一番大きいからだ。しかし、社会危機に直面したとき、政権は民衆に取り入るためにエリート連盟の粛清を図ることがある。たとえば、反腐敗、資本攻撃などである。しかし、これは往々にしてご都合主義的態度に過ぎず、一部を犠牲にしたとしても、基本方向とエリート連盟の基礎を変えるものではない。だがいったんエリート連盟のその他の要素が離反を企てたときは、政権も民衆と提携することでそれに対応するかもしれない。
たとえばブルジョア階級が革命を企てたとき、政権は民衆の貧富の格差に対する不満を利用して、ポピュリズムを扇動し、矛先をブルジョア階級に向けることができる。これは効果的な手である。中国社会は昔から貧富を均す意識があり、現実にも豊かな者を恨む感情がある。もしも民主・法治・人権の面で民衆がブルジョア階級と同じ側に立つとしても、政権が貧富の格差是正の旗を掲げれば、民衆はすぐにブルジョア階級を捨てて、政権の側に移る。貧富を均すことは永遠に資本のカードにはなりえず、ブルジョア階級が中国問題の根源を「官民矛盾」と言おうとしても、政権は「労使矛盾」こそが根本であり、「ブルジョア階級の復活」が民衆の地位を低下させたと民衆に軽々と信じさせるであろう。労働者が自らの状況を改善することは、正しい路線の政権に戻ることによってのみ(誤った路線の汚名は権力闘争の失敗者に担わせる)、労働者を搾取する資本家を妥当することによってのみ実現できる。
一般に、このようにすることはすでに私有化・市場化された中国経済に壊滅的打撃を与えるので、政権はそんな自殺行為はなしえないと考えられている。しかし、政権が滅亡の瀬戸際にあるときは、経済的損失は政権を拘束できない。「わが亡きあとに洪水よ来たれ」という発想は、死を免れさえすれば洪水も怖くないのと同じことだ。たしかに、歴史的には独裁政権が貧富を均すことでブルジョア革命に対抗した先例はないが、それはかつての政権が豊かな人のものだったので、そのような考えが浮かばなかったに過ぎない。現政権は貧富を均すことで権力を握ったのであり、それ(共産党)が当時民衆の支持を得たのはそのためであった。現政権が官僚と資本が結託して一体となっていたとしても(?国有企業=党営企業では?)、大部分はこっそりと汚職をしているので、態度を変えることの邪魔にはならない。路線闘争で少数の官僚と官僚企業家を犠牲にすればすむ。政権の命を救うことに比べれば、その程度の犠牲はなんでもない。いわんや貧富を均すといっても、羊頭狗肉であり、革命を要求するブルジョア階級をつぶし、独占資本家階級を保護し続けるのだ。中国政治に詳しい人なら想像がつくが、その手の芝居を打つのは難しくない。今日のエリート連盟は労働者農民からは政権が理想にそむいたと見られているから、もし政権が貧富を均す立場に戻ったら、やはり中国の人口の大多数を占める労働者農民の支持を集められるだろう。毛沢東は死んでおらず、いつでも再び民衆の階級闘争の衝動を引き出すことができる。政権のこの切り札について、ブルジョア階級はさめた認識を持っておくべきである。抜け出すのは簡単ではない。将来の民衆の争奪では、ブルジョア階級はこれで行き詰るだろう。
ポピュリズムの切り札だけでなく、政権にはナショナリズムの切り札もある。政権が外国勢力が政権転覆を企てているとみなすか、国内矛盾が一定水準まで激化したときには、ナショナリズムを扇動して国際的脅威に対抗したり、国内矛盾を国際問題に転化したりするのは独裁政権の常套手段である。そして、台湾の存在は、戦争の発動による矛盾の転化のための開戦の標的を提供している。
独裁政権がナショナリズムとポピュリズムを使って民衆と連合すると、一般に必ずファシズムという怪物を生み出す。将来の中国にファッショ化の危険は存在する。しかし、ナショナリズムであれポピュリズムであれ、独裁政権にとってはいずれも「両刃の剣」である。それによって他人を害することはできるが、最後は自分に戻ってくる。いかなるファシズム政権も長期間継続はできなかった。ポピュリズムの扇動は、経済の崩壊を招き、社会危機を引き起こし、独裁政権自体も崩壊させる。そしてナショナリズムの扇動は現政権にとって、対外的には西側列強の相手ではないので自ら辱めを受けることとなり、対内的には国内民族間の衝突と分裂を引き起こし、最終的に身を滅ぼす。
三、超越者
中国の政治変革は膠着状態にある。しかし、膠着はいつまでも維持されるわけではなく、つもり積もった危機はいつかは爆発する。もしも出口を探し出せなければ、そのときの災難はかつての「暴民―暴政」サイクルよりひどいだろう。なぜなら経済の一体化と生態環境の窮地は今日の中国にすでに暴民負担能力を失わせており、いったん暴民が湧き起これば、暴政が形成される時間もなく、社会は破滅に向かうだろう。その速度は今の想像よりはるかに速いだろう。
暴民が方々に起こるという局面は中国でまさに生まれつつある。これは誰でも見ることができる。災難を避けたければ、別の道を切り開かねばならない。現有の要素と要素連合がどれも変革を担えないのであれば、すべての要素を超えてはじめて窮地を抜け出せる。
超越とは(第三章第一節)
超越はまず超越者に現れる。超越者の第一層の含意は、階級あるいは集団利益から自由であり、一部の人のために局部的な問題を解決するのではなく、全社会のために全体的に問題を解決する。第二層の含意は、新思考を行い、新たな道を開き、情勢の挑戦に保守ではなく変革でこたえる。前者は立場であり、後者は能力である。そして両方とも不可欠である。
国家の政治システムの変革は、民衆の責任ではなく、国際的な義務でもない。よって、政権、資本と思想の三要素の中の超越者が担わなければならない。権力を独裁統治の終結のために用いようとする者が政権超越者である。富を社会の改造のために用いようとする企業家が資本超越者である。思想超越者とは第一に自らの生計を超越し、第二に前人の教条を超越しなければならない。3種の超越者はいずれもエリート連盟の反逆者である。歴史上の特権階級に対する革命の多くが特権階級の反逆者によって指導されていたのと同様、中国社会の超越もまたエリート連盟の超越者によって推進される。
超越は至高の理想を追求するためではなく、超越しなければ困難を脱することができないという現実から生ずる。中国の利害対立はすでに乗り越えることのできないところまで来ている。社会学者が言っているように、各階級はそれぞれ別の時代に属し、対話も調和もできない。このような本質的な分裂に直面しているので、中国の変革は必ず階級を超越したものでなければならない。未来はどれか一つの階級の名で作られてはならない――なぜならそれはより多くの分裂と対立を生み出すだけだからである。超越は全面的でなければならず、各階級と各要素がみな超越されてはじめて急進と保守、貧困と奢侈、暴民と暴政、東側と西側……が超越されえる。それはシステム全体の転換であり、「切れ切れの」変遷ではない。変遷は同一のシステム内の論理に従うしかないが、システム自体が行き詰っていたら、変遷の行く末も袋小路である。中国の現有の独裁システムはまさにこの袋小路に向かっており、超越はシステムの交換でなければならない。
思想超越者――「なしうる」から「なすべき」へ(第三章第二節)
システム交換は「自由」行為であり、選択の結果である。新システムは発展によって自然に出現するのではないし、「石を手探りして河を渡」ってたどり着けるものでもない。なぜならそれらはいずれも変遷だからだ。新システムは思想の自覚的創建と社会の自覚的選択・受容によってのみ生ずる。
米国が植民地から今日の米国に転換したのは、米国の「国父」たちが米国憲法を制定したことに始まる。その薄い数ページの文章が、今日米国が世界に覇を唱える起点となった。システム創建のときのごく僅かの違いがその後の現実のプロセスの中で巨大な違いに変わりうる。思想作用の大きさはここに見て取れる。
システム創建は繰り返すことはできない。ある社会において成功したシステムを、別の社会に踏襲することは絶対にできない。中国に西側のシステムを「持ってくる」ことはできない。誰も二回同じ河に踏み入ることはできず、いずれの社会の新システムもそれ自身の現実の土壌の上に再建しなければならない。このような超越がなければ、土に合わずに育たないという結果しか生まない。今日の中国にとって、思想の任務は中国の転換に適したシステムを探し出すことである。
人間性には違いはなく、価値観や理念も共通なのだから、別に一からやり直す必要はないという人もいる。しかし、新システムは価値観と理念だけではなく、具体的な構造とメカニズムのほうがより多い。どの社会の構造とメカニズムもみな同じではなく、どの社会も思想者が自分で研究しなければならない。
思想の超越はシステム創建のほかにも、理想と現実のギャップを乗り越え、古いシステムから新しいシステムに切り替える道を探し出すことが含まれる。理想の「なすべき」と現実の「なしうる」の間には相互決定の関係があり、「なすべき」は可能なものでなければならず、「なしうる」は必ずなすべきものでなければならない。二者はどちらか一方が他より重要ということはない。「なしうる」と「なすべき」を一体に融合されたものが方法である。もしも方法の中に融合できなければ、「なすべき」は空中楼閣に過ぎず、「なしうる」もまたシニシズムとご都合主義に陥ってしまう。中国の超越にはいままでにない新しい方法が必要であり、それが思想超越者の任務である。
方法の軽視は中国思想界の通弊である。道筋のない理念と目標は往々にしてスローガン倒れになり、現実の中で前進できないだけでなく、理想と現実の落差から急進化しやすい。なぜなら挫折の最も都合のよい解釈は鎮圧であり、政権を打倒してはじめて理想を実現できるという結論に自然に至る。しかし、打倒は思想の超越ではなく、権力の超越に過ぎない。もしも本当に政権を打倒できたとしても、方法のない理想は動乱をもたらすだけである。思想の超越の目印は急進ではなく、反対にできるだけ穏健に転換を実現することである。中国には革命の条件も動乱に耐えられる能力もないのだから、打倒する闘争は社会を動揺と災難に陥れる。思想がなすべきはそのような前途を避け、他の道を探すことである。
政権超越者――歴史の偉人になる(第三章第三節)
政権に積極的な要素を探すという話題は、たとえご都合主義とは見られないとしても、むなしい試みと見られるだろう。しかし、確固不動らしく見える潔癖は軟弱と自信のなさの現れである。社会変革の推進には、すべての可能な要素を取り込むべきである。中国の平和的転換は、政権からの協力がなければ実現しがたい。政権は全体としては政治変革の障害だが、政権集団は決して一枚岩ではない。政権内部の超越的要素が作用を発揮するのを期待しかつ働きかけることは、決して政権に「投降」することではなく、より効果的に独裁を終わらせることになる。
政権は領袖と官僚集団から構成される。高度に独裁的な構造の中では、領袖は皇帝や毛沢東のように唯一人でも良い。中国の現政権の領袖は小さなグループであり、最高ランクの数人の権力者と最高職位に昇進する可能性のある少数者によって構成される。領袖のほかに、政権組織のその他のメンバーはみな官僚集団に属する。官僚に中にはもちろん超越的な者もいる。しかし、その超越性は官僚ヒエラルキーのトップに近づいてはじめて作用を発揮する。トップに達しなければ、官僚の超越はより高い地位に向かうしかなく、体制を超越することはありえない。あえて超越すれば官僚ヒエラルキーから転落し、それまでの努力は水の泡となってしまう。トップに達した後も超越性を維持していれば、より高い地位に上る必要はないので、はじめて体制が超越の対象となる。大多数の独裁領袖は当然まったく超越性はなく、絶対権力の独占だけを考えている。領袖と官僚集団が一致している状況下では、上意下達の政治改革が発生する可能性はなく、変化は危機が政権を倒すか、下からの革命だけである。そのような前途はとりあえずここでは議論しない(それは別のテーマである)。しかし、歴史上は確かに領袖が官僚集団の願望を省みず政治変革をスタートさせたという前例がある。近い例では、蒋経国、ゴルバチョフなど、それから文化大革命という空前の超越を行った毛沢東(価値判断は別として、文化大革命ももちろん一種の政治変革である。)
出典:http://boxun.com/hero/2006/wanglx/6_4.shtml
そうなればエリート連盟も民衆をコントロールしやすい。民衆に選挙権があり、自由に表現できるので、政治的な地位がないといって嘆きようがない。政権に対する不満も自分の選択が間違っていたことに帰するしかない。こうしてブルジョア階級は政権を操縦できるだけでなく、民主理念からあらさがしをされる心配もない。代議制政権の階級属性はこのようにして覆い隠される。
エリート連盟は人類の昔からの現象である。昔は限られた狭い領地に分割されていた。各領地のエリート連盟は独裁政権の主導下に一体となり、連盟同士がお互いに争い、頻繁に戦争が起きた。資本主義のグローバル化に伴い、障壁が打破され、ブルジョア階級を盟主とする世界エリート連盟が形成された。連盟の基礎はグローバル化する資本のルールであり、共同で貧富二元世界を維持することにある(?)。このような背景の下で、国際資本は中国が代議制に転換するのを必ずや支持する。なぜなら中国のエリート連盟が独裁政権に主導される限り、世界と闘争し続け、資本主導となってはじめて、中国のエリート連盟はグローバルエリート連盟の信頼しえる一員となるからだ。これは国際要素が中国の政治変革に影響を与えるおもな方向である。
民衆はブルジョア階級革命に利用できる同盟者に過ぎず、決着がつけばまた被統治の地位に戻る。人口と資源の制限が資本主義が中国において恩恵をもたらす対象を制限するので(?)、貧富の格差は避けがたい(?前後の結びつきは必然か?)。したがって、たとえ古いエリート連盟が新しいエリート連盟に地位を譲ったとしても、民衆に対しては形は変わっても依然として本質は変わらない。
政権と民衆の連合――ファシズムに向かう
一般的に、政権は自分から自ら主導するエリート連盟を打破することはない。なぜなら政権の分け前が一番大きいからだ。しかし、社会危機に直面したとき、政権は民衆に取り入るためにエリート連盟の粛清を図ることがある。たとえば、反腐敗、資本攻撃などである。しかし、これは往々にしてご都合主義的態度に過ぎず、一部を犠牲にしたとしても、基本方向とエリート連盟の基礎を変えるものではない。だがいったんエリート連盟のその他の要素が離反を企てたときは、政権も民衆と提携することでそれに対応するかもしれない。
たとえばブルジョア階級が革命を企てたとき、政権は民衆の貧富の格差に対する不満を利用して、ポピュリズムを扇動し、矛先をブルジョア階級に向けることができる。これは効果的な手である。中国社会は昔から貧富を均す意識があり、現実にも豊かな者を恨む感情がある。もしも民主・法治・人権の面で民衆がブルジョア階級と同じ側に立つとしても、政権が貧富の格差是正の旗を掲げれば、民衆はすぐにブルジョア階級を捨てて、政権の側に移る。貧富を均すことは永遠に資本のカードにはなりえず、ブルジョア階級が中国問題の根源を「官民矛盾」と言おうとしても、政権は「労使矛盾」こそが根本であり、「ブルジョア階級の復活」が民衆の地位を低下させたと民衆に軽々と信じさせるであろう。労働者が自らの状況を改善することは、正しい路線の政権に戻ることによってのみ(誤った路線の汚名は権力闘争の失敗者に担わせる)、労働者を搾取する資本家を妥当することによってのみ実現できる。
一般に、このようにすることはすでに私有化・市場化された中国経済に壊滅的打撃を与えるので、政権はそんな自殺行為はなしえないと考えられている。しかし、政権が滅亡の瀬戸際にあるときは、経済的損失は政権を拘束できない。「わが亡きあとに洪水よ来たれ」という発想は、死を免れさえすれば洪水も怖くないのと同じことだ。たしかに、歴史的には独裁政権が貧富を均すことでブルジョア革命に対抗した先例はないが、それはかつての政権が豊かな人のものだったので、そのような考えが浮かばなかったに過ぎない。現政権は貧富を均すことで権力を握ったのであり、それ(共産党)が当時民衆の支持を得たのはそのためであった。現政権が官僚と資本が結託して一体となっていたとしても(?国有企業=党営企業では?)、大部分はこっそりと汚職をしているので、態度を変えることの邪魔にはならない。路線闘争で少数の官僚と官僚企業家を犠牲にすればすむ。政権の命を救うことに比べれば、その程度の犠牲はなんでもない。いわんや貧富を均すといっても、羊頭狗肉であり、革命を要求するブルジョア階級をつぶし、独占資本家階級を保護し続けるのだ。中国政治に詳しい人なら想像がつくが、その手の芝居を打つのは難しくない。今日のエリート連盟は労働者農民からは政権が理想にそむいたと見られているから、もし政権が貧富を均す立場に戻ったら、やはり中国の人口の大多数を占める労働者農民の支持を集められるだろう。毛沢東は死んでおらず、いつでも再び民衆の階級闘争の衝動を引き出すことができる。政権のこの切り札について、ブルジョア階級はさめた認識を持っておくべきである。抜け出すのは簡単ではない。将来の民衆の争奪では、ブルジョア階級はこれで行き詰るだろう。
ポピュリズムの切り札だけでなく、政権にはナショナリズムの切り札もある。政権が外国勢力が政権転覆を企てているとみなすか、国内矛盾が一定水準まで激化したときには、ナショナリズムを扇動して国際的脅威に対抗したり、国内矛盾を国際問題に転化したりするのは独裁政権の常套手段である。そして、台湾の存在は、戦争の発動による矛盾の転化のための開戦の標的を提供している。
独裁政権がナショナリズムとポピュリズムを使って民衆と連合すると、一般に必ずファシズムという怪物を生み出す。将来の中国にファッショ化の危険は存在する。しかし、ナショナリズムであれポピュリズムであれ、独裁政権にとってはいずれも「両刃の剣」である。それによって他人を害することはできるが、最後は自分に戻ってくる。いかなるファシズム政権も長期間継続はできなかった。ポピュリズムの扇動は、経済の崩壊を招き、社会危機を引き起こし、独裁政権自体も崩壊させる。そしてナショナリズムの扇動は現政権にとって、対外的には西側列強の相手ではないので自ら辱めを受けることとなり、対内的には国内民族間の衝突と分裂を引き起こし、最終的に身を滅ぼす。
三、超越者
中国の政治変革は膠着状態にある。しかし、膠着はいつまでも維持されるわけではなく、つもり積もった危機はいつかは爆発する。もしも出口を探し出せなければ、そのときの災難はかつての「暴民―暴政」サイクルよりひどいだろう。なぜなら経済の一体化と生態環境の窮地は今日の中国にすでに暴民負担能力を失わせており、いったん暴民が湧き起これば、暴政が形成される時間もなく、社会は破滅に向かうだろう。その速度は今の想像よりはるかに速いだろう。
暴民が方々に起こるという局面は中国でまさに生まれつつある。これは誰でも見ることができる。災難を避けたければ、別の道を切り開かねばならない。現有の要素と要素連合がどれも変革を担えないのであれば、すべての要素を超えてはじめて窮地を抜け出せる。
超越とは(第三章第一節)
超越はまず超越者に現れる。超越者の第一層の含意は、階級あるいは集団利益から自由であり、一部の人のために局部的な問題を解決するのではなく、全社会のために全体的に問題を解決する。第二層の含意は、新思考を行い、新たな道を開き、情勢の挑戦に保守ではなく変革でこたえる。前者は立場であり、後者は能力である。そして両方とも不可欠である。
国家の政治システムの変革は、民衆の責任ではなく、国際的な義務でもない。よって、政権、資本と思想の三要素の中の超越者が担わなければならない。権力を独裁統治の終結のために用いようとする者が政権超越者である。富を社会の改造のために用いようとする企業家が資本超越者である。思想超越者とは第一に自らの生計を超越し、第二に前人の教条を超越しなければならない。3種の超越者はいずれもエリート連盟の反逆者である。歴史上の特権階級に対する革命の多くが特権階級の反逆者によって指導されていたのと同様、中国社会の超越もまたエリート連盟の超越者によって推進される。
超越は至高の理想を追求するためではなく、超越しなければ困難を脱することができないという現実から生ずる。中国の利害対立はすでに乗り越えることのできないところまで来ている。社会学者が言っているように、各階級はそれぞれ別の時代に属し、対話も調和もできない。このような本質的な分裂に直面しているので、中国の変革は必ず階級を超越したものでなければならない。未来はどれか一つの階級の名で作られてはならない――なぜならそれはより多くの分裂と対立を生み出すだけだからである。超越は全面的でなければならず、各階級と各要素がみな超越されてはじめて急進と保守、貧困と奢侈、暴民と暴政、東側と西側……が超越されえる。それはシステム全体の転換であり、「切れ切れの」変遷ではない。変遷は同一のシステム内の論理に従うしかないが、システム自体が行き詰っていたら、変遷の行く末も袋小路である。中国の現有の独裁システムはまさにこの袋小路に向かっており、超越はシステムの交換でなければならない。
思想超越者――「なしうる」から「なすべき」へ(第三章第二節)
システム交換は「自由」行為であり、選択の結果である。新システムは発展によって自然に出現するのではないし、「石を手探りして河を渡」ってたどり着けるものでもない。なぜならそれらはいずれも変遷だからだ。新システムは思想の自覚的創建と社会の自覚的選択・受容によってのみ生ずる。
米国が植民地から今日の米国に転換したのは、米国の「国父」たちが米国憲法を制定したことに始まる。その薄い数ページの文章が、今日米国が世界に覇を唱える起点となった。システム創建のときのごく僅かの違いがその後の現実のプロセスの中で巨大な違いに変わりうる。思想作用の大きさはここに見て取れる。
システム創建は繰り返すことはできない。ある社会において成功したシステムを、別の社会に踏襲することは絶対にできない。中国に西側のシステムを「持ってくる」ことはできない。誰も二回同じ河に踏み入ることはできず、いずれの社会の新システムもそれ自身の現実の土壌の上に再建しなければならない。このような超越がなければ、土に合わずに育たないという結果しか生まない。今日の中国にとって、思想の任務は中国の転換に適したシステムを探し出すことである。
人間性には違いはなく、価値観や理念も共通なのだから、別に一からやり直す必要はないという人もいる。しかし、新システムは価値観と理念だけではなく、具体的な構造とメカニズムのほうがより多い。どの社会の構造とメカニズムもみな同じではなく、どの社会も思想者が自分で研究しなければならない。
思想の超越はシステム創建のほかにも、理想と現実のギャップを乗り越え、古いシステムから新しいシステムに切り替える道を探し出すことが含まれる。理想の「なすべき」と現実の「なしうる」の間には相互決定の関係があり、「なすべき」は可能なものでなければならず、「なしうる」は必ずなすべきものでなければならない。二者はどちらか一方が他より重要ということはない。「なしうる」と「なすべき」を一体に融合されたものが方法である。もしも方法の中に融合できなければ、「なすべき」は空中楼閣に過ぎず、「なしうる」もまたシニシズムとご都合主義に陥ってしまう。中国の超越にはいままでにない新しい方法が必要であり、それが思想超越者の任務である。
方法の軽視は中国思想界の通弊である。道筋のない理念と目標は往々にしてスローガン倒れになり、現実の中で前進できないだけでなく、理想と現実の落差から急進化しやすい。なぜなら挫折の最も都合のよい解釈は鎮圧であり、政権を打倒してはじめて理想を実現できるという結論に自然に至る。しかし、打倒は思想の超越ではなく、権力の超越に過ぎない。もしも本当に政権を打倒できたとしても、方法のない理想は動乱をもたらすだけである。思想の超越の目印は急進ではなく、反対にできるだけ穏健に転換を実現することである。中国には革命の条件も動乱に耐えられる能力もないのだから、打倒する闘争は社会を動揺と災難に陥れる。思想がなすべきはそのような前途を避け、他の道を探すことである。
政権超越者――歴史の偉人になる(第三章第三節)
政権に積極的な要素を探すという話題は、たとえご都合主義とは見られないとしても、むなしい試みと見られるだろう。しかし、確固不動らしく見える潔癖は軟弱と自信のなさの現れである。社会変革の推進には、すべての可能な要素を取り込むべきである。中国の平和的転換は、政権からの協力がなければ実現しがたい。政権は全体としては政治変革の障害だが、政権集団は決して一枚岩ではない。政権内部の超越的要素が作用を発揮するのを期待しかつ働きかけることは、決して政権に「投降」することではなく、より効果的に独裁を終わらせることになる。
政権は領袖と官僚集団から構成される。高度に独裁的な構造の中では、領袖は皇帝や毛沢東のように唯一人でも良い。中国の現政権の領袖は小さなグループであり、最高ランクの数人の権力者と最高職位に昇進する可能性のある少数者によって構成される。領袖のほかに、政権組織のその他のメンバーはみな官僚集団に属する。官僚に中にはもちろん超越的な者もいる。しかし、その超越性は官僚ヒエラルキーのトップに近づいてはじめて作用を発揮する。トップに達しなければ、官僚の超越はより高い地位に向かうしかなく、体制を超越することはありえない。あえて超越すれば官僚ヒエラルキーから転落し、それまでの努力は水の泡となってしまう。トップに達した後も超越性を維持していれば、より高い地位に上る必要はないので、はじめて体制が超越の対象となる。大多数の独裁領袖は当然まったく超越性はなく、絶対権力の独占だけを考えている。領袖と官僚集団が一致している状況下では、上意下達の政治改革が発生する可能性はなく、変化は危機が政権を倒すか、下からの革命だけである。そのような前途はとりあえずここでは議論しない(それは別のテーマである)。しかし、歴史上は確かに領袖が官僚集団の願望を省みず政治変革をスタートさせたという前例がある。近い例では、蒋経国、ゴルバチョフなど、それから文化大革命という空前の超越を行った毛沢東(価値判断は別として、文化大革命ももちろん一種の政治変革である。)