『資本論』学習資料No.37(通算第87回) (1)
◎序章B『資本論』の著述プランと利子・信用論(2)(大谷禎之介著『マルクスの利子生み資本論』全4巻の紹介 №6)
第1巻の〈序章B 『資本論』の著述プランと利子・信用論〉の第2回目です。〈A 「経済学批判」体系プランにおける利子と信用〉の〈(2)「経済学批判」体系プランにおける利子〉という小項目のなかで、大谷氏は〈増分である利潤からこれを生みだすものとして区別される価値は,自己を増殖する価値,資本である。そして,利潤をもたらす資本の成立によって,貨幣はある率で利潤を生むという使用価値をもった商品として流通にはいることができるようになるのであり,こうして利子および利子生み資本が成立する。利子にたいする利子生み資本の関係は,自己を増殖する価値とその増分との関係としては,利潤にたいする利潤をもたらす資本の関係と等しいだけでなく,むしろ前者は,後者の「純粋に抽象的な形態」なのである〉(87頁、太字は傍点による強調)と述べ、それに章末注〔9〕として『経済学批判要項』の一文が付けられています。それが興味深いので、重引・紹介しておきます。
〈利潤をもたらす資本は,現実の資本であり,自己を再生産すると同時にまた自己を累加しつつあるものとして措定された価値であり,しかも,同じままにとどまる前提として,自己によって措定された剰余価値としての自己自身から区別されている。これにたいして,利子をもたらす資本は,利潤をもたらす資本の純粋に抽象的な形態である。資本が,それの価値〔の大きさ〕に応じて(これには生産力の一定の段階が前提される)利潤をもたらすものとして措定されていることによって,商品が,すなわち貨幣という形態で措定されている商品が(自立化した価値という,言い換えれば--いまではそう言うことができるが--実現された資本という,この商品にふさわしい形態で措定されている商品が),資本として流通にはいることができる。資本が資本として商品になることができるのである。この場合には資本は利子つきで貸し出される資本である。資本の流通の--あるいは資本が経る交換の--形態は,その場合,これまでに考察された形態とは独自的に異なるものとして現われる。これまでわれわれは,資本が商品の規定においても貨幣の規定においても自己を措定することを見てきた。しかしこのことが行なわれるのは,商品と貨幣とが資本の循環の契機として現われ,資本がかわるがわる商品と貨幣として自己を実現していくかぎりにおいてでしかない。商品および貨幣は,消えては,絶えずふたたび生みだされる,資本の存在諸様式であり,資本の生活過程の諸契機にすぎない。といって,資本としての資本が,それ自身で流通の契機となることはなかった。資本そのもの〔が流通の契機となるのは〕,商品として〔であった〕。商品が売られたのは資本としてではなかったし,貨幣も資本として〔買ったの〕ではなかった。ひとことで言えば,商品も貨幣も--そして厳密に言えば,われわれが妥当な形態と見なさなければならないのは後者だけであるが,利潤をもたらす価値として流通にはいったのではなかったのである。(『経済学批判要綱』。MEGAII/1.2,S.738.)〉 (112-113頁)
なぜ、この一文が興味深いかといいますと、宇野弘蔵は、マルクスの利子生み資本論に異論を唱え、マルクスが利子生み資本を説明して、貨幣が商品として流通に入り売買(本当は貸し借り)されるとしていることに対して、利子生み資本というのは、資本として売買されることであり、それは架空資本のような株式や国債のような形態をとったもののことであり、それが資本として商品になり、売買されるのだと述べているのですが(これは目の前の現象にただしがみついているだけなのですが)、こうした宇野の批判に対する反論として重要ではないかと思ったからです。
ここではマルクスは利子生み資本を貨幣という形態で商品になっていると一方で言いながら、他方ではそれは資本として流通に入るとも述べています。つまり貨幣という形態で措定されている商品が、資本として流通に入ることによって、資本が資本として商品になるとしているのです。
これに対して、資本が商品の形態や貨幣の形態をとる場合は、それらは資本の存在様式であり、資本そのものが流通の契機になることは無かった。資本が流通はいる場合は単なる商品としてであり、単なる貨幣としてであったとしています。それらは利潤をもたらす価値として流通に入ったのではなかった、と。
だから利子生み資本の場合、資本が資本として流通に入るということが一つの眼目であることが分かります。貨幣が商品になるという場合も、それが利潤を生むという使用価値によってであって、つまり資本としてなのです。だから貨幣が商品になるのであって、資本が商品になるのではない、という宇野のマルクス批判はまったく的外れとしか言いようがないのです。なぜ貨幣が商品になるのかが理解されていないといえます。貨幣が商品になるのはその貨幣が利潤を生むという使用価値を持つからです。つまり資本という規定性によってなのです。
その次も宇野のマルクス批判に対する回答として重要だと思いました。
〈利子のところでは二つのことが考察されるべきである。/第1に,利子と利潤とへの利潤の分割。(イギリス人はこれら両者を合わせて,総利潤〔gross profit〕と呼ぶ。)この区別は,貨幣資本家〔monied capitalist〕から成る一階級が産業資本家から成る一階級に対立するようになると,感じられるもの,だれにでもわかるものとなる。第2に,資本そのものが商品となる,言い換えれば,商品(貨幣)が資本として売られる。これはたとえば,資本が,他のすべての商品と同様に,その価格を需要供給に合わせることを意味する。つまり,需要供給が利子率を規定するのである。だからここで,資本としての資本が流通のなかにはいるのである。/貨幣資本家と産業資本家とが二つの特殊的な階級を形成しうるのは,ただ,利潤が収入の二つの分枝に分離していくことができるからでしかない。二種類の資本家と言えば,これはたんに事実を表現したものにすぎないが,資本家の二つの特殊的階級が成長することができるためには,そのための基礎となる分裂が,すなわち,収入の二つの特殊的形態への利潤の分離が,現に生じていなければならない。/……賃金と利潤--必要労働と剰余労働--のあいだには,ある自然的な関係〔natural relation〕が存在する。しかし,利潤と利子とのあいだには,収入のこれら相異なる形態のもとに配置されるこれら二つの階級のあいだの競争によって決定される関係以外に,なんらかの関係があるだろうか。だが,この競争が存在するのには,そしてこの二つの階級が存在するのには,利潤と利子とへの剰余価値の分割がすでに前提されているのである。その一般性において考察された資本は,けっしてたんなる抽象ではない。一国民の総資本を,たとえば総賃労働(あるいはまた土地所有)との区別において考察するとき,あるいは,資本を他のある階級と区別されるある階級の一般的経済的土台として考察するとき,私は資本をその一般性において考察しているのである。それはちょうど,私がたとえば,人間を生理学的に獣と区別して考察する場合のようなものである。利潤と利子との現実的な区別は,産業資本家階級にたいする貨幣資本家階級〔moneyed class of capitalists〕の区別として存在している。しかしこうした二つの階級が対立しうるのには,つまり資本家たちの二重の存在は,資本によって生みだされた剰余価値の分離〔Diremtion〕を前提するのである。」(『経済学批判要綱』。MEGAII/1.2,S.714-715.)〉 (113-114頁)
ここではマルクスは〈資本そのものが商品となる〉ということを言い換えて、〈商品(貨幣)が資本として売られる〉とも述べています。つまりこの場合の商品である貨幣は単なる貨幣ではありません。それは平均利潤を生むという使用価値を持った貨幣なのです。そして売買は一つの仮象であって、実際には貸し借りなのです。貸し借りによって貨幣は資本として流通に入るわけです。だからこそそれは資本として流通に入り、利子という価格を持つのです。
今回はただ『要綱』から引用だけで、しかもやや難解で、おまけにただ宇野弘蔵の利子論の批判だけなのですが、とりあえず、ここでの紹介はこうした紹介者の問題意識だけにもとづいたものですので、ご了承ください。今回の大谷本の紹介はこれだけにしておきます。
◎「標準労働日のための闘争」
これから検討します、第5~7節には「標準労働日のための闘争」という共通の表題が付いています。
私たちは第1節の第7パラグラフで、第5パラグラフで紹介された資本家側の言い分に対する労働者の側の言い分の最後で、〈ぼくは標準労働日を要求する。なぜならば、ほかの売り手がみなやるように、ぼくも自分の商品の価値を要求するからだ〉と述べていたことを知っています。ここで初めて「標準労働日」という用語が出てきたのです。
標準労働日というのは果たして何かを考えますと、ここでマルクスはそれについてそれは労働力商品の価値に該当するものだと述べています。
その具体的な内容については〈平均労働者が合理的な労働基準のもとで生きて行くことのできる平均期間が30年だとすれば、きみが毎日ぼくに支払うぼくの労働力の価値、その全価値の 1/365×30 すなわち 1/10950 である。〉と述べ、それが〈正常な長さの労働日〉だとしています。
ところで労働日というのは、1日における労働の継続時間であり、労働というのは労働力の使用価値です。だからそれが労働力の価値とどういう関係にあるのかが今問題になっているわけです。すべての商品は使用価値と価値との統一物です。しかしある特殊な商品はその独特の使用価値故に、その価値もまた独特なものとして現れます。例えば家屋の使用を一定期限に限って販売する場合、この商品の価値は、その使用によって損耗する程度によって決まってきます。例えばその家屋が10年でその使用価値をすべて無くすと考えますと、1カ月ではその家屋の建設に支出されたすべての労働時間、すなわちその価値(これはいま520万円とします)の520分の1、すなわち1万円分だけ損耗すると考えることが出来ます。だから家屋の1カ月の使用価値に含まれている価値は1万円ということになるわけです。
マルクスは『61-63草稿』で次のように述べています。
〈したがって、この商品--労働能力--の独自な使用価値から、一方では、その消費そのものが価値増殖〔Verwertung〕、価値創造である、ということが出てくるのと同様に、他方ではこの使用価値の独自な性質から、それが使用され価値増殖的に利用〔Verwerten〕される範囲は、その交換価値そのものを破壊しないためには、ある制限内に封じ込められなければならない、ということが出てくる。〉 (草稿集④285頁)
つまり労働力の価値は、労働力の再生産費であり、労働力を再生産するために必要な生活手段の価値に帰着します。しかし労働力の使用価値である労働も、そもそも1日に支出されうる労働時間はどれだけかは決まっていません。確かにそれは1日24時間も支出できないのは当然としても、労働時間は一体何時間がその価値に合致するものなのかが問題なのです。そこには肉体的な社会的な限界があることが指摘されました。
労働力の価値は労働力を日々再生産を可能にするために必要な生活手段の価値ですが、労働力はただ必要な生活手段を消費していれば常に再生産され得るというものではありません。そのためにはその使用価値である労働そのものが一定の限度内にあってこそ、それは再生産可能となるのです。ではその再生産可能な労働時間とは何か、それが標準労働日だということでしょう。そして標準労働日にもとづいた労働で消耗した生命力を回復して、再び健康的な体力を取り戻し、同じように労働を可能にするのに必要な生活手段の価値が、すなわち労働力の価値ということです。だから労働力の価値はその使用価値である労働が一定の限度内(標準労働日)にあることが前提されてはじめて規定されうるものなのです。
そして最後の第8パラグラフの締めくくりは次のようになっていました。
〈要するに、まったく弾力性のあるいろいろな制限は別として、商品交換そのものの性質からは、労働日の限界は、したがって剰余労働の限界も、出てこないのである。資本家が、労働日をできるだけ延長してできれば1労働日を2労働日にでもしようとするとき、彼は買い手としての自分の権利を主張するのである。他方、売られた商品の独自な性質には、買い手によるそれの消費にたいする制限が含まれているのであって、労働者が、労働日を一定の正常な長さに制限しようとするとき、彼は売り手としての自分の権利を主張するのである。だから、ここでは一つの二律背反が生ずるのである。つまり、どちらも等しく商品交換の法則によって保証されている権利対権利である。同等な権利と権利とのあいだでは力がことを決する。こういうわけで、資本主義的生産の歴史では、労働日の標準化は、労働日の限界をめぐる闘争--総資本家すなわち資本家階級と総労働者すなわち労働者階級とのあいだの闘争--として現われるのである。〉
つまり標準労働日というのは、何か経済法則として決まってくるようなものではなく、それは労働力の価値もとづいたものとはいえ、最終的には総資本家階級と総労働者階級との力関係によって社会的に法的に決められるものだということです。だからそれがどういう歴史的経緯を辿って来たのかをこれからの諸節で検討されるものと思われます。
またこの第5節には「標準労働日のための闘争」という主題のあとに、「14世紀なかばから17世紀末までの労働日延長のための強制法」という副題が付いています(フランス語版ではこの副題がそのまま第5節の表題になっています)。つまりこの第5節の主要な問題はこの副題だということです。
しかしこの副題のテーマが実際に論じられるのは第7パラグラフ以降で、それまでの前半部分ではそもそも労働日とは何か、標準労働日というものはどうして階級闘争によって、そして最終的には国家によって法的に決められねばならないのか、という問題がまず論じられています。
第5節 標準労働日のための闘争 14世紀半ばから17世紀末までの労働日延長のための強制法
◎第1パラグラフ(「1労働日とはなにか?」という問いに対する資本の答え)
【1】〈(イ)「1労働日とはなにか?」(ロ)資本によって日価値を支払われる労働力を資本が消費してよい時間はどれだけか? (ハ)労働日は、労働力そのものの再生産に必要な労働時間を越えて、どれだけ延長されうるか? (ニ)これらの問いにたいして、すでに見たように、資本は次のように答える。(ホ)労働日は、毎日、まる24時間から、労働力がその役だちを繰り返すために絶対に欠くことのできないわずかばかりの休息時間を引いたものである。(ヘ)まず第一に自明なことは、労働者は彼の一生活日の全体をつうじて労働力以外のなにものでもないということ、したがってまた、彼の処分しうる時間はすぺて自然的にも法的にも労働時間であり、したがって資本の自己増殖のためのものだということである。(ト)人間的教養のための、精神的発達のための、社会的諸機能の遂行のための、社交のための、肉体的および精神的生命力の自由な営みのための時間などは、日曜の安息時間でさえも--そしてたとえ安息日厳守の国においてであろうと(104)--ただふざけたことでしかない! (チ)ところが、資本は、剰余労働を求めるその無際限な盲目的な衝動、その人狼的渇望をもって、労働日の精神的な最大限度だけではなく、純粋に肉体的な最大限度をも踏み越える。(リ)資本は、身体の成長のためや発達のためや健康維持のための時間を横取りする。(ヌ)資本は、外気や日光を吸うために必要/な時間を取り上げる。(ル)資本は、食事時間をへずり、できればそれを生産過程そのものに合併する。(ヲ)したがって、ただの生産手段としての労働者に食物があてがわれるのは、ボイラーに石炭が、機械に油脂が加えられるようなものである。(ワ)生命力を集積し更新し活気づけるための健康な睡眠を、資本は、まったく疲れきった有機体の蘇生のためにどうしても欠くことのできない時間だけの麻痺状態に圧縮する。(カ)ここでは労働力の正常な維持が労働日の限界を決定するのではなく、逆に、労働力の1日の可能なかぎりの最大の支出が、たとえそれがどんなに不健康で無理で苦痛であろうとも、労働者の休息時間の限界を決定する。(ヨ)資本は労働力の寿命を問題にしない。(タ)資本が関心をもつのは、ただただ、1労働日に流動化されうる労働力の最大限だけである。(レ)資本が労働力の寿命の短縮によってこの目標に到達するのは、ちょうど、貧欲な農業者が土地の豊度の略奪によって収穫の増大に成功するようなものである。〉 (全集第23a巻346-347頁)
(イ)(ロ)(ハ)「1労働日とはなんでしょうか?」資本によってその日価値が支払われた労働力を資本が消費してよい時間というのはどれだけでしょうか? 労働日は、労働力そのものの再生産に必要な労働時間(必要労働時間)を越えて、どれだけ(剰余労働時間を)延長されうるのでしょうか?
この部分のフランス語版を参考のために紹介しておきます。以下、それぞれに該当するフランス語版をまず紹介することにします。
〈1労働日とはなにか? 1日だけ資本によって価値が買われる労働力を、資本が消費する権利のある時間の長さとは、なんであるか? 労働日は、労働力の再生産に必要な労働を越えてどの点まで延長できるか? 〉 (江夏・上杉訳267頁)
「1労働日というのは何か」という問題は、すでに第1節で問題にされました。まずマルクスは最初に労働日の最小限を規定し、それは資本主義的生産様式のもとでは必要労働時間までに短縮されることはないとしました。つまり剰余労働時間がなくなればそれはもはや資本主義的生産ではないのだということです。
ではその最大限はというと、それは二重に規定されているとしました。一つは純粋に肉体的な制限です。休息、睡眠、食事をするなどの肉体的な諸欲求を満たすために必要な時間がまず労働日を制限します。さらにそれに加えて社会的・慣行的な諸制限があります。知的及び社会的な諸欲求の充足のための時間がそれです。それらが1日の労働時間を規制するのだと指摘されたのです。
しかしこうした諸制限そのものは弾力的な性格をもつものであり、だから変動の余地は極めて大きいことも指摘されていました。
そして「1労働日とは何か?」と問いには、〈とにかく、自然の1生活日よりは短い。どれだけ短いのか? 資本家は、この極限〔ultima Thule*〕、労働日の必然的限界については独特な見解をもっている〉と述べていました。このパラグラフではその〈独特な見解〉がより詳しく検討されます。
(ニ)(ホ) これらの問いにたいして、すでに第1節で見ましたように、資本は次のように答えます。労働日は、毎日、まる24時間から、労働力がその役だちを繰り返すために絶対に欠くことのできないわずかばかりの休息時間を引いたものである、と。
同じくまずフランス語版です。
〈これらすべての問いにたいしては、すでに見ることができたように、資本はこう答える。労働日とは、まる24時間から、労働力がその役立ちを再開するために絶対に欠くことのできない少しばかりの休息時間を、差し引いたものである。〉(江夏・上杉訳267頁)
第1節では資本家はただ資本の人格化であり、資本としては〈自分を価値増殖し、剰余価値を創造し、自分の不変部分、生産手段でできるだけ多量の剰余労働を吸収しようとする衝動である〉とだけ指摘されていました。だから資本にとっては1日の生活時間を可能な限り労働時間として使用したいわけです。しかし労働力がただ1日の使用でダメになってしまってはもともこうもないわけですから、そうならないための必要最低限の休息時間を除いたものが、資本にとっての1日の労働時間であり、1労働日だということになるわけです。
(ヘ)(ト) まず第一に資本にとって自明なことは、労働者は彼の一生活日の全体をつうじて労働力以外のなにものでもないということです。たがら彼の処分しうる時間はすぺて自然的にも法的にも労働時間であり、したがって資本の自己増殖のためのものだということです。人間的教養のためや、精神的発達のためや、社会的諸機能の遂行のためや、あるいは社交のための、要するに肉体的および精神的生命力の自由な営みのための時間などは、日曜の安息時間でさえも--そしてたとえ安息日厳守の国においてであろうと--ただふざけたことでしかない! ということです。
フランス語版です。
〈自明なことだが、労働者は自分の生涯を通じて労働力以外のなにものでもなく、したがって、自分の自由にできる時間はすべて、法的にも自然的にも、資本および資本化することに属している労働時間である。教育のための、知的発展のための、社会的職分の遂行のための、親戚や友人との交際のための、肉体力や精神力の自由な活動のための時間は、日曜日の聖餐式のための時間でさえも--しかも主日を聖なるものとして祝う国(71)で--、全く愚にもつかぬことである! 〉(江夏・上杉訳267頁)
ここからはすべて「資本にとっては」という前提が省かれていますが、あくまでも資本にとっては、資本からみれば、という前提のもとに言われています。
第一に自明なことは、資本はまる1日分の労働力を買ったのですから、まる1日の労働力の使用権を得たわけです。だから労働者の1日の生活時間のすべては労働力以外の何ものでもないということです。だから労働者が自由にできる時間もすべて、法的にも自然的にも、資本のための労働時間なのだということです。労働者が人間的教養や精神的発達のためや、社会活動に参加するための時間など、要するに肉体的・精神的な生命力の自由な営みと発展のための時間などは、資本にとってはとんでもないということです。これはキリスト教国でも、日曜礼拝のための時間さえも、資本にとってはとんでもないということなのです。
(チ)(リ)(ヌ)(ル) ところが、資本は、剰余労働を求めるその無際限な盲目的な衝動、その人狼的渇望をもって、労働日の精神的な最大限度だけではなく、純粋に肉体的な最大限度をも踏み越えます。資本は、身体の成長のためや発達のためや健康維持のための時間を横取りします。資本は、外気や日光を吸うために必要な時間をも取り上げます。資本は、食事時間をへずり、できればそれを生産過程そのものに合併しようとします。
フランス語版です。
〈ところが、資本は、剰余労働をもとめるその過度な盲目的熱情のあまり、その貧欲のあまり、たんに労働日の精神的限度ばかりでなく、さらにその肉体的な極限をも踏み越える。資本は、身体の成長や発育や健康維持が必要とする時間を横取りする。資本は、外気を吸い日光を享受するのに用いられるべき時間を奪う。資本は食事の時間を出し惜しみ、この時間をできるかぎり生産過程そのものに合体させる。〉(江夏・上杉訳267-268頁)
だから資本はその剰余労働を求める際限のない欲求や盲目的な情熱や貪欲さのあまり、労働日の肉体的な社会的な制限されえをも踏み越えるのです。第3節で詳しく見てきましたように、資本は、児童を苛酷な労働に酷使して、その成長や発育や健康維持に必要な時間をも横取りしました。縫製労働者を狭い空間に押し込めて、夜間労働を強いて、外気に触れ日光を享受する時間さえも奪って来たのです。おまけに食事時間さえも削って、それを生産過程に合併しようとしてきました。
(ヲ)(ワ)(カ) だから、ただの生産手段でしかない労働者に食物があてがわれるのは、ボイラーに石炭が、機械に油脂が加えられるようなもなのです。生命力を集積し更新し活気づけるための健康な睡眠を、資本は、まったく疲れきった有機体の蘇生のためにどうしても欠くことのできない時間だけの麻痺状態に圧縮します。ここでは労働力の正常な維持が労働日の限界を決定するのではなく、逆に、労働力の1日の可能なかぎりの最大の支出が、たとえそれがどんなに不健康で無理で苦痛であろうとも、労働者の休息時間の限界を決定するのです。
フランス語版です。
〈したがって、単なる労働手段の役に引き下げられた労働者には、ボイラーに石炭が、機械に油や獣脂が供給されるように、食物が供給される。資本は、生命力を更新して元気を回復させるのに充てられる睡眠時間を、鈍感な麻痺状態の最低時間--この最低時間を欠いては、使い果たされた有機体はもはや機能することができない--に圧縮する。労働力の正常な維持が労働日の制限にたいする掟として役立つどころか、逆に、労働力の一日の最大限の支出が、それがどんなにはげしくどんなに骨の折れるものであろうとも、労働者の休息時間の限界を規定する。〉(江夏・上杉訳268頁)
そもそも労働者は資本にとっては剰余労働を吸収するための手段でしかありません。資本にとっては労働者も機械や道具や役畜と同じ生産のための手段でしかないのです。だから労働者に食事を与えるのは、役畜に飼料をあたえ、機械に油を指し、ボイラーに石炭をくべるのと同じことなのです。
だから同じように、労働者の生命力を更新して活気づかせるために必要な睡眠も、資本にとってはただどんなに疲れ切っていたとしてもとにかく人間有機体の生命が維持されていればよいだけのものに鈍感な麻痺状態になるような最低限まで削ろうとするのです。
だから第1節で見ましたように、労働力の正常な維持を保証することが(肉的的・社会的な制限が)労働日を制限するのではなくて、労働力の1日の最大限の支出が、とにかく徹底的にそこから剰余労働をしぼれるだけしぼることが、労働者の休息時間を規制するという逆転した関係を作り出すのです。
(ヨ)(タ)(レ) 資本は労働力の寿命を問題にしません。資本が関心をもつのは、ただただ、1労働日に流動化されうる労働力の最大限だけです。資本が労働力の寿命の短縮によってこの目標に到達しようとするのは、ちょうど、貧欲な農業者が土地の豊度の略奪によって収穫の増大に成功しようとするようなものです。
フランス語版です。
〈資本は労働力の寿命を少しも気にかけない。資本がもっぱら関心をもつものは、1日のうちに支出することのできる労働力の最大限である。そして資本は、労働者の寿命を短縮することでその目的を達成するが、このことは、貧欲な耕作者が土地の沃度を汲みつくすことでその土地からもっと多量の収穫を得るのと同じである。〉(江夏・上杉訳268頁)
だから資本の本性を自由気ままに任せていれば、それは交換価値の法則をも踏み越えて、労働力の価値を越えてしまいます。資本は労働力の寿命などには少しも気にはしません。本来は労働力の価値は労働者が20年なら20年のあいだ同じ労働力として維持され再生産されることが、その労働力の価値の規定には含まれているはずですが、資本はそんなことはまったく気にしないのです。とにかく資本にとって最大の関心事は、1日のうちに支出できる労働を可能な限り絞り出すということです。だからその結果、労働者の寿命が短縮しようがそんなとこは資本のあずかり知らないことなのです。それは資本主義的農業が収奪農業であるのとよく似ています。つまり土地の肥沃度を当面の生産で汲み尽くして荒廃させても、とにかく当面の収穫を最大限得ようとする農業と同じなのです。
この第1パラグラフではまず資本の本質的な性向を確認しています。資本にとって剰余労働を最大限吸収することこそがその本性であり、だからこの資本の本性をそのままにすれば、労働日の限界などは無きに等しいことになるということが、まず確認されているわけです。
◎原注104
【原注104】〈104 (イ)たとえばイギリスでは、今でもまだあちこちの農村で、自宅の前の小園で労働して安息日を冒したというかどで労働者に禁固刑が宣告されることがある。(ロ)同じ労働者が、たとえ信仰上の気まぐれからであろうと、日曜に金属工場とか製紙工場とかガラス工場とかを休めば、彼は契約違反で処罰されるのである。(ハ)正統派の議会も、安息日の冒涜が資本の「価値増殖過程」で行なわれる場合には、耳にふたをしている。(ニ)ロンドンの魚屋や鳥屋の旦雇い人たちが日曜労働の廃止を要求しているある陳情書(1863年8月)のなかでは、彼らの労働は週の初めの6日間は毎日平均15時間で、日曜は8時間から10時間だと言っている。(ホ)この陳情書からは、同時に、エクセター・ホール〔77〕の貴族的な偽信者たちの気むずかしい食道楽がことにこの「日曜労働」を激励するということも推測される。(ヘ)これらの「聖者たち」は、「自分のからだをだいじにすることでは」〔“in cute curanda"〕あんなに熱心でありながら、第三者の過度労働や窮乏や空腹には忍従の精神をもって堪えるということによって、彼らのキリスト教の信仰を証明するのである。満腹は君たち(労働者)には大いに害がある。〔Obseqium venteis istis peniciosius est.〕〉(全集第23a巻347頁)
(イ)(ロ)(ハ) たとえばイギリスでは、今でもまだあちこちの農村で、自宅の前の小園で労働して安息日を冒したというかどで労働者に禁固刑が宣告されることがあります。同じ労働者が、たとえ信仰上の気まぐれからであろうと、日曜に金属工場とか製紙工場とかガラス工場とかを休みますと、彼は契約違反で処罰されるのです。正統派の議会も、安息日の冒涜が資本の「価値増殖過程」で行なわれる場合には、耳にふたをしているのです。
これは〈人間的教養のための、精神的発達のための、社会的諸機能の遂行のための、社交のための、肉体的および精神的生命力の自由な営みのための時間などは、日曜の安息時間でさえも--そしてたとえ安息日厳守の国においてであろうと(104)--ただふざけたことでしかない! 〉という一文に付けられた原注です。
〈正統派の議会も、安息日の冒涜が資本の「価値増殖過程」で行なわれる場合には、耳にふたをしている〉という部分はフランス語版では〈正教派である議会は、安息日の冒涜が「資本という神」の名誉と利益のために行なわれるばあい、この冒涜を気にかけない〉(江夏・上杉訳268頁)となっています。
つまり安息日厳守のキリスト教の国でも、いざ資本の剰余価値に対する貪欲さにはたちうちできないということです。
当時のイギリスの保守的な農村地域では、中世の残滓として、安息日に自宅にある小さな農園で労働したことが、安息日を冒したとして禁固刑に処されるところもあったということですが、しかし同じ労働者が日曜日でも工場で働くことを強要され、それを安息日だからと休んだとしたら、たちまち契約違反で罰さられるということです。つまり正教派である議会(イギリス語版では〈この古き伝統を守る議会〉とある)も、「資本という神」の前には、キリスト教の教義もへったくれもないということです。
(ニ)(ホ)(ヘ) ロンドンの魚屋や鳥屋の旦雇い人たちが日曜労働の廃止を要求しているある陳情書(1863年8月)のなかで、彼らの労働は週の初めの6日間は毎日平均15時間で、日曜は8時間から10時間だと言っています。この陳情書からは、同時に、エクセター・ホールの貴族的な偽信者たちの気むずかしい食道楽が、ことにこの「日曜労働」を激励するということも推測されます。これらの「聖者たち」は、「自分のからだをだいじにすることでは」〔“in cute curanda"〕あんなに熱心でありながら、第三者の過度労働や窮乏や空腹には忍従の精神をもって堪えるということによって、彼らのキリスト教の信仰を証明するのです。満腹は君たち(労働者)には大いに害がある、と。〔Obseqium venteis istis peniciosius est.〕
ロンドンの魚や家禽の商店で雇われている日雇人たちが日曜労働の廃止を訴えた陳述書によれば、彼らは平日は毎日平均15時間、日曜日でも8から10時間も働かされているということです。そしてこの陳述書から分かることは、この安息日の禁を破ることを奨励しているのは、なによりもエクスター・ホール(ロンドンにある宗教団体や慈善団体の集会が催される所)の貴族的な偏狭な信者たちの気難しい食道楽だというのです。彼らは「自分たちの身体ことに気を配る」ことには熱心ですが、第三者、つまり労働者の過度労働や窮乏や空腹には忍従の精神でもって耐えることで(つまり無関心を装うことで)、自分たちのキリスト教徒としての身分を証明しているのです。美食は君たちには(つまり労働者には)有害である、と。
新日本新書版にはいくつかの訳者注がついています。
まず〈エクセター・ホール〉については、〈ロンドン中心部のストランド街にある宗教団体や慈善団体の集会所、現在はホテル〉(457頁)との説明があります。また全集版には注解77が付いていて〈エクセター・ホール--ロンドンにある建物で、宗教団体や慈善団体の集会所。〉(全集第23a巻末15頁)とあり、フランス語版では本文中に訳者注が挿入されていて、〈ロンドンにある宗教団体や慈善団体の集会所〉(286頁)とあります。
次に〈「自分のからだをだいじにすることでは」〔“in cute curanda"〕〉という部分については〈ホラティウス『書簡体詩』、第1巻、詩II、第29行より〉(457頁)という説明があります。
〈満腹は君たち(労働者)には大いに害がある。〔Obseqium venteis istis peniciosius est.〕〉という部分についても〈ホラティウス『風刺詩』、第2巻、詩Ⅶ、第1040行の言い換え。鈴木一郎訳、『世界文学体系』67、筑摩書房、190ページ参照〉(457頁)という説明があります。
◎第2パラグラフ(剰余労働を吸収しようとする資本主義的生産の本質的傾向は、労働者の寿命をまでも縮めても、生産時間を延長しようとする)
【2】〈(イ)つまり、本質的に剰余価値の生産であり剰余労働の吸収である資本主義的生産は労働日の延長によって人間労働力の萎縮を生産し、そのためにこの労働力はその正常な精神的および肉体的な発達と活動との諸条件を奪われるの/であるが、それだけではない。(ロ)資本主義的生は労働力そのものの早すぎる消耗と死滅とを生産する(105)。(ハ)それは、労働者の生活時間を短縮することによって、ある与えられた期間のなかでの労働者の生産時間を延長するのである。〉(全集第23a巻347-348頁)
(イ)(ロ)(ハ) つまり、本質的に剰余価値の生産であり剰余労働の吸収である資本主義的生産は労働日の延長によって人間労働力の萎縮を生産し、そのためにこの労働力はその正常な精神的および肉体的な発達と活動との諸条件を奪われるのですが、それだけではありません。資本主義的生は労働力そのものの早すぎる消耗と死滅とを生産します。それは、労働者の生活時間を短縮することによって、ある与えられた期間のなかでの労働者の生産時間を延長するのです。
だから、資本主義的生産というのは本質的に剰余価値の生産であり、剰余労働の吸収ですから、それは際限のない労働者に対する搾取欲として現れます。だからそれは労働日の延長によって労働者の精神的なあるいは肉体的な発達と活動との諸条件を奪い、さらには労働力の早すぎる消耗と死滅をもたらすのです。資本主義的生産は、労働者の寿命を縮めても、ある期間の労働者の生産期間を引き延ばそうとするのです。これこそが資本主義的生産の本質的傾向であり、結果なのです。
ここで〈それは、労働者の生活時間を短縮することによって、ある与えられた期間のなかでの労働者の生産時間を延長するのである〉という部分は、新日本新書版では〈それは、労働者の生存期間を短縮することによって、ある与えられた諸期限内における労働者の生産時間を延長する〉(457頁)となっています。フランス語版でも〈それは、労働者の寿命を縮めることによって、ある期間内での彼の生産期間を延長する〉(269頁)となっています。つまり〈生活時間〉というのはあまり適訳ではないということです。
((2)に続く。)











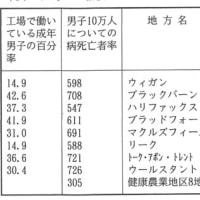
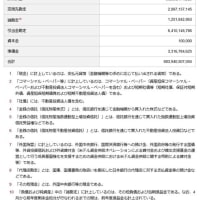

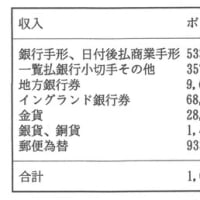
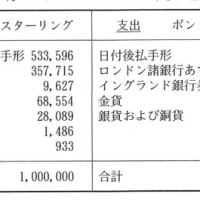
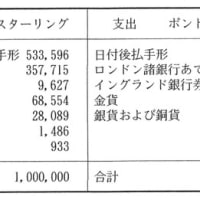
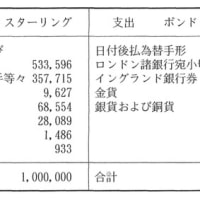
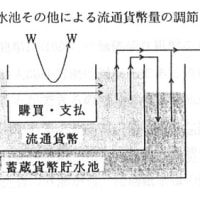






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます