『資本論』学習資料No.35(通算第85回)(4)
◎第20パラグラフ(製パン業の続き。アイルランドの製パン職人)
【20】〈1858-1860年には、アイルランドの製パン職人は、夜間労働と日曜労働とに反対する運動のための大集会を自費で組織した。公衆は、たとえば1860年のダブリンの5月集会で、アイルランド人的熱情で彼らに味方した。この運動によって、ウェクスフォード、キルケニー、クロンメル、ウォータフォード、等々では夜間労働なしの昼間労働が実際に首尾よく実現された。
「賃職人の苦痛が人も知るようにあらゆる限度を越えていたリメリクでは、この運動は、製パン親方、ことに製パン兼製粉業者の反対にあって失敗した。リメリクの実例は、エニスやティペラリでの敗退を招いた。公衆の不液が最も激しい形で表明されたコークでは、親方たちは、職人を追い出すという自分たちの権力の行使によってこの運動を失敗に終わらせた。ダブリンでは親方たちは最も頑強に抵抗し、運動の先頭に立った職人たちをい、じめることによって、そのほかのものに譲歩を強制し、夜間労働と日曜労働に服すること、を強制した(84)。」
アイルランドですきまなく武装していたイギリス政府の委員会も、ダブリンやリメリクやコークなどの無情な製パン親方たちにたいしてはただ哀れっぼく抗議して次のように言うのである。
「本委員会の信ずるところでは、労働時間は自然法則によって制限されているのであって、この法則は罰なしに犯されるものではないのである。親方たちが彼らの労働者に、その宗教的信念にたいする違背や国法の侵犯や世論の無視を、追放という威嚇をもって強制することによって」(宗教的信念にたいする違背などということはすべて日曜労働に関するものである)「彼らは資本と労働とのあいだに悪意を起こさせ、また宗教や道徳や公共の秩序にとって危険な一例を与えるものである。……本委員会の信ずるところでは、12時間を越える労働日の延長は労働者の家庭的および私的生活の横領的侵害であり、また、1人の男の家庭生活を妨害し、息子、兄弟、夫、父としての彼の家族義務の遂行を妨害することによって、有害な道徳的結果を招くものである。12時間を越える労働は、労働者の健康を破壊する傾向があり、早老や若死にを招き、したがってまた労働者家族が家長からの世話や扶助をそれが最も必要な時期に奪い取られる(“are deprived") という不幸を招くものである(85)。」〉
このパラグラフは同じ製パン業の問題ですが、それまではロンドンの製パン業だったのが、今回はアイルランドの製パン業が問題になっています。
アイルランドの製パン労働者は、夜間労働と日曜労働に反対して立ち上がり、大衆集会を開いて抗議したということです。その結果、ところによっては夜間労働が禁止されたところもあったということですが、しかし製パン親方の頑強な抵抗にあって挫折させられたということが書かれています。そして『1861年のアイルランド製パン業調査委員会報告書』からの引用がありますが、それは製パン親方に哀れっぽく訴えるような内容でしかないことが指摘されています。
ここで〈アイルランドですきまなく武装していたイギリス政府の委員会も〉というのがいま一つピント来ませんが、新日本新書版では、この部分は〈イギリス政府はアイルランドにおいて寸分のすきなく武装しているのであるが、〉となっています。ついでに初版とフランス語版、イギリス語版も紹介しておきましょう。
〔初版〕〈アイルランドで完全武装していたイギリス政府の委員会は、〉
〔フランス語版〕〈アイルランドで全身武装していたイギリス政府の委員会は、〉
〔イギリス語版〕〈英国政府委員会は、その政府は、アイルランドで、歯に至るまで武装して、そのことをいかに示すかをよく知っていたのだが、〉
どうもよく分かりませんが、イギリス語版が一番分かりやすいような気がします。イギリス語版はこのあとも部分も続けて紹介しますと、次のようになっています。
〈英国政府委員会は、その政府は、アイルランドで、歯に至るまで武装して、そのことをいかに示すかをよく知っていたのだが、柔らかく、あたかも葬式に参列したかのような声色で、容赦しようともしないダブリン、リメリック、コーク他の、製パン親方達に次の様に忠告した。〉
要するにイギリス政府はアイルランドに対しては完全武装して望むほど強権的に対応するのですが、製パン労働者の過度労働の問題に関しては、アイルランドの製パン業の容赦のない親方たちに対して、ただへりくだって、哀れっぽくお願いするだけなのだ、ということではないでしょうか。つまり〈すきまなく武装していた〉という文言は、〈ただ哀れっぼく抗議して次のように言う〉という文言に対比させるためのものではないかと思います。
◎注84.85
【84.85】〈84 『1861年のアイルランド製パン業調査委員会報告書』。
85 同前。〉
これは第20パラグラフに出てくる二つの引用の典拠を示すものです。
◎第21パラグラフ(スコットランドの農業労働者の闘いとロンドンの鉄道労働者の過度労働)
【21】〈われわれは今までアイルランドにいた。海峡の向こう側、スコットランドでは、農業労働者が、この黎(スキ)を扱う男が、酷烈きわまる風土のさなかで日曜の4時間の追加労働(この安息日のやかましい国で!)をともなう彼の13時間から14時間の労働を訴えており(86)、同時に他方ではロンドンの大陪審の前に3人の鉄道労働者が、すなわち1人の乗客車掌と1人の機関手と1人の信号手とが立っている。ある大きな鉄道事故が数百の乗客をあの世に輸送したのである。鉄道労働者の怠慢が事故の原因なのである。彼らは陪審員の前で口をそろえて次のように言っている。10年から12年前までは自分たちの労働は1日にたった8時間だった。それが最近の5、6年のあいだに14時間、18時、20時闘とねじあげられ、そして遊覧列車季節のように旅行好きが特にひどく押し寄せるときには、休みなしに40-50時間続くことも多い。自分たちも普通の人間であって巨人ではない。ある一定の点で自分たちの労働力はきかなくなる。自分たちは麻痺に襲われる。自分たちの頭は考えることをやめ、目は見ることをやめる。あくまで「尊敬に値するイギリスの陪審員」〔“respectable British Juryman"〕は、彼らを「殺人」〔“manslaughrer"〕のかどで陪審裁判に付するという評決を答申し、一つの穏やかな添付書のなかで次のようなつつましやかな願望を表明する。鉄道関係の大資本家諸氏は、どうか将来は、必要数の「労働力」の買い入れではもっとぜいたくであり、代価を支払った労働力の搾取では「もっと節制的」か「もっと禁欲的」か「もっと倹約的」であってもらいたい、と(87)。〉
先のパラグラフではアイルランドの製パン労働者の闘いが紹介されていますが、今度はスコットランドの農業労働者が、やはり酷烈な気候のなかでの長時間労働を訴えて立ち上がっているということです。
またロンドンの鉄道事故がセンセーショナルに報じられたが、事故の背景には鉄道労働者の過酷な労働の実態があることが裁判のなかで明らかになったことが紹介されています。にも関わらず、鉄道労働者の労働条件の改善が指示されるのではなく、この場合も、陪審員はただ鉄道会社の資本家に労働力の搾取ではもっと禁欲的で倹約的であって欲しいとお願いするだけだったということです。
〈彼らを「殺人」〔“manslaughrer"〕のかどで陪審裁判に付するという評決を答申し〉という部分は、新日本新書版では〈彼らを「“故殺"*」のかどで陪審裁判に付すという票決でもって答え〉となっていて、次のような訳者注がついています。
〈* 過失致死など、殺意なく不法に人を殺すこと。「謀殺」の反対語。〉(434頁)
因みに初版は〈“manslaughrer"(殺人罪)〉、フランス語版は〈過失致死〈manslaughrer〉〉、イギリス語版は〈殺人の罪〉になっています。
◎注86
【86】〈86 1866年1月5日の、グラスゴーに近いラスウェードでの農業労働者の公開集会。(1866年1月13日の『ワータマンズ・アドヴォケート』紙を見よ。)1865年末以来、まずスコットランドで、農業労働者のあいだに労働組合が結成されたことは、一つの歴史的な事件である。イングランドの最も抑圧されていた農業地方の一つであるバッキンガムシャでは、1867年3月、賃金労働者が、週賃金を9-10シリングから12シリングに引き上げさせるための一大ストライキを行なった。--(前述のことからもわかるように、イギリスの農業プロレタリアートの運動は、1830年のあとの彼らの激しい示威運動が鎮圧されてからは、また、ことに新たな救貧法の実施以後は、まったく中絶していたが、60年代には再び始まって、ついに1872年に至って画期的なものになるのである。この点には第2巻で立ち帰ることにするが、同様に、イギリスの農村労働者の状態について1867年以来刊行されている青書にもそこで言及することにする。第3版への補足。)〉
これは〈海峡の向こう側、スコットランドでは、農業労働者が、この黎(スキ)を扱う男が、酷烈きわまる風土のさなかで日曜の4時間の追加労働(この安息日のやかましい国で!)をともなう彼の13時間から14時間の労働を訴えており(86)〉という本文に付けられた原注です。
ここで〈グラスゴーに近いラスウェードでの〉という部分は新日本新書版では〈エディンバラ*近くのラウスウェイドにおける〉となっていて、次のような訳者注が付いています。
〈*ドイツ語原本では、初版以来「グラスゴウ」となっているが、誤り。各国語版では訂正されている。ラスウェイドはエディンバラ南東の村〉(434頁)
因みに初版やフランス語版は同じですが、イギリス語版では訂正されています。なお初版やフランス語版ではこの原注は最初の部分だけで(〈……一つの歴史的な事件である。〉までで)短いものになっています(付属資料参照)。
〈イングランドの最も抑圧されていた農業地方の一つであるバッキンガムシャでは、……〉以下の部分はマルクスの第三版への追加によることが新日本新書版では訳者注として挿入されています。
つまりこの原注そのものは第22パラグラフのスコットランドの農業労働者の闘いについて、その情報原を示すととにも、スコットランドで農業労働者のあいだで労働組合が結成されたことの歴史的意義を確認するものだったのですが、その後、それに関連して、イングランドの農業労働者の闘いも付け加えられたということのようです。
そしてさらに( )に入れた追加がなされたことが分かります。この括弧内の文章は、イギリスの農業労働者の闘いは、1830年の激しい示威運動が鎮圧されたあと、さらに救貧法が実施されたあとは、鎮静していたが、それが再び運動が始まり1872年に至って画期的なものになったと書かれています。
〈救貧法〉の部分は新日本新書版では〈救貧法*〔1834年〕〉となっていて、つぎのような訳者注がついています。
〈* 救貧法は、イギリスの貧民救済と取り締まりを目的とした、16世紀にはじまる法律。貧民に救済を与える一方で、労働能力のある者を強制労働させる労役場を教区に設け、そこで働かぬ者は浮浪者として苛酷に取り締まった。〉(434頁)
また新日本新書版では〈この点には第2巻で立ち帰ることにするが、同様に、イギリスの農村労働者の状態について1867年以来刊行されている青書にもそこで言及することにする。〉という部分にも訳者による次のような挿入文があります。
〈現行版の『資本論』の第2部および第3部には、この記述は見あたらない。〉(433頁)
つまりマルクスはこのように〈第2巻で立ち帰る〉と書いていますが、実際にはそれに該当すものは見あたらないのだそうです。
◎注87
【87】〈87 『レノルズ・〔ニューズ〕ペーパー』、1866年1月〔21日〕。引き続いて、同じ週刊紙は毎週のように『恐ろしい大事故』、『戦標の悲劇』などという「センセーショナルな見出し」のもとにたくさんの新しい鉄道事故を報道している。これに答えてノース・スタフォード線の一労働者は次のように言っている。「機関手や火夫の注意が一瞬でもゆるめばその結果がどうなるかは、だれでも知っている。そして、ひどい悪天候のなかで休むひまもなく無制限に労働を延長されては、どうしてそうならずにいられようか? 毎日現われる一例をあげれば、次のようなことがある。今週の月曜、ある火夫が早朝から彼の1日の仕事を始めた。彼は14時間50分後にそれを終わった。茶を飲むひまさえなく、彼はまたもや仕事に呼び出された。こうして、彼は29時間15分のあいだ絶えまなしに労苦を続けなければならなかった。彼の1週間の仕事の残りは次のように組まれていた。水曜15時間、木曜15時間35分、金曜14時間半、土曜14時間10分。1週間分合計88時間30分。そこで、彼がたった6労働日分の支払しか受け取らなかったときの彼の驚きを想像せよ。この男は新まいだったので、1日の仕事とはなんのことか、と尋ねた。答え、13時間、だから1週間では78時間。では余分の10時間40分にたいする支払はどうなるのか? 長い争論のあげくに、彼は10ペンス」(10銀グロシェンにも足りない)「の手当を受け取ったのである。」同前、1866年2月4日号。〉
これは第21パラグラフの後半部分の鉄道事故とそれに関する鉄道労働者の裁判所での陳述の内容の情報源を示すものですが、同時にそれに関連する鉄道労働者の追加的な言及が取り上げられています。それを見ると鉄道労働者の苛酷な労働の実態が具体的に暴露されています。
◎第22パラグラフ(さらなる過度労働の二つの具体例)
【22】〈殺された人々の霊がオデュッセウスのもとに押しかけたよりももっと熱心にわれわれのところに押しかけてくる、そして腕に抱えた青書がなくても一目で過度労働の色が見てとれる、あらゆる職業とあらゆる年齢と男女両性の色とりどりの労働者群のなかから、われわれはさらに二人の人物を取り出してみよう。この二人がなしている著しい対照は、資本の前では万人が平等だということを示している。それは、婦人服製造女工と鍛冶工である。〉
このパラグラフは、それまで見てきた過度労働の数々の例を振り返りつつ、さらに二つの例を見てみようとする繋ぎのパラグラフといえます。
全集版より初版やフランス語版の方が分かりやすいので、両方を紹介しておきましょう。
〔初版〕〈打ち殺された人々の霊が、オデュッセウス〔ギリシアの伝説上の英雄〕のもとに群れをなして押しかけたよりももっと熱心に、われわれのところに群れをなして押しかけてくるし、小脇にかかえた青書を見なくても一目で超過労働が察せられるというような、ありとあらゆる職業とあらゆる年齢の男女から成る雑多な労働者群のなかから、われわれはさらに、2人の人物--この2人の人物の顕著な対照が、すべての人間は資本の前では平等であるということを、示しているのだが--、婦人服裁縫女工と鍛冶工とを、選び出してみよう。〉(江夏訳277頁)
〔フランス語版〕〈地獄でオデュッセウス〔ギリシアの伝説上の英雄〕の前に現われた死の亡霊よりもさらに数多くわれわれの前に現われ、その小脇に抱えた青書を開かなくても一見して過度労働の跡が認められるような、あらゆる職業とあらゆる年齢と男女両性の労働者の雑多な群衆のなかから、われわれはついでにもう2人の人物を取り上げよう。この2人の顕著な対照が、すべての人間は資本の前で平等である、ということを証明してくれる人物--婦人服製造女工と鍛冶工--を。〉(江夏・上杉訳254頁)
ついでに訳者注がついている新日本新書版も紹介しておきます。
〈あらゆる職業、性からなる労働者たちの種々雑多な群れが、オデュッセウスに群がり寄る打ち殺された人々の魂魄(*)よりもずっと熱心にわれわれのところに群がり寄る。そしてその小わきにかかえた青書を見なくても一目で彼らの過度労働が見てとれる、この群れのなかからわれわれは、さらにもう二人の人物--婦人服仕立女工と鍛冶工とを取り出そう。彼らのいちじるしい対照ぶりは、資本の前での万人が平等であることを実証するのである。
*〔ホメロス『オデュッセイア』、第11書、第34行以下。呉茂一訳、岩波文庫、上、326ページ以下。冥界に着いたオデュッセウスが羊の血をいけにえにささげ、亡母や戦死者などの霊を呼び出し、それと語り合う場面をさす〕〉(434-435頁)
これまで見てきたさまざまな過度労働によって殺されてきたあらゆる年齢や男女を問わない労働者たちの群れの魂は私たちの胸を打ちますが、さらに二人の人物(婦人服縫製工と鍛冶工)の例を取り上げようということです。
◎第23パラグラフ(20歳の婦人服製造女工メアリ・アン・ウォークリの死亡の例)
【23】〈1863年6月の最後の週に、ロンドンのすべての日刊新聞は、『単なる過度労働からの死亡』〔“Death from simple Overwork"〕という「センセーショナル」な見出しの記事を載せた。それは、ある非常に名声の高い宮廷用婦人服製造所に雇われていて、エリズというやさしい名の婦人に搾取されていた20歳の婦人服製造女工メアリ・アン・ウォークリの死亡に関するものだった。何度も語られた古い話が今また新たに発見されたのであって(88)、これらの娘たちは平均16時間半、だが社交季節にはしばしば30時間絶えまなく労働し、彼女たちの「労働力」がきかなくなると時おりシェリー酒やポートワインやコーヒーを与えられて活動を続けさせられるというのである。そしてそれはちょうど社交季節の盛りのことだった。新しく輸入されたイギリス皇太子妃のもとで催される誓忠舞踏会のための貴婦人用衣装を一瞬のうちにつくりあげるという魔術が必要だった。メアリ・アン・ウォークリは、ほかの60人の娘たちといっしょに、必要な空気容積の3分の1も与えないような一室に30人ずつはいって、26時間半休みなく労働し、夜は、一つの寝室をいくつかの板壁で仕切った息詰まる穴の一つで一つのベッドに2人ずつ寝た(89)。しかも、これは、ロンドンでも良いほうの婦人服製造工場の一つだったのである。メアリ・アン・ウォークリは金曜に病気になり、そして、エリズ夫人の驚いたことには、前もって最後の1着を仕上げもしないで日曜に死んだ。遅ればせに死の床に呼ばれた医師キーズ氏は、「検屍陪審」〔“Coroner's Jury"〕の前で率直な言葉で次のように証言した。
「メアリ・アン・ウォークリは詰め込みすぎた作業室での長い労働時間のために、そして狭すぎる換気の悪い寝室のために、死んだのだ。」
この医師に礼儀作法というものを教えるために、この証言にたいして「検屍陪審」は次のように言明した。
「死亡者は卒中で死んだのであるが、その死が人員過剰な作業場での過度労働などによって早められたのではないかと考えられる理由はある。」
われわれの「白色奴隷は」、と自由貿易論者コブデン、ブライト両氏の機関紙『モーニング・スター』は叫んだ、「われわれの白色奴隷は、墓にはいるまでこき使われ、疲れ果てて声もなく死んで行くのだ(90)。」〉
このパラグラフは先のパラグラフで言及するとしていた〈二人の人物〉の例うち〈婦人服製造女工〉の場合です。
ここでは1863年6月にさまざまな日刊紙にどぎつい見出しで記事になった婦人服製造女工メアリ・アン・ウォークリの過度労働による死亡について、それらの報道の内容を紹介する形で書かれています。『61-63草稿』の注解ではこのニュースを報じた新聞について、次のような指摘があります。
〈〔注解〕……1863年6月にロンドンの新聞(とりわけ1863年6月24日付の『ザ・タイムズ』の“Worked to death…"という〔書き出しの〕記事、7ページ5段、同じく“Ten days ago…"という〔書き出しの〕記事、11ページ5段および6段、1863年6月23日付の『モーニング・スター』の記事「われわれの白色奴隷」、4ページ6段-5ページ1段)は、婦人服製造女工メアリ・アン・ウォークリの過度労働による死亡について報じた。〉 (草稿集④282頁)
そこには婦人服製造女工の恐ろしいほどの過度労働の実態が生々しく描かれています。彼女らは30時間も休みなしに働かされ、しかも必要な空気容積もないような部屋で働き、とうとうメアリ・アン・ウォークリは死んでしまったというものです。
◎注88
【88】〈88 フリードリヒ・エンゲルス『イギリスにおける労働者階級の状態』、253、254ページ参照。〔本全集、第2巻、426-427(原)ページを見よ。〕〉
これは〈何度も語られた古い話が今また新たに発見されたのであって(88)〉という本文につけられた原注です。エンゲルスの『状態』の参照箇所が挙げられています。エンゲルスは手工業では労働はより劣悪な条件でなされているとして、ロンドンの婦人装身具製造女工と縫製女工の例を紹介しています(付属資料参照)。
◎注89
【89】〈89 保健局勤務の医師レズビ博士はその当時次のように言明した。「大人に必要な空気の最小限度は、寝室で300立方フィート、居室で500立方フィートであるべきだ。」ロンドンのある病院の医長リチャードソン博士は次のように言っている。「各種の裁縫女工や婦人服製造女工や衣服製造女工や普通の裁縫女工は三重の困苦に悩んでいる--過度労働と空気不足と栄養不良または消化不良とである。概してこの種の労働は、どんな事情のもとでも、男よりも女のほうに適している。しかし、この営業の害悪は、それが、ことに首都では、26人ほどの資本家に独占されていて、彼らは、資本から生ずる(that spring from capital)権力手段によって、節約を労働からしぼり出す(force economy out of labour;彼の考えている意味では、労働力の乱費によって出費を節約する)ということである。彼らの権力は、この部類の女工全体のあいだで感知される。1人の女裁縫師がわずかな顧客でも獲得できたとすれば、競争は彼女に、客を失わないために自宅で死ぬほど労働することを強制し、そして必然的に彼女は自分の女助手たちにも同じ過度労働を押しつけなければならないのである。彼女の営業が失敗するか、または彼女が独立してやってゆけなくなれば、彼女は、労働がより少ないわけではないが支払が確実であるような店に助けを求める。そうなれば、彼女はただの女奴隷になり、社会の潮のみちひきにつれてあちこちに投げ出される。ある時は自宅の小部屋で飢えているか、または飢えかかっている。その次にはまた24時間のうち15時間か16時間も、じつに18時間も、ほとんど耐えられない空気のなかで働き、その食物は、品質がよい場合でも、きれいな空気が足りないので消化ができない。これらの犠牲によって肺病は生きてゆくのであって、それは一種の空気病にほかならないのである。」(リチャードソン博士『労働と過度労働』、所載、『ソーシァル・サイエンス・レヴェー』、1863年7月18日号。)〉
これは〈これらの娘たちは平均16時間半、だが社交季節にはしばしば30時間絶えまなく労働し、彼女たちの「労働力」がきかなくなると時おりシェリー酒やポートワインやコーヒーを与えられて活動を続けさせられるというのである。そしてそれはちょうど社交季節の盛りのことだった。新しく輸入されたイギリス皇太子妃のもとで催される誓忠舞踏会のための貴婦人用衣装を一瞬のうちにつくりあげるという魔術が必要だった。メアリ・アン・ウォークリは、ほかの60人の娘たちといっしょに、必要な空気容積の3分の1も与えないような一室に30人ずつはいって、26時間半休みなく労働し、夜は、一つの寝室をいくつかの板壁で仕切った息詰まる穴の一つで一つのベッドに2人ずつ寝た(89)〉という本文につけられた原注です。
最初は〈必要な空気容積の3分の1も与えないような一室に30人ずつはいって、26時間半休みなく労働し、夜は、一つの寝室をいくつかの板壁で仕切った息詰まる穴の一つで一つのベッドに2人ずつ寝た〉という本文に関連して、保険局勤務医師のレズビの大人に必要な空気の最小限度なるものが紹介されています。
その次に、ある病院院長のリチャードソンの論文からの引用があり、縫製女工や婦人服製造女工の奴隷労働の実態が述べられています。これらはいずれも当時の労働者が如何に苛酷な労働条件のもとに働かされていたかを示すものです。
◎注90
【90】〈90 『モーニング・スター』、1863年6月23日。『タイムズ』紙は、ブライトたちに反対してアメリカの奴隷主を弁護するためにこの事件を利用した。同紙は次のように言う。「われわれの非常に多くが考えるところでは、われわれがわれわれ自身の若い婦人たちを鞭のうなりのかわりに飢餓の責め苦で死ぬまで働かせているあいだは、われわれには、奴隷主として生まれて自分たちの奴隷を少なくとも良く食わせ適度に働かせている家族に砲火や刀剣を向ける権利は、ほとんどないのである。」(『タイムズ』、1863年7月2日。)同じやり方で、トーリ党の機関誌『スタンダード』〔1863年8月15日〕は、ニューマン・ホール師を罵倒して次のように述べた。「彼は奴隷主たちを破門しているが、ロンドンの御者や乗合馬車の車掌たちを犬なみの賃金で1日にたった16時間労働させるような偉い人たちとは、いっしょに祈りを上げるのだ。」最後に、トマス・カーライル氏が神託を下したのであるが、彼については、私はすでに1850年に次のように述べたことがある(75)。「天才は消え失せ、崇拝が残っている」と。ある短い寓話のなかで、彼は現代史上のただ一つの大事件であるアメリカの南北戦争を、次のようなことに帰着させている。すなわち、北部のピーターは南部のポールの脳天を力いっぱいひっぱたこうとしているが、それというのも、北部のピーターは自分の労働者を「日ぎめ」で雇っているのに、南部のポールはそれを「一生涯雇いきりにしている」からだ、というのである。(『マクミランズ・マガジン』。アメリカの小イリアス、1863年8月号。)こうして、都市の--けっして農村のではない!--賃金労働者にたいするトーリ党的同情のあぶくは、ついにはじけた。その核心はすなわち--奴隷制!〉
これは〈われわれの「白色奴隷は」、と自由貿易論者コブデン、ブライト両氏の機関紙『モーニング・スター』は叫んだ、「われわれの白色奴隷は、墓にはいるまでこき使われ、疲れ果てて声もなく死んで行くのだ(90)。〉という本文に付けられた原注です。
ここでは現在のイギリスの労働者のおかれた状況を、アメリカの黒人奴隷のおかれた状況と対比して、少しも変わらないではないかということを述べているものを『モーニング・スター』と『スタンダード』とカーライルの『マクミランズ・マガジン』紙のなかから引用紹介しています。
『モーニング・スター』の記事は、『タイムズ』紙が自由貿易論者のブライトたちに反対するために、このあわれなメアリ・アン・ウォークリの死を、アメリカの奴隷主を擁護するために利用したと批判しています。つまりイギリス国内でこのような白色奴隷のもとで女工を殺しているわれわれは、少なくとも黒人奴隷を適度に食わせているアメリカの黒人奴隷主達を批判する資格はないというのです。
トーリ党の機関紙『スタンダード』は、同じやり方で、南北戦争のときに北部を支持したニューマン・ホール師を罵倒して、彼はアメリカの奴隷主を破門したが、ロンドンの御者や乗合馬車の車掌たちを犬なみの賃金で働かせる偉い人たちには媚びるだと批判したということです。
最後のトマス・カーライルについてですが、これも南北戦争について、北部の白色奴隷制は労働者を日ぎめで雇っているのに対して、南部の黒人奴隷制は黒人を一生涯雇いきりにしているというだけの違いで、北部は南部を攻めているのだというのです。
マルクスが1850年に〈「天才は消え失せ、崇拝が残っている」〉と述べたと書いていますが、これは『新ライン新聞、政治経済評論』1850年4月、第4号の書評のなかにある「1 トマス・カーライル編『近代論叢』、第1冊『現在』、第2冊『模範刑務所』、ロンドン、1850年」という論文です。言われている箇所は次のようなものです。
〈ちなみに、ドイヅ交学全体のなかで、カーライルにもっとも影響を及ぼしたのは、ヘーゲルではなくて、文学の薬剤師であるジャン・ポールだったことは、特徴的である。
このパンフレットのなかでは、カーライルがシュトラウスとともにしている天才崇拝から、天才がなくなって、崇拝だけが残っている。〉(全集第7巻260頁)
〈最後に、トマス・カーライル氏が神託を下したのであるが〉という部分はフランス語版では〈最後に、天才崇拝〈hero workship〉の発明者であるチェルシイの巫(カンナギ)、トーマス・カーライルが語ったが、〉(江夏・上杉訳256頁)となっています。
〈アメリカの小イリアス〉という部分は、新日本新書版では〈「クルミの殻のなかのアメリカのイリアス*」〉となっていて、次のような訳者注が付いています。
〈* ホメロスの叙事詩『イリアス』全巻がクルミに収まるほどの細字でコピーされたと伝えるプリニウスの記述にもとづくもの〉(438頁)
最後の〈こうして、都市の--けっして農村のではない!--賃金労働老にたいするトーリ党的同情のあぶくは、ついにはじけた。その核心はすなわち--奴隷制!〉という部分は、フランス語版では〈最後に、トーリ党員たちは、彼らの博愛の最後の言葉を述べた。奴隷制! と。〉(江夏・上杉訳256頁)となっています。
要するに都市労働者へのトーリ党の同情というものの本音が透けて見えた、それは奴隷制の擁護だということでしょうか。
◎第24パラグラフ(鍛冶工の例)
【24】〈「死ぬまで労働することは、婦人服製造女工の仕事場だけでのことではなく、幾千の仕事場で、じつに商売の繁昌している仕事場ならばどこでも、日常の事柄である。……鍛冶工を例にとってみよう。詩人の言葉を信じてよいならば、鍛冶工ほど元気で快活な男はない。彼は早朝に起きて、太陽よりもさきに火花を散らす。彼はほかのだれよりもよく食い、よく飲み、よく眠る。ただ単に肉体的に見れば、彼は、労働が適度であるかぎり、じっさい人間の最上の状態の一つにある。だが、われわれは彼について都市に行き、この強い男に負わされる労働の重荷を見てみよう。また、わが国の死亡率表の上で彼がどんな地位を占めているかを見てみよう。マラルボウン」(ロンドンの最大区の一つ) 「では、鍛冶工は毎年1000人につき31人の割合で、またはイギリスの成年男子の平均死亡率よりも11人多い割合で、死んでいる。その仕事は、ほとんど本能的とも言える人間の一技能であって、それ自体としては非難するべきものではないが、それが、ただ労働の過重だけによって、この男を破壊するものになるのである。彼は毎日何度かハンマーを打ちおろし、どれだけか歩行し、どれだけか呼吸し、どれだけか仕事をして、平均してたとえば50年生きることができる。だれかが彼を強制して、どれだけかより多く打たせ、どれだけかより多く歩かせ、1日にどれだけかより多く呼吸させ、全部を合計して彼の生命支出を毎日4分の1ずつ増加させようとする。彼はやってみる。そして結果は、彼がある限られた期間に4分の1たくさんの仕事をして、50歳ではなく37歳で死ぬということである(91)。」〉
このパラグラフは、第22パラグラフで〈あらゆる職業とあらゆる年齢と男女両性の色とりどりの労働者群のなかから、われわれはさらに二人の人物を取り出してみよう〉と述べて、〈婦人服製造女工と鍛冶工〉が挙げられていましたが、第23パラグラフで〈婦人服製造女工〉が取り上げられましたので、今回は〈鍛冶工〉を取り上げるわけです。〈この二人がなしている著しい対照は〉とマルクスが述べているのは、一方は若いが虚弱で肺病病みの女性労働者、他方は一見すると肉体的な健康を誇る肉体労働者という対照的な二人ですが、しかし結局は、〈資本の前では万人が平等だということを示している〉というのです。それはどうしてでしょうか。
このパラグラフはすべて原注89)で引用されていたリチャードソン博士の『労働と過度労働』からの抜粋になっています。
婦人服製造女工の過度労働による死というセンセーショナルな記事がありましたが、しかし死ぬまで労働することはどこでも日常のことであり、同じことだと述べています。そしていかにも健康的な印象を受ける鍛冶工の労働も同じことなのだと述べています。というのは彼らの死亡率が平均より高く、平均年齢も短いことからそれは窺い知れるからだということです。
「過労死」という言葉は、決して昔の話ではなくて、今も“現役"です。まさに資本主義が資本主義であるかぎり、資本の本性は何一つ変わらず、過度労働による死は現実であり続けます。
岸田首相は「異次元の少子化対策」などと言っていますが、「少子化」というのは、資本の搾取が過度になり、必要労働時間の確保さえできなくなってしまったこと、つまり労働力の再生産さえままならなくなってしまっていることを示しています。これが根本的な原因であって、小手先対処で克服できるようなものではないわけです。
◎注91
【91】〈91 リチャードソン博士『労働と過度労働』。所載、『ソーシァル・サイエンス・レヴュー』、1863年7月18日号。〉
これは第24パラグラフで引用されていたものの典拠を示すものです。このリチャードソンの著書は原注89)でも引用されていたものです。
(付属資料に続きます。)











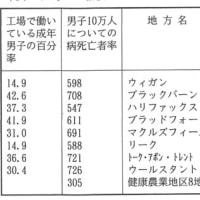
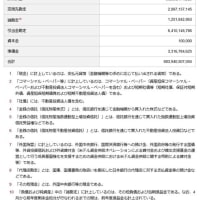

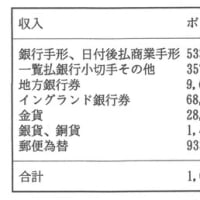
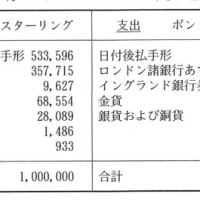
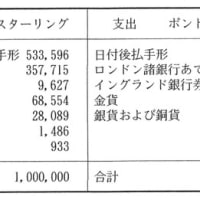
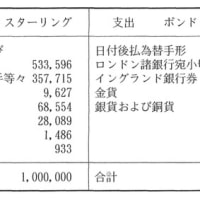
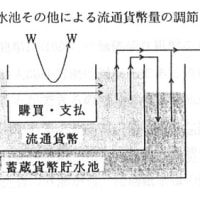






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます