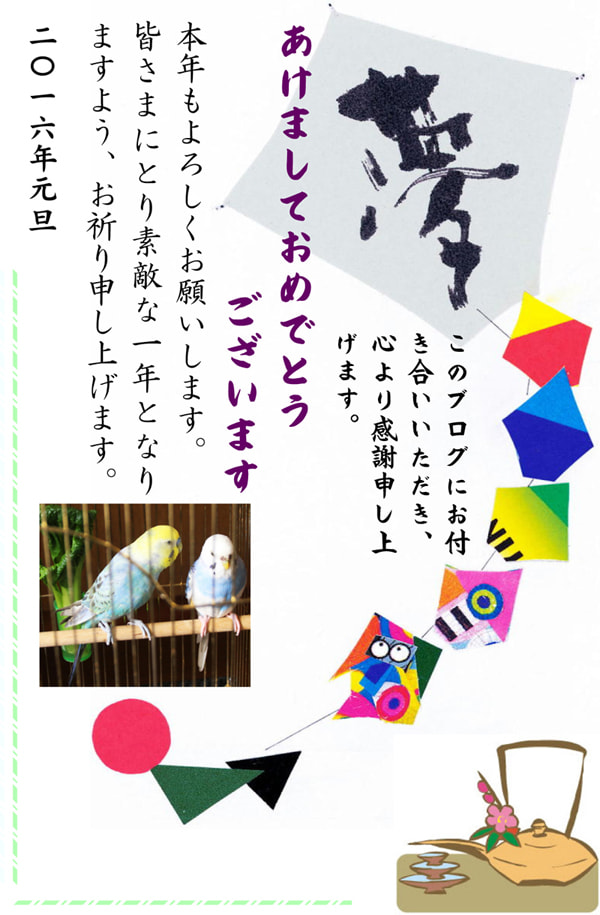世界平和アピール七人委員会のホームページに「今月のことばNo.21」に、小沼通二氏のエッセイが掲載された。【http://worldpeace7.jp/?p=826】
小沼通二氏は1931年生まれだから現在は84歳のはず。84歳とはとても思えないほどエネルギッシュに活動されている。「日本学術会議原子核特別委員会委員長、日本物理学会会長、アジア太平洋物理学会連合会長、ノーベル平和賞を受賞したパグウォッシュ会議の評議員などを務め」、現在は世界平和アピール七人委員会の事務局長として活動されている。その活動に心から敬意を表したい。
以下引用させてももらう。
山田洋次監督の「母と暮らせば」の上映が昨年末の2015年12月に始まった。この映画のもととなった「父と暮らせば」の井上ひさしさんは、わたくしたち七人委員会の仲間だった。またこの映画作成に協力したとして、長崎市、長崎大学、長崎原爆資料館に続いて、16人の個人名が挙げられているのだが、その筆頭は七人委員会の土山秀夫さんであり、かねてから親しい朝長(ともなが)万左男さん(日本赤十字社長崎原爆病院名誉院長)、調漸(しらべ・すすむ)さん(長崎大学副学長)の名前もある。3人とも医学者である。
ところでわたくしは、一昨年11月から昨年11月までの間に長崎に3回行く用事があった。長崎にはそれ以前に何度も行ったことがあるのだが、昨年8月から11月にかけて、被爆直後の医師たちの詳細な記録をいくつも読み、土山さんからも被爆後のご経験を改めて詳しくお聞きし、きわめて困難な中での献身的な救護活動の実情を思い起こしながら、爆心地の周囲の丘を歩くという機会を得た。
長崎に投下されたプルトニウム爆弾は盆地の上空500mでさく裂したので、周囲の丘は遮るものなく直撃された。平和公園にある平和祈念像は北北東の丘、長崎原爆資料館と国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館は南南東すぐの丘にある。わたくしは、昨年10月、爆心地から西500mの丘の上にある市立城山小学校の遺構として保存されている被爆校舎を訪ねた。この小学校の児童は1400人が死亡し、翌年の卒業式に参加できた卒業生は14人だけだったという。東に戻り、爆心地を通って東北東の丘にある浦上天主堂を再訪してから、東南東500mの長崎大学医学部のキャンパスに行った。ここが被爆当時の長崎医科大学であり、ほとんどが木造校舎だったため全壊全焼、授業中の1,2年生は全滅、学生・教職員890名ほどが死亡した。「母と暮らせば」は、母と2人で暮らす長崎医大学生の息子の8月9日朝の変わりのない登校と、授業が始まった階段教室、それが瞬時にして消滅するところから始まる。
わたくしが、長崎医科大学の跡をぜひ訪ねたいと思ったのは、すでに述べたように、被爆直後の医師たちの献身的な活動を知ったからだった。9月までに読んだのは、① 調來助・吉沢康雄『医師の証言 長崎原爆体験』(東京大学出版会、1982年)、② 『長崎医大原子爆弾救護報告』(朝日新聞社、1070年)、③ 『原子爆弾災害調査報告書 総括編』(日本学術振興会、1951年)、④ 『原子爆弾災害調査報告集』第一分冊(日本学術振興会、1953年)などである。①は長崎医大付属病院で被爆し、被爆死した病院長の後任となって救護と大学再建に多大の努力をした調來助教授(調漸さんの祖父)からの聞き書きであって、付録に詳細な被爆者調査結果がついている。②は長崎医大物理的療養科の永井隆助教授のグループの救護活動報告、③、④は日本中の学界の人たちがそれぞれ分析した結果をまとめたものであり、1945年11月と1946年2月の報告会の速記録もついている。①の付録は、医師数人と学生50人を組織して10月下旬から11月上旬という短期間に、印刷させた調査票に記入していく形で5000人の被爆者の調査を実施し、調教授が後遺症に苦しみながら一人で約1年かけて統計的分析を行った貴重な医学報告書である。土山さんもこの調査に協力した一員だった。
11月には、長崎大学医学部構内にある原爆医学展示室を案内してもらい、原爆後障害医療研究所に丁寧に整理して保存されている1945年の記入済調査票の原本まで見せていただき、粛然とした思いだった。この時に⑤ 泰山弘道『完全版 長崎原爆の記録』(東京図書出版会、2007年)の存在を知った。この著者も大村海軍病院長として被爆者の治療に尽力し、壊滅した長崎医大再建を目指した医師であって、本書によってわたくしの視野をさらに広げることができた。
井上さんは、「父と暮らせば」のあと、沖縄戦についての戯曲「木の上の軍隊」を、2010年7月上演を目指して準備していたのに、4月に亡くなった。これは、蓬来竜太氏が脚本を完成させて、2013年4月に公演された。長崎を舞台に「母と暮らせば」を作りたいと考えていた井上さんの遺志を聞いた山田監督が実現させたのが、今回の映画だった。これは間違いなく山田監督の不滅の映画なのだが、それと同時に、井上さんが目指した3部作の画竜点睛にもなっている。
小沼通二氏は1931年生まれだから現在は84歳のはず。84歳とはとても思えないほどエネルギッシュに活動されている。「日本学術会議原子核特別委員会委員長、日本物理学会会長、アジア太平洋物理学会連合会長、ノーベル平和賞を受賞したパグウォッシュ会議の評議員などを務め」、現在は世界平和アピール七人委員会の事務局長として活動されている。その活動に心から敬意を表したい。
以下引用させてももらう。
山田洋次監督の「母と暮らせば」の上映が昨年末の2015年12月に始まった。この映画のもととなった「父と暮らせば」の井上ひさしさんは、わたくしたち七人委員会の仲間だった。またこの映画作成に協力したとして、長崎市、長崎大学、長崎原爆資料館に続いて、16人の個人名が挙げられているのだが、その筆頭は七人委員会の土山秀夫さんであり、かねてから親しい朝長(ともなが)万左男さん(日本赤十字社長崎原爆病院名誉院長)、調漸(しらべ・すすむ)さん(長崎大学副学長)の名前もある。3人とも医学者である。
ところでわたくしは、一昨年11月から昨年11月までの間に長崎に3回行く用事があった。長崎にはそれ以前に何度も行ったことがあるのだが、昨年8月から11月にかけて、被爆直後の医師たちの詳細な記録をいくつも読み、土山さんからも被爆後のご経験を改めて詳しくお聞きし、きわめて困難な中での献身的な救護活動の実情を思い起こしながら、爆心地の周囲の丘を歩くという機会を得た。
長崎に投下されたプルトニウム爆弾は盆地の上空500mでさく裂したので、周囲の丘は遮るものなく直撃された。平和公園にある平和祈念像は北北東の丘、長崎原爆資料館と国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館は南南東すぐの丘にある。わたくしは、昨年10月、爆心地から西500mの丘の上にある市立城山小学校の遺構として保存されている被爆校舎を訪ねた。この小学校の児童は1400人が死亡し、翌年の卒業式に参加できた卒業生は14人だけだったという。東に戻り、爆心地を通って東北東の丘にある浦上天主堂を再訪してから、東南東500mの長崎大学医学部のキャンパスに行った。ここが被爆当時の長崎医科大学であり、ほとんどが木造校舎だったため全壊全焼、授業中の1,2年生は全滅、学生・教職員890名ほどが死亡した。「母と暮らせば」は、母と2人で暮らす長崎医大学生の息子の8月9日朝の変わりのない登校と、授業が始まった階段教室、それが瞬時にして消滅するところから始まる。
わたくしが、長崎医科大学の跡をぜひ訪ねたいと思ったのは、すでに述べたように、被爆直後の医師たちの献身的な活動を知ったからだった。9月までに読んだのは、① 調來助・吉沢康雄『医師の証言 長崎原爆体験』(東京大学出版会、1982年)、② 『長崎医大原子爆弾救護報告』(朝日新聞社、1070年)、③ 『原子爆弾災害調査報告書 総括編』(日本学術振興会、1951年)、④ 『原子爆弾災害調査報告集』第一分冊(日本学術振興会、1953年)などである。①は長崎医大付属病院で被爆し、被爆死した病院長の後任となって救護と大学再建に多大の努力をした調來助教授(調漸さんの祖父)からの聞き書きであって、付録に詳細な被爆者調査結果がついている。②は長崎医大物理的療養科の永井隆助教授のグループの救護活動報告、③、④は日本中の学界の人たちがそれぞれ分析した結果をまとめたものであり、1945年11月と1946年2月の報告会の速記録もついている。①の付録は、医師数人と学生50人を組織して10月下旬から11月上旬という短期間に、印刷させた調査票に記入していく形で5000人の被爆者の調査を実施し、調教授が後遺症に苦しみながら一人で約1年かけて統計的分析を行った貴重な医学報告書である。土山さんもこの調査に協力した一員だった。
11月には、長崎大学医学部構内にある原爆医学展示室を案内してもらい、原爆後障害医療研究所に丁寧に整理して保存されている1945年の記入済調査票の原本まで見せていただき、粛然とした思いだった。この時に⑤ 泰山弘道『完全版 長崎原爆の記録』(東京図書出版会、2007年)の存在を知った。この著者も大村海軍病院長として被爆者の治療に尽力し、壊滅した長崎医大再建を目指した医師であって、本書によってわたくしの視野をさらに広げることができた。
井上さんは、「父と暮らせば」のあと、沖縄戦についての戯曲「木の上の軍隊」を、2010年7月上演を目指して準備していたのに、4月に亡くなった。これは、蓬来竜太氏が脚本を完成させて、2013年4月に公演された。長崎を舞台に「母と暮らせば」を作りたいと考えていた井上さんの遺志を聞いた山田監督が実現させたのが、今回の映画だった。これは間違いなく山田監督の不滅の映画なのだが、それと同時に、井上さんが目指した3部作の画竜点睛にもなっている。