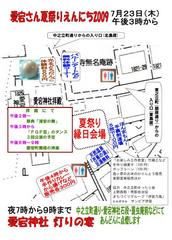朝夕の涼しさに秋を感じる…このまま秋になるのかなぁ。
「秋」といえば、やっぱりお祭り!!伊賀は祭ばっかりしてるのね??
9月に入ると恒例の「上野天神祭講演会」が開催されます。
国指定重要無形民俗文化財「上野天神祭ダンジリ行列」(国指定文化財のデータベースより)
【上野天神祭のダンジリ行事は三重県上野市(現伊賀市)の菅原神社の秋祭りとして行われ、印【しるし】、ダンジリ、鬼行列などが町内を巡行する行事である。】
実際の行列では、神輿の渡御に供奉(ぐぶ:行幸などの行列に供をすること)し、露払いの役目を果たす「大御幣(だいごへい)」がいき、町々の悪疫退散と五穀豊穣を祈念して「鬼行列」が練り歩き、その後に9基の「だんじり(楼車)」が続きます。
正式に(「鬼行列」という)名前があろうがなかろうが、粛々と祭りは続くのです。
前置きが長くなってしまいましたが、今年の「上野天神祭講演会」は

(伊和ジャーナルより)

西部自治協HPより
講師は、吉野歴史資料館館長:池田 淳(きよし)先生。
歴史大好きの方へ、参考までに「奈良の名所・遺跡」ブログです。
そして、過去の講演会の様子は
2006年講演会
2007年講演会
2008年講演会記録は残念ながらありませんでした
「秋」といえば、やっぱりお祭り!!伊賀は祭ばっかりしてるのね??
9月に入ると恒例の「上野天神祭講演会」が開催されます。
国指定重要無形民俗文化財「上野天神祭ダンジリ行列」(国指定文化財のデータベースより)
【上野天神祭のダンジリ行事は三重県上野市(現伊賀市)の菅原神社の秋祭りとして行われ、印【しるし】、ダンジリ、鬼行列などが町内を巡行する行事である。】
実際の行列では、神輿の渡御に供奉(ぐぶ:行幸などの行列に供をすること)し、露払いの役目を果たす「大御幣(だいごへい)」がいき、町々の悪疫退散と五穀豊穣を祈念して「鬼行列」が練り歩き、その後に9基の「だんじり(楼車)」が続きます。
正式に(「鬼行列」という)名前があろうがなかろうが、粛々と祭りは続くのです。
前置きが長くなってしまいましたが、今年の「上野天神祭講演会」は

(伊和ジャーナルより)

西部自治協HPより
講師は、吉野歴史資料館館長:池田 淳(きよし)先生。
歴史大好きの方へ、参考までに「奈良の名所・遺跡」ブログです。
そして、過去の講演会の様子は
2006年講演会
2007年講演会
2008年講演会記録は残念ながらありませんでした



































 こどもたちの熱いダンスに
こどもたちの熱いダンスに