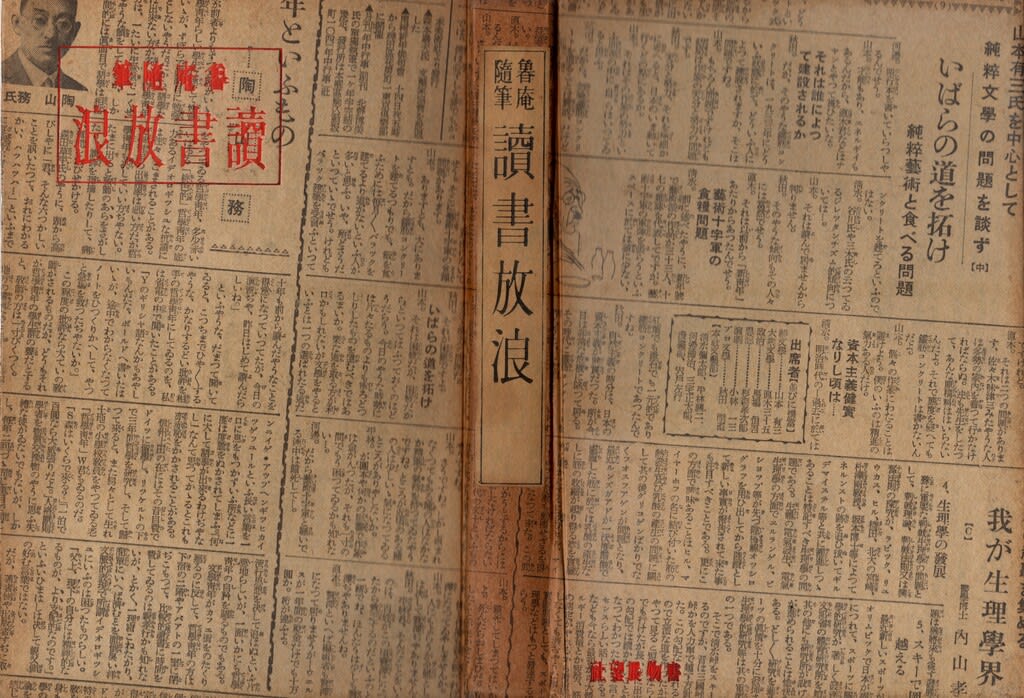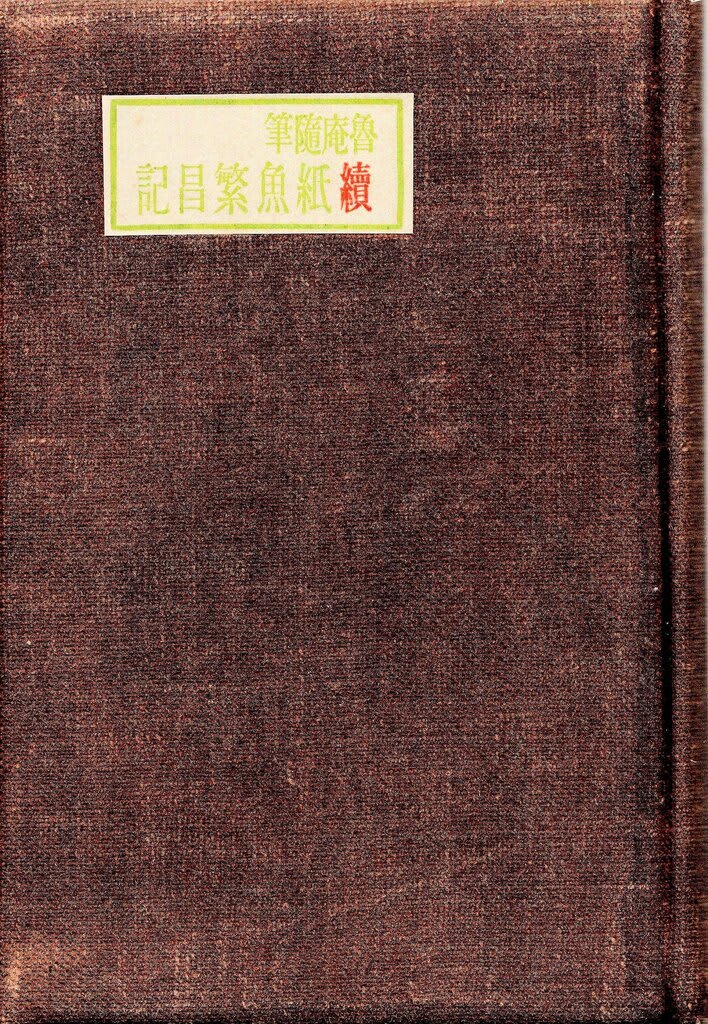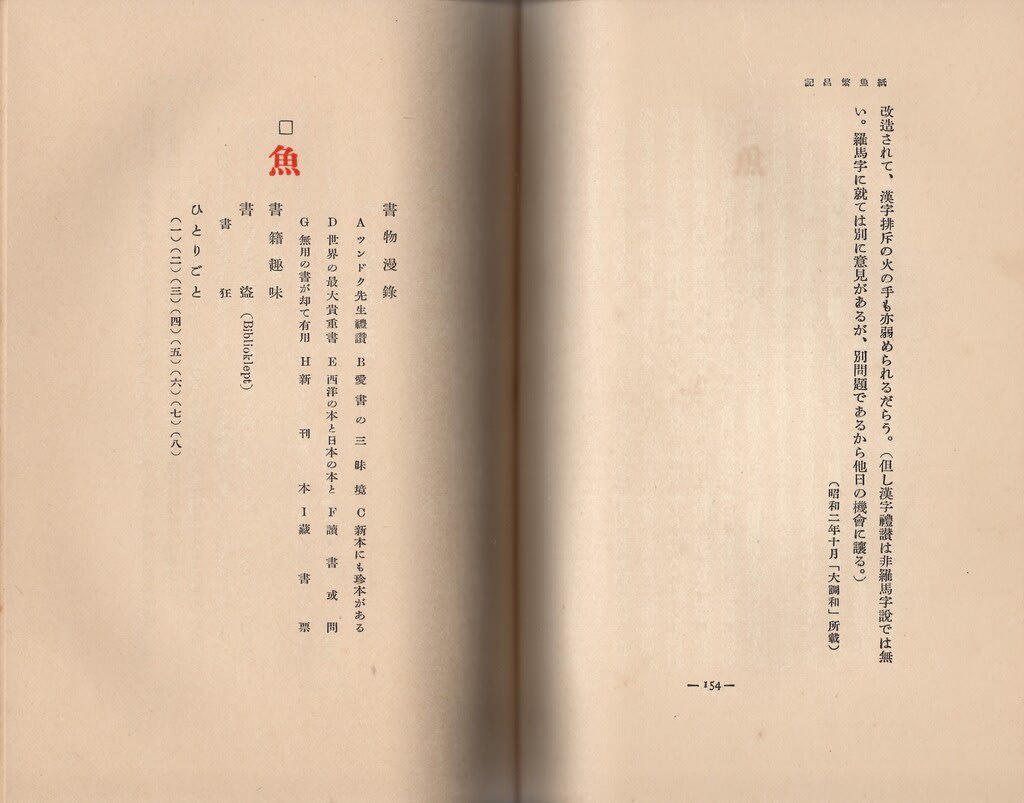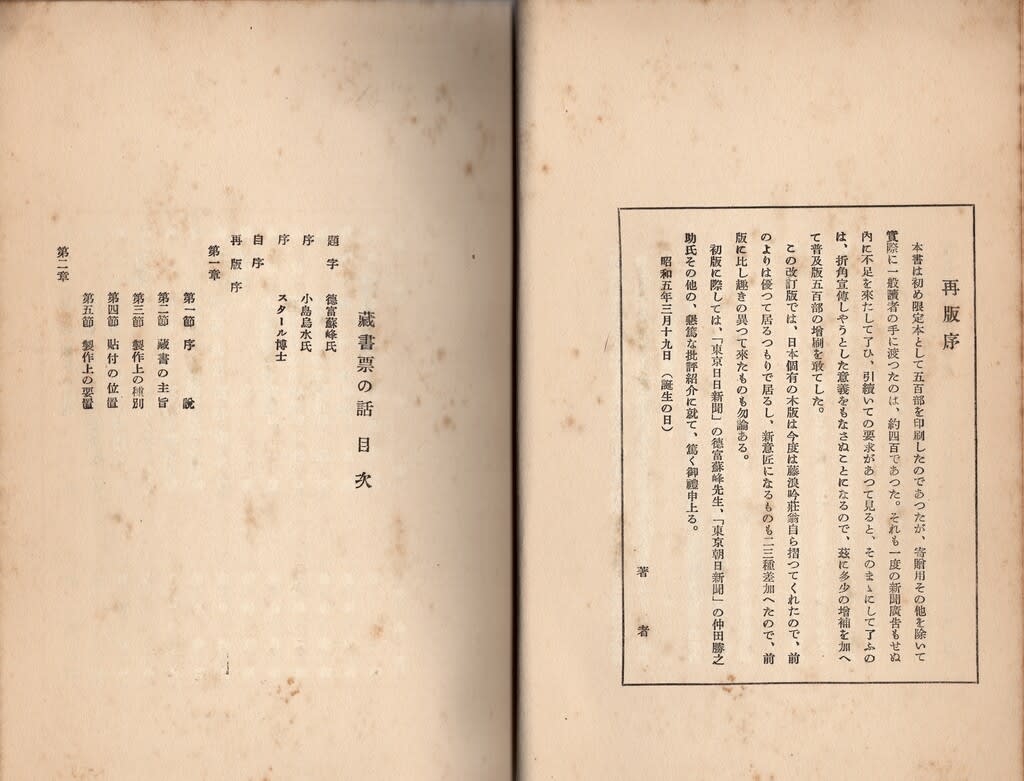雑誌「貸本文化」
私が学生時代を送った昭和40年代までは、地元に貸本屋というものがあった記憶があります。なぜこの雑誌が手元にあるのか分かりませんが、おそらく「創刊号」というものに魅力があったのだろうと思います。創刊号から4号まで、3、4号が合併号なので3冊。
雑誌を出すということは、熱意をいくら込めて創刊しても、3号まで出すとどうしても息切れしてしまい、「3号雑誌」と言われるぐらいで頓挫してしまうことが多かったからだと思います。
で、この雑誌も3号どまりなのかと、調べてみると、その後の号もバラで古書店の目録に出ていました。「貸本屋」というもの自体が先細りの業種でしたから、この雑誌も同じ運命なのかと思いましたが、興味が湧いたので、国会図書館の所蔵を調べてみました。すると、終刊は2004年6月の第20号だったことが分かりました。創刊が1977年1月ですから、27年間も続いた雑誌でした。
創刊号

残念ながら、お名前に心当たりのある方がひとりもいませんでした。
裏表紙に表示してある書誌情報

2号

3・4号合併号「石子順造追悼号」

第3号になって、お名前だけは知っている石子順造、長友千代治の名が初めて出てきます。
3冊の表紙をスキャンした時点では、所蔵はこの3冊だけでしたが、冒頭に書いたように、何号まで出ていたのかを調べるうちに、古書店検索で、「創刊号、5号から18号までの揃い」という在庫があるお店を見つけて、ついポチっとしてしまいました。
20号が終刊だというのが分かったのはその後でした。ですから、あと19号と20号の2冊を調達出来れば、創刊から終刊まで揃うことになります。
手元に届いた「創刊号、5号から18号までの揃い」は状態がとても良かったです。



発行年順に並べていくと、増刊号(特集・貸本屋大惣)が1冊だけありました。

ここで、増刊号で特集された「貸本屋大惣」は、100円ショップで名を成したダイソーと関係があるのでは? と、ふと思って知らべてみましたが、「大惣」は、江戸時代後期から明治時代に名古屋にあった大野屋 惣八(おおのや そうはち)の貸本屋で、ダイソーは「大創」からきている名称で、まったく無関係でした"(-""-)"