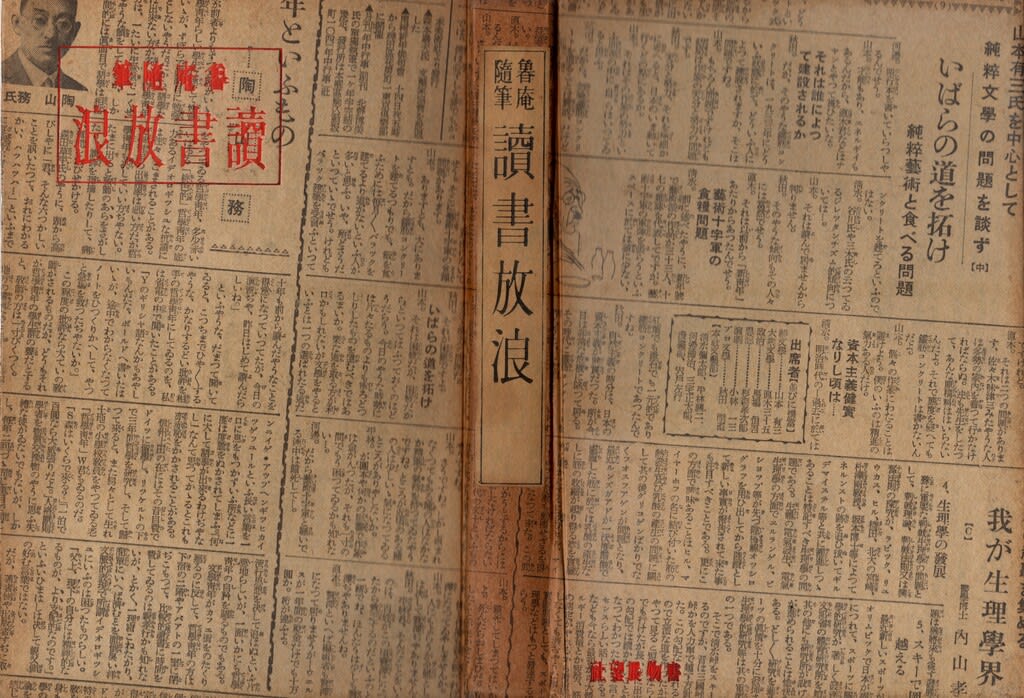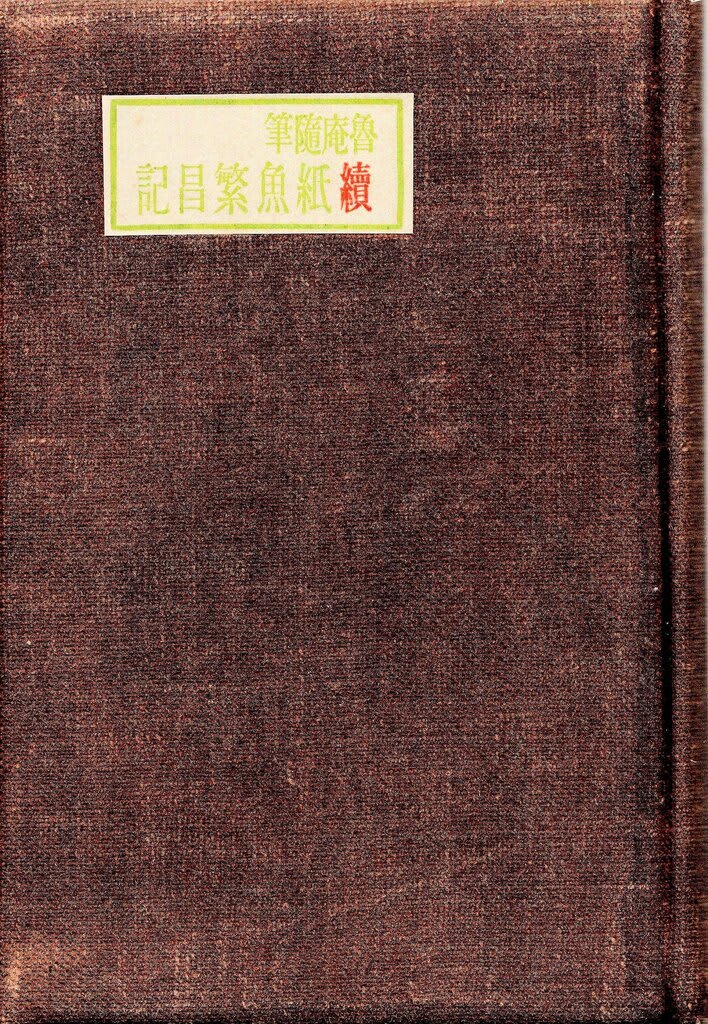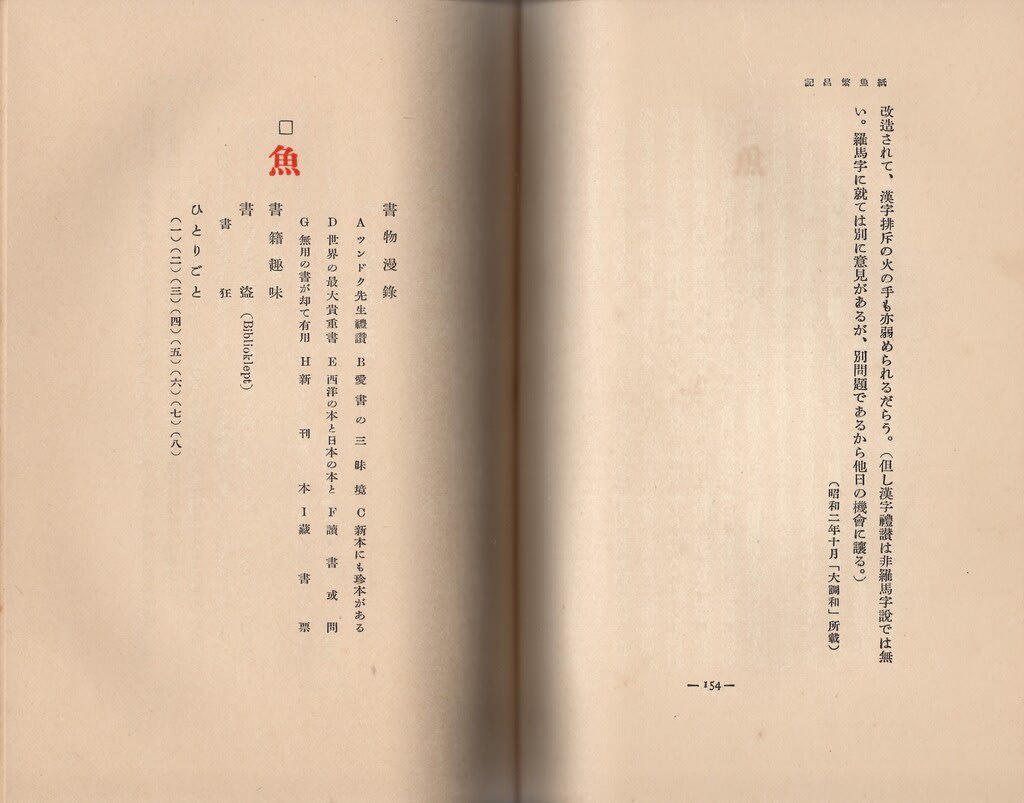内田魯庵『紙魚繁盛記』斎藤昌三・柳田泉/編纂 昭和7(1932)年2月10日 書物展望社/発行
内田魯庵(1868年5月26日~1929年6月29日)の没後に刊行されたもので、編纂者の斎藤昌三の造本のこだわりが、至る所にちりばめられています。
函
函貼りは砂糖袋の紙を使い、「粋と甘いを利かしてみた」そうです。
表紙(セロファン紙が貼り付けてあるので、そのままスキャンしています)
かぶせたセロファン紙が糊付けしてあるので、表紙に使われている布の感触を直接触れたことがなく、色合いからビロードだと何となく思い込んでいました。
ところが、斎藤昌三の「あとがき」を見てビックリ。表紙に使われている素材は「酒嚢」。「酒嚢」とは何かを調べると、「伝統ある造り酒屋で、日本酒の製造工程で、もろみを入れてお酒を絞るときに使われた綿の袋」なのだそうです。その袋には強度が求められるため、手織木綿(帆布)を柿渋に漬けた布が使われます。長年使用することにより、日本酒の成分と柿の渋が絡み合い、独特の色とむらが生じるのだそうです。
それを表紙素材として選んだ斎藤昌三の見識が素晴らしいですね。
表題紙
内田魯庵の近影のページの後に、蔵書票の紹介
その次に限定部数の表示ページがあります
目次の一部
□魚 の項のページを開いてみると、「魚」が朱色で印刷されています。
奥付 限定部数がここには表記されていません
斎藤昌三の趣意はこれだけにとどまりません。表紙から開き直してみます。
まずは、本の天小口は「天金」です。
オモテ見返し (右ページの半分はセロファン紙がかかっています)
ウラ見返し(左側半分にはセロファン紙がかかっています)
オモテ見返しとウラ見返しに銀色の、和紙を食い荒らす「紙魚」が印刷してあります。それだけではなく、見返し紙には虫食いがある和紙を印刷したのではなく、実際に虫食いがある和紙を使っているのです。触ると、虫食い跡が分かります。見返し紙をこのようにするために、虫食い本を集めたのだそうです。――ということは、一冊ずつ見返しが異なるということになります。いやはや、恐れ入ります。
そんな手の込んだ本を「買って満足」と、ただ積んでおいたのでは、バチが当たりますね。