仏教漢語50話 興膳 宏 著
同書は、書評に出ていた。内容は興味的だから読んだ。
丁度、朝日でも記事で、紹介されている。注目される本。
仏教は紀元前5世紀 インドで発生 1世紀後、中国に伝来。
その思想・仏典はインド(サンスクリット)語であった。
これを漢語化された。それは下記の2通の方法だった。
音訳(原語の音を漢字で表記・漢語にはカナの表記が無い〕
例示
*阿吽(アイウエオはアで始まりンで終わる。古代インド語も同じ。あてがっている漢字は音を借用しているのみ。それの意味では、無い。相撲の立会い「阿吽の呼吸」八百長も阿吽)
*阿弥陀(大衆的な如来さま。阿弥陀堂・帽子をあみだに被る。あみだ籤)
(現代でもある。的士【タクシー】
意訳(意味を漢語に翻訳)例示
*居士(家の主。高位高官「一言居士」)
*布施(法を聞き布施する。財施・法施。Danaの訳。Donar=英語
(現代=電脳 【パソコン】
玄関(幽遠な真理に入る為のカンヌキ・鍵)
我慢(自分の力を過信。思い上がる)・
道楽(仏道修行で得た、悟りの楽しみ。
塔 (Stupa=卒塔婆。五重の塔。ロンドン塔・テレビ塔)
火車(地獄からのお迎え。ひのくるま。中国では=汽車)
六道(6つの迷いの道。御堂筋=冥土筋。
(眼・耳・鼻・口・2つの排泄器=体が外と繋がる穴)
仏教漢語は日本文学に影響をあたえている。
落語でも良く取り入りいれられてる。
日本語に多いに関係している。
漢語から日本語になった時は如何なる変化をなしたのだろう!
漢字を其の侭、日本語よみにしたのだろうか?
上記の例示は意味・用法が転化し、日常化した言葉。
省略では全容の紹介は難しい!
ご興味の皆さんはご1讀を!
_____________
アクセスの不通で掲載の時間が開きました。
下書きの原稿を推敲して掲載します。
アクセスのご継讀を!
アクセス・ランキング 100~250位前後です。
大幅なランクの下落です。UPをはかります。 ランクUPにご協力をお願いします。
(知人よりアドバイス。アクセスを気にせず、自分を楽しめと) タイトルは”硬派的社評漫筆” です 。
最新の画像[もっと見る]
-
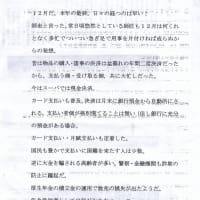 12-1 12月
8年前
12-1 12月
8年前
-
 1-1 24年 年賀
12年前
1-1 24年 年賀
12年前
-
 9-2 ツイカンパンヘルニア
13年前
9-2 ツイカンパンヘルニア
13年前
-
 謹賀新年
14年前
謹賀新年
14年前
-
 フインランド 物語
16年前
フインランド 物語
16年前
-
 uniq + lock=ユニクロのPR
17年前
uniq + lock=ユニクロのPR
17年前
-
 ひばり
17年前
ひばり
17年前
-
 驚いた!!
17年前
驚いた!!
17年前
-
 メィー メィー 森のこ山羊
17年前
メィー メィー 森のこ山羊
17年前
-
 続 機位 不明
17年前
続 機位 不明
17年前









