| ラヂオアクティヴィティ[Ra.] 第二部・国境なき恐怖 207平和の願い  今夜、京の町をとりかこむ山々に壮大な送り火が燃え上がる。 これが大文字の送り火である。 足利尊氏説を述べたが、別の説もある。それによると、盆の翌日の夜、松明の火を空に投げ上げて、虚空を行く霊を見送るという風習があったと伝えられ、大文字の送り火は、これが山に点火されて、空中に固定されたものであるという。神秘的なものもある。 他には弘法大師説などがある。文献の上ではじめて出てくるのは慶長八(一六〇三)年で、それよりさかのぼっての記録は今のところ見当たらないらしい。 精霊送りの行事で、万灯絵が大規模化したものであることは間違いないという人もいる。弘法大師説では、弘法大師が故事にあやかって護摩の行をしたことに始まりとする説である。 そして、やはり有力な説は足利義政説である。 わずか二十代なかばで陣中に没した息子義尚の霊をなぐさめるため、相国寺の横川景三和尚のすすめで義政がはじめたものだという言い伝えである。 義尚は、「応仁の乱の責任はお前だ。お前さえ生まれなければ」と非難された。 家を焼かれ、各所に避難しなければならなかった京都市民は応仁の乱の戦争被害者であったが、戦乱が終わったとき、生き残った彼らは、義尚に同情したのだろう。 応仁の乱は、たった一人のヒーローさえつくらなかった。誰が勝ったのかも判然としない。歴史的には、大内とか織田といったような下層の武士が覇権を握るが、それは地方のことであり、京都とは関係ない。 犠牲者の屍と焼け跡だけを残された京都の市民のほかに、戦死者の霊をなぐさめるものはなかっただろう。 記録はないが、如意岳の大文字と義政との関係はありうるという。 誰でも知っているとおり、如意岳は銀閣寺の裏山である。義政は、不足がちな資金をやりくりして銀閣寺を造営しているうち、裏山の斜面に、あるイメージを抱いた。 これをそっくり残しておきながら、なおかつ人々をアッと驚かせ、自分の美的欲望を満足させるような一大モニュメントを刻みつけておこうと思ったのではないだろうかという。銀閣寺と如意岳大文字とは、いうなればこれで一対なのだと考えている人もいる。 もっとも、義尚の霊をなぐさめるためにと義政が本気で考えたのかどうか、それはだいぶ眉唾ものだといってよいという。 義政と富子、この夫婦を世間なみの基準で考えることはできないという。息子である義尚の不運を自分たちの責任として考えるような彼らだったかとなると、否定的になるという。 だから、これを義尚と結びつけたのは京都市民なのだという。陰謀をめぐらし、武器を持って戦闘に勝ち残ったわけではないが、生き残ったという負い目を率直に示しているのが彼らだったというのである。 銀閣寺の裏山にある如意岳は、東山三十六峰のなかでも比叡山につぐ雄峰で、市内のたいていの場所から見ることができる。大文字はこの如意岳の中腹七千坪の斜面に、七十五の火床をならべて「大」が夜空に赤く浮かび上がると同時に、北山の東から西かけて四つの火がともる。 東から、松ヶ崎の「妙法」これは「妙」と「法」とが、相接してならんだ二つの山にともされる。次が西加茂の「船形」、帆かけ船の形。金閣寺の裏山に「左大文字」があり、いちばん西に、北嵯峨の鳥居の形。この五つ火をあわせて「五山の火」と呼ばれる。むかしは、このほかにも、変った形があったらしく、「い」、「一」、「竹の先に鈴」、「蛇」、「長刀」などが記録に残っているという。文字どおり京の四辺の山々に巨大な火模様が描かれたわけで、さぞかし壮観だったことだろう。 惜しいことに廃絶してその場所さえはっきりしないという。 如意岳の麓に浄土寺という寺があって、火災にあったとき、本尊の阿弥陀仏が光明を放ってこの山頂にとんだ。そのゆかりを崇あがめて火を焚くようになった、などともいわれている。 「大」の原字は弘法大師の筆だとか、相国寺の横川景三が書いたとか諸説あるが、これも口承のたぐいであるそうだ。 盂蘭盆会、虚空を翔かけってこの世にかえって来た亡き人の魂が、再び冥界にとび帰ってゆく。人びとはその夜空の暗さを憐れんで、山々に火を焚いたのだろう。 五山の火を守る土地の人びとは、この一夜の行事のため多大の犠牲をはらって奉仕をつづけている。それぞれの火床をうけもった家では、燃え方が悪いと家に不幸がつづくというので、風向からマッチのすり方までこまかに気を配り、それこそ家中が総出でつきっきりとなるという。
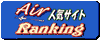 ありがとうございます。 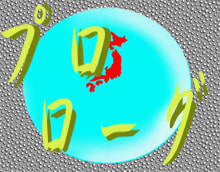 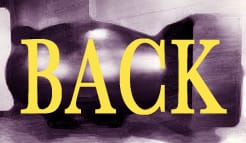  Index[Ra.] |
最新の画像[もっと見る]
-
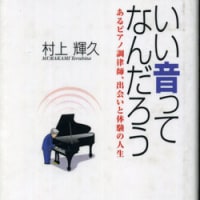 いい音ってなんだろう-あるピアノ調律師、出会いと体験の人生-
12年前
いい音ってなんだろう-あるピアノ調律師、出会いと体験の人生-
12年前
-
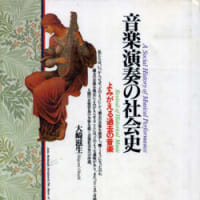 音楽演奏の社会史-よみがえる過去の音楽-
12年前
音楽演奏の社会史-よみがえる過去の音楽-
12年前
-
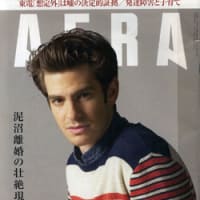 AERA ’12.7.16
12年前
AERA ’12.7.16
12年前
-
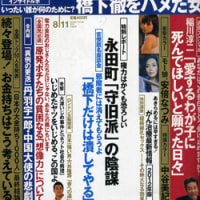 週刊現代 2012-8-11
12年前
週刊現代 2012-8-11
12年前
-
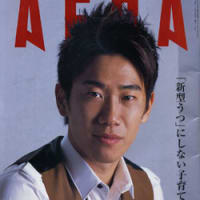 AERA ’12.7.9
12年前
AERA ’12.7.9
12年前
-
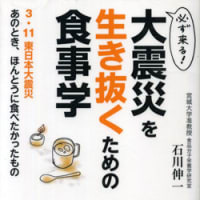 必ず来る!大震災を生き抜くための食事学-3・11東日本大震災あのとき、ほんとうに食べたかったもの-
12年前
必ず来る!大震災を生き抜くための食事学-3・11東日本大震災あのとき、ほんとうに食べたかったもの-
12年前
-
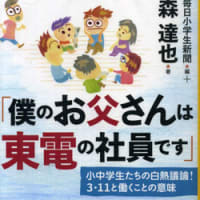 僕のお父さんは東電の社員です-小中学生たちの白熱議論!3・11と働くことの意味-
12年前
僕のお父さんは東電の社員です-小中学生たちの白熱議論!3・11と働くことの意味-
12年前
-
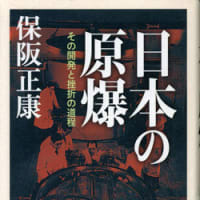 日本の原爆-その開発と挫折の道程-
12年前
日本の原爆-その開発と挫折の道程-
12年前
-
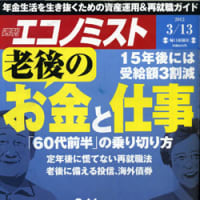 エコノミスト-週刊エコノミスト- 2012-3/13
12年前
エコノミスト-週刊エコノミスト- 2012-3/13
12年前
-
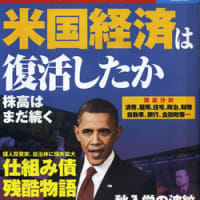 エコノミスト-週刊エコノミスト- 2012-3/6
12年前
エコノミスト-週刊エコノミスト- 2012-3/6
12年前









