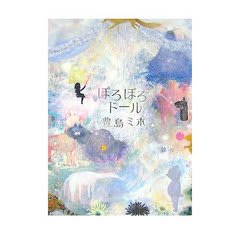「絶望ォーーーーに身をよじれィ 虫けらどもォオオーーッ!!」
とは、かの有名な『切り裂きジャック』(ジョジョの奇妙な冒険 三巻参照)のお言葉ですが、この小説とはなんら関係ありません。あしからず。
で、本谷有希子さんの『ぜつぼう』ですが、一時まぐれで大ブレイクしたお笑い芸人『ピロチキ』(誰がどう読んでも、あの『猿○石』が浮かんでくる)の戸越。外国人の相方に逃げられ、それでも別の外国人をとっかえひっかえし、そのうちブームは過ぎ去り、仕事を干され、やがて引きこもりになるわ、睡眠障害に悩まされるわ、とずんずん絶望の果てへ陥っていきます。そんなある日、ひょんな出会いで田舎の農村へ行くはめに。そしてそこで出逢った女性シズミとの日々の中で真実の絶望の姿を模索しはじめる。
ところどころ、いつもの本谷さんならではの笑える記述が見受けられるものの、今作はかなり純文学寄りに書かれている感じです。ナニかを狙っている感じです。
同郷ということもあって、田舎の農作業の描写ではコチラの風景が見事に重なってきます。いや実際、農作業なんてしたことないんだけど、なんとなく雰囲気が。
ラストはかなり印象的で、こういうの好きだなぁ、と思いました。
やっぱ本谷有希子はスゴい!決して同郷贔屓などではなく、いや多少はあるけれど、とにかく、
「さすが本谷!俺たちに出来ないことを平然とやってのけるッ!
そこにシビれる!あこがれるゥ!」
と、そんなカンジです。(いやホント、まったくジョジョとは関係ない話だから)
とは、かの有名な『切り裂きジャック』(ジョジョの奇妙な冒険 三巻参照)のお言葉ですが、この小説とはなんら関係ありません。あしからず。
で、本谷有希子さんの『ぜつぼう』ですが、一時まぐれで大ブレイクしたお笑い芸人『ピロチキ』(誰がどう読んでも、あの『猿○石』が浮かんでくる)の戸越。外国人の相方に逃げられ、それでも別の外国人をとっかえひっかえし、そのうちブームは過ぎ去り、仕事を干され、やがて引きこもりになるわ、睡眠障害に悩まされるわ、とずんずん絶望の果てへ陥っていきます。そんなある日、ひょんな出会いで田舎の農村へ行くはめに。そしてそこで出逢った女性シズミとの日々の中で真実の絶望の姿を模索しはじめる。
ところどころ、いつもの本谷さんならではの笑える記述が見受けられるものの、今作はかなり純文学寄りに書かれている感じです。ナニかを狙っている感じです。
同郷ということもあって、田舎の農作業の描写ではコチラの風景が見事に重なってきます。いや実際、農作業なんてしたことないんだけど、なんとなく雰囲気が。
ラストはかなり印象的で、こういうの好きだなぁ、と思いました。
やっぱ本谷有希子はスゴい!決して同郷贔屓などではなく、いや多少はあるけれど、とにかく、
「さすが本谷!俺たちに出来ないことを平然とやってのけるッ!
そこにシビれる!あこがれるゥ!」
と、そんなカンジです。(いやホント、まったくジョジョとは関係ない話だから)