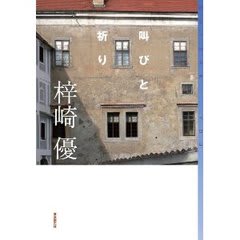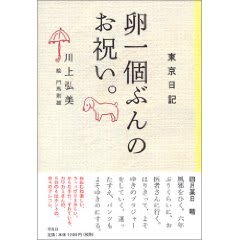斬新である。ときに斬新は奇抜となって甚だ気色の悪いものとなりがちだが、一旦受け入れてしまうと麻薬のようにクセとなる。まずこの作品も、そういった類いで間違いはなかろう。なんせ、タイトルからして気色悪い。いったいなにがなんやら、音の響きすらままならない。しかしそれが、とてつもなく心をひっぱるのもこれ事実。そして徐にページを繰れば、これまたえもいわれぬ独特文章。常々、自分は文章にはリズムが大切だと思っている。言ってしまえばリズムに乗れなければ、その本を読むのが苦痛になる。リズムのない文章など論外とすら思う。
さて、リズムはその作家、その文人、種々様々あって、読み手のこちらもそのときの心情にあわせて読みたく思う。それはまったく音楽や映画などと同じで、こんな気分の日はコイツだな、と選出するように、今日はこの人の文章だな、となる。しかるに、そのリズムを知るためにはある程度の予備知識が必要である。が、一聴一見もないアーティストでそいつはままならぬ。だがしかし、初めて出逢うモノには、自然、期待が膨らむ。そこにはもちろんリスクも含まれたりもするが、自分が手にした時点でそこには縁(えにし)が発生していると思われるので、ないがしろにはすまい。偏見なしのニュートラルな状態で入ってくるソレは、素晴らしく心地良いか、それとも気色悪いか。
斬新である。基本だの枠だのセオリーだの、そんなもん、もうとっぱらう前に「ナニソレ?」という感じ。だがしかし、そこには確たる作者独自の個性がある。それが即ち「リズム」である。読み始めは気色ばんだ。なんだか、その奇抜さが確信的なものに思えて気色の悪さがもたらされた。しかし人間というものは不思議なもので、いや私の性根が捩れているまでなのだろうが、単なる小奇麗で纏まった美しさよりも、薄汚くて猥雑な逞しさに惹かれてしまう。するとどうだろう、その猥雑なリズムに乗ってするすると物語が入ってくる。言葉の流れが気持ちよく脳髄を滑ってゆく。あたかも太宰の「ソレ」のような感覚すら覚えた。
独自のリズムは後半、加速度を増し、狂乱の調べ。そして容赦なし、潔いラストは一瞬で辺りを静寂におとしいれる。感覚的に凄まじく気色悪い快感を読後もたらしてくれた、クセになる逸品である。
ちなみに作者の肩書きは……


自称「文筆歌手」である。

なんか、いい。
さて、リズムはその作家、その文人、種々様々あって、読み手のこちらもそのときの心情にあわせて読みたく思う。それはまったく音楽や映画などと同じで、こんな気分の日はコイツだな、と選出するように、今日はこの人の文章だな、となる。しかるに、そのリズムを知るためにはある程度の予備知識が必要である。が、一聴一見もないアーティストでそいつはままならぬ。だがしかし、初めて出逢うモノには、自然、期待が膨らむ。そこにはもちろんリスクも含まれたりもするが、自分が手にした時点でそこには縁(えにし)が発生していると思われるので、ないがしろにはすまい。偏見なしのニュートラルな状態で入ってくるソレは、素晴らしく心地良いか、それとも気色悪いか。
斬新である。基本だの枠だのセオリーだの、そんなもん、もうとっぱらう前に「ナニソレ?」という感じ。だがしかし、そこには確たる作者独自の個性がある。それが即ち「リズム」である。読み始めは気色ばんだ。なんだか、その奇抜さが確信的なものに思えて気色の悪さがもたらされた。しかし人間というものは不思議なもので、いや私の性根が捩れているまでなのだろうが、単なる小奇麗で纏まった美しさよりも、薄汚くて猥雑な逞しさに惹かれてしまう。するとどうだろう、その猥雑なリズムに乗ってするすると物語が入ってくる。言葉の流れが気持ちよく脳髄を滑ってゆく。あたかも太宰の「ソレ」のような感覚すら覚えた。
独自のリズムは後半、加速度を増し、狂乱の調べ。そして容赦なし、潔いラストは一瞬で辺りを静寂におとしいれる。感覚的に凄まじく気色悪い快感を読後もたらしてくれた、クセになる逸品である。
ちなみに作者の肩書きは……


自称「文筆歌手」である。

なんか、いい。