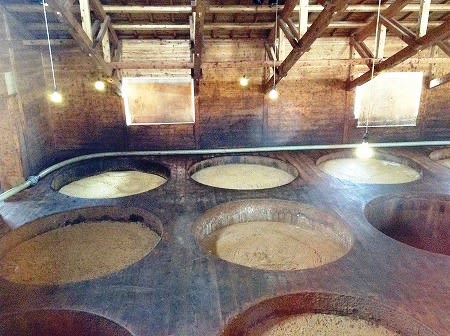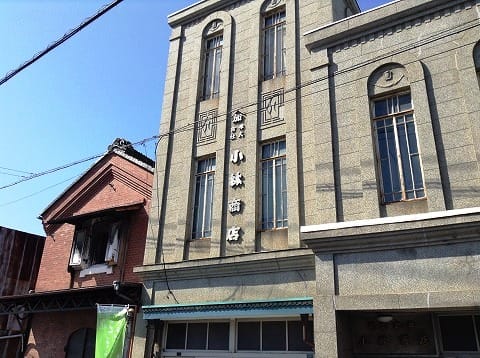● prologue
天気の良い秋の日、高麗川へと出かけました。
ほんの少し前までは、そういう地名があることさえ知らなかった私。
夏に秩父に行った時に、高麗駅を通って(へえ)と思ったのが最初です。
「こうらい」ではなく「こま」と読むんですね。
今回は高麗川(こまがわ)散策。
横浜から行くと、とてもとても遠くて、行く前から貧血になりそうですが、それでもいい気候に背中を押されて出かけました。
池袋で純と待ち合わせます。もうこの段階で、かなりの遠征気分。
それからさらに長い時間をかけて、JR高麗川駅に着きました。
浜っ子には遠い遠い奥武蔵までやってきましたよ~。
駅を降りると、まっさきに目に入ったのは、にらみをきかせた朝鮮風のトーテムポール。
うわっ、見おろされてる!赤くて怖いっ!
● 高麗川駅のチャンスン
威嚇顔の下に「天下大将軍」「地下女将軍」と書かれているこのポール、高麗駅にあるのを前に見たことがあります。
初めに見た時には、かなりおびえました。
だって顔つきがとってもリアルで怖いんですもの。
これは将軍標(チャンスン)といって、朝鮮半島では村の入り口に魔除けのために建てられるものだそうです。
チャンスンなんて、韓国人の名前みたいですね。
そもそも「天下大将軍」と「地下女将軍」って何でしょう?
勇ましい女の将軍が地下にいるのでしょうか?
今でははっきりとわからないそうです。
魔を退治する強い将軍は、仁王像や狛犬のような役目なのでしょうけれど、見た目は韓国版トーテムポール。どうも慣れません。
駅前から、一気にコリアンワールドに突入したようで、韓国に行ったことがない私はなんだか及び腰です。
中国に行ったことはあるし、横浜には大きな中華街があるので、中国の町並みには慣れていますが、朝鮮文化にはあまり馴染みがありません。
この辺りは韓国カラーが強いんだなあと思います。
駅前のバスロータリーにも、モダンなオブジェがありました。
赤色なのは、朝鮮風にしているからでしょうか。
「日韓交流の塔」と書いてあり、上の方には、やはり男女の将軍様の威嚇顔が書かれていました。
これもチャンスンの一種ですね。
駅舎の屋根も高麗風に赤かったのですが、お手洗いだけ教会風でした。
風見鶏まで立っている、洋風のとんがり小屋です。なぜここだけ~?
● 大きな石碑
高い建物が少なく、広い空が広がるのどかな駅前から、歩き出します。
しばらく歩いて、まず最初に到着したのが、大きな石碑のあるところ。
「四本木の板石塔婆」と言われている、市の指定文化財だそうです。
高さ2.66mもあり、市内最大だとか。
書かれているのは、阿弥陀如来の種字(梵字)だそうです。
うーん、さっぱり読めませーん。
そこから直角に道を曲がっていきます。
地図を広げて確認していたら、すぐ横に車が止まり、運転していたおばさまが「迷ってるの?」と聞いてくれました。
優しいわ。
● 神社ふたつ
次に訪れたのは、熊野神社。
境内は広く、掃除も行き届いていますが、人けがありません。
完全に無人です。
誰が書いたのか、明らかに手書きの扁額。
なんというか、インパクトがありました。
→
高麗川熊野神社
それからまたてくてく歩いて、別の鳥居を見つけます。
新田義貞が鎌倉幕府攻撃の時に立ち寄った稲野辺神社です。
この辺りだけこんもりと高い木々がそびえており、本当にちょっとした鎮守の森になっています。
日光に光る蜘蛛の糸に触らないように、リンボーダンスのようにかがみながら、参拝しました。
→
稲野辺神社
● お寺ふたつ
稲野辺神社の斜め向かいに建光寺がありましたが、大々的に掃除をしている最中だったので、遠くからお辞儀をして、先に進みました。
→
建光寺
さらに歩きます。初めての道ですが、迷うほど入り組んでもいないため、のんびりした気持ちで散策できます。
とはいえ、「あれ、この表示、まっすぐかな?曲がるのかな?」と迷いながら、表示が指す方向を目指して、辿り着いたのはまたお寺でした。
弘法大師の像があり、なんとなく雰囲気が違うなと思ったら、ここは観音霊場の霊厳寺。
武蔵野三十三観音があるのだそうです。
そういえば、前にも所沢の方で武蔵野霊場のお寺に行ったことがあるなあと思い出しました。
純はそのうち巡り始める様子です。
→
霊厳寺
● 橋と祠
途中、新堀橋という細い橋を通りました。
幅2mほどの人道橋ですが、橋の入り口に建てられた2本のポールが、擦り傷だらけだったので、やんちゃなバイクがぶつかりながらブイブイ通って行くんだろうなあと思います。
近くには出世橋と呼ばれる橋もありましたが、私達は通りませんでした。
(出世が遠のく・・・)
--------------------------------------------
左岸■埼玉県日高市北平沢字金剛寺
右岸■埼玉県日高市新堀字吹上
材質■橋面:木、橋脚:コンクリート製、桁:鋼製
サイズ■長さ約45m、幅2.0m、高さ4.9m
車輌制限■幅1.5m、重量1.5t
通過日■2013.11.30
--------------------------------------------
道すがら、鳥居を見つけたので寄ってみました。
小さな祠で、集落の守り神なのでしょう。
道を歩けばお地蔵さんの祠がある京都のようです。
なんの神様が祀られているのかわかりませんが、八百万の神々のどれかということでお参りしました。
→
新堀の社
● 高麗家住宅
日が高くなってきました。
朝は早起きしたため、ほとんど何も食べていません。
お腹が空いて、パワーダウンしてきた感じ。
とぼとぼ歩いていたら、古い藁葺き屋根の古民家が見えてきました。
ここは、代々高麗神社の神職を務めてきた江戸時代の高麗家の家。
民家の中が見えるようになっており、朝鮮大陸風の暮らしぶりが見られます。
国指定の重要文化財だそうです。
● 高麗神社
高麗家住宅の隣には、この日のハイライト、高麗神社がありました。
この辺りは、716年に武蔵国高麗郡が設置された地です。
668年に高句麗が唐・新羅に滅ぼされ、日本に亡命してきた帰化人1800人を、朝廷はこの地に移住させたとのこと。
高句麗王族の高麗若光(じゃっこう)が祀られています。
ハングル語で書かれた絵馬がたくさん奉納されていました。
奈良時代に日本まで逃げのびてくるなんて、大変だったことでしょう。
大昔に、そんな渡来人を手厚く保護した当時の朝廷は心が広かったなあと思います。
当時は人が少なくて、土地がたくさんあったことでしょう。
そして大陸からの渡来人は、仏教を始めいろいろな技術を教えてくれる物知りの人達として、大切にしてもらったんでしょうね。
平成28年(2016)には、高麗郡が設置されて1300年を迎えるそうで、あちこちにポスターが貼られていました。
現代の宮司は若光の子孫でちょうど60代目に当たるとか。
伝統が脈々と続いています。
→
高麗神社
● 高麗神社のチャンスン
住居の敷地から高麗神社の境内へ入りましたが、出るときは参道を歩きます。
と、ここにも大きなチャンスンがありました。
石造りで赤く塗られていませんが、それでもやっぱり迫力満点~。
顔のパーツ、どれを見てもコワイです。子供だったら恐怖で泣いているレベルです。
大韓民国民団埼玉県地方本部(ものものしい名前)によって奉納されたものだそうです。
● 釜めしランチ
お腹が空いてきたので、ランチにしました。
向かったのは、
食事処 和(なごみ)。
普通の一軒家です。よそさまのお宅を訪ねる感じで、チャイムを押し、靴を脱いで家の中に上がりました。
通された和室は広々として静かでした。
ここで純は五目釜めし、私は鮭釜飯セットをいただきました。
なんだか安心できる料理が並びます。
ずっと歩いてきたので、ほっと一息つけました。
飾られていた、温かみあふれる夫婦雛。
女将さんに聞いたところ、この土地の作家さんの手によるものだとのことでした。
● ひっつき虫の攻撃
おいしいご飯を頂いて元気が出て、また歩き出します。
通りに出ると、目の前の山に大きなお寺が見えます。
次に向かう聖天院でした。
ショートカットをしたら、なにか引っかかった感触が。
マフラーにひっつき虫(オナモミ)がびっしりと付いてしまいました!
ショック!子供の頃、外で遊んでいたらよくひっつかれていたことを、最近ではすっかり忘れていました。
ルートナビは純に任せて、しばらくの間、シラミを取るサルのように、オナモミをマフラーから取り除くことに集中します。
ここにもチャンスンがいました。が、写真には収めませんでした。
広々とした境内なのに、ほとんど参拝客はいませんでした。
→
聖天院
● 野々宮神社
それから、純のリクエストで野々宮神社へと向かいました。
途中で道に迷ってしまい、二人連れの小学生の女の子に聞きます。
二人とも神社の場所は知っていましたが、「こっちの道が近いよ」「え、こっちだよ!」と、二人とも別の方角の道を指して譲りません。
うーん、こういう時、二人とも傷つけないように、どんな采配をすればいいのかしら?大人ってむずかしーい。
結局、近かったのか遠かったのかわからない道を歩き、工場の敷地内じゃない?と思うような荷物クレーンの通るそばを通ったりしながら、神社へとたどり着きました。
その途中、さっきの女の子たちが振り返りながら自転車で追い越していったので、「きっと私たちのことが気になったんだね」と純と話しました。
まあ、あんまり場所を聞かれる神社じゃなさそうですしね。
京都・嵐山の野宮神社に名前が近いなあと思ったら、そこから分霊したのだそう。
個人的に気になる倭姫命が祀られていました。
→
野々宮神社
● 謎の階段
「地図を見ると、どうもこの神社のそばに、不思議な細い階段があるらしい」という純に先導されて、社の奥をウロウロ散策してみました。
すると、鬱蒼とした茂みの中にひっそりと隠れた階段を発見。
本当に細いです。うわあ、これはどこに続いているんでしょう。
ワクワクしながら降りかけたら「だめだめ降りちゃ。コースアウトになっちゃうから」と純に止められて、しぶしぶ足を止めました。
もう、冒険したかったのに~。
● こおばんち
でも、冒険なんて言っていられないくらい、そろそろ脚がくたびれてきました。
なんといっても昼食休憩以外ずっと歩き通し。
「駅までバスに乗ろう」とバス停に行っても、20分ほど待たなくてはならず、「それならバス停1つ分歩いちゃおうか」など話して、結局ずるずると歩いて行きました。
途中、こんな駅名標を見つけました。
ここ、何かの駅なの?とキョロキョロしましたが、目の前は車道で、そういうわけではなさそう。
お店の宣伝のようです。ここで見るのが初めてでしたが、そのあと別の場所でも、同じ感じの看板を見かけました。
それにしても気になる、こおばんち。
● ここは日高牧場
黙々と歩いていたら、馬がいました。
えっ、馬?
よく見ると、何頭もいます。
移動動物園かな?
建物には「牧場」と書いてありました。
牧場があるなんて!
近寄ってみることにしました。
ボーイ・ミーツ・ホース。
関係者限定というわけではなさそうで、ほかにも小さい子供連れの家族が吸い寄せられてきます。
大きな馬やポニーなどが、牧場の柵の中で草をはんだり、こちらを眺めたりしていました。
乗馬のレッスンをしている少年もいました。
黒ヤギもいて、ヤギ好きの純は気になる様子。
ほかの訪問客にも人気で、そばにずっとお客さんがいたため、私達は諦めてポニーのそばにいきました。
そういえばここは日高市。北海道の日高になぞらえて、サラブレッドを飼っているのかしら・・・?
● あいあい橋
牧場のすぐとなりにあるあいあい橋を渡りました。
もともと、この橋が気になって、地図にチェックしていたのです。
歩行者専用の橋。カーブが素敵でした。
--------------------------------------------
場所■埼玉県日高市巾着田(きんちゃくだ)
下 ■高麗川
対象■歩行者専用橋
架橋■平成8年3月
材質■橋面:木、橋脚:コンクリート製、桁:鋼製
サイズ■全長91.2m
通過日■2013.11.30
特記■日本最大級の木造トラス橋 「彩の国さいたま景観賞」
トラス構造■「トラス」は三角を意味する言葉で、各部材を三角形に組み合わせて強度を確保したもの
--------------------------------------------
● 朝採れカフェソフト
電車が来るまで少し時間があったので、近くの農作物直販所、
朝採れファーム高麗郷へ。
ここでソフトクリームを食べました。
牧場に行くと、ソフトクリームを食べたい気分になりますよね?ね?
純はバニラ、私は備前屋の狭山茶抹茶味。
歩き疲れた身体に、いっそうおいしく感じました。
● 農作物直販所のチャンスン
ここにも将軍標がありました。
わー、今日はいったいいくつ見ればいいのかしら。
でも、これまでのものよりも、顔つきが愉快でファンキーなので、ほっとします。
足元にはなぜか、白雪姫の小人が。どうしてここに(笑)?
● 高麗駅のチャンスン
純は、予定としては高麗川駅に戻りたかったようですが、気がついたら高麗駅の方が近くなっていたため、そちらへ向かいます。
この駅前には、以前秩父に行く電車の中から見た将軍標が立っています。
遠くで見た時ですら腰が引けたのに、近くで見たら、さらに怖さ倍増ー!
この辺りの人たちは、もうすっかり慣れているようで、目にとめることもなく通りすぎていきますが、私は彼らの強い目線を感じて、視線を合わせられませんでした。
ハッ、もしかして、外から来たヨソモンなので、完全に睨まれてる・・・?
● epilogue
今日はこの界隈で、計6体のチャンスンを見ました。
高麗川駅前で2体、高麗神社、聖天院、朝採れファーム高麗郷、そして高麗駅前。
刺激強すぎ~!チャンスン多すぎ~!
気がつけば、チャンスン巡礼みたいになっているではありませんか。
後で調べてみると「日本にあるチャンスンは、埼玉県日高市の高麗神社、聖天院、西武池袋線高麗駅前、西多摩郡日の出町の東光院妙見宮」と書かれていました。
高麗川駅のものは2つとも入っていませんが(地図表とオブジェですからね)、つまりは日本にあるチャンスンのほとんどを、この日一日で見たことになります。
ひ~、赤い将軍たちにとことん睨まれた一日だわー。
帰りは高麗駅から電車に乗り、また延々と時間をかけて帰宅しました。
日本に、もっといえば埼玉の奥の方に、これほどまでに朝鮮文化が息づいた韓国のような場所があることに驚きました。
食がメインの場所、中華街の韓国版は大久保界隈になりますが、ここは少し違って生活に根ざした文化的な場所。
日韓関係はどうも難しいままの状態が続いていますが、こうした文化的交流の地についてもっと知られてもいいのに、と思いました。
2年後の高麗郡1300年祭が、どんな盛り上がりを見せるのか、今から楽しみです。